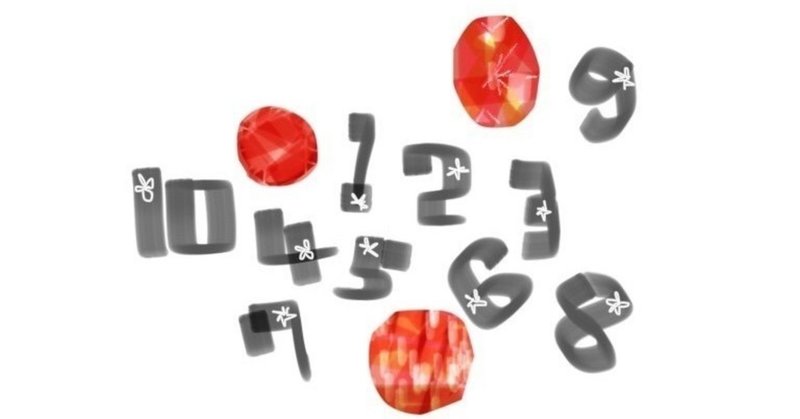
なぜ数字で考えることが重要なのか?
こんばんは。りょうへいです。
今日は「なぜ数字で考えることが重要なのか?」というお話をさせて頂きます。
日本語は多様な表現のある言語で、そのおかげで自分の感情を表現したり。相手に分かりやすく伝えることが出来る美しい言葉です。
ただ、多様な表現を持つ日本語を操る日本人にも、多くの人が苦手としていることがあります。
それが、「数字で物事を考える」ということです。
例えば上司に仕事の進捗状況を伝える際
上司「頼んでいた仕事はどの程度進んでいますか?」
部下「はい、大体終わっています!」
このような場面に出くわしたことはありませんでしょうか。
更に上司が
「そうか、大体終わっているなら安心して大丈夫そうだな」
となってしまうと、最悪の場合期日までにきちんと仕事が終わらない可能性まで出てきてしまいます。
数字を用いない報告には、双方の伝達や認識に著しい誤差を生んでしまう危険性があるのです。
ちなみにこのような状況の場合、これは決して部下だけの責任ではなく、上司にも責任がある可能性があります。なぜなら
・進捗は数字で説明するように指示をしていない
・よって、具体的な数字で進捗状況を管理出来ていない
このようなが指導状況が想定されるからです。
数字で考えることが浸透していない組織は、思わぬ所で計画通りに進まないことが多々あります。
では、数字で考えるとは具体的にはどのようなことなのでしょうか?
今回は一冊の本を紹介させて頂き、数字から物事を考える教養についての解説をしていきたいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◇徹底的に数字で考える
今回ご紹介させて頂くのはこの本です。
ビジネス数学教育家というユニークな肩書きを持つ、深沢真太郎さんの著書で
・きちんと数字を用いてビジネス教育を行いたい管理職の方
・これから成果をあげる上で数字を意識していきたいビジネスパーソン
このような方にオススメの書籍となっています。
著者である深沢さんは、数字で考えるメリットについて、以下のようなメリットがあるということを仰っています。
1.問題解決能力が高まる
2.説得力のあるプレゼンテーションが出来る
3.ファクト(事実)ベースで信頼感が持てる
このメリットについて、次章から詳しい解説をさせて頂きます。
1.問題解決能力が高まる
仕事とは問題解決の連続です。付加価値とは、問題解決によって生まれるものなので、必然的に仕事をする上で私たちは何らかの問題解決をしているのです。
では、問題を解決していく際に必要なものとは何でしょうか?
それは、具体的な数字です。
例えば飲食店で、「今月売上が下がっちゃったよ」と言っても、何の解決にもなりませんよね。
・具体的にどれぐらい下がったのか?
・分類するとどの分野がどれぐらい大きく下がったのか?
こう言った具体的な数字をもとに、解決策を考えるはずです。
そこで数字をきちんと考えられる人が、問題解決に向かって順序立てて進んでいくことが出来るのです。
ここでいう数字とは、難解な数学の教養のことではなくて、四則演算ができれば十分です。
カレーの売り上げが100食分下がっているから、今月は120食増を目指す。そのためには売り上げがいくら必要で、具体的にはいつまでに何をどれぐらいやるのか
この程度でも、数字で考える力が組織に浸透していれば、問題解決の能力は高まり、全員が共通認識を持って仕事に取り組むことが出来ます。
2.説得力のあるプレゼンテーションが出来る
更に、数字で考えることは説得力を大きく増すことになります。
例えばあなたが誰かの上司だった場合、「自分がやりたいからやる」という人と「現実に数字がどれぐらいになりそうだからやる」という人では、どちらの意見を採用しますか?
独創的な実績や経験を持っている部下なら分かりませんが、私なら具体的な数字を持ってきた部下の意見を採用します。
なぜなら、数字はデータを改ざんしない限り嘘はつけず、確かにそこにあるあることを証明してくれるからです。
「日本は高齢化社会だから、介護事業をやりましょう」
よりも
「日本では現在、年少人口が1524万人に対して、高齢者人口は3588万人います。これは日本の総人口の28.4%を占める数値です。今後日本の総人口は1億人を下回る中、高齢者人口は減らず、35%を超えるという統計が出ています。よって当社でも、介護事業を推進していく必要があると思います」
と言われた方が、説得力がありますよね。
プレゼンテーションを行う際、具体的な数字は大きな説得力を伴うのです。
主観だけではない意見を持っていると周りからみなされれば、多くの人を動かすことが出来ます。
以上のことからも、数字で物事を考えるということは重要なんですね。
3.ファクト(事実)ベースで信頼感が持てる
先ほどの文章でも触れていますが、数値は信頼につながります。
高齢者の割合が多くなっているというのは事実として数字が示しているもので、総務省統計局が嘘をついていない限り、確かな信頼を持てるものです。
一方で、主観による「何となく増えてきた」というだけでは、信頼感はなく、そのことを言う人に依存するしかありません。
ビジネスの場面でも同じで、数字を具体的に先方に示すことは可能です。
これをしっかりとやらないと、相手からしたら「それ、どこ情報なの?」と疑わざるを得ませんよね。
数字は事実としてそこにあるものなので、嘘をつきません。相手に対して説得をする場合だけでなく、自分が誰かに説得を受ける場合でも同じです。
「その情報はどこから得たもので、具体的にどれぐらいの数字なんですか?」
と聞けば、裏のあるような情報や欺こうとしている人は答えられなくなります。
そのぐらい数字が持つ信頼度は高いんですね。
最後に
いかがでしたでしょうか?
ここまでは主にファクト(事実)ベースでの数字で考える重要性について解説をしましたが、著書ではアサンプション(仮説)ベースでの数字の考え方や、ビジネスに使える統計学にも言及をしています。
仮説思考、PDCA、分析手法など、仕事を進めていく上で大切なことが沢山書かれている良本ですので、気になる方は是非手に取ってみてくださいね。
この記事を読んでくれた方が、数字で考える重要性をより理解し、個人や組織で活躍をして頂ければ幸いです。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
頂いたサポート代を全てうまい棒に変換し、1年後にnoteで写真公開することを目論んでいます。
