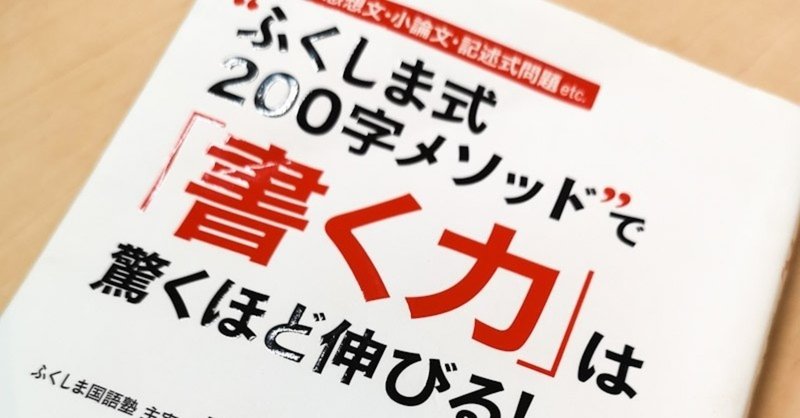
もう「何を書くか」で悩まない、書く「型」を身に付ければ、内容は追いついてくる!│【書評】❝ふくしま式200字メソッド❞で「書く力」は驚くほど伸びる!
こんにちは、緑志新です。
本日まとめていくのは「❝ふくしま式200字メソッド❞で「書く力」は驚くほど伸びる!」福嶋隆史氏 著書です。
3つあるテーマから「伝える能力を磨く」を今回ピックアップしていきます。ぜひ最後までお付き合いください。
この本を読めばこんな力が身に付く
・文章の「型」が身につく
・「型」が身につけば200字を800字、1200字に膨らますことが簡単にできるようになる
・「型」を身に付ければ質の高い文章を書くことができる
どうすれば文章が書けるようになるのか
これまでの日本語教育は、書く内容について、重視する傾向にありました。
例えば、日記を書くことに戸惑っている子供に対して、あなたが親なら
どのようなアドバイスをしますか?
多くの人は「あのときはあんなことがあったから、こんな風に書けばいいんじゃないの?」
といったような内容について提案するのではないでしょうか。
ふくしま式の日本語教育では、書く方法について、重視しています。
例えば、著者の福嶋氏は同じ問いに対して「文章の型に言葉を当てはめて作るといいよ」といった風に教えます。
これまでの日本語教育とふくしま式の教育を比べてみると、ほとんどの日本人が前者の方法によって育ってきたのではないかと思います。
今回私が興味を持った一番の理由も、これまでの教育法とは異なった観点を持った本だからです。
文章には黄金の型が存在する
結論
全体構造は「根拠」→「結論」。そして全体を支える骨組みは「対比関係」
【「ア」を否定し、「イ」を肯定する】
具体的には以下の内容…
【ア】は、【1】なため、【A】である。
↕<対比関係(くらべる力)>
しかし、【イ】は、【2】なため、【B】である。
↓<因果関係(たどる力)>
したがって、【ア】よりも【イ】のほうが【C】であると言える。
この形をひたすら真似して練習しまくることが重要!!
国語力の本質は論理的思考力
国語力とは整理力
上記の例文では、型によって自分の主張が整理された状態になっています。
そして整理するために必要なことが「論理的思考力」だと言っています。
文部科学省による学習指導要領には、国語とは以下の要項に分類されています。
①話す力┓
┃ 発信力
②書く力┛
③聞く力┓
┃ 受信力
④読む力┛
著者はこれを以下に再定義して能力を高める提案をしています。
【重要】
・言いかえる力
・くらべる力
・たどる力
これら「3つの力」を駆使して話し、聞き、書き、読むことで国語力を向上させることが出来る。
事例を用いて「黄金の型」、「論理的思考力の3つの力」を理解し、身に付ける。
3つの力の特長と事例
ここからは具体的な事例を説明していきます。
【言いかえる力 …同等関係を整理する力】
抽象⇔具体の関係性
例)
「みかん、バナナ、りんご」
具体化↑ ↓抽象化
「果物」
比較をする際は対象同じ抽象度がであることが重要
【くらべる力 …対比関係を整理する力】
反対の事柄を比べるときの関係
【ア】は、【1】なため、【A】である。
しかし、【イ】は、【2】なため、【B】である。
黄金の型そのものです。
例)
タクシーは一度に乗れる人数が少ないため、運賃が高い。
一方、バスは一度に乗れる人数が多いため、運賃が安い。
【たどる力 …因果関係を整理する力】
原因と結果(根拠と結論)の関係
大半が納得する客観的な因果関係
例)
①
この公園にはゴミ箱がない
↕
だからゴミ箱を設置しよう
②
この公園にはゴミ箱がない
↕
なのでゴミが散乱して汚れている
↕
だからゴミ箱を設置しよう
②の方が客観的な説明になっています。
「たどる力」とはこのように原因・結果をたどりながら客観性を
維持していくことです。
3つの力を使って型の質(特に対比)を高める
質の高さとは以下のことを満たしていることが条件
「客観性が高い」 10人中8人が納得する
「独自性が高い」 10人中2人しか思いつかない
「普遍性が高い」 様々なことがらに当てはまる
独自性・普遍性を高めるためには
①静的→動的に視点に変える
止まっている画ではなく、動いている画をイメージできるかがポイント。
例えば自転車と三輪車を例に挙げると、
静的観点では、大きさや車輪の形といった相違点が見つかるが、それでは常識レベルを脱することが難しい。
一方、動的観点ではスピードの違い、一漕ぎで進む距離といった相違点が見つかり、最終的には用途の違い(自転車は移動手段、三輪車は遊具)といったレベルにまで達します。
このように、「普段思ってはいるけど、口に出して来なかったこと」こそが独自性を持ち、また人の生活とは常に動的なため、普遍性も兼ね備えています。
②具体的(物理視点)→抽象的(心理視点) 言いかえ
例えば、青空と曇り空の違いを「雲の有無」や「傘を持っていく必要性」から、「前向きな気持ちになりやすいかどうか」と表現すると、一般的な観点から離れて独自性を高めることができます。また人の心理という普遍的な観点により共感を得られやすくなります。
たどる力により、説得力を増す効果が発揮
①②はくらべる力を軸とした技術です。ここに「たどる力=因果関係」を加えることで文章はより説得力の高いものに変わります。
②の例 青空と曇り空の違いを「前向きな気持ちになりやすいかどうか」で文章を作成する場合、「くらべる力」だけでは以下のようになります。
「曇り空は嫌な感じがする、しかし、青空はいい感じがする。
なので曇り空は青空とくらべて、前向きな気持ちになりやすい。」
これは人によっては共感されない可能性があります。
独自性を高めた結果、それは主観的な文章に陥りやすい傾向にあります。
これに説得力を持たせるのが「たどる力」です。
曇り空には雲がある
↓だから
日が差さない
↓だから
心も暗くなる
「曇り空は、雲があり日が差さないため、心も暗くなる感じがする。
しかし、青空は、雲がなく日が差すため、心も明るくなる感じがする。
なので曇り空は青空とくらべて、前向きな気持ちになりやすい。」
このようにたどる力は、主観的な心理観点を補う役割を果たしたと言えます。またこれらは表現やセンスの問題ではなく、型や技術の問題であり、
繰り返し心がけることで、誰でも使えるようになるスキルです。
<ステップアップ>
理想の型に近づくテクニックを身に付ける①
実際に例文を用いて、細かな改善点を体得することができます。
例文
メールは書くのが文字なので、気持ちが分かりづらい。
しかし、電話には声があるため、怒っているかどうかなどが伝わりやすい。
改善後
メールは機械的な文字によって伝えるため、喜怒哀楽が伝わりづらい。
しかし、電話は生身の声によって伝えるため、喜怒哀楽が伝わりやすい。
①<観点を統一する→くらべる力>
【分かる/受け手】【伝わる/送り手】
どちらかに合わせる
②<抽象度を統一する→言いかえる力>
天秤に乗せるようなイメージで抽象⇔具体のバランスを合わせる
気持ち(具体化が必要) ⇔ 怒っている(抽象化が必要)
→(結果)喜怒哀楽でバランスをとる
③<因果関係を整える→たどる力>
文字によって伝える
↓ 根拠が薄い<機械的な>
喜怒哀楽が伝わりづらい
声によって伝える
↓ 根拠あり、統一<生身の>
喜怒哀楽が伝わりやすい
「声によって伝える」→「喜怒哀楽が伝わりやすい」は客観的にも理解できます。しかし「文字によって伝える」→「喜怒哀楽が伝わりづらい」というのは、やや主観的で理解されづらいかもしれません。
そこで「くらべる力」を使います。
機械的 ⇔ 人間的(上の文章では言いかえて「生身」としている)
これを入れることで説得力が増します。
<ステップアップ>
理想の型に近づくテクニックを身に付ける②
例文
バスにはバス停があり、いつでもどこでも乗れるわけではないので、不自由である。
それに対して、タクシーにはバス停がなく、どこででも乗ったり降りたりできるので、自由である。
だから、バスよりもタクシーの方が、自由に乗り降りできる乗り物だと言える。
改善後
バスは、発着場所および乗車できる時間帯が限られているものであり、不自由である。
それに対して、タクシーは発着場所および乗車できる時間帯が限られていないものであり、自由である。
だから、バスよりタクシーの方が、急な移動が必要になった際に役に立つ手段であると言える。
①<観点の数を揃える>
いつでもどこでも ⇔ どこででも
乗れるわけではない ⇔ 乗ったり降りたりできる
対比は常に鏡で見るように同じ表現を心掛ける。
②<アンバランスな観点を抽象化する>
バスにはバス停があり
→バスには決まった乗り場があり
タクシーにはバス停がなく
→タクシーには決まった乗り場がない
しかしタクシーにも「タクシー乗り場がある」ことを踏まえて
「バスは、発着場所が限られている
タクシーは、発着場所が限られていない」とすることが妥当です。
③<結論を区別する【たどる力】>
例文の「どこででも乗ったり降りたりできるので、自由である。」と「自由に乗り降りできる乗り物だと言える。」
これを「だから」で繋いでいます。だからは因果関係を表すので同じ内容ではいけません。これでは小泉進次郎氏の言い回しになってしまします。
これらは静的→動的なにシフトチェンジして、独自性のある観点を取り入れることが良いでしょう。
改善ではどこか、堅苦しく、不自然な感じもありますが、著者はまずは型通り書けるようになり、そこから型を破り、型から離れるというプロセスを踏んでいくことが出来ると記しています。
その上で、「鏡に映したかのごとく」忠実な文章を練習することが重要だと述べています。
【本書から活用できること】
①比較の意識
文章だけではなく、日常で無意識に比較をしている。これらが意識して出来だすと、書くだけではなく、話す内容にも説得力を付加するこができる。
②3つの力は反復練習
3つの力は奥が深いが、的が絞られている。また日本語なので日常的に使う頻度が高いため意識した練習を行うことで力を身につけることができる。
【読み終えて】
文章を書くという作業を、構造的にすることで、まるでスポーツをしているような感覚を感じた。例えば野球のピッチャーであれば、正しい姿勢、フォームを体に染み込ませる。そのベースが出来てから、ボールの握り方を変えていくことで変化球を体得する。練習方法が分かれば反復することができる。文章作成でこのように感じたことは今まで一度もなかった。
今回著書の半分程度の重要な部分をまとめたが、残り半分は応用を行っている。応用が身に付けば、より長い文章も内容に迷うことはない。書くという行為をイチから学びたい方には良い本ではないかと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
