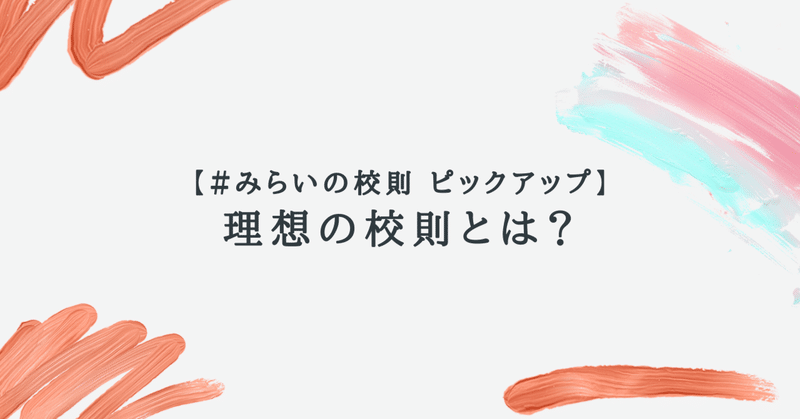
【#みらいの校則 ピックアップ】理想の校則とは?
2021年9月27日から12月31日までの約3ヶ月の間、校則についての考えやユニークなアイディアを募集した「#みらいの校則」投稿コンテスト。すでに審査結果は発表されましたが、コンテスト後に投稿された記事や受賞作以外の印象深い記事など、5本をピックアップしました。(受賞作品についてはこちらの記事をご覧ください。)
社会に出る準備段階としての校則のあり方
作者が通っていた中高は校則が厳しかったため、社会に出た際にちょうど良さが分からず、奇抜なファッションに目覚めてしまったといいます。社会に出る準備段階として校則があるのならば社会に出た時に恥ずかしくない校則を設けてほしい ―。
例えば、ほとんどの学校で化粧は禁じられていますが、就活の時期になると、「女性はノーメークはマナー違反だが、ビジネスシーンにふさわしくないメイクも避けるべき」という暗黙のルールに直面します。
社会人になった際に求められるあいまいな常識に対して、校則がどのように橋渡しできるのか、という問題意識に気づかされる記事です。
作者の植田さんが考えたみらいの校則は、「校則を自分で考えて設定し、併せて何のためにその内容にしたのかという目的や在りたい姿を明確にさせる」というもの。
予測のできない世の中で生き延びるために「自分で考える力」が必要であり、それを学生のうちから身につけることは、社会に出たときの大きな「無形資産」になると語っています。
自分で自分の行動を決める
作者の岩下さんが通った高校は「自ら学び、自ら問う」という教育方針と「生徒諸君を信頼し、規則は最低限とする」という方針に基づき、校則は原則として無く「心得」という形で示されていました。
それゆえに、学校や先生の信頼を損なわないことを大前提としつつ、「自分らしくいたい」「自分らしくって何だろう」と自らを問う行動を学校生活で日々繰り返していたそうです。
校則内容の変更ではなく、そもそも学校に必要なルールをどういった形で示すのか、という新たな視点を得ることができます。
こちらの作者が考えたみらいの校則は、「生徒は、その学校の信用を傷つけ、学校全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」というもの。これは、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止) の「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」を言い換えたもので、「学校の信用を傷つける行為とは何か、学校全体の不名誉となるような行為とは何かを考えさせる校則をみらいの校則にしたらどうだろうか」と語っています。
学校の信用を傷つける行為とは果たして何だろう…。生徒でなくても深く考えさせられる問いです。
テクノロジーが助けるみらいの校則づくり
こちらの記事では、みらいの校則の決定・運用・管理について、子ども主体を前提としつつ、具体的にどう進めるべきか、作者の考えがまとめられています。
例えば、子どもたちが決めるべき範囲に関しては「小・中・高と子どもたちの発達段階による段階設定」を設けたり、ルールの決定段階ではチャットツールを利用して、話し合いの「透明化」と「可視化」を進めたりするという提案がされています。
最後に作者が書いているように、これらの実現を「みらい」まで待つ必要はないのかもしれません。
「#みらいの校則」に寄せられた記事からも分かるように、皆が目指す校則のかたちは人それぞれです。一方で校則は皆が守るものであり、対話を通じて一つの方向性に定める必要があります。そのためには、まず互いがどのような校則を理想としているのか、知ることから始まるのではないでしょうか。
▼ そのほかの「#みらいの校則」記事はこちら
