
クレヨンで書かれた「難民」の文字
デザインを通じて、海外の価値観にハッとすることがある。
その一例が今回のお話。
ドイツの留学生誘致サイトを見ていたとき、フッターにこのバナーを発見した。
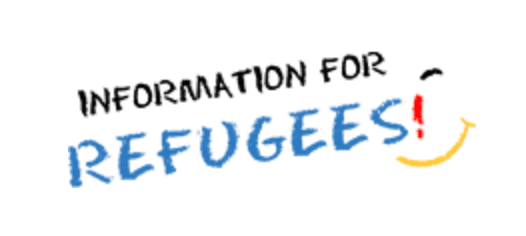
日本語にすると「難民の方への情報はこちら!」といった訳になる。
初めて見たとき、頭を殴られたような気持ちになった。
そうだ、自分が難民という言葉で想像するのは、難民キャンプで毛布にくるまり、ジッとこちらを見据えている小さな子どもだ。
私の頭の中には、難民と呼ばれる人たちが、ドイツのような先進国の大学に行って勉強するというイメージがなかった。
今、難民であるという事実は見えていても、彼らには、その後の人生があることを全く考えられていなかった。
難民という言葉には悲惨なイメージがあり、こんな可愛らしい手書きのクレヨンで書かれる可能性がある言葉だと考えたこともなかった。
難民キャンプで暮らす層と、難民の中でも富裕層には差があるのかもしれないが、私の中で彼らの未来にまで考えが及んでいなかったことに変わりはない。そして、彼らが難民となる前の暮らしにも。働いたり、勉強したり、普通の暮らしがあったに違いないのに…。
いくつか関連記事を見つけたので、共有。
日本語と英語の言葉のニュアンスにも差があるのかもしれない。
日本語の難民は、字面から「困難にあっている人」という意味を真っ先に感じる。英語のrefugeeは「逃げる」という言葉が語源になっており、ネイティブとしての感覚はわからないものの、「逃げてきた人」という能動的な意味合いをより感じるように思う。
このデザインに出会った頃よりも後の話になるが、オランダでシリア出身の青年に出会ったこともある。
そういった経験から、少しづつではあるが、狭かった自分の考えも変わってきたように思う。
まだまだ足りないし、関心を持つだけでは変わらないという気持ちもある。そして、難民の方について考えることも、もちろん大切なことだが、日本の中にも、政治を始め、関心を持ち行動すべきことはたくさんある。
全て地続きのものとして考えて、少しずつでもできることをやっていきたい。
参考:ドイツ留学生誘致サイト
@hapibi_nileでTwitterもやってまーす;) フォローしていただけると泣いて喜びます! Twitter: https://mobile.twitter.com/hapibi_nile
