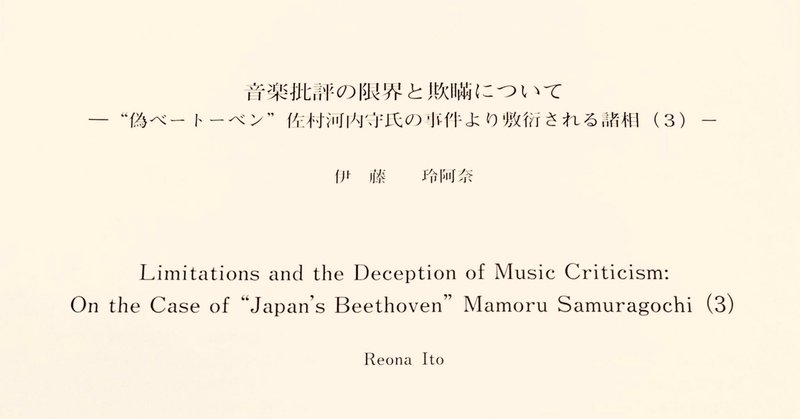
【論文公開3】音楽批評の限界と欺瞞について
皆さん、こんにちは! 在米27年目、ニューヨークはハーレム在住の指揮者、伊藤玲阿奈(れおな)です。
論文公開の第3弾は、私が客員准教授(執筆当時は客員研究員)を務める武蔵野学院大学の紀要にて発表したもので、音楽批評の限界と欺瞞を論考しました(執筆2017年/公刊2018年)。後に発表した「音楽理論における科学革命」や「荘子の天籟問答」と比べると学術論文として傷があるかもしれません。自分の考え方が7年前とは異なる部分もあります。それでも、基本線においては間違ったことを言っていないと思っています。
論文はある程度の専門家を読者として想定しており、学術的な厳密さを重視した硬い文章ゆえに、たいへん読みにくいです。講演や著作における私のいつもの調子とは落差が激しいことはご諒解ください。
*オリジナルの文章は一切変えていませんが、読みやすさを考慮した改行や、24年現在「傍点」「イタリック体」などがNoteでは反映できないため一部で太字に変更するなどの処置を加えました。
論文タイトル&キーワード
音楽批評の限界と欺瞞について
―“偽ベートーベン”佐村河内守氏の事件より敷衍される諸相(3)-
伊藤 玲阿奈
Limitations and the Deception of Music Criticism
On the Case of “Japan’s Beethoven” Mamoru Samuragochi (3)
Reona Ito
【キーワード】クラシック音楽 音楽批評 佐村河内守 新垣隆 カント 美学 ロゴス
1.はじめに ~本寄稿シリーズの目的
全聾の作曲家として交響曲第1番「Hiroshima」などの作品を発表し、評論家からの一定の評価と世間からの高い注目を集めていた佐村河内守氏が、彼の「ゴーストライター」であった新垣隆氏によって代作の事実や全聾は虚偽であったこと等を記者会見で暴露されたのは2014年(平成26年)2月5日のことだった。クラシック音楽という一般的に高尚なイメージを保つ分野で、全聾というベートーベンを意識させる設定を捏造し、大部分を他人に代作させた作品を発表していた事実、しかも、当事者であるゴーストライター本人による暴露会見という扇情的な状況も手伝って、それから暫く日本中がこの話題について口にし、議論したのではないだろうか。
一般大衆の興味は措くとしても、“偽ベートーベン”佐村河内守氏の事件からは、代作・著作権・売名行為・慈善活動の偽善・障がい者のイメージ・音楽産業とマーケティング・音楽批評への信頼など、驚くほど多様な観点が見出され、音楽よりむしろ現在の日本社会を分析する上での研究対象として重大な意義があるように思われる。
本紀要第13輯に始まる筆者の一連の寄稿の目的は、音楽家としての立場から、この事件の諸相に関して感情ではなく冷静で客観的な分析を行う為に必要と思われる論考を敷衍的に呈示することで、現代日本社会研究に対する一助となることである。
2.不信を表明された音楽批評 ~「批評家は切腹ものである」
本寄稿シリーズの第3回目となる本稿で論じるのは音楽批評の問題である。
具体例を引くことはしないが、あらゆる客観的証拠からして、佐村河内氏による交響曲第1番が、他の同ジャンル作品よりも音楽批評家や関連メディアの俎上に載せられる圧倒的に機会が多く、かつ、好意的な(その一部は熱狂的とさえ言える)批評によってかなりの割合が占められていたという事実があった。そして、全聾や広島といった話題性が耳目を引く契機となったにせよ、この交響曲の初演や初録音の際、その初期段階で批評を行ったであろう専門家たるプロ音楽批評家の「後押し」又は「お墨付き」も(メディアを介して)一般大衆への普及に大きな役割を果たしたことは疑いようがない。
事件直後、インターネット上で様々な意見に目を通して興味深かったことは、多くの人々が「あれは本当に良い曲だったのか?」という疑問を投げかけていたことである。それまで作曲家と曲の存在を知っているのみだった筆者の許にも、その答えを求める質問が友人達から寄せられたのだが、それらの中には「実際は大した曲でないのに全聾の作曲家だから感動して評価したなら、批評家は切腹ものであるし、踊らされた聴衆は反省すべき」という感想を添える人もいた。これは、やや過激ながら一般的意見の典型例と見做しても妥当すると思われる。なぜなら、音楽作品の良し悪しという基準が確かに存在するという考え方が、まるで疑いようのない真理の如く浸透しているからである。そして、音楽批評という行為はこの考え方に立脚して成立しているという認識が一般的だからである。つまり、「本当に良い曲だったのか」と気になる人々が相当数存在したのは、情に流されて音楽の良し悪しを見抜けない批評家への批判意識が根底にあるがゆえなのである。
しかし、佐村河内事件では様々に不信を表明された音楽批評について、角度を変えて批評行為そのものを論理的に深く考えていくと、決して一元的な認識に収まらないことに気付くであろう。そして、不信を表明する側にも再考を促す論理さえも発見できるのである。
音楽之友社が昭和41年に刊行した「標準音楽辞典」に於ける「音楽批評」の項は、東京帝国大学美学科出身で、「芸術学」(東京大学出版会)「音楽美の構造」(音楽之友社)などの著書をもつ音楽学者・渡辺護によって執筆されている。その項の中で渡辺は、音楽批評の定義を「われわれの社会生活の中で提示される音楽作品や演奏についての報告や、価値批判をのべるのが音楽批評である」としている(注1)。分かり易い妥当な定義であるが、同項目では次のような一節も存在することが目を引く。
音楽批評にたいし世間は時に不当な要求をしがちである。第1には徹底的な客観性を要求することは誤りである。芸術批評はこのような客観性を持ち得ない。同じ演奏にたいする批評が多少異なるのはやむをえない。音楽批評があたかも裁判官の宣告のように絶対的な力があるものと見られがちであり、そのためその影響力は不当に拡大されてしまう。
この記述からすれば、世間に浸透している音楽批評に対する先ほどの“暗黙の前提”――すなわち音楽に対して客観的(もしくは絶対的・決定論的)価値判断を遂行できるという前提――自体が間違っているということになる。しかし同時に、「価値批判をのべる」ことが音楽批評の定義であると渡辺は言う。これはどういうことを意味するのであろうか?言い方を変えれば、「芸術批評は客観性を持ち得ない」理由(すなわち“暗黙の前提”が誤っているという根拠)を示さずに批評を価値批判として定義していることが矛盾のようにみえ、我々に混乱を招くのである。考えてみればたしかに、「芸術に答えはないのだ」とは誰にでも頭では理解しえる主張である。しかし、それでは批評行為の意味はどこにあるのだろうか、また、芸術に回答がないことが何となくでも分かっているはずの人々がどうして批評を気にするのだろうか、という疑問が湧いてくる。
このように、批評行為を巡っては、生活世界に於いて大多数の人々が意識をせずに何となく通り過ぎているであろう疑問、もしくは矛盾と断言できる要素が存在することが観察できるのであるが、これを論理的にしっかりと言語化して整理すると、音楽批評行為を分析しつつ限界をも見据えることが可能になることであろう。したがって、本稿ではこの課題に取り組むことにより、音楽批評が重要な役割を演じた佐村河内事件に対して、読者があらたな分析を可能になるような角度を獲得することを目的に定めることとする。ただし課題に取り組むにあたっては、あくまでも純粋な音楽批評行為に焦点をあて、音楽産業と音楽批評家の癒着、批評の読み手が内容を鵜呑みにすること、批評が権力のように通用する現象など、社会学的・心理学的側面は考察外とする。
3.音楽批評行為の分析、そして限界について
3.1 美的判断(≒批評行為)を巡る“奇妙な現象”のカントによる言語化
批評行為について考察するにあたり、イマヌエル・カントが近代美学を打ち立てた著作「判断力批判」から、第一部第二編「美学的判断力の弁証論」の中にある「趣味のアンチノミー(二律背反)」と呼ばれる一節をまず引用したい。
(一)正命題。趣味判断は、概念に基づくものではない、もしそうだとしたら趣味判断は論議せられ得る(証明によって決定され得る)ことになるからである。
(二)反対命題。趣味判断は、概念に基づくものである。さもないと判断が相違するにも拘らず我々はその判断について論争できなくなる(他の人達が我々の判断に必然的に同意することを要求できなくなる)からである。
「趣味taste(英)/ Geschmack(独)」という17~18世紀に使用された特殊な美学的術語が使われていることが21世紀の読者を混乱させるかもしれないが、この術語は実質的に「美の判定能力」を意味するので(注2)、ここでは、これを「美的判断」という言葉に置き換えると両命題の意味がはっきりするであろう。また、「論議」と「論争」の語法の違いについては、カントによると、判断間の対立の一致を図ろうとする点では両者は同じであるのに対して、違いは、前者は証明可能な客観的概念を判断根拠とし、後者はそうでないという点にある。(「判断力批判」第56節)
わざわざこのアンチノミーを引くのは、美について判断する行為――これはつまり対象の美的価値を判定する行為(注3)なので、批評行為と根幹で同義である――を巡る“奇妙な現象”が的確に言語化されているからである。カントの厳密な学説との若干の齟齬を怖れずに筆者なりにまとめるならば、美的判断に於いては、その規定根拠は判断する者それぞれの主観的なものに過ぎないにもかかわらず、どうしても普遍的妥当性(客観性)を要求してしまうということだ。音楽に当てはめて言えば、ある音楽作品の解釈や批評は、感官(聴覚)を通じて得られた感覚的なデータに基づいている訳だから、そこから下される判断はあくまでも主観的であり本来は普遍的妥当性など要求できず、客観的証明に基づかない「論争」のみ可能である。しかし、それにもかかわらず、音楽家にせよ批評家にせよ、自分の判断に対して普遍的妥当性を求めてしまう、つまり必然的な同意を求めてしまうという事実も厳然として存在する。この“奇妙な現象”は、プラトン(例えば「ヒッピアス(大)」(注4)や「饗宴」)の時代から続く、「美とは何か?」という問いにまつわる大きな謎の一つなのである。
(K.フィードラ―以降、美と芸術は切り離して考えるのが常識であるから、美的判断を芸術批評は区別しなければならないという意見が出るかもしれない。しかし、現象面をみると感性的体験の記述であることに変わりない訳であるから、それは結局のところ単なる言語使用上の違いに終始すると筆者は考えている。)
カントは、独断論(ライプニッツ・ヴォルフ学派)と懐疑論(ヒューム)を調停したように、自ら名付けるところの「批判主義Kritizismus」でもって両極端を避けて中間を調停的に求める哲学的姿勢を一貫して保持していた(注5)。ここで引用した美的判断に対するカントの鋭い眼差しと思考も、主観的なはずであるのに客観的であることを要請することで、一元的決定論または相対主義的自由論という両極端な論に陥りやすい美的判断の“奇妙な現象”に対してその姿勢を如実に示している。そのような批判主義の代表例が「純粋理性批判」に於ける有名な超越論的弁証論であり、その部分と同様に、「判断力批判」でも美的判断に関してアンチノミーの提示と解決を図るという手法を用いたのである。
現在の我々にとってカントの美的判断に於けるこの試みがすべて成功しているとは言い難い。理由をいくつかあげれば、まず「判断力批判」では「美」の用語法は自然美を主に指していること、現在は18世紀では考えられなかった程に美に対する考え方や向き合い方が多様化しているためカントの目的論的な把握では今の我々にとっては説得力に乏しいのは否めないこと、などである。そしてなによりも、アリストテレス的な「(自然の)合目的性」――美的対象が構想力と悟性との自由な働きを調和させること――という美の謎を解くキーワードとなる概念を開示してはいるものの、カントは超感性的基体と感性的基体の統一的な理論構築を目指している訳では決してない為に、アンチノミーを論理的に解決したとしても謎そのものはどうしてもそのまま残ってしまうのである。(注6)
カントは、客体が主体に従うというコペルニクス的転回を行った点で、(フッサールではなくランベルト流の意味に於ける)現象学的なアプローチであった。つまり、客体たる作品自体ではなく、享受する主体の心にそれがどのように現れるかに注目しているのである。それでもなおカントは美的判断について考察を試みて、「主体の無私の態度によって判断の正しさが保証される、という骨格の基礎づけ」(注7)を行おうとした限りに於いては、美を客観的に規定できるとした以前の存在論的な立場に近い「比較的古い立場を継承して」おり(注7)、そこにも後続の哲学者から批判が加えられることになる。美的判断を巡る“奇妙な現象”は、現在までに様々な説が唱えられど、いまだ原理は不思議のままであり続けている。つまるところ、現在われわれが知る限りに於いて、美であれ芸術であれ感性的体験(美的体験)について客観的に判断して記述するための統一的原理は発見されておらず、美という感性的なものを客観的概念として規定して、そこから演繹するという、プラトンらが行ったような存在論的アプローチが取り得ないのである。(美学用語としての「美的体験」の「美的」はaesthetic であり、バウムガルテンによる定義にみられるように元々は「感性の」という語義であるから、美と芸術が分離していても芸術享受は「美的体験」という術語で言い表せえる。しかし、「美的」の語が現代日本人一般にとっては「美しいbeautiful」という意味であるので、ここでは筆者は意図的に「感性的体験」と記述した。以下も同様である。)
3.2 前節の応用による批評行為についての言語化
ここに至り、批評行為についてより厳密に言語化を試みることが出来る。
先に挙げた渡辺護の記述を引用しつつ述べれば、「価値批判をのべる」のが批評であるとの定義は、批評がある概念(考え方・信念・主義・イデオロギーなど)に基づいて判断を下す行為であることを意味する。しかしながら、数学的証明に於ける手順とは決定的に異なり、感性的体験に由来する現象(美学用語としての「美」)について演繹しながら客観的に記述できる統一的原理が存在しないために、「芸術批評は客観性を持ち得ない」。ここから導き出せることは、批評行為とは、当事者が経験や認識を高めることを繰り返すことによって、己がある感性的体験を判断するうえで“依拠する概念群”を帰納的に形成し、それに基づいた価値判断を記述すること、ということになる。その際に、当事者は、感性的体験記述の統一的原理が存在しないことを怖れたり意識したりしては批評自体が不可能となるので、“依拠する概念群”がどの程度の主観性と客観性のバランスを保っているかに意識を向けることだろう。そのうえで、その作品についての諸々の意味について読み手に自分の考えを伝え、読み手にとってその作品に接する上での手ほどきとなる、という社会的責務を背負っているのである。
このように整理すると、批評行為の限界と範囲もおのずから次のように策定できる。限界は、言うまでもなく、その性質から決して原理的客観性に裏打ちされないため決定論を打ち出せず、批評の意義も正確さも、究極的には読み手に対する説得力や読み手の共感に依存するということ。そして、範囲は、価値判断の際に依拠する概念群によって決まるということ。概念群の候補は無数に考えられる。音楽理論、形式、音楽史の成果、演奏テクニック、感情の表出、作者の意図、という具合に。換言すれば、批評行為とは、“依拠する概念群”という部分をどう捉えるかによって、その流儀や傾向といった類別が決まってくるという訳である。
繰り返すが、依拠する概念が明確でも、記述対象が感性的体験であり統一的原理が存在しない以上、その概念を統一的に明確な基準で使用することは不可能である。ましてや音楽は、即物的には物体の振動が媒質たる空気を伝わって耳に届く現象に過ぎない抽象的芸術の極致であるし、渡辺が「同じ演奏にたいする批評が多少異なるのはやむをえない」と述べるのも無理はない。ただ、筆者の考えでは、渡辺のこの部分の記述には不満を感じる。なぜなら、“依拠する概念群”という批評函数の変項がまったく違う中身であれば、そこから帰結される批評内容もまったく違うものになることは疑いないからだ。したがって、「多少異なる」という表現は甘いと言わざるをえない。実際に、同じ作品や演奏についてプロによって書かれた音楽批評を見比べると、正反対の評価を下していることは多々みられる。佐村河内氏の交響曲第1番に於いても、肯定派・否定派とさまざまに分かれていた。それは「多少異なる」どころではなかったのである。
以上のように言語化して論理的な整理を施してやっと、批評行為とは結局のところ批評者の“依拠する概念群”からの判断――“精神活動”とも言い換え可能だろう――にかかっており、その個性の差異がダイレクトに反映されるものだという結論を導くことが出来る。(「芸術批評は客観性をもちえない」)そして、だからこそ、たとえば小林英雄や吉田秀和の“作品”のように、批評そのものが芸術品のように受容されるという契機がひらかれるのであるし、“批評の批評”つまりメタ的な現象も起こることになるのである。
ところが、生活世界に於いては、この結論部分のみが「芸術に答えはない」式に漠然と認知されるのみで、その結論を導く上記のような過程については全く思考されていないのが実情である。この結論を経験的に認知しているにもかかわらず佐村河内事件の折に「本当に良い曲だったのか」「批評家は切腹もの」などの感想を表明する者が続出したのは、このような実情に人々が甘んじていることを証明しているように筆者には思われる。批評を行う、もしくは批評について語るならば、感性的体験を認識に還元することへの批判的思考が必要なのである。
もちろん、このことは批評家が何を書いてもよいということを意味しないし、擁護をしている訳でもない。批評する者は、絶対的に通用する判断基準が存在しえないぶん、自分の価値判断にどれだけ首尾一貫性や普遍性があり、読者への説得力をもっているか、などの諸点を注意深く吟味しなければならない。さもなくば自分の趣味や見識をかえって疑われる結果になりかねない。佐村河内事件に於いても、自らが“依拠する概念群”の妥当性や普遍性が高く、それに基づいて首尾一貫した論旨を純粋に展開しえた批評家については、事件後にその批評を修正する必要はほとんどなく、その価値も減じることはないのではないか。逆に、妥当性や普遍性に乏しい概念に基づいて価値判断を下していた場合、その生命は事件によって断たれたことだろう。
3.3 佐村河内事件のケースにみる批評の生命力について
では、この事件のケースでは、生命を保つ批評と保てない批評とは具体的にはどのようなものだろうか。両者を隔てる要因のなかで、筆者が決定的と考えるのは批評家による“音楽外要素”の扱い方についてである。
佐村河内事件に特徴的なことは、「交響曲第1番」という音楽作品の“外”の要素――つまり、ベートーベンを想起させる「全聾」という障がい、そして交響曲の題名にも関連する「被爆二世」(これは事実である)という要素――が批評に於いても重要な役割を演じたことである。これは佐村河内氏本人のドキュメンタリー出演に加え、その名も「交響曲第1番」という著作を発表してベストセラーになっていたという背景がある。批評するにあたり、作曲家と作品をより知るために批評家はそれらを“勉強”したことだろう。しかし皮肉なことに、批評家が勉強したそれらの音楽外要素を価値判断の過程に盛り込んでいた場合、事件後にその批評は根拠を喪失し、説得力を持たなくなって生命を奪われてしまう。むしろ、音楽外要素をなるべく価値判断の過程から排除して、純粋に音楽的な現象に注目して論理展開していた批評は、そのレベルが高ければ今なお有効であり、生命力を保っているはずなのである。
注意すべきことは、別に「全聾」や「原爆」という音楽外要素が“依拠する概念群”としては妥当性や普遍性に乏しかったという訳ではない、ということだ。なぜなら事件前の時点では、それらは明証性を保持しており、妥当しているし客観的な事実であったことは間違いないのだから。したがってそれを批評に持ち出すこと自体に何ら問題はなく、言及すること自体は自然の成り行きであるとさえ言える。
佐村河内事件に於ける批評の生命力についての本当の核心は、作品そのものと音楽外要素との関係性である。言い換えるならば、ある音楽作品を判断するという行為に音楽外要素がどこまで必要であるのか、という音楽の自律性にかかわる問題である。
このような音楽の自律性についての認識も批評家の“依拠する概念群”の一つであるべきだ。これについて明確な認識を持っていないと、「全聾」「原爆」などの音楽外要素が音楽作品そのものの価値と安易に融合されてしまう。むろん、融合されていてもその体系内で論理に一貫性がある限りは説得力を持つだろうから、それはそれで批評として立派に成立するのであり、筆者はそれを否定する立場には立っていない。むしろ、近年の主潮とは異なり、音楽に於ける感情移入を積極的に支持している。ただし、音楽を音楽として自律させているのは、和声・リズム・形式・楽器法などの実際に楽譜に記されている純音楽的な要素であるのだから、音楽作品を価値判断するにあたり純音楽的要素と音楽外要素をどのような関係で捉えるかという問題には、どんな形の批評を書くにせよ、どんな立場に立つにせよ常に目を光らせて意識しておくべきなのである。
3.4 音楽批評界の限界と欺瞞
実際のところ、現在のプロの批評家ならば、「絶対音楽」と「標題音楽」の対立、ハンスリックによる形式主義美学批評の創始、ストラヴィンスキーらの反ロマン主義音楽などの歴史事情を十分に学んできているはずなので、安易な音楽外要素の価値判断への取り込みはしなかったはずだ。つまり、程度の差はあっても批評としての生命を保っているものが相当数あったに違いない。それでも、事件後に沈黙したり多くを語りたがらない批評家が存在したのは、自身の名誉に対する心理的な要因があるのかもしれないし、佐村河内氏や音楽産業界の発した音楽外要素(特にブランディングや広報戦略)の拡散に手を貸してしまった悔恨や羞恥心の反映かもしれない。しかし筆者の考えでは、自己の価値観(つまり“依拠する概念群”)に従って純粋に評価できる音楽なら堂々とその旨を言い続けるべきで、この点にかんして現在の日本に於ける音楽批評界の限界および欺瞞をみるのである。
つまり筆者にとっては、「交響曲第1番」の価値判断の結果に対して非難するのではなく(価値判断について論争しても無益に近いのは本章前半で示した通りだ)、事件の前後に関係なくどれだけ同じ価値観の体系内で説得力のある主張を展開しているかを吟味するということが重要であって、これこそが音楽批評に対する読み手側の本来のあるべき姿であると信じているのである。そして批評家は、音楽外要素が真実でなかったせいで以前の価値判断を変更せざるをえないのであれば、それを素直に表明し、自らの価値観の体系から新たに判断を組みなおして読み手に提示するべきだ。音楽外要素の真偽がどうあろうと己の体系に照らし合わせて変更しないで済むのなら、それを表明し続けるべきだ。しかし、いずれの実行も出来ない一定数の批評家が存在したせいで、音楽批評界の限界と欺瞞を世間に露呈することになり、ますます音楽批評への不信を表明されることになった。
この章の最後に、過去の興味深い事例を引く。それは、天才と称される程の名声を博していたにもかかわらず33歳で夭折したルーマニア人ピアニスト、ディヌ・リパッティ(1917-1950)に関するものである。リパッティは“名演・名盤”を紹介する関連本では現在でも紹介されることがあり、特にショパンの演奏録音で名高い。その彼が遺した録音群に関連して、音楽業界の公刊物等で触れられることは少ないが、音楽批評や音楽を享受する我々の態度に疑問を投げかける逸話がある。大手レコード会社であるEMIより1966年から販売されていた、リパッティが演奏したとされるショパンの協奏曲のレコードが、1981年になって、BBCによる放送を聞いた視聴者の疑義がきっかけとなり、全く別人のハリナ・ツェルニー=ステファンスカの演奏であると判明しスキャンダルとなったのである。ただの「間違い」事件として収まらないのは、販売元のEMIは元より、リパッティ夫人までが亡き夫の演奏だと信じて太鼓判を押しており、欧米や日本の批評家もこぞって絶賛していた録音であったこともあるが、何よりも「偽物」と判明してからその録音が「名盤」として取り上げられることが全く無くなってしまったという事実が、音楽批評や視聴者に今なお鋭い波紋を呼ぶからである。
この事件は、当事者たる演奏者自身は与り知らぬものである。しかし、EMI関係者による意図的な虚偽だったとしたら(真実は判明していない)、これは詐欺であり表面的には佐村河内事件に類似している。そして、この二例からは次のような点が観察できる。
(1)鑑賞対象へのイメージやレッテルという音楽外要素が、批評家愛好家を問わず音楽享受や価値判断に決定的に影響する。
(2)それが偽りだった場合でも、巧妙に偽装されていると純音楽的な正邪を最初から見抜ける者は皆無に近い。
(3)一旦、イメージやレッテルが崩れた場合、以前にどれだけ称賛されていようと以後それらは軽んじられる、又は無視される結果となる。
「鑑賞対象へのイメージやレッテル」とは、供給側の需要側へ向けたブランディング戦略、より具体的には何らかの音楽外要素を設定した産物である。リパッティ事件ではショパンと同じく病気で夭逝した天才ピアニストの持つ背景が設定として最大限に利用され、佐村河内事件では、本格的な交響曲を手掛けるクラシック音楽作曲家、そしてベートーベンを想起させる「全聾」という障がい、加えて更に悲劇性を高める「被爆二世」(これは事実である)などが設定として利用された。これらの点は、音楽外要素によって音楽批評の内容が実際の事態と乖離するまでに左右されうるという事実を端的に示しており、これはたしかに当事者たちにとっては大変不都合であり不名誉なものであることは確かである。
それでも上記(1)(2)は人間にとって“自然な”限界であって、これらは織り込み済みとして接するくらいの冷静な態度が読み手には必要だろう。その体系内で論が通っていて一定以上の説得力を持つのであれば、それを後から責めるのは酷であり不公平であるし、このような態度は音楽批評の健全な発展をかえって阻害することになるだろう。一方、実行可能性に対して踏み出さないという意味での限界と、良心や本心に反しているのを知りながら行為するという意味での欺瞞、この二つを生み出すのは、やはり(3)であろう。沈黙や無視は立派な意志された行為であり、これについては完全に批評家の怠惰と臆病に起因するのではなかろうか。
4.終わりに ~自らの行為への徹底したロゴスによる関心、そして責任
もともと美的(≒感性的・芸術的)体験とは先理論的であって、頭で言語化されるよりも前に、すでに人間の生のある側面をなにものかが充たしてくれるような体験である。哲学者のみならず批評家も、ある意味で“無理やりに”それを言語化を試みていることには間違いない。まして形がなく実体がつかめない音楽体験については原理的に言語化は困難をきわめる。
哲学は言葉(ロゴス)によって徹底的にある問題を問い詰めていく学問である。本稿でも示された通り、カントはじめ美学を追究した哲学者の成果は、批評について言語を用いて根底から考察するうえでは不可欠なものだ。ところが残念ながら日常生活世界ではここまで徹底的に感性的な事象を言語化して分析をほどこす人などごく稀で、大半が“何となく”で通り過ぎていく。
筆者にとって、佐村河内事件に於ける音楽批評を巡る核心的問題は、「交響曲第1番」などの諸作品への批評家の判定結果にあるのではなく、まさにここにあった。批評家であれば、感性的体験を認識へと還元して価値判断を下す行為について徹底した自己分析を加え、創りあげられた己の体系に対して一貫性と良心を保持することが重要であり、それが不十分であるケースが多発したことが問題で、読み手の側であれば、同じく感性的体験を言語化することへの限界について意識が足りないがゆえに、作品への批評家の判定結果にとらわれ過ぎ、批判しても意味がない部分まで批判をしたり、もしくは不公平と思われる態度で批評に接することが一般的にみられたことが問題なのである。
これは取りも直さず、自らの行為に対して徹底した関心(言葉による分析)をもつこと、そして、自らの行為に対する責任をもつことの大切さと同義である。後者は日本の一般社会でも頻繁に唱えられるが前者については少ないかもしれない。西洋に於けるロゴスの伝統と密着している前者が本稿の論を進めるうえで大変有益であったことは既に見た通りで、ここから筆者は、健全な社会を育む為に、われわれ日本人は徹底したロゴス的関心を持つことにも意識をより向けるべきであると思われてならないのである。
注
1 『標準音楽辞典』(1966)音楽之友社 p. 207
2 佐々木健一(1995)『美学辞典』東京大学出版会 p. 191~192
3 Ibid. p. 199
4 偽書説もあるが、そうであっても古代から美的判断の奇妙な性質に対する問題意識が存在する証左であることに変わりない。
5 「純粋理性批判無用論」に於ける用法である。『縮刷版カント事典』(2014年・弘文堂)の「批判主義」の項を参照した。
6 石川文康(1995)『カント入門』ちくま新書p. 197
岩崎武雄(1973)『カント』 勁草書房p.271~272
7 佐々木 p. 229 及び p. 234の注8
主要参考文献
(注で記載した文献、および以前の寄稿で記載した文献については省く)
中島義道(1997)『カントの人間学』 講談社現代新書
中山元(2013)『自由の哲学者カント』 光文社
カント、イマヌエル[中山元訳](初版1781・第2版1787)全7巻 光文社古典新訳文庫
本論文の初出
武蔵野学院大学日本総合研究所研究紀要《第15輯・2018》・大学側の転載許可済み
********
楽しんで頂けたなら、下の💗をポチっ!
もしお役に立ったなら、サポート(投げ銭)を是非よろしくお願いします!
執筆者プロフィール:伊藤玲阿奈 Reona Ito
指揮者・文筆家。ジョージ・ワシントン大学国際関係学部を卒業後、指揮者になることを決意。ジュリアード音楽院・マネス音楽院の夜間課程にて学び、アーロン・コープランド音楽院(オーケストラ指揮科)修士課程卒業。ニューヨークを拠点に、カーネギーホールや国連協会後援による国際平和コンサートなど各地で活動。2014年「アメリカ賞」(プロオーケストラ指揮部門)受賞。武蔵野学院大学大学院客員准教授。2020年11月、光文社新書より初の著作『「宇宙の音楽」を聴く』を上梓。
執筆活動へのサポートを賜ることができましたら幸いです!
