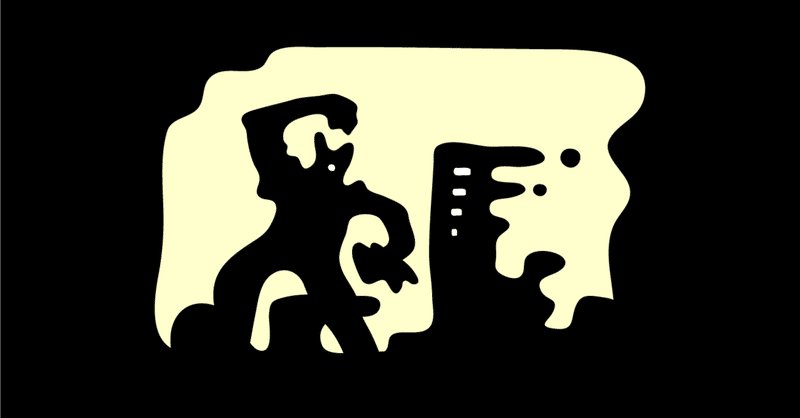
ルビと約物と字面
ルビを振る、ルビに振られる
ルビとは、主に漢字の横や上に小さな振り仮名を付けることだったようですが、いま「主に」と書いたように、ルビを振られる対象は漢字に限りません。私なんかへそ曲がりなので、本来とか、もともとというのが苦手で、そこからはずれたことをしたくなります。
ぶれるわけですね。何かに触れて、つまり軽くぶつかって、その反動を楽しみながらちょっとよける感じ。ずらすにも似ています。ようするに素直ではないのです。
*
『村上龍料理小説集』の「Subject 5」に面白い試みがあります。
ある男性が昔関係のあった女性と偶然に再会する。女性の横には小さな女の子がいる。男性は女性と会話しながら、同時にその女の子とも会話する。そんな話なのですが、母親である女性の話す言葉にルビが振られています。そのルビが女の子の言葉だという趣向です。
ネタバレにならないように気をつけて要約しましたが、ルビの使い方という点ではネタバレになったかもしれません。ごめんなさい。こんなルビの楽しみ方もあるということで、ご勘弁願います。
noteには器用な方がたくさんいらっしゃるので、ルビをつかったいろいろな斬新な試みがなされているのではないかとわくわくしています。ルビ詩とかルビ小説なんて具合に。
二つの物語(詩)が同時進行する。ある物語(詩)の終り(最後の連)で結末が二つに分かれる。建て前と本音が併記された小説(散文詩)。ルビに乗っ取られる一種の文字禍の掌編――。
上で紹介した村上龍の掌編の要約を読んで、何かひらめいた方がいらゃっしゃいましたら、お書きになった作品をぜひ読ませてください。
*
ところでなんで、ルビを「振る」というのでしょう。こういう疑問が浮かんだときには、すぐには調べません。ああでもないこうでもないと、うじうじ考えるのが楽しいのです。振り仮名と関係ありそうだとは思います。ちょっと言葉を並べて遊んでもらいます。
かなをふる。まな、真字、真字。かな、仮字、仮字。
本当のものと仮の姿というイメージでしょうか。まなにかなをふる。まなかな。ふーむ。おもしろそうですね。
漢語系の言葉に大和言葉を振るというのも面白そう。逆に大和言葉に漢語を振るのもぞくぞくします。以前にやったことがあります。というか、私はつねに頭の中で大和言葉(和語)と漢語を行き来して楽しんでいるみたいです。
掛詞の名人
「振る」と言えば、foolとfullが英語の原文にあり、それが掛詞(かけことば)になっていて、それを日本語でも掛詞にした、そんな話を柳瀬尚紀先生から伺った記憶があります。
大学生時代に翻訳学校にも通っていて、そこの授業で聞いたのです。柳瀬先生はつねに英語と日本語での言葉遊びを考えているような人で、とてもチャーミングな翻訳家でした。
こういう原文があるんだけど、なんとか洒落にならないからな、というふうによく授業で話を振るのです。
あるとき、先生の作った訳文に「よこしま」という言葉が見えたので、「さかしま」はどうですかと提案してみたところ、それはいいと先生がおっしゃってメモなさっていた覚えがあります。原文の作者名とか、どんな訳文だったかはすっかり忘れてしまいました。残念です。
翻訳でルビをつかって掛詞を処理したり、註の代わりにやはりルビで地名や人名の説明をする場合がありますが、個人的には好きです。ルイス・キャロルの作品なんかは言葉の遊びが多いので、邦訳ではそうした例には事欠きません。
そんなわけで、キャロルの訳書を開くと字面が黒めでべたーっとしていたりします。あと、ジェイムズ・ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』の柳瀬尚紀訳が忘れられません。
柳瀬尚紀先生は掛詞の名人です。「駄洒落の名人」とは言いたくありません。駄洒落やオヤジギャグというのは、掛詞の別称であり蔑称でもあるからです。
つなぐ名人
そういう字面の文章の書き手で思い出すのは、高山宏先生と蓮實重彦先生です。
ルビはもちろん傍点(傍点はルビを使って作るみたいです)などの約物をやたらお使いになるので、字面がべたーとしています。絨毯の複雑な模様にも似ています。
高山先生は概念や物や言葉をつなぐ名人ですから、真字/仮字という「ルビの原則的な使用」(比喩です)を、西洋/東洋、日/英、センス/ノン・ナンセンス、真偽、正誤、真贋、虚実、正邪、善悪、聖俗といったペアにまで広げて、各ペアの両者をつなげてしまうというアクロバットのような芸を見せてくれます。
約物と各種レトリックを多用した魔術的かつ華麗な文体は、アリュージョンとイリュージョンに満ちあふれ、ときに書かれている内容に書かれている文章の言葉が擬態するとか、シニフィエにシニフィアンが擬態する、あるいはその逆もあり――という様相を呈します。
宙吊りにする名人
蓮實先生の文章では、たとえば「近い」という言葉が本当に「近い」のかという疑問を常に意識し、人が文字通りに言葉を取るという錯覚と抽象にきわめて敏感であり、要するに言葉による錯覚を検討しつつ抽象と断定を周到に回避しながら書き進めるような言葉の身振りを実践なさっているので、必然的に文章が読みにくくなり、その結果の一つとして字面がべたーっとします。
蓮實先生の文章では、ルビよりも、むしろ傍点をほどこした文字が目につきます。それは先生が、つなぐ人ではないからです。だから、文字そのものに視線を向けるように促す傍点をつかっていらっしゃったのだろうと想像します。
*
蓮實先生は、つなぐ名人では断じてなく、むしろ宙吊りにする名人なのです。ジル・ドゥルーズ的な意味での宙吊りと言うべきでしょう。
宙吊りという身振りは、約物のつかいかたにあらわれています。とくに「、」(読点)、「。」(句点)、「「」」(鉤括弧)です。センテンスの息を長くし、括弧でくくることで疑問を呈すのです。読んでいて息切れする字面になります。
詳しく言うと、こと(事・言)を宙吊りにする名人なのです。蓮實先生は物しか信じません。蓮實先生にとって映画は影ではありません。影はこと(事・言)だからです。先生にとって映画はあくまでも物なのです。もちろん言葉(声と文字)もです。
蓮實先生の宙吊り芸については、近いうちに別の記事で書くつもりでいます。
つむぐ名人
高山先生と蓮實先生の言葉の身振りを足して二で割ると丸山圭三郎先生の文章になる、なんて言いたくなりますがやめておきます(書きましたけど)。
言い直します。丸山先生は「似ているものをつむぐ名人」です。「似ている」は「同じ・同一」と異なり印象です。
たとえばラカンとソシュールは似ているなあと感じると、それに似ていることが先生の著書『言葉・狂気・エロス――無意識の深みにうごめくもの』に書いてあるのです。とても便利です。考えの整理ができるからです。
そうした個人的な理由から、あの本が好きです。現代思想でややこしそうなところは、たいていあの本の中で扱ってあります。さまざまな固有名詞が出てきますが、丸山先生は自分の問題として記述しているところに共感を覚えます。自分なりに解釈して説明しているので読みやすいという意味です。
あとレトリックも大変お上手です。これは大切なことだと思います。特にああいうややこしいことを扱う場合には。
『言葉・狂気・エロス』を読んで、あるいは読みながら、フーコー、ドゥルーズ、デリダ、ジョルジュ・バタイユ、マラルメ、ベケット、ウィトゲンシュタイン、ニーチェを読むと、「似ている」ところを感じて、つまり既視感を覚えて、分かったような気分になります。分かった気分ではありません。分かったような気分です。
「分かった」は同一性とか本物を指向しますが、「分かったような」は似ているへのこだわりだと言えます。「分かる」や「悟る」を求めていない、つまり欲深くない人には最適の本だと思います。あの本の字面もべたーっとして、いい顔をしています。
曖昧放置プレイの名手たち
とりわけ、ジャック・デリダ、ジャック・ラカン――ラカンの残したテクストは少ないのですが、だからこそ、結果的にソシュールやマラルメと同じく曖昧放置プレイの名手として名を残しているとも言え、寡黙、場合によっては沈黙(死者は饒舌なレトリシャンです)と「テクストの不在」こそが最強のレトリックなのです――、ミシェル・フーコー、ジル・ドゥルーズといった書き手は、言葉の多義性や多層性、ひいては言語の限界性を意識したうえで文章(=レトリック)をつづったのですから(ほんまかいな)、その文章について語る文章やその翻訳が、ルビや約物を使わざるをえないのは当然であり必然だという気がします(もちろんこれは趣味とレトリックの問題でもあり、使わない強者もいます)。
あなたが見ているのは文字
ルビや約物は、一瞬だけ文字が文字であることを見せてくれます。
あなたが見ているのは文字ですよ、と注意を喚起しているのが、ルビや約物なのかもしれません。
あなたが見ているのは文字ですよ。
あなたが見ているのは文字ですよ。
でも、一瞬だけです。人は文字が文字であることを見留められないのです。文字の向こうに目を向けるほうがずっと楽だし、そうするように学習してきたからでしょう。
*
あなたが見ているのは文字ですよ
上の傍点を見てください。傍点は本来は縦書き用のものです。横書きで打つと間が抜けて見えないこともないです。傍点(圏点とか脇点とも言います)は活版印刷の時代に強調したい文字列の脇にほどこすものだったそうです。
上の傍点が、脇ではなく下の文字を強調するどころか、間が抜けて見えたり、元気がなく見えるのは、パソコンやスマホの画面で見ているからかもしれません。
活版印刷された本の文字は立って見えるのにたいし、液晶画面上の文字は浮いて見えます。「昔はよかった」的な話はしたくありませんが、私にはそう見えます。
浮いた文字にルビを振っても、薄羽蜉蝣のようにどこかはかなげで悲しくなることがあります。苦し紛れに、薄羽蜉蝣(うすばかげろう)というふうに丸括弧をつかうことがよくあります。
*
活版印刷が過去のものとなり、さらには印刷よりもモニター画面で文章を読んだり書いたりする機会が圧倒的に多くなったいま、見る文字を強調したいのであれば、太文字にすればいいのでしょうか。
あなたが見ているのは文字ですよ。
活字を拾って組んでいた時代には、太文字にするのはいまのように簡単ではなかったようです。書体が異なるわけですから、活字一式(全活字)をセットで揃えなければならなかったからでしょうか。
いずれにせよ、時代は変わりました。文字を強調したいときにもちいる方法も変わりました。
変わらないのは、文字が文字だと強調させたところで、人は一瞬だけ文字に視線を注いでも、次の瞬間には文字の向こうに目をむけてしまうということのようです。
あなたが見ているのは文字なのです。
#村上龍 #柳瀬尚紀 #蓮實重彦 #高山宏 #丸山圭三郎 #ルイス・キャロル #ジェイムズ・ジョイス #翻訳 #掛詞 #ルビ #約物 #文字 #活字 #印刷
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
