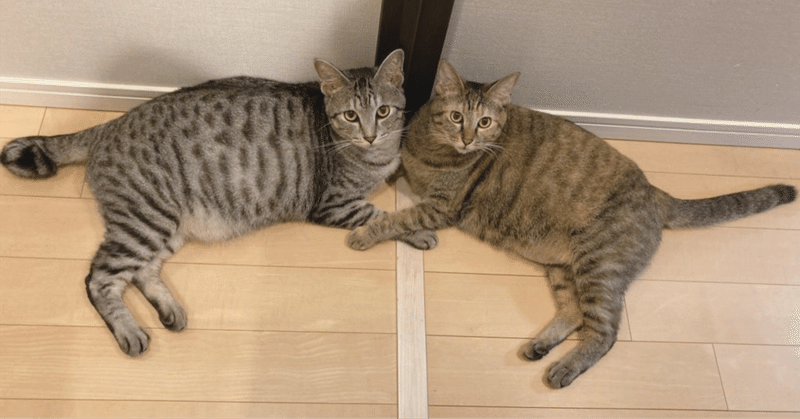
『杳子』で迷う
謎解き
小説を読むさいに、何らかの見立てを設ける場合があります。見立てなんて言うと、もっともらしく響きますが、図式的な先入観をもって読書に臨むことでしょう。
ようするに決めつけて読むわけです。
たとえば、謎解きです。ジャンルがミステリーの小説であれば、謎解きがテーマなはずですから、「正しく」謎を設定して、「正しく」解いていけば、「正しい」解にたどり着けるでしょう。
*
ミステリーではない小説で謎解きをする場合があります。
エンターテインメントでも、いわゆる純文学でも、名作として広く読まれていたり、古典的な作品でも、そうした読み方ができそうな小説があります。
非ミステリー作品の謎解きでは、謎があると読者が勝手に決めつけるわけですから、誰もが納得のできる説明が不可欠になります。
『杳子』で謎解きをする
私も『杳子』を読みながら、謎解きをしてきました。
具体的には、疑問に思うことを謎と見なして、その答えをさがす作業になりますが、これは楽しいものです。ついつい、はまってしまいます。
ただし、自分の都合のいいようにこじつける恐れがあるので要注意です。私なんかしょっちゅう、こじつけて失敗しています。
ある見立て(図式)を設けて読もうとすると、その見立てに合う部分だけでなく合わない部分が出てきて、こけるのです。
見立てに合わないところが一箇所でもあれば、その見立ては外れたことになります。一種の計画倒れですが、見立て倒れとも言えるでしょう。
ようするに、こけたのです。
『杳子』の謎
「まばらにまだらに『杳子』を読む」という連載で私の見立てた謎を振りかえってみます。
*谷底の岩場での杳子と「彼」の出会いを描いた「一」という章で、「岩」という言葉がたくさん出てくるのに、その辺にごろごろしているはずの「石」が三回しか出てこないのは、なぜか? (「まばらにまだらに『杳子』を読む(07)」)
*そもそも、平たい岩のうえでうずくまっている杳子を、どうして「彼」はすぐに助けようとしないのか? (「まばらにまだらに『杳子』を読む(01」))
*杳子がケルンの「直立の無意味さに」を「長いこと眺め耽(ふけ)っていた」と妙なことが書いてあるけど、その「無意味さ」には何らかの意味があるのではないか? (「まばらにまだらに『杳子』を読む(04)」)
*「岩」は「違和」とか「異和」と、そして「石」は「意志」と読むことができるのではないか? (「まばらにまだらに『杳子』を読む(04)」 & 「まばらにまだらに『杳子』を読む(07)」)
*この作品では、ケルンや「ケルンみたいなもの」がやたら出てくるが、その成分が「岩 ⇒ 石 ⇒ 砂 ⇒ 土」と変化しているのではないか? (「まばらにまだらに『杳子』を読む(07)」)
*杳子がとつぜん「ヨウコ」という具合に表記されるのは、いったいどういうことか? (「まばらにまだらに『杳子』を読む(09)」)
*なんで、杳子にとって「石」は、ただの「石」ではなくて「石ころ」なのか? (「まばらにまだらに『杳子』を読む(09)」)
*この作品全体をとおしての視点的人物である「彼」の名前のイニシャルがSなのは、なぜか? (「まばらにまだらに『杳子』を読む(10)」)
*この作品で「上」「下」「左」「右」、とくに「左」「右」という文字がが頻出するが、これはいったいどういうことなのか? (「まばらにまだらに『杳子』を読む(11)」)
*Sは、8、∞、∽、§ ではないか? (「まばらにまだらに『杳子』を読む(11)」)
*杳子の名前は、じつは「陽子」ではないか? (「まばらにまだらに『杳子』を読む(11)」)
*
いまになって、あたらめて自分の見立てた「謎」を読んでみると、吹き出しそうになるものがあります。でも、その見立てをしていたときには、それなりに本気だったのです。
正気かどうかは分かりませんが(そんなこと本人に分かりますか?)、本気だったことは確かです。連想が高じた妄想癖があるという自覚もあります、いまのところは。
見立て倒れ
結論から言いますと、上に並べたどの謎解きも失敗に終わっています。見立てが外れて計画倒れ――。そもそも謎解きを構成するのに必要な条件を満たしていないからです。
ようするに見立て倒れ。
謎があるにちがいないという見立てに合わない細部が必ずあって、謎解きをするどころか、その謎解きの前提そのものが、成立しないという結果になっているのです。
私は謎解きが苦手なのです。
そのくせ、つい手を出すのですから、困ったものです。
ヨウコとS
たとえば、いまでも「ヨウコ」と「S」にこだわっています、性懲りもなく――。私は凝り性なのです。つまり、懲り性になるべきなのです。
*
詳しいこじつけは、「まばらにまだらに『杳子』を読む(11)」をご覧になっていただきたいのですが、以下の引用箇所にある「陽」が「杳子=ヨウコ」を指し、「樹」がSを指していると私は妄想していたわけです。
赤みをました秋の陽が痩せ細った樹の上へ沈もうとしているところだった。
(『杳子』p.170『杳子・妻隠』新潮文庫所収)
*「赤みをました」「陽」:「赤」は古井の作品で特別な意味をもつ、とりわけ女性に形容されることの多い文字。しかも「ヨウ」と読める。
*「痩せ細った樹」:古井の作品で「なにげなく」振られているルビには要注意。「見て見て」という注目印。この小説で、Sは痩せた男性として描かれている。
*陽(日)が樹(木)の上へ沈もうとしているところ:まもなく陽(日)が樹(木)の下に沈む。
日 ⇒ 木
木 ⇒ 日
つまり、杳。この文字は、この作品のタイトルにあり、この作品の冒頭の文字でもあるのです。最後の一文にも見えます。
「だから、何?」と言われれば、「さあ、何なんでしょう?」くらいしか返す言葉が浮かばないのですが――。
*
なんで杳子が陽子ではないかと思うかなのですが、この小説でSを視点的人物にして「杳子」という表記が出てくるのとは別に、「杳子」が文字として出てくるのは杳子の手紙の署名でしかないわけです(p.117)。
とつぜん「ヨウコ」という表記が出てくるのは、Sが初めて杳子の家に電話をしたときで、電話に出た杳子の姉とSとの会話において、二人が杳子を指すさいに「ヨウコ」と書かれています(p.134)。以後、杳子の姉が杳子を呼ぶときにも「ヨウコ」と表記されます(p.141、p.153、p.157)。
【※微妙なのは「あなたもヨウコをお好きなのでしょう」(p.152)という姉がSに言う言葉なのですが……。この返事としてSが間接的な I love you. という意思表明(告白)をする唯一の場面ですから、この表記はいかにも意味深に感じられます。】
このことから、杳子は何らかの心理的な抵抗があって自分の名前の表記を嫌い、同音の別の漢字(たとえば、杳とは正反対の意味をもつ陽)を当てた表記を勝手に個人的に(あるいは「わがまま」から家でも)もちいているのではないかという気がします。
赤みをました秋の陽が痩せ細った樹の上へ沈もうとしているところだった。(p.170)
上の引用箇所から、その「ヨウコ」が「陽子」ではないかと、私は勝手に(あるいはわがままから)考えたという次第です。
*陽(日)が樹(木)の上へ沈もうとしているところ:まもなく陽(日)が樹(木)の下に沈む。
日 ⇒ 木
木 ⇒ 日
つまり、杳。
というふうに。
*
以上が、「ヨウコ」をめぐっての、これまでの私の見立て、言い換えると安易な連想からの妄想です。
「S」についても、「まばらにまだらに『杳子』を読む(11)」で血迷ったことを書き連ねています。
それにしても、
なんで、「S」が「樹」なのか?
迷走した見立てが、そこで立ち往生してしまったわけです。
見立ての立ち往生――。
*
立ち往生したところで懲りて断念すればいいのですが、懲りない私はめげずに妄想をつづけます。
「立つ」と言えば、Sは「立つ」人物、杳子は「坐っている」とか「横になっている」ほうが落ち着くらしい人物として描かれています。
ということは、
Sは stand ではないでしょうか?――「立つ・立てる」です。
「立つ・立てる」だからというわけではありませんが、性懲りもなく、またもや見立てをしたくなりました。
「樹」という漢字には、「き・たてる(たつ)・うえる(うう)」という意味があり、人名では「いつき・き・しげ・たつ・たつき・な・みき・むら」と読ませる場合があるようです(漢字源・学研より)。「たつる・たかし」という人名も見聞きした覚えがあります。
しかも、古井先生の専門だったドイツ語では、「立つ」は stehen だった(さらに言い訳しますと、古井先生は、エッセイでドイツ語の単語を出すと、それに相当する英語の単語で補足説明する癖があるのです)。
でも、「坐る・座る・sit」も ドイツとでは sitzen というふうに「S」だったりしますが、ま、いっか――。 テキトーなのです。
「明ける」、「赤」
話は逸れますが、古井由吉の小説には表記上の特徴があります。
すると杳子はいきなり目をあけて、路地の気配を窺う猫のような目つきになったかと思うと、さっと店の扉を押しあけて入ってきた。
(古井由吉『杳子』(『杳子・妻隠』所収)新潮文庫・p.47・太文字は引用者による・以下同様)
十分と待たせずに杳子は喫茶店の扉をおずおずと押し開けて入ってくる。(p.83)
それなのに、今では窓を残らず明けて、部屋の境いのドアも明けて、吹き抜けの中に横になっていても、肌がじっとり汗ばんでくる。(p.105)
以下は『妻隠』からの引用です。
寿夫は右へ一歩動いて老婆のために道を明けてやった。そして相変わらず渋面を守っていた。
(古井由吉『妻隠』(『杳子・妻隠』所収)新潮文庫・p.174)
*
古井由吉は、作家活動の初期から晩年にいたるまで、「開ける」と「空ける」を書き分ける現在の標準的な表記だけでなく、そのどちらの場合にも「明ける」をよくもちいていました(「開ける」も、平仮名だけの「あける」もつかっていましたが少ない気がします)。
なお、こうした書き分けない表記は、かつては広く行われていた表記だったようです。川端康成や徳田秋声や夏目漱石の小説でも見た記憶があります。
また、古井は「明・日・月・赤・白」という文字を、おそらく偏愛した書き手でもありました。このことについては、拙文「「日、月、白、明」、そして「見、目、耳、自」が」に詳しく書いてあります。
*
表記のばらつきや、ある特定の文字が頻出する場合に、私はなぜかとは考えません。その表記を楽しむだけです。
というのは、建前でして、じつはこだわります。
*
「明ける」や「明・赤」に対する古井の偏愛(私がそう思っているだけですけど)には、強く興味を惹かれます。
「あける・明ける」の語源の説明には、たとえば「アカ(明・赤)と同源で、明るくなる意)(広辞苑)とありますが、それを読むたびに、思わずうなずき、考えこむ自分がいます。
なぜかと言いますと、『杳子』の最終章である「八」における、「赤」と「白」の氾濫(「白」はこの小説では杳子の顔を形容するさいに頻用される文字です)と、最後の最後のほうになってくり返される「赤」が気になっているからです。
これは、いったいどういうことなのか、と。
そんな私は、「赤の誘惑」というか赤の魅惑に身をまかせます。詳細は、拙文「異、違、移」をお読みください。
*
「あける」をめぐる表記のぶれは不思議と言えば不思議ですが、おそらく解はないと思うので、謎解きはしません。
ただ、そのなかの「明ける」という表記と、「赤」という文字が出てくるたびに、気になってその前後をくり返し読む癖があります。
「明ける」と表記されているときには、なにか特別の意味があるように感じることもあるし、感じないときもあります。私はそういうふうに揺れることが好きなのかもしれません。
右往左往
昨夜、お風呂に入る前に、Sは stand というよりも名字ではないか、Sで始まる名字はないだろうかと考えていて、「左」で始まる名字をネットで検索してみました。
なんで「左」なのかと言いますと、次のような理由があるからなのです。
*
『杳子』という作品では、杳子と「彼」(S)が並ぶときには、ほぼいつも杳子が「右」で、Sは「左」にいるのです。二人の定位置と言えます(「まばらにまだらに『杳子』を読む(11)」)。
でも、左・右は left・right(ドイツ語では links・rechts )なので困っていたのですが、とつぜん左近司祥子(さこんじさちこ)という、大学時代に哲学を教えていただいた先生のお名前を思いだしたのです。
そんなわけで、漢字の「左」で始まって、しかもローマ字で「S」で始まる名字をネット検索してみました。
「左近司・さこんじ」のほかに、「左近・さこん」、「左近田・さこんだ」、「左右田・そうだ」という名字がありました。
その続きを湯船のなかで考えていたということなのです。ややこしくて、ごめんなさい(私は出来事を時系列に整理して述べるのが苦手なのです)。
とにかく、右往左往していたのです。ああでもないこうでもない、ああだこうだ、と。
*
そんなわけで、お風呂で湯船に浸かりながら、ふと浮かんだことがあります。
Sは「左近田(さこんだ)」ではないだろうか? と。
で、結論から言いますと、Sの氏名は、左近田樹(さこんだたてる)ではないかと思うに至りました。
stand、立てる
アナグラムなのです。アナグラムごっこというか、アナグラム地獄に落ちて右往左往していました。
で、結論をお話しします。
*
左近田樹(さこんだたてる)
SAKONDA TATERU
STAND AKERU 字余り OAT
立てる 明ける
*
左近田樹(さこんだたてる)
SAKONDA TATERU
OSAA ARUKEN 字余り DTT
O沢 歩けん
*
言い訳というか、どういうふうに、こじつけたか(妄想したか)を白状いたします。片っ端から列挙していきます。
*
この作品で、「S」以外にアルファベット、つまり、ローマ字のイニシャルが出てくるところがあります。
彼は午後の一時頃、K岳の頂上から西の空に黒雲のひろがりを認めて、追い立てられるような気持ちで尾根を下り、尾根の途中から谷に入ってきた。道はまずO沢にむかってまっすぐに下り、それから沢にそって陰気な灌木の間を下るともなく続き、一時間半ほどしてようやく谷底に降り着いた。(p.8)
そのうちの一人は途中で滝から落ちたあと、無意識のまま二日かかってこの出会いまで降りてきて、O谷をふらついているところを、通りがかりのパーティーに保護された。(p.10)
*
杳子からSへの手紙にある文句です。
――いつまでも横になっているわけにもいきませんので、そろそろ立って暮らすよう心がけています。椅子にきちんと腰をかけて、午後の暑い時間を過ごしていると、首から上を薄い空気の中へ差し入れているみたいな気持ちがします。人間とは立って歩くもの、横になってばかりいては、病人か獣です。夕方になって陽ざしが柔らかくなると、家を出て近所を散歩します。(p.117)
似たフレーズは、「一」にも出てきます。
人間であるということは、立って歩くことなんだなあ、と杳子は思ったという。(p.21)
*
最終章「八」で「明ける」が出てくるところです。
階段をのぼりきったところで左手の扉をゆっくり明けると、薄暗がりの中から、階下よりも濃密なにおいが彼の顔を柔らかくなぜた。(p.153)
*
杳子・陽子・明ける・赤・右・西空――日 ⇒ 木
S・立てる・樹・左 ――木 ⇒ 日
(※「右」には「西」という意味もあるそうなのです。漢字源・学研より。)
*
『杳子・妻隠』をお持ちの方は、ぜひラストのp.169とp.170をご覧ください。
軀を起こすと、杳子は髪をなぜつけながら窓辺へ行ってカーテンを細く開き、いつのまにか西空にひろがった赤い光の中に立った。
「明日、病院に行きます。入院しなくても済みそう。そのつもりになれば、健康になるなんて簡単なことよ。でも、薬を呑まされるのは、口惜くやしいわ……」
そう嘆いて、杳子は赤い光の中へ目を凝らした。彼はそばに行って右腕で杳子を包んで、杳子にならって表の景色を見つめた。家々の間をひとすじに遠ざかる細い道のむこうで、赤みをました秋の陽が痩せ細った樹の上へ沈もうとしているところだった。
(pp.169-170)
*
「だから、何?」と言われれば、「さあ、何なんでしょう?」くらいしか返す言葉が浮かばないのですが――。
*
あえて、何を言いたいのかを申しますと、「(いつも杳子の左にいて)Sは杳子を立てる」、「杳子は立って(Sに立ててもらって)人間らしくなる(明ける)」「落ちていく杳子がSと出会って(谷底・西空)、二人は重なり(日没)、これからは杳子がSから離れていく余韻を残して作品は終わる」という感じ……。
ぜんぜん説得力がないですね。まさに見立て倒れ。右往左往した結果が支離滅裂。まったく収拾がついていない。私の人生にそっくり――。
とにもかくにも、
『杳子』は見立てで読める作品では断じてない。これは確かなようです。
『杳子』は、紋切り型の通念を宙吊りにする言葉の身振りに満ちた言語作品なのです。この小説に読みにくさがあるとすれば、理由はそこから来ていると思います。
私はこの作品の傍らで開いておくのにふさわしい文章として、「Ⅱ「怪物」の主題による変奏――ジル・ドゥルーズ『差違と反復』を読む」(蓮實重彦『フーコー・ドゥルーズ・デリダ』所収・河出文庫または講談社文芸文庫)を挙げたいです。
蓮實重彦の「ジル・ドゥルーズ論」には、抽象的な通念と言葉遣いに苛立ち嫌悪し、そうした言葉を宙吊りにしようとする言葉の身振りを感じます。
両者の言葉の身振りは遠く離れてながら、ともに振れている。そんな気がしてなりません。
【このあたりについては、拙文「振りまわされる(線状について・05)」で詳しく書いています。】
迷う権利
思えば、私はこんなことを書いていたのでした。
テーマを捏造して作品をさばいてみたり、図式化をして読解した気分になったところで、作品にはテーマや図式に抗う細部がかならずあります。そのことに意識的でありたいと思います。
(拙文「まばらにまだらに『杳子』を読む(09)」より)
*
安易な連想による見立てに走りがちな自分への戒めとして、以下の蓮實重彦先生の文も、これまでいくつかの記事に引用してきました。
8を横にすれば無限の符牒としての ∞ が得られると指摘してみせたところで、しかし「作品」としての『覗く人』は8への還元を素直にうけ入れたりはしないし、まただいいち、8の主題の反復は、はじめからこれみよがしに配置されていて、隠された構造というより、むしろ表層に露呈した可視的な細部であって、視線を表皮へとつなぎとめる機能しか果たしていないのだ。8を触媒として結ばれゆく細部は、密かな連繋を生きるというよりあからさまな類似を誇示しているのであり、だから『覗く人』で8に着目し、無限を語ることは、迷う権利を放棄することにほかならないのである。
(「アラン・ロブ=グリエ――テマティスムの廃墟」(蓮實重彦著『批評 あるいは仮死の祭典』せりか書房所収)p.90・太文字は引用者による)
*
これまでの自分のおこないを振りかえると、これからも私が「右往左往する権利」を行使しつづけることは間違いなさそうです。
見立てをしたり、謎解きをする――こういう楽しいことはやめられそうもありません。たとえ、失敗ばかりしても、です。
私の失敗談、みなさんのご参考になれば幸いです。
#読書感想文 #この経験に学べ #古井由吉 #杳子 #蓮實重彦 #アラン・ロブ =グリエ #左近司祥子 #名前 #文字 #漢字 #謎解き #アナグラム #ミステリー #失敗談
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
