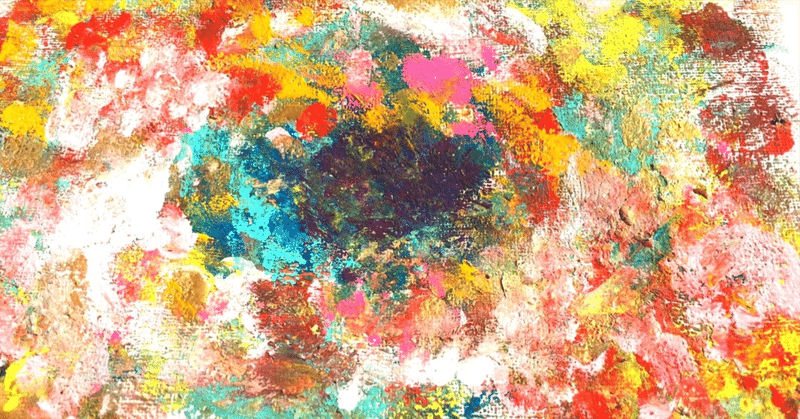
祈りのカクテル.2
《祈りのカクテル》草稿
1998年12月9日 第一稿完成 大坪朱莉
2001年3月4日 改編 窪田敏行
私は作家としての活動を始めてから、一つ軸を持つことにしていた。
「自分が欲している言葉を紡いでいくこと」
これが私の作家としての軸になっているものだ。
何をもって作品を『完成した』とするのか、作品制作に迷ったとき、どこを目指して書き進めていくのか、終わりのない創作活動には一読者に過ぎなかった頃には想像もつかないような覚悟と度胸が必要とされた。
私は自分が求めている言葉を、自分の手で紡いでいく。
他者が紡いだ作品や教訓を受け、自身に影響を与えることはある。私はこれまでに何度も、沢山の作品に助けられてきた。しかし、どこまでいってもそれは、他者の言葉なのだ。
気に入った本を何度も読み返す読書スタイルの私は、『自分自身の言葉によって紡がれた物語が欲しい』と思うようになった。
自分の言葉であれば、素直に反省も出来れば聞く気にもなる。一度作ってしまえば、何度も読み返して都度過去の自分にアクセスできる。私は、自身の『聖書小説』に当たるものを作りたいと思うようになった。
「小説を書いています」というと、周囲の人達は当然のことのように「どのジャンルの作品を書いているのか」「どの文学賞に応募するのか(作家としての地位が築かれてからはどの文学賞を取ったのか)」など、沢山のことを聞かれる。これは至極真っ当な質問だと思う。
しかし、はっきり言って私は自身が書いた作品がどのジャンルの作品なのか、どういう文学賞を取った作品なのかには、興味がない。
人は他人に対してあまり興味がないので社交辞令程度に聞くことがそれ以外にないというのが本当のところだと思うが、作家としての活動歴が短かったとき、私はいつもこの質問にどう答えるのか迷っていた。
私は、どこか特定のジャンルに当てはまるような作品を書こうとは思っていない。むしろ、どのジャンルの作品であると分類されることに、少なくない抵抗を感じている。
人間社会の複雑怪奇を鮮明に描き出すことが出来たとしたら、どこか一つのジャンルに作品を押し込んで評価することなど、出来はしないと私は思う。
不気味で恐ろしい感覚を与える。読んでいて読者の奥深くに眠っていたものが表に引きずり出される。それが文豪が描く作品だと私は思っている。
私は、小説家ではなく文豪になりたかった。
自身が書いた作品が結果的にどのような評価を受けるのかは私にはコントロールできない。だから、私は自分が欲している言葉を自分のために紡いでいく。その言葉が、本当に自身の奥深くから湧き上がってきたもので、自身の背中を押してくれたり、傷を癒してくれるようなものになっていたのであれば、結果的にたくさんの人達が読んでも良い影響を与えられるものになっているだろう。
私はそう考えることで自身の創作活動を潤滑に進めることが出来た。強いて言えば、「私が書いているのは『聖書小説』です」というくらいだろう。
筆が止まったことは一度もない。
私は小説に限らず、エッセイや詩、論説文など思いついたことは何でも書くタイプの作家だ。心の底から自由を愛しているし、自身の知的好奇心を満たし続けてくれるものでないと、何事も続かない。だから、作品を書くという作業そのものにさえ、変化を必要とする。
『渓谷の川辺にて』
私が筆を執ってから最初に完成させた作品だ。
人の『寂しい』という感情がいかに人を飲み込んでいくのか、描いたつもりだ。私はどうしようもなく、書かざるを得ないような状況に追い込まれていた。
基本的に、芸術家というものは、積極的な選択を取ってなるものではない。そうせざるを得なかったどうしようもない人達が、自身の痛みを排斥するようにして活動する場所だ。
私は、どうしても書かざるを得ない状況に追い込まれていた。
どうしても自身の中で向き合わなければならないテーマについて、深く考える『空白の時間』が、訪れたのだ。
第一の作品を完成させたことを機に、私は物事を健康的に深く考える術を手にした。淵の長い渓谷の暗闇に放り込まれることなく、命綱をつけ、遠くまで見渡せるライトを装着し、一つ一つ手元、足元を確認しながら暗闇の中へと降りていくことが出来るようになったのだ。
私は、そこから一度も止まることなく作品を書き続けている。書かなければならない。そう思わされている。
私が書いているというよりは、勝手に手が動いていて、私はそれを『読んでいる』という実感がある。私は著者というよりは、一番の読者だ。
そういう気がする。
続き
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
