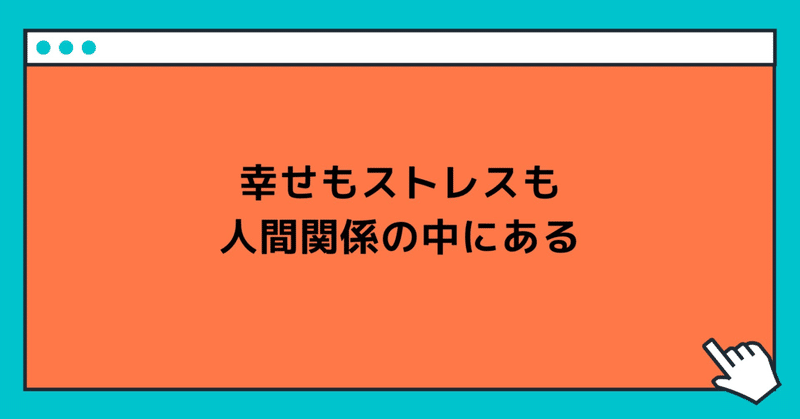
幸せもストレスも人間関係の中にある
人が生きていく上で
完全に人との関わりを
断つことはできないし
故に人とのコミュニケーションや
人との比較によって
劣等感を感じたり
思い通りにいかないことで
イライラすることは多々ある。
特に職場の人間関係が
職場における
最も大きなストレス源になっていると
言われていますし
時代と共に
人間関係が徐々に希薄になっているのも
自然なことなのかもしれません。
が
一方で「嫌われる勇気」の
元になっている
アドラー心理学では
幸せも人間関係の中にある
と言われている。
人生は、仲間に関心を持ち、全体の一部であり、人類の幸福に貢献することである
人との繋がりこそが
幸福を感じるために
必須なことでもあると言われています。
人間は人との共存によって
繁栄してきた生き物と言われていますし
個人で感じる喜びも
あるのでしょうが
どこかでその喜びを
他者と分かち合いたい
という思いも湧いてくるし
でもまた一方で
他人にはどうせ理解されない
他人から否定されたくない
他人から横取りされたくない
という思いもある。
私自身も
人との関わり方に
喜びを感じる人なのか
それとも
ストレスを感じる人なのか
考えていた時期が長くあって
今はどう受け止めているか
というお話をしたいと思います。
◯白か黒で考えない
何事においてもそうなんですけど
白か黒か
ゼロかヒャクか
で考えないで
グラデーション的に考えた方が良いと思います。
結論
完全に孤独を求める必要もないし
逆に
常に多くの人と関わって
1人の時間を作らない
という必要もない。
孤独と他人との関わりを
30対70
くらいの割合が心地良い人もいるし
孤独が90%くらい
あっても良い
と考える人がいても良い。
ただ
完全に孤独になる必要もないし
その逆も然り
ということだと思います。
結構この感覚が無い人が
少なくなくて
自分は寂しがりやだから
常に誰かといたい
とか
1人が楽だから
常に1人が良い
という判断をしがちなんですよね。
極端に偏った判断や行動を
取りがち。
孤独を好む人も
多少の人間関係は
確保していた方が良いし
誰かと常に一緒にいたいような人も
時には1人になって
色々と考える時間も大事である
ということです。
◯「他人」ではなく「仲間」であると捉える
アドラー心理学的な考え方ですが
自分達は自分のメリットを
求めるのではなく
周りにいる人たちを
「他人」と捉えるのではなく
「仲間」であると捉えることで
対人関係において
自分の居場所が作られて
その仲間たちのために
他者貢献しようと思えるようになる。
それを共同体感覚と
呼ぶのですが
この共同体感覚を
感じられるようになることで
幸福感を抱くことができる
と言われています。
会社など
立場によって
力関係が違うこともありますが
それでも目の前にいる人に対して
「敵」ではなく「仲間」
と思えるかどうか。
「仲間」と思うことによって
何かをしてあげたのに
見返りがない
とか
損をした
という利己的な判断をしなくなる。
孤独をやたら望む人は
他人に対して
赤の他人
と捉えたり
敵である
敵になり得るかもしれない
という意識が強い可能性があります。
横の関係性を意識して
他者を信頼することができると
人間関係における
ストレスを減らせるかもしれません😌
--------------------
【お話聞きサービス】
オンラインで悩みや相談
雑談などなんでもOKです🙆♂️
友人や家族だからこそ話せないこともあると思います。
精神科看護師の私がしっかりと悩みを聴きますので
各種SNSのDMなどから連絡下さい✨
note
https://note.com/ray_mentalnote
Instagram
https://www.instagram.com/ray_mentalnurse/
Twitter
https://mobile.twitter.com/ray_mentalnurse
LINE
https://lin.ee/aWqzomC
※企業、学校などで
メンタルヘルスについて
講演する人をお探しであれば
DMからご連絡ください😌✨
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
サポートしていただけると相当喜びます😭
