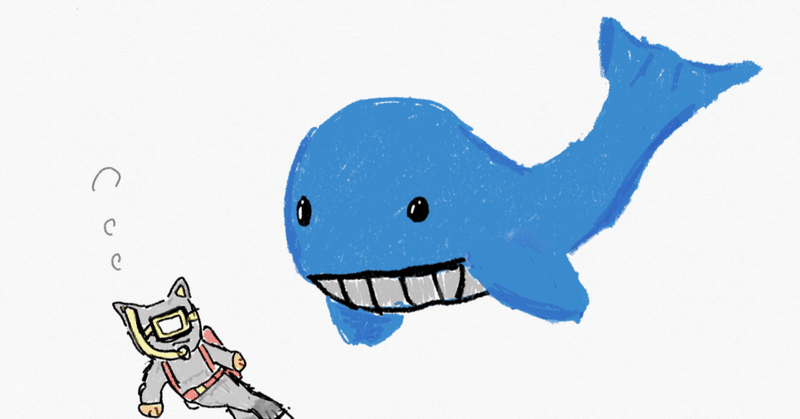
主体的で対話的な深い学びをしてかなきゃ
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
「何のためにこの事業をしているんですか?」
そんなクリティカルとも言えるような質問が、これからは、この世の中でどんどん飛び交うようになってくるでしょう。
いきなりこんな預言者めいたことを言い始めて「あ、ついにおかしくなったか」と思った方はご名答かもしれませんが、僕がおかしいのは今に始まったことでは無いような気もしているので当たらずとも遠からじ的なところでしょうか。
実は、冒頭の言葉は“探求型インターンシップ”に臨む“ごく普通”の県立高校の学生さん達がほぼ必ず企業経営者に対して投げかけてくる定番の質問項目のうちの一つだったりしているそうです。
そんな話を聞かせてもらう機会があって、僕も仲間も「いよいよ、こういう段階に来たんだなぁ」と感慨深くもありつつ、危機感のようなモノも覚えました。
“感慨深さ”については、特に“ごく普通”の県立高校の学生さん達から“こういう質問”が働く大人たちに向けて投げかけられるような“対話的な姿勢”が若者の中ではとても当たり前になってきているということについてです。
学習指導要領の中の「主体的・対話的な深い学び」が、しっかり高校生にも根付いていて、冒頭の質問のように「そもそもの目的を問う」ということをしっかり考えるということが当然の姿勢になっているのがハッキリと見て取れるわけです。ということは、これからの若者世代が世の中の中心になっていった時には、多くの働く人たちが「そもそもの目的を問う」ということが普遍的になっていく可能性が高いわけです。
そうなると、今現在もこれまでも僕や仲間が遭遇してきたような自らのキャリアについて“問い”をもたずに何となくや一般論に流されてしまう“キャリア迷子”が少なくなっていくということなのかもしれないことに“感慨深さ”を感じています。
それと同時に在る“危機感”は、あと5~6年後には「そもそもを問う」若者たちが全員社会に出て働くことになるわけですが、その若者達に選ばれて入ってきてもらう様々な組織が果たして「そもぞもを問う」若者達の投げかける“問い”について、考えて、答えを返すことができるのかどうか?ということに“危機感”を覚えています。
もちろん、“経営理念”を掲げている企業がたくさんあることも知っていますし、“ミッション・ビジョン・バリュー・パーパス”を掲げている企業がたくさんあることも知っています。そして、それらの企業の経営者であれば、冒頭のような「なんのためにこの事業をしているのか?」に答えることは、きっと出来るんだろうとは思っています。
でも、そんな若者達が組織に入ってきて実際に働くのは、いつだって必ず“現場”です。
そして、その“現場”でその若者達が一緒に働くことになる先輩や上司にも当然の如く「そもそもの問い」が投げかけられてくるわけです。
その時に、「なんのためにこの仕事をしているんですか?」という“問い”に対して“現場”にいる人がみんな、考えて、答えを返すことができるのかどうか。
もちろん、「なにをくだらねーこと言ってんだよ。つべこべ言ってねーで、黙って手を動かせ!」というように、先輩や上司が“今までの時代”のように返答したって別にそれはそれでいいのかもしれません。
ただ、そういう“対話的ではない対応”が現場で行われてしまうのであれば、数多ある組織の中からせっかくそこを選んで入ってきてくれた若者達は、わざわざそんな“対話的ではない組織の実態”を知ってまで残ってくれるとは思えません。
もっと言えば、“対話的な若者”を受け入れることができる“対話的な組織”でなければ本当の意味で“選ばれる組織”になることはもうできなくなるんじゃないだろうか。そういう“危機感”を、かなり強めに覚えています。
「これは恐らく、僕の妄想ではないんだろうな」
そんな強い実感が、この国の一地方である群馬県内の若者とほんの少し接するだけでもヒシヒシと感じられています。
既に2027年問題として言われている若者世代の人口減がすぐにやってくることは明白ですし、2040年問題も言われています。そして、これは必ずやってくるモノですし、その時も案外とすぐにやってきます。
5~6年後には「主体的・対話的で深い学び」を深く内面化した若者達がほぼ全員社会に出てくることは確実です。その時はきっとまだ若者達は“少数派”ですが、それ以降はずっと“そういう若者”が社会に出続けてくることになりますので、数年間であっという間に増えていき、そこから10年後には圧倒的“多数派”であり、且つ、世の中の“主流派”になっていきます。
そしてその時には、労働人口が今より2割減っていると言われている2040年がやってきています。
労働人口が2割減るのであれば、とっても単純に考えても「2割以上の企業が減る。しかも、中小企業から確実に減っていく」のは間違いありません。
となれば、そんな恐ろしい波に飲み込まれないためにできることがあるとすれば、その中の一つは確実にこれです。
「主体的・対話的で深い学びを、今の大人が、身に付けるために変化すること」
これをしておかないと、2040年よりも先を生き延びていくことは出来ないだろうなということが、結構ハッキリと見えてきたなぁと感じています。
そのためにも、冒頭のような“問い”を持って、自らに、お互いに、問いかけて常に考えていく必要があるんじゃないかと思っています。
ここ最近よく売れている本や話題になっている作品にもこういう「そもそもの問い」が題名に入っていたりするのは、恐らく“このこと”に何となく気が付いている人たちが多い証拠なのかもしれません。
『なぜ僕らは働くのか』や『君たちはどう生きるか』なんかはその典型なのかもしれません。
「そもそもの問い」を常に持って考え続ける。
そして、自分自身が身を置いている日々の“現場”で仕事をする中で、「何のためにこの仕事をやっているのか?」を考え続け、答えを出し続けながら、成果を上げる。
それが行われているのであれば、いつ誰に“問い”を向けられたとしてもごく当たり前のように答えてあげればいいだけですし、それを投げかけてきた若者達にも同じように“問い”を向けてあげればいいだけなのかもしれません。
そうやって、主体的に、そして対話的に、一緒に働く人達と深い学び合いをしていけば、その時代の若者とだろうがその時代のおっさんおばさんとだろうが、みんなが共に働くことができるんだろうと思っています。
既にこの“社会”を先に生きている大人の在り方次第で、この先の時代に待ち構えていると言われている問題をそこまで“問題”にせずに生きていけるんじゃないだろうかと考えている僕は、自分でも楽観的なのか悲観的なのか、時々迷ってしまいます。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
