
なぜ僕は大学3年生を1年間休学して、日本各地の農家さんや漁師さんのところで修行させてもらう旅に出たのか。|生きる行脚#0@田辺大貴
※ここでは休学する「前」に自分が思っていたこととか、当時の感情をできるかぎり思い出して書きました。「あのときとは変わったなぁ」って自分でも思うこともあれば、「前も今もそんなに変わってないな」って思うこともあります。あくまでも「当時の」僕が思っていたこととして捉え、温かい目で読んでいただけたらと思います。
大学入学と、「逆」学歴コンプレックス。
いきなりだけど、大学入学した当初、僕には学歴コンプレックスがあった。「学歴コンプレックス」っていうのは、
学歴コンプレックス:多くの場合、学歴が他人と比べて低いことを過剰に気にして卑屈になったり高学歴の人をひがんでしまうこと。
ってことだ。だけど、僕の場合は上に挙げたような学歴コンプレックスとはちょっと違った、特殊なものだった。
時は高校3年生の受験期ら辺までさかのぼる。大学受験においては、後期試験では前期試験よりもレベルを下げた大学を受験するのが一般的だけど、僕は後期も前期と同じ大学の、同じ学部を受験することにした。僕の学力が後期でその大学のその学部を受験するのに値しないことを十二分に知っている担任の先生からは、前期と後期で志望校を変えないことを伝えたとき、「ほんとにそれでいいんだな? 今年大学に行くのは厳しくなるぞ?」と脅されるように念を押された。そこで「見てろよこの野郎おぉぉ!!!」と唇を噛み締めるような思いをさせられた僕は後期試験の面接に全てを懸けて死に物狂いで準備をして臨んで、運良くその年の受験倍率が低かったこともあってケツから3番目(もしかすると2番目だったかもしれない。)という成績でどうにか滑り込み合格してしまった。
大学入学後、同じ年に入学した子たちと受験の話になって「一応後期試験で合格したけど…」みたいに言うと「すごいね」とか「優秀だね」みたいなリアクションを一時はされるけど、「前期試験でも受験したけど落ちたんだよね…」って説明すると「あぁ…。そうだったのね…」みたいなビミョーな反応をされることが多くて、その度に「自分はここにいちゃいけないんだよな…。ここに僕の居場所はないんだよな…」って思った。(今思えば、自分が変に意識して思い込んでただけだったと思う。)
入学してからしばらくは、前期試験で落ちて本来いるはずのない自分が、後期試験で運良く合格してしまって大学にいることに後ろめたさがあった。学力の見合ってない自分がこの大学にいるのだと思うと、嫌で嫌でしょうがなかった。
まさに、学歴が低いことを嘆く一般的な学歴コンプレックスとは「逆」で、自分の学力が大学のレベルに及んでいないことを嘆く類のコンプレックスで、コンプレックス以外のなんでもなかった。
そして僕は、この後ろめたさとか「いづらさ」といった負の感情を消すためだけに、なんのためになるかわからない教養科目とか入門系の基礎的な科目を、目的もなくただ数字とか成績を求めて必要以上に推敲に推敲を重ねたレポートを書いたり、試験に向けた勉強(果たしてあれが勉強と言えるかはだいぶ疑わしい。)をした。(※今に活きていることもあるから、無駄なことだったとは思ってない。)
そんななんのためになるかわからないような教養とか入門系の基礎的な授業をとっていた1年生の頃の成績はそれなりに良い方で、大学から支給される奨学金をもらうことができた。
そういう目に見える形があるものをもらえたから自分がある程度がんばったのかなとは思えたし、高校生のときは成績赤点(定期試験が赤点+提出物を全く出さない ⇒ 高校生なのに単位がとれるか怪しい、みたいな状態。)をとって親が学校に呼び出される(「親を召喚される」と学生の間では言われ、卒業とか次の学年に進むのが危ぶまれる事態。)くらいだったから親が喜んでくれたのもよかったんだけど、奨学金なんてもらっても僕は嬉しくなくて、素直に喜べなかった。
「あれ?思ってたのとなんか違うぞ?」
って感じで、なんというか、からっぽだった。良い成績をとったら僕の心は満たされるはずだと思っていたのに、嬉しくない。SNSを眺めていると大学に行かずに消防士とか自衛官になった友達の様子が見れたりして、
「この人たちはもう社会に出て世の中の役に立つようなことをしてるのに、僕は勉強だけして、大学生ってだけで周りからちやほやしてもらって。良い成績なんてとっても誰の役にも立ってないじゃん…。学んだ知識を世の中に還元なんてできないじゃん…。自分のことさえ満足させれてないけど、こんなのただの自己満足とかエゴみたいなもんじゃん…」
と思った。
そして、「あの数字とか成績をひたすら追ってたあの時間は、あれは、いったいなんだったんだ…」っていう深い虚無感だけが残った。
感染症をきっかけに大学を出て、外の世界の楽しさに触れるようになる。
大学1年生が終わる頃あたりにもう間もなく2年が経とうとしてる今でも流行っている例の感染症が出てきて、2年生からは授業をオンラインで受けるようになった。そうなると大学に行く必要がなくなったり、試験もオンラインで受けるようになって試験勉強に時間を費やす必要がなくなったりして、時間に余裕ができるようになった。
そこで、「せっかく農学部にいるのに野菜をどうやって作るとかあんまり農業のこと知らないなー。」となんとなく思って2年生の後半が始まるほんの少し前あたりから、大学近くの畑の一部を借りて家庭菜園みたいな感で野菜を作っている学生の集まりみたいなところに顔を出してみることにした。
すると、いろんなところに足を運んでいるアクティブでおもしろい後輩たち(休学したから今は同級生だけど。)との出会いがあって、いろんなことに誘ってもらって農家さんのところに行って一緒に作業させてもらったり、集落の行事とか活動に参加させてもらったり、有機農業のマルシェのスタッフをやらせてもらったり、地域おこし協力隊の方のところに遊びに行かせてもらったりするようになって、大学っていうある種閉じられたコミュニティから出て、大学とは関係のない世界に触れるようになった。
そこで大学にだけいたら出会わなかったであろういろんな職業とか幅広い年齢の人たちと出会って、「この職業は実際はこういう仕事をしていて、こんな感じだよ。」みたいなお仕事の話とか「自分が学生のときはこんな感じだったなぁ。」みたいな学生時代の話を聞いたり、実際に畑に行って農家さんと話しながら作業させてもらっていると「えっ⁉そうなの⁉」みたいな発見があって新鮮で、オンライン授業で画面越しに難しい専門用語だらけの理論の話とか、「なにそれ…?」って思うような化学物質の動態とか化学反応の話を聞いているときよりも自分の知らなかった世界が拓かれていくような感覚があってすごくワクワクしたし、おもしろかったし、楽しかったし、嬉しかった。


事情を知らない人が見たら、ただのヤバいやつにしか見えないと思う。
自分は何を学んでるんだろう…。本当に学びたいことって…。
2年生の後半からは、専門的な内容の授業を受けるようになった。
だけど僕は、
「あぁ…、こういう感じか…。なんか想像してたのと違うんだよな…。」
って常に思いながら授業を受けていた。
実際にお米とか野菜をどう作るとか、「こういうことが起こったときにはこうするといい」みたいな実際の現場で実践できることを学べるのかと思ってたけど、授業で扱うのは全然そんな話じゃなくて、「病原菌が何『界』の何『属』に分類されて―。」とか「グルコースは最終的にピルビン酸まで代謝されてその過程でNADHとFADHが―。」みたいな感じで自分が想像してた「農業を学ぶ」って感覚はほとんどなくて、高校のときに勉強した生物学の延長線上にある話とか、専門的で細分化されたうちの一部分の話を聞いているような感じだった。
また実際に農家さんのところへ行って一緒に作業させてもらっても授業で聞いたような話を農家さんの口から直接聞くことはなくて(あったとしても植物の必須元素のうち特に重要とされるN(窒素)・P(リン)・K(カリウム)と、ぎりぎり『育種価』があるかないか、くらい。)、
「農学部にいるのに米とか野菜をどうやって作るとか、牛とか豚をどうやって育てるとか農家さんが日常的にやってることを全然知らないっておかしいと思うんだけどなぁ…」
みたいな大学で学ぶ「農学」と実際の「農業」とのズレというかギャップに違和感を感じていて、
「仮にちゃんと授業を聞いて良い成績がとれたとしても、それで社会に出て農家さんと関わるような仕事をしたときに役に立てんの…?」
とか、
「90分の授業をたったの15回聞いただけで学んだって言えんの? 卒業後は公務員とか農協の普及指導員になる人も多いみたいだけど、90分の授業をたった15回受けただけの自分が、何年っていう長い時間をかけて農業と向き合ってきた農家さんに言えることなんてほんとにあんの? 『普及指導員』なんて言ってるけど、教えて『もらう』側なんじゃないの?」
みたいなことを思っていた。
そして入学当初、僕は動物が好きっていう単純な理由で畜産系の分野に進むことを考えていた。だけど大して知りもせず、よく調べもしなかったくせに、なんとなくのイメージで「日本って畜産が盛んなイメージないからなぁ…。産業として勢いがないってことは就職先は限られるだろうし、そんなにいい就職先もないんだろうな…。」みたいなことを思って、3年生のときに決まる専攻を、興味なんてなかったのに大規模化とかICT化といった「今キテる!」みたいなイメージがあった米、野菜、果物といった植物系にしようとして、受けたいとも思っていない植物系の授業ばかりを渋々受けていた。
そんな風に、自分が興味のあることじゃなくて、就職とか世の中の動きを気にして「自分が好きじゃないのはわかってるけど、こっちの方がいいから…。」って自分に言い聞かせて、自分に嘘をついてというか無理をさせて勉強していた。だから、どうしても「これがほんとに学びたかったことなの?」みたいな気持ちにならざるをえなかった。
あとは、授業のときに自分の研究分野について熱心に語ってくださる先生もいたけど、研究の内容によっては「それって誰のための研究なの?」とか「誰が求めてんの?その技術。」とか、「それって、お金がほしい教授と、都合よく研究をしてもらいたい企業のただの癒着なんじゃないの?」って思うこともあって、もちろん、すべての研究に対して思っていたわけではないけど「研究ってなんのためにあんの?誰のためにあんの?」みたいに懐疑的に思っていたということもあった。(当時は自分の気が早かったし、まだ研究をしていなくて研究についてよくわかっていなかったことが大きかったと思う。)
なんとなく、「オチ」が予想できた。
オンライン授業と言っても先生 ➡ 学生という一方通行の授業だけでなく、グループディスカッションをしたりグループで課題に取り組まなければいけない授業もある。僕は、対面でもオンライン上でも一度も言葉を交わしていない人たちとメールやチャットだけでやり取りをしてグループで課題に取り組まなければいけない授業を受けていた。だけど、締め切りに間に合わせられなかったり他の人の担当分を引き受けなければならないことがあったりして、先生にも相談してみたけど「それをグループでうまくですね…」みたいな当たり前のことを言われて話ができず、なんとか単位はとれたものの「もっとうまくやる方法があったはずだよな…」っていうもどかしさと、「たくさんの時間を費やしたのに…。あの時間はなんだったんだ…。」っていうバカバカしさとかやるせなさを感じたことがあった。
「大学にはいろんな人がいる」ってよく聞くけど、僕にはあまりその感覚がない。確かに出身地とか高校くらいは色々だけど、違うのはその程度で僕がいる大学で大半を占めているのは日本人の学生だし、似たような学力や境遇、経歴の学生が集まってるし、基本的に大学生は授業とかサークルとかバイトとか固定された大学生特有のコミュニティのなかにいるから、実際のところそんなに「多様」って感じでもなくて、同じような感じというか、均されていて、実は狭いところなんじゃないかな、と僕は思う。
そしてこの「大学とか学部は違えど『大学を出て、似たような大学生活を送ってきて―』っていうバックグラウンドは多くの人が似たような感じで、篩(ふるい)にかけられて同じくらいの能力値、似たような背景とか境遇、経歴の人が集められる」っていう世の中の仕組みとそれによる狭さは社会に出て会社に勤めて働くようになっても多くが同じような感じだろうから、
「楽をしたい人がおいしい思いをして。そのツケは真面目にやってる人に回されて、最終的には真面目にやってる人がバカを見る。」
っていう構造が大きく変わることもないんだろうなってなんとなく察しがついて、「大学を卒業した後もまた同じような思いをすることになるのか…」って想像すると、単純に「嫌だな…。社会に出たくないな…」と思った。
トドメのダブルパンチ
11月中旬からの感染症第3波の拡大と例年にない大雪の影響で、1・2月に予定していた農家さん訪問や地域おこし協力隊の方が企画していたプログラムへの参加は、ものの見事に、すべてお流れとなった。
先に書いたように、学んでいることとか大学の環境にはもやもやを残しつつも、週末に農家さんのところに行ったりしてなんだかんだ大学の外に足を運んで自分の知らなかった世界に触れることができていたのが自分にとって唯一の救いだった。
だから、このタイミングでの感染症の拡大と大雪はまさしく僕にとって「トドメのダブルパンチ」となった。
それでも、もやもやは積もり続ける。
2年生も終盤となった12月、1月。3年生も近づいてそろそろインターンとか就活のことを考え始めないといけないタイミングを迎えようとしていた。
僕が在籍しているのは地方大学の農学部ということで、周りは公務員とか農協、地方銀行に就職する人が多いような気がする。
就職活動のときは「人のために」とか「地元のために」みたいな聞こえの良いことを並べるけど、実際のところ「安定が―。」とか「収入が―。」とか「福利厚生が―。」みたいな結局は「自分のこと」が根底にある気がして(もちろん幸せのかたちは人それぞれだから、それを否定したいってことではない。)、
「それでほんとに誰かの役に立てたり、何かが変わったり世の中が良くなったりするの?」
って僕は思っていたし、「自分のこと」のためにやりたくもないことを嫌そうな顔をして、「定時にならないかなー。早く帰りたいなー。」なんて思いながら渋々やって、死んだ魚みたいな目をしてこの元気がない世の中をつくってる大人になんてなりたくないな、っても思っていた。
そして僕には、特にこれと言って好きなこととか没頭できるようなことがない。だからそういう「自分のこと」を一番大事にしたいとはそんなに思わないし、世の中的に良いって言われたりとか肩書きがあるような職業に就くことも僕が求めてることじゃないな、と思った。僕は、「これだ!」って思えるような実感があることを渇望していた。
他にも、「大学に入ってまだ何も成し遂げていないというか『なにもしていない』のにこのまま4年で『ただ大学にいた』ってだけで卒業して、何も刻まれることのない空白の4年間を過ごして自分は納得できるの?」とか、「やりたいことをやってきたのか」って自分に問いかけたときに「やってきてない。やりたくもないことを歯を食いしばって、我慢して我慢して、ひたすら耐えながらやってきた。」ってしか言えないな、っていう感情もあった。
簡単に言えば、
「このまま『大学にいた』ってだけで終わってたまるか。」
って思って、流されていくことに抗いたくなったというか、待ったをかけたくなった。
だけど、時間は感染症には脇目も振らずに進み、就職や将来のことといった人生における大きな決断の締め切りは刻一刻と迫ってくる。
世の中的には「良い」とされることが僕のなかでは全然良くなくて、「世の流れなんてクソくらえだ。」って世間に対する反骨心を抱いてどうにかしたいと思いつつも、「じゃあなにがしたいのか」「自分はどうすればいいのか」っていうのはわからなかった。
自分はこの世の中の常識に盾突きたいと思いながらも、周りが渋々動き始めているのを見てやっぱりどこか心のなかで「自分もそうした方がいいんじゃないか…。」みたいな不安とか焦りの感情もあって、このやり場のないもやもやをどこにぶつければいいのかわからなかった。
ここまで、大学入学当初から2年生の後半あたりまでの感情とか当時考えていたことの動きを長々と綴ってきたけど、読んでくれている方には、総じて、「とにかくもやもやしてたんだな。」と思ってもらえればいいと思う。

2021年2月9日(火)、きっかけとなった47キャラバン。
学んでいることとか将来のことに対して悶々としながらもどうすることもできず「あぁ…、また1日が終わる…。」みたいな感じの毎日を過ごした12月、1月が終わって2月に入ったある日の朝、他の大学のフリーゼミがきっかけでつながらせていただいていた福岡の先輩から
「株式会社ポケットマルシェ(現:株式会社雨風太陽)っていう産直ECの会社のCEOの高橋博之さんって方が47キャラバンっていう企画で全国を周って講演してて、直近で新潟にも行くみたいなんだけど、それに同行してる大学生をTwitterで探してるっぽいからぜひ見てみて!」
というLINEが送られてきていた。
高橋さんのツイートを見てみると「進路に迷う」「生きる意味/目的を見出せず社会に出ることに希望を感じられない」「くすぶっている魂が着火される」「人生が変わる」といったことが書いてあって、「これまさしく今の僕やん!!!」って思った。だから、「高橋さんに会えば、もしかしたらこのもやもやした感じがどうにかなるかもしれない。」と思い、すぐにツイートにリプライをして、47キャラバンの新潟と福島での講演に同行させていただいた。
(大雪のなか死ぬんじゃないかってまじで思いながら高橋さんに会いに行った話とか、そのときに感じたり思ったりしたことはこのレポートに書いてあるので今回は割愛。)
そこで学歴コンプレックスがあって勉強をしてみたけどなんか違うなって思ったこととか、学んでいることへの違和感とか自分の将来に対するもやもやとか、これまでに書いてきたような悶々とした想いをぶつけてみると、一言、「日本中の一次産業の生産者さんのとこ周ってみれば?」と言われた。
高橋さんが講演で話しているのを聞いたり移動中の車の中で話していると、「やってみればいいじゃん。」とか「お前ならできる。」って背中を押されてるような感じがして、「僕だってできるんじゃないか。」って自信がついたというか、心に火が点いた。
そして、「ここで何もしなければ結局何も変わらず、これからもずっとこのもやもやを抱えて生き続けることになるかもしれない。でも、この人の言うようにしてみたらなにか変わるかもしれない。高橋さんの言うことに賭けてみたい。何かを変えることができるのは、今しかないかもしれない。」と思った。
そこで僕は、3年生(2021年度)の1年間を休学し、一次産業を生業とされている日本各地の漁師さん・農家さんのところに住み込みで1週間~1か月くらいずつ滞在し、漁師さん・農家さんが普段やっているようなことを隣で一緒にやらせてもらう修行に出ることを決めた。溜まりに溜まったもやもやが、爆発した瞬間だった。
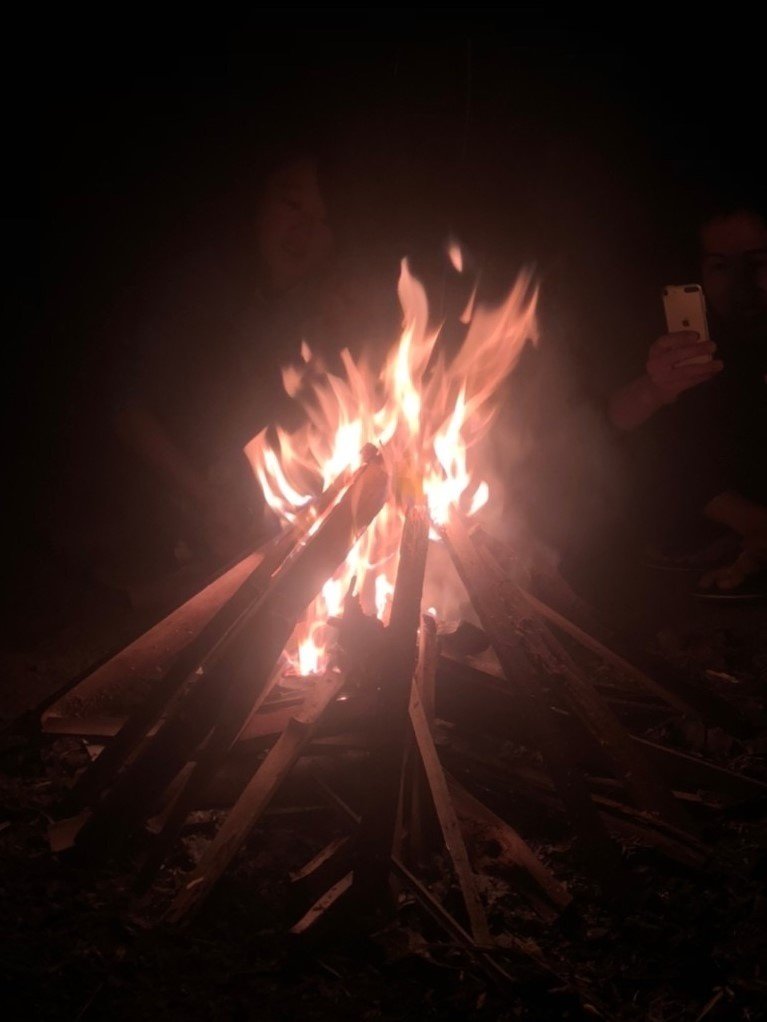
<番外編①> 僕にとっては、「大きな挑戦」だった。
もやもやが高じた結果、こういうことをしようと思ったのが確かに一番の理由だけど、僕にはもう一つ、これをやる大きな意味があった。
先にも書いたように、「大学」っていうのは均されてて、閉じられた、ある種特殊な環境だと思う。だから、周りと違うことをすると「他の人と違うことがしたい痛いヤツ」とか「目立ちたいだけ」って直接言われることはなくても、心のどこかで決めつけられて、白い目で見られて、別に誰が言ったわけでもないけどやりたいと思ったことに素直に踏み出しづらい「無言の圧力」っていうか、「大学」って環境ならではの「出る杭は打たれる」文化が少なからずあるように感じる。
そんなこともあって「別にやりたいことじゃないけど、どうすればいいかわからないから仕方なくそうしてる」とか、「やりたいことはあるけど、周りの目が気になって他人と違うこととか他人がやってないようなことになかなか踏み出せない」みたいな人って実は結構いるんじゃないかな、って僕は思う。
確かに「踏み出してなにかをする」って勇気がいることだと思うし、周りはそんなことをする元気がないみたいだったから、「俺がやる。」って思った。
「『やりたいことをやる』って選択もちゃんとあるんだからな。やりたくもないことを無理をして、死んだ目をしてやるだけじゃないぞ。」
って、背中で語りたいな、って想いがあった。
それに、先にも書いたように高校ではあまりにも成績が悪すぎて学校に親を呼び出されて、大学にはケツから3番目(もしかしたら2番目)の成績で入ったくらいの、普通の学生を通り越してもはや劣等生の僕が実際に行動している背中を見せることで、学生とか僕と歳の近い人のなかで
「あの田辺がやったぞ。あいつがやったんだから、自分だってなにかできるんじゃないか。」
って自分を奮い立たせて何かに挑戦する人が出てきたり、生き方の選択肢が広がったらいいな、と思った。
僕は、大学っていう環境にある息苦しさとか窮屈な空気感に、一矢報いてやりたかった。
<番外編②> なぜ、「生きる行脚」だったのか。
僕はこの1年間の修行を、「生きる行脚」と銘打って旅をすることにした。
だけど、名付けた自分が言うのもなんだけど、「生きる行脚」って正直なところ自分でも口に出すのが恥ずかしくなるくらい、語呂が悪い気がする。「行脚」っていうのは、
行脚:僧が諸国をめぐり歩いて修行すること。
って意味で、その前に「生きる」が付いて「生きる行脚」。「各地を旅しながら生きる修行をする」みたいな感じはそうなんだけど、やっぱり語呂がイマイチな感じがする。
でも、この企画名を変えようとは思わなかった。この企画名にした理由があったから、このまま1年間貫き通そうと思った。
まず、一次産業っていう産業で物理的に命を扱ったり命と向き合ったり、一次産業を生業とされている方の生き様を通して「生きる」とはどういうことなのかを感じたり考えたいと思った。
また先にも書いたように、自分がやってる背中を見せることで、死んだ魚みたいな目をしてやりたくもないことを惰性でやるだけじゃなくて、自分の人生を自分で「選んで」生きてほしいっていう想いがあった。「周りがそうしてるからそうする」っていう”当たり前”に、「ほんとにそれでいいの?」って一石を投じたかった。
そして、資格とかスキルみたいに勉強をしてどうこうってことじゃなくて、人との関わりを通して「人との関わり合いのなかで生きる」ってことがどういうことなのかを感じたり、学べたりするんじゃないかな、と思った。
そんなわけで、単純に「食べものがどうやって作られているのか」を知るだけじゃなくて、総じて、いろんな意味での「生きる」が詰まっていると思ったから、「生きる行脚」と銘打って、この日本各地で一次産業を生業とされている方の隣で一緒に作業をさせてもらう旅をすることにした。
※本来、「なんでこんなことをやることにしたのか」って話は一番最初に書くものだということはわかっていたのですが、当時の感情はすごく複雑で言葉にするのが難しく、これを書くには相当苦戦するだろうなってなんとなくわかっていたので一番最後に書くことになりました。
でもようやく、当時考えていたこととか思っていたことを自分のできるかぎり目一杯言葉にできたと思っているので、やりきった気持ちです。
もう既に、この1年間の修行の旅でお世話になった日本各地の漁師さん・農家さんのところでのレポートというかエピソードは上がっていると思うので、順を追って読んでいただいて、この1年間で僕が見てきた景色とか、僕が感じたこと、考えたことから一緒に「生きる修行」の旅に出たような気分になっていただけたらと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
