
【注目】プラットフォームビジネスについて!急増するプラットフォームサービス。正しく理解できていますか??
こんにちは、PreVenture編集部です!
今回のテーマは「PaaSについて」です。近年、プラットフォームサービスが急増しています。国内のプラットフォーム企業で言うとランサーズなどがあげられるでしょう。海外ではITプラットフォーマーが急増しています。アメリカではGoogle、Amazon、Facebook、Apple、Microsoftなど有名企業が、中国ではアリババやMeituan、JDなどが主要な企業としてあげられます。
しかし、なぜプラットフォーマーはその規模を拡大することができるのでしょうか。今回の記事では、プラットフォームビジネスの特徴やポイント、今後の可能性についてご紹介します。
プラットフォームビジネスについての理解があいまい
スタートアップについての理解を深めたい
ベンチャー転職に興味がある
といった方は是非ご覧ください!
プラットフォーム企業

まず初めに日本・アメリカ・中国のプラットフォーム企業の詳細を紹介します!
日本のプラットフォーム企業
ランサーズ
ランサーズ株式会社は、クラウドソーシングのサービスのウェブサイトであるLancersの運営を行う企業です。 個人-個人間や個人-法人間で請負業務のマッチングサービスを提供しており、近年では地方在住者へのオンラインビジネスマッチングにも取り組んでいます。
Smart HR
株式会社SmartHRはクラウド人事労務ソフト「SmartHR」を開発しています。質問に答えるだけで重要書類が作成できるソフトウェアの開発や提供を行い、働くすべての人の生産性向上を支得ることを目指しています
メルカリ
フリマアプリの「メルカリ」を運営する企業で、Jリーグクラブチーム鹿島アントラーズをグループに持っています。フリマ事業だけでなく様々な事業を横展開している事業会社です。
アメリカのプラットフォーム企業
Google
Googleは、インターネット関連のサービスと製品に特化したアメリカ合衆国の企業です。Alphabetの子会社で、世界最大の検索エンジン、オンライン広告、クラウドコンピューティング、ソフトウェア、ハードウェア関連の様々な事業を展開しています。
Amazon
Amazon.com, Inc.は、アメリカ合衆国のワシントン州シアトルに本拠地を置く企業です。主軸はインターネット経由の小売ですが、その他にもクラウドコンピューティングなどを手掛けています。 同社は「世界で最も影響力のある経済的・文化的勢力の一つ」と呼ばれ、世界で最も価値のあるブランドとされています。
Meta(旧Facebook)
メタ・プラットフォームズ、通称Metaは、アメリカ合衆国のカリフォルニア州メンローパークに本社を置く多国籍テクノロジー・コングロマリットです。Instagramを買収したことでも知られています。
Apple
Apple Inc.は、アメリカ合衆国の多国籍テクノロジー企業です。カリフォルニア州クパチーノに本社を置き、デジタル家庭電化製品、ソフトウェア、オンラインサービスの開発・販売を行っています。
Microsoft
マイクロソフト(Microsoft Corporation)は、アメリカ合衆国に本拠地を置く、世界的に有名なテクノロジー企業です。マイクロソフトは、1975年にビル・ゲイツとポール・アレンによって創立され、現在はソフトウェア、ハードウェア、クラウドコンピューティング、人工知能(AI)、ビジネスソリューションなど、さまざまな分野で幅広い製品とサービスを提供しています。
中国のプラットフォーム企業
アリババ
アリババグループ(Alibaba Group Holding Limited)は、中国に本拠地を置く世界的なテクノロジーおよび電子商取引(eコマース)企業です。アリババは1999年にジャック・マー(Jack Ma)によって設立され、その後急速に成長し、中国および世界中で幅広いオンラインサービスとプラットフォームを提供しています。
Meituan
美団点评(Meituan Dianping)は、中国に本拠地を置く大手のオンデマンド配達およびオンラインサービスプラットフォームです。美団点评は、食品宅配、外食、ホテル予約、エンターテインメントチケット、美容サービス、旅行など、さまざまなサービスを提供し、消費者に便益をもたらすプラットフォームを構築しています。
JD
"JD.com"(ジェイディー・ドットコム)は、中国に本拠地を置く大手の電子商取引(eコマース)企業です。元々は「京東商城」として知られていましたが、一般的には"JD"と略されています。JD.comは、商品のオンライン販売および物流インフラストラクチャーの構築に焦点を当て、さまざまな商品を販売しています。
PaaSとは
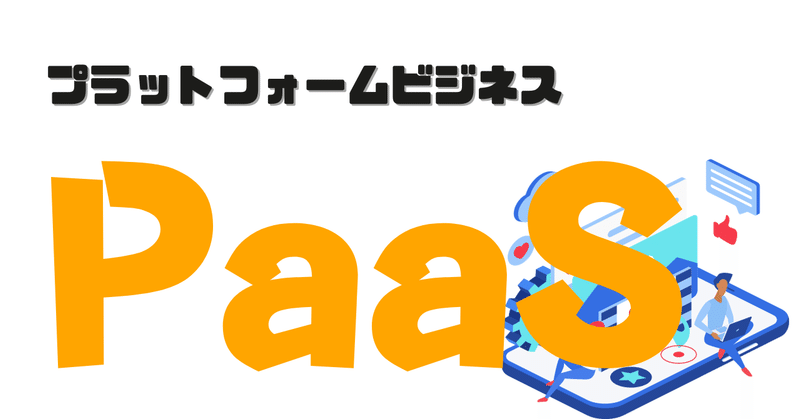
PaaSとは「Platform as a Service」のことで、クラウドにあるプラットフォームの利用をサービスとしています。大規模なデータセンターに、アプリケーションを稼動するためのネットワーク、サーバシステム、OSやミドルウェアなどのプラットフォームが用意され、企業ユーザがそのプラットフォーム上で開発を行うことができます。
SaaSとの違い
SaaSがソフトウェアを提供するのに対して、PaaSはそのソフトウェアを開発する基盤であるプラットフォームを提供していると言う違いがあります。
PaaSのビジネスモデル

PaaSのビジネスモデルは、サブスクリプション型のモデルをとっている場合が多いです。
MicrosoftのMicrosoft Azure、GoogleのGoogle Cloudで提供されるGoogle App Engine(GAE)、そしてAmazonのAmazon Web Services(AWS) は世界3大クラウドと呼ばれ、PaaSの代表例となっています。
また、専門知識がなくても自由にアプリ制作を行えるプラットフォームとして有名なのが
Kintoneです。Salesforce Platformも容易な操作性が魅力です。
PaaSのサービスには多様なサービスがあります。月額課金モデルを採用し安定した収益を得ることができる点も、プラットフォームビジネスの特徴です。
以下、ビジネスモデルの大枠を紹介します。
仲介型プラットフォーム
仲介型プラットフォームは、商品やサービスの提供を受けたい需要者と、提供を行いたい提供者をそれぞれネットワーク化しつなぐ形式です。UberやメルカリなどのCtoCプラットフォームがここに分類されています。
OS型プラットフォーム
多様なサービスのOSとして機能し、他社サービス・アプリケーションを含むサービスを提供する形式です。Apple Storeの「iphone」やシーメンスの「Mindsphere」などが分類されます。
ソリューション型プラットフォーム
特定機能に特化した横断的機能を提供し、他社(供給者)の需要者へのビジネス活動をデジタルツール提供により支援するプラットフォームのことを指しています。エアレジ、ペイペイ、ファームノートなどのプラットフォームがここに該当しています。主に決済サービスとの相性が良いことがわかります。
コンテンツ型プラットフォーム
コンテンツの蓄積により、利用ユーザーが集まり、利用価値が高まっていくプラットフォームのことを指しています。FacebookやNetflixがここに当たり、主にエンタメ系との愛障害でしょう。
PaaSを利用するメリット

PaaSを利用する側のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
今回はPaaSを利用するメリットを5つ紹介します。
開発をすぐ始められる
PaaSではクラウド上にアプリケーションの実行に必要なプラットフォームが用意されており、ユーザーは導入後からすぐにこれらのサービスを利用できます。そのため、ミドルウェアのインストールやバックアップの設定といった細かいセットアップを行う必要がなく、これらの作業中に開発チームを待たせる必要もないことから、ユーザーの負荷軽減につながります。このように、PaaSの利用開始直後から、自社の取り掛かりたいアプリケーション開発を開始できる点は大きなメリットとして数えてもいいでしょう。
開発の時間を短縮
PaaSの導入によって利用できるようになるプラットフォームには、ワークフロー・ディレクトリサービス・セキュリティ機能・検索といったコーディング済みのアプリケーションコンポーネントが組み込まれているものも少なくはありません。これらのアプリケーションコンポーネントをうまく利用することで、新たなアプリケーション開発にかかる時間を短縮できます。
環境の複製および配布が簡単
PaaSにより提供されるプラットフォームを活用すれば、同じ環境のコンピュータを簡単に複製・配布できます。そのため、必要となったときに必要な分だけ開発環境を準備することが可能です。また、コンピュータをテスト前の状態に戻すことも簡単に行えるため、システム開発における検証・テストを行う際、大量のコンピュータを用いて作業を効率的に進められます。このような点も、ユーザーの負担を軽減することにつながるでしょう。
初期費用および運用コストを抑えられる
基本的に、何か新しい開発を行う際には大きな初期投資が必要になってくるという課題があります。しかし、従量課金制のPaaSを導入すれば、ユーザーの使用した分しか費用が発生しないため、運用コストの抑制につながります。また、ハードウェア・OSなどを購入せずに済むため、初期投資も抑えることが可能です。そのほか、開発に必要な機器を安全な設置場所に確保しておくためのコストも発生しないため、費用対効果を重視しているならばPaaSの導入は非常に有効だといえます。
柔軟に拡張ができる
オンプレミスの方式(ITリソースを自社やデータセンター内に設置し、ユーザー自身で管理・運用を行う方式)を採用すると、開発機能が無駄になったり不十分になったりしたときに、スペックの拡張・縮小の対応を柔軟に行うことが難しいです。これに対して、PaaSでは、必要なスペックの増減に応じて利用内容を柔軟に変更できるため、無駄な費用が発生しません。柔軟に拡張ができることは、費用対効果を重視する利用者にとっては最も便利だと言える点かもしれません。
PaaSの市場規模

さて、ここまでで紹介してきたPaaSの市場規模はどれくらいになっているのでしょうか。
IaaS(Information as a Service)も含めたPaaSの国内市場規模は今後も大きく拡大していくとされています。ITRの発表によると2021年に1兆円規模に達した国内PaaS市場は2025年度には2兆円に達するとされています。
また、海外のPaaSの市場規模はさらに大きなものになっています。株式会社グローバルインフォメーションは、市場調査レポート「世界のPaaS(Platform as a Service)市場:タイプ(アプリケーション、インテグレーション、データベース)、展開タイプ、組織規模、垂直産業、地域別 - 業界分析と予測(2021年~2027年)によると、2027年には1,673億米ドルになると予想されています。
(参考)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000712.000071640.html
PaaSが成長する理由
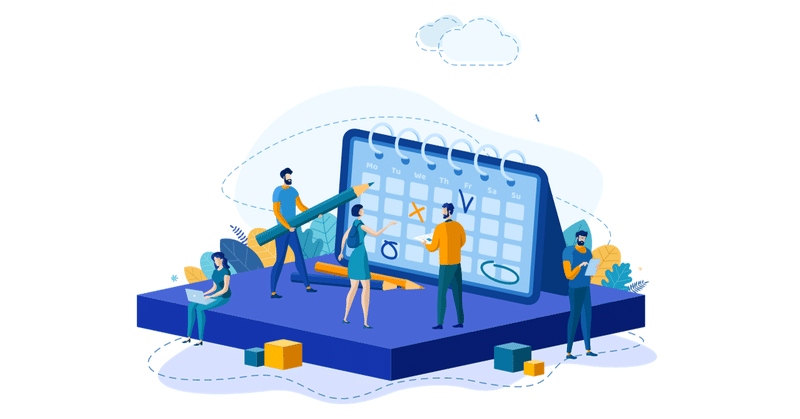
PaaSが、ここまで成長を続けてきて、今後も成長していくと考えられている理由はどこにあるのでしょうか。ここでは注目すべき二つのワードに視点を当ててみていきます。
そのキーワードとは「ネットワーク効果」と「データの利活用」です。
これら二つの方法で安定した利益を獲得できる上に、ターゲットは世界中に存在しているため、PaaSは成長を続けるだろうと見込まれています。
ネットワーク効果
一つ目のキーワードは「ネットワーク効果」です。ネットワーク効果とは、その製品やサービスのユーザーが増えれば増えるほど、それぞれのユーザーがその製品・サービス自体から得られる効用や価値が大きくなることを指します。ネットワーク効果が働くかどうかは、プラットフォームサービスをはじめ、ITサービスにおいてカギとなります。
プラットフォームビジネスでは、プラットフォームの運営者、プラットフォーム上の事業者、消費者の3者が関係しています。消費者が増えることで、事業者が増えます。そして、事業者が増えることで、消費者が増えるといったようにスパイラル式にプラットフォームのユーザーは増加します。
また、プラットフォームビジネスではネットワーク効果が働いた特定の製品・サービスが急成長してシェアが高くなる傾向があります。つまり、「ひとり勝ち」現象が起こりやすいのです。ひとたびユーザー数の拡大サイクルに入ると増加スピードが加速し、LINEのようにユーザー数が爆発的に増える結果となります。
データの利活用
二つ目のキーワードは「データの利活用」です。プラットフォーム提供者はプラットフォームそのものに加えてデータを提供していることがあります。PaaS企業はプラットフォームを利用している利用者のデータ(利用履歴、閲覧履歴)を蓄積し、必要に応じて利用事業者に提供しています。TwitterやInstagramのインプレッション数はこれの一例ですね。
ただ、このようなデータの活用が一部法律に触れてしまう場合もあるようなので、注意する必要は十分にあります。経済産業省のレポート『第四次産業⾰命に向けた横断的制度研究会 報告書の概要』でもこれらの点はしっかりと取り上げられています。
PaaSの課題
国内でも海外でも成長が予想されているPaaS企業ですが、課題として上がっているのはどのような例があるのでしょうか。国内のプラットフォームビジネスの課題を3つ紹介します。
セキュリティレベルが会社次第になること
ここでいう「会社」とは、そのプラットフォームを提供しているPaaS企業のことを指します。イメージしていただきやすいように例を挙げると、Googleが個人情報を流出してしまったらそれを使っている皆さんの個人情報が全て世間に出てしまう、といったところです。ユーザー側のセキュリティ対策の意識向上により改善傾向にあることも事実ではありますが、それでも事業会社側に依拠してしまうでしょう。
自由度がひくい
PaaSは、CPUやストレージといったインフラ環境を自由に選択できません。導入後に希望する言語やミドルウェアが利用できないケースも考えられます。全ての言語に対応しているPaaSは存在していないので、ここの親和性はしっかりと見定めなければいけません。
オンプレミスと比べると自由度が低いため、特別な製品がインストールできない場合もあります。他にも、障害時の一次対応も再起動を行うなどの作業に限られてきてしまうなど、利用する上での自由度が低いことが課題だとされています。
巨大企業が席巻している
最後の課題として、「巨大企業が席巻している」ことがあげられます。PaaSはその特性から、一つ巨大企業が誕生してしまうと他の企業がそれに取って代わるのが非常に難しいと言うものでもあります。実際にGAFAMに変わる企業が今後簡単に出てくるかというと、そうではありません。巨大企業とどのように競争していけるかは新しいPaaS企業の解決する必要のある課題であると言えるでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。今回のテーマは「PaaSについて」でした!
GAFAMがここまで大きくなった今でさえ、PaaSの市場規模はどんどん拡大しています。裏を返せばこれはどんな企業でもやり方次第でGAFAMに勝てる可能性があると言うことかもしれません。日本からNext GAFAMが出てくるのでしょうか。今後のベンチャー企業の活躍に期待です!!
最後に。。。
弊社では、転職前にベンチャー適性がわかる診断サービス「PreVenture」も運営をしています。40問の質問に答えるだけでベンチャー企業への適性診断を無料で受けることができます。ベンチャー/スタートアップ企業で働くことに興味がありましたらぜひ参考にしてみてください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
