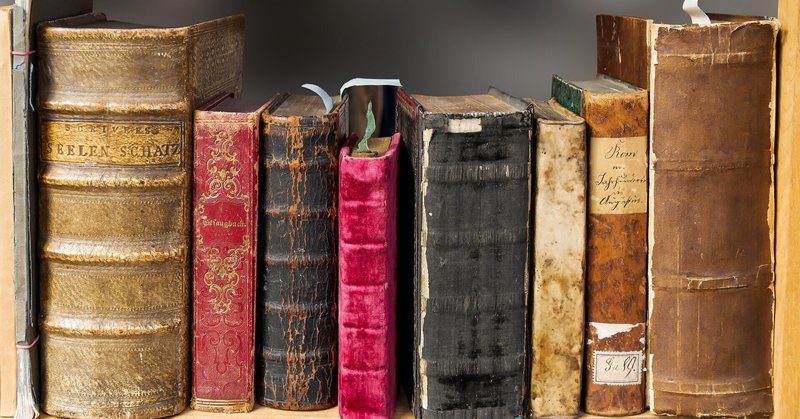
「受験国語は前提知識がなくても解ける」は本当か?!
みなさん、こんにちは。
今日はこのまえアメリカ在住の中学生と国語の勉強をしていたとこの話を少し。
受験国語といえば(受験英語も)、前提知識は関係ない、答えは全て本文に書いてあるというのが前提ですよね。
僕は今まで問題を解いていて、確かに前提知識がないものがトピックでも特に違和感なく対応できていました。
それは本文の中に出てくる言葉の説明がされていて、直接されていない場合は注釈が本文の横に書いてあったからだと思います。
先日、生まれてからずっと中国育ちの小学生の子に国語の入試問題を見てもらったところ、少し理解が難しかったと言っていました。
その文章のトピックは「落語」だったのですが、落語は日本外ではあまり一般的でないので難しく感じたのかもしれません。
しかし、僕もその問題に目を通したところ、ちゃんと落語の背景などが説明され、落語を知っているかはあまり関係ないように感じました。
というのも、そもそも僕自身が落語をほとんど知らなかったのですが、それでも問題なく設問には対応できたのです。
このように、前提知識がないということがちょっとしたプレッシャーになり、余計に問題が難しく感じるということはあるのかもしれません。
このようなことがあったあとに、アメリカ在住の中学生と国語の勉強をしていたのですが、その文章のトピックは「うち」でした。
本文はこちらの本から↓
ここでの「うち」は関西出身の人が1人称として使っているものではありません(英語とちがって日本語は1人称の種類が多いというのも受験国語ではよくあるテーマですね!)。
ここでの「うち」とは「うちの会社」、「うちの中では」といった自分のコミュニティを表すものです。
筆者の指摘としては、日本語の「うち」の概念は英語の「private / official」のような関係で説明できないというものでした。
たしかに、「うちの会社」は"private"なのか"official"なのかよくわかりませんね…
「うち」は「my」もしくは「our」にあたる表現ですが、それでも単に自分の所有を表しているわけではないような気がします。
「うち」とはなんとなく「身内」のような響きがありので、英語のように単純に「だれのもの」という事実を示しているのではないのかもしれません。
さらに、筆者はこの「うち」が可変的であることは日本の伝統的な家屋において障子やついたてによって部屋が緩く分けられるのに通づるものがあるように思うといい、「private / official」が明確に分かれている英語を使う西洋諸国の建築はドアという固定の仕切りがあるということを指摘しています。
なるほど、なかなか面白いです!
読んでいるだけならそれでいいのでしょうし、読書とは本来そのようであればいいと思う僕ですが、試験では答えを導き出さなければいけません。
この問題を僕が初めに解いたとき、なかなか難しかったのですが、それでもなんの違和感もなく解くことができました。
しかし、アメリカ育ちのその中学生は「世間」といった言葉の意味をいまいちしっかり捉えられずに、その問題を解くのが難しかったようなのです。
その子は概念として「世間」というものがあること、日本の伝統的な家には畳の部屋があり、それを障子で仕切るというようなことはもちろん知っていました。それもそのはず、生まれてからしばらくは日本育ちなのです。
しかし、全体として文を読むと筆者の意図がなんとなく捉え所がないように思ったそうです。
僕はそれを聞いたうえで、改めて問題を見返してみたのですが、言われてみれば確かに他の受験国語の問題に比べ背景知識の説明は少なく、文化によっては理解しにくいものであるかもしれないと思いました。
なにも筆者の説明が足りないとか、これが理由でこの文章がダメであると言っているわけではありません。そもそもこの文章は国語の受験のためにかかれたものではないはずです。
自分が当たり前のように思っている文化や背景が他の人にとっては当たり前でないということはみんな頭で理解しています。
僕はずっと日本で育ち、自宅にも畳の部屋があったものの、それほど「世間」というものを意識して生きてこなかったと思います。
だからそこ、文化によって生活や思考が影響を受けると頭でわかっていても、無意識のレベルでそれが他の人にどのような影響を与えるかを考えることが難しいのだと思います。
ましてやその子は日本の文化もある程度わかっていたのですから、さらに話は複雑になります。
なんとも不思議な経験に思いましたが、それでも、これからより一層、自分が無意識に物事を判断しているのだと注意すべきと学ばせてくれるエピソードでした。
自分が何かを伝えるときはそれを意識する必要がありますし、試験はやはり本文を読めば全て理解できるようにしておかなければいけないと思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
