
映画『バービー』 フェミニズムの歴史と現在地。今観るべき作品。(長いネタバレ感想文 )
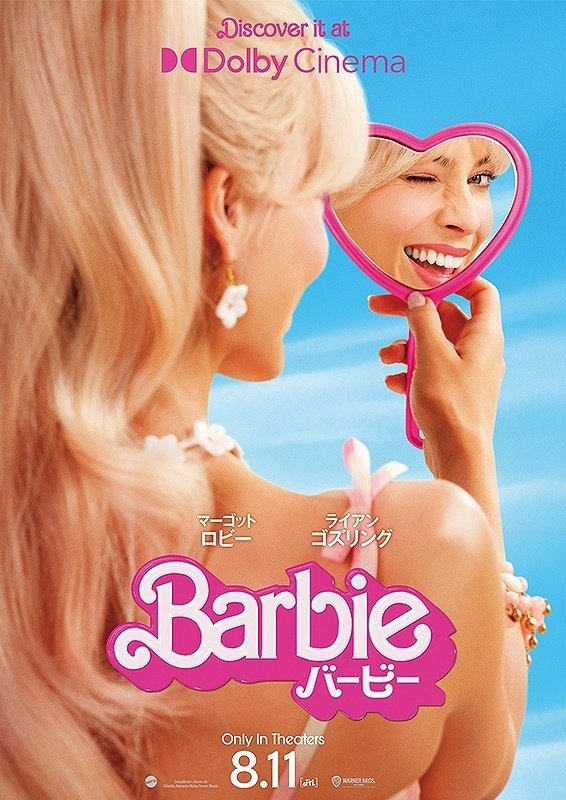
皆さんが「フェミニズム」という単語にどういう感情を抱くか分かりませんが、私はネガティブなイメージがないため、無頓着に使用しますのでご了承ください。
私は時折、近代カルチャー史(文化・芸術作品)における女性の扱われ方を考察することがあります。
noteだと、「探偵」における女性史的なことを長々語りました。
女性映画監督とフェミニズムのあり方にも興味があります。
(今回は海外の監督を中心に語ります)
「男社会」だった映画界でのエポックメイキングは、ジェーン・カンピオンの『ピアノ・レッスン』(1993年)でしょうか。
ニュージーランド出身の映画監督として、そして女性監督として初めてのカンヌ国際映画祭パルム・ドール。
米アカデミーを受賞した最新作『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(2021年)は観ていませんが、『ある貴婦人の肖像』(1996年)や『イン・ザ・カット』(2003年)など、戦う姿勢を刺々しく前面に押し出すようにして「社会の中で抑圧される女性」を描写する印象があります。
一方、フランスのコリーヌ・セローは『赤ちゃんに乾杯!』(1985年)で、「男どもに子育ての苦労」という試練を与えます。
コメディーの形を借りて「女性の苦労を知れ!」という、ソフトな「フェミニズム」映画なのです。
この映画はアメリカで『スリーメン&ベビー』(87年)としてリメイクされるほど、女性監督初の(?)世界的なヒット作品ではないかと私は思っています。
実際、コリーヌ・セロー作品は『女はみんな生きている』(2001年)や『サン・ジャックへの道』(05年)など、その軽妙な作風の裏で、男どもを軽く鼻で笑うようなフェミニズムの臭いを常にちらつかせている印象です。
そしてアメリカではキャスリン・ビグロー。
女性初の米アカデミー監督賞受賞者。
(日本アカデミーでは女性監督の受賞者はいるのかな?西川美和のノミネートくらいしか記憶にないけど)
アカデミー受賞作は『ハート・ロッカー』(08年)ですが、私は『ゼロ・ダーク・サーティ』(12年)にフェミニズムを感じます。
つまり、軍隊という男社会における女性指揮官に、映画界という男社会における女性監督という自分自身を投影していると思うのです。
1947年生まれのコリーヌ・セロー、1951年生まれのキャスリン・ビグロー、1954年生まれのジェーン・カンピオン、この辺りの世代が開拓者だと思うんです。
細かいことを言えば、古くはチェコのヴェラ・ヒティロヴァ(1929年生まれ)の『ひなぎく』(1966年)なんかもありますけどね。前衛的ですが、ガールズ・ムービーの草分けだと思っています。
あるいは、ハンガリーのイルディコー・エニェディ(1955年生まれ)の『私の20世紀』(1989年)とか、ありますけどね。 まあ、同世代ですね。
そうした開拓者世代の少し後の世代は、「戦う姿勢」よりも「女性の視点」を活かした映画を撮り始めます。
代表例はソフィア・コッポラ(1971年生まれ)ですかね。
例えば『ロスト・イン・トランスレーション』(2003年)。
私の記憶では、下着姿のスカーレット・ヨハンソンのお尻から映画が始まるんです。記憶違いかもしれませんけど。
そこに性的な意味は全く無く、自然体と退屈と孤独を「尻」で描写する。
こんな描写は「戦うフェミニズム」作家たちには絶対に無いことでしょう。
例えば『マリー・アントワネット』(06年)なんかは、女子大生の海外旅行みたいな視点に思えるんですよ。
こうして、当たり前のように「女性の視点」で映画を撮れるようになると、また新しい若い才能が出てきます。
『17歳の瞳に映る世界』(20年)のエリザ・ヒットマン(米 1979年生まれ)とか、
『燃ゆる女の肖像』(19年)、『秘密の森の、その向こう』(21年)のセリーヌ・シアマ(仏 1978年生まれ)とか、
『ノマドランド』(20年)、『エターナルズ』(21年)のクロエ・ジャオ(中国 1982年生まれ)とか。
そして、縁がなくて『レディ・バード』(17年)、『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(19年)を見逃して、今回『バービー』で初鑑賞となった1983年生まれのグレタ・ガーウィグ。
そうです、やっとこの映画の感想に入ります。

映画は秀逸なパロディーで始まりますが、これは単なるパロディーにとどまらず、バービー登場以前のお人形は「赤ちゃん」しかなかったこと、つまりそれは「女性=母親になるべき者」という思想しか世の中になかったことを示唆します。
そしてバービー人形の登場によって、「母親」しか選択肢のなかった女の子が、「世の中で活躍できる女性の姿」を夢想して遊べるようになったわけです。
この段階で充分な「フェミニズム映画」です。
ところが今時の若者には「バービーは理想的な女性像の押し付け」と受け止められている。
この2つのエピソードで、私が延々語ってきた「女性史」を描ききってしまう。
さらに言えば、自身は「性器がない」と言って母親になる可能性を否定しますが、廃盤になったという妊婦バービーも登場させて「母親になることも選択肢の一つ」という多様性も抜かりなく提示します。
簡単に言えば、「母親」という女性の単一の選択肢が「多様な選択肢の一つ」に変化しているのです。
そして「母と娘の物語」を折り込むことで(父親を登場させないことで)、「これは私たち女性の問題なんだよ」と発するのです。

そしてこの映画の、そしてフェミニズムの着地点は、男女の対立でも結婚でもありません。
「男社会」の現実世界、「女社会」のバービーランド、そのいずれも「互いにその存在を認め合うことが必要だよね」「でも発展途上で、まだまだこれからだよね」という「現在地」が示されます。
私は『アナと雪の女王』(13年)が、「留守を預かっといて」「ちょっとそこまで乗せてって」「誰でもいいから私を愛してキスして」「お前、氷納入業者ね」「ソリにドリンクホルダー付けてやったから」ヒャッホー!という男は女のための「便利道具」という思想に、ディズニーとしては新しいかもしれないけど、フェミニズムとしては先祖返りしてしまったと驚いたもんですが、この映画はフェミニズムの最先端。
「女か男か」ではなく、「女も男も」の世界。
それを目指しましょうよ(まだまだだけどね)という未来志向の映画。
そう考えると、トム兄が牽引する映画界の近年の大ヒット作(『トップガン マーヴェリック』(22年)や『ミッション インポッシブル/デッドレコニング』(23年))は、マッチョな「男」映画なんですな。
(2023.09.02 T・ジョイ PRINCE 品川にて鑑賞 ★★★★★)
余談
そんなバービーとコラボできる僕らのあーりんはやっぱりすごいと思うんだ。


