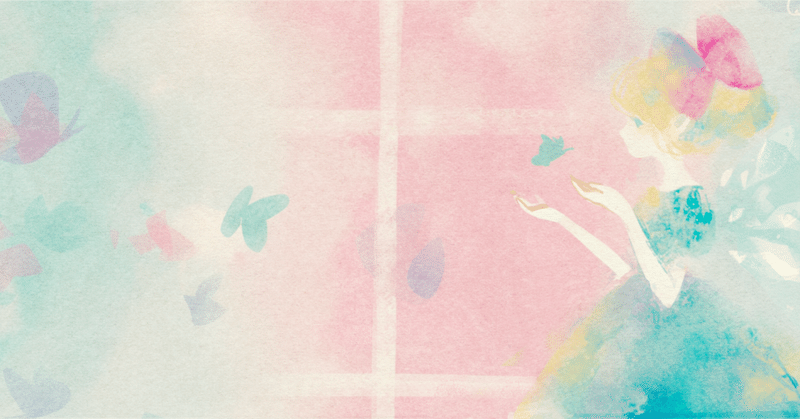
【連載小説】「心の雛」第十六話
(第一話はこちらから)
https://note.com/pekomogu/n/ne7057318d519
※この小説は、創作大賞2024「ファンタジー小説部門」応募作品です。
(本文 第十六話 2,436字)
「ひ、な…………」
「先生……」
お互いかすれた声で名を呼びあい、震える指先に触れ合った。
ずっと閉じられていた先生の瞼が開き、鳶色の瞳が私を探し出した。ホッと胸をなでおろす。……生きていた。先生が生きていてくれた。目を開けてくれた。
私は目を閉じておでこを先生の指先にくっつけた。
「僕は……生きている、のか……?」
「えぇ、そうです。死んじゃダメですよ」
「……傷、止血しているのか? ……雛は無事ですか? どこも怪我とかはしていませんか?」
先生が捕獲ちゃんという『妖精虐殺道具』によって私の代わりに大怪我を負ったのはほんの数十分前。私の身体全体を朱に染め、先生の頬から首、肩にかけて真っ赤になっているのはまぎれもなく先生自身の血である。私のこの姿は返り血がほとんどで自分の血を出すのに小さな穴を開けたくらいだったのだけど、先生にはよく分からなかったらしい。
妖精の生き血にはあらゆる傷を治す効果がある。人間が喉から手がでるほど欲しがっている代物だ。私は躊躇わず先生に自分の血を塗りたくった。おかげで先生の傷はたちどころに塞がってくれた。
「よ……っと。……ふぅ。あぁ、ひどい状態ですね……」
先生がゆっくりと起き上がって部屋をぐるりと見渡した。診察室はあらゆるものが散乱し、ところどころに血しぶきもあり、ひどい有り様だった。
「あぁ、雛。鼻血が出ていますよ」
「え?」
先生が床に散乱していたごちゃごちゃのモノの中からティッシュを見つけ、私の顔を拭いてくれようとした。
「あ、いいです。これも生き血なので」
私は鼻をぐりぐりと先生の首筋に押し当てた。魔法をたくさん使いすぎたせいだろう。魔力を消費しすぎると鼻血を垂らしてぶっ倒れてしまう。鼻血とて血に変わりはないんだから無駄なく使いたい。
ふいに、足元でパリパリと乾いた音がした。
「……これは」
先生が小さく呟き、落ちていた音の正体をつまんだ。干からびたそれは――茶色く縮れてしまっていたがうっすらと模様があって――それは妖精の羽のようだった。私の残っていた下羽か。
「もういりません。そんなもの」
私は努めて明るく言った。
だって、本当のこと。きっと魔力をたくさん使いすぎたのね。唯一残っていた羽がこんなになって落ち葉みたいに背中から取れてしまったけれど、先生の命があるのなら惜しくも何ともない。
「どうせもう飛べないんだから」
「……雛……」
先生を見上げると、口をへの字にして悲しそうにしていた。
まずは状況確認だ。私は、先生が私を守って怪我をした時のこと、それから叶とかいう悪魔女を外に追い出し、玄関の鍵までかけたことを端的に報告した。激しい出血をした先生は貧血なのだろう、顔面蒼白のまま壁に寄りかかって聞いていた。
「……雛に魔法を使わせてしまった。申し訳ない」
「先生のせいじゃないです」
「……君が無事で本当に良かった」
「……先生」
いつもの先生の声が聞けて、私は身体中からどっと力が抜けていくのが分かった。先生の中指だけじゃ物足りなく、手のひらまでぐいぐいと近付いてぴたりと寄り添った。
「私も、先生が生きててくれて良かったです……」
今の私はどういう気持ちなのだろう。こんなにくっついているのだから先生はいろんな私の心に触れているはずだ。
「さっきは悲しさ、それから嬉しさ、喜び。雛の心は素直で、とても温かいですね」
先生がふわりと微笑み、しばらくの間両手で私をそっとなで続けてくれた……。
「さて、どうしましょうか。叶様がここに戻ってくるのも時間の問題ですね」
少し落ち着きを取り戻した先生が真面目な顔で今後の対策を講じ始めた。私はふくれっ面になった。
「あんな女。治してほしいだなんて言ってますけど、治らないですよ」
「手厳しいですね。彼女の心は確かに痛々しいくらい悲しげなものだったんですよ?」
「いいんです。悲しげだろうが何だろうが妖精の力に縋るから、今をどうにかしようなんて考えずに諦めてしまっているんですよ」
私はきっぱりと断言した。彼女は弱い。先生と同じく心の病を治す医者、とか言っていても自分でどうにかできないんじゃ、どうしようもないではないか。
「あんな道具まで持ち出して」
捕獲ちゃんを思い出し、思わずぶるりと震えた。
「まぁ、僕も雛の力で今ここに生きているわけだから、あまり強いことは言えないですよ……」
「先生だから私は治したんです。私が治したいからしたんです。先生が負い目を感じることは何も無いんです」
「……えぇ」
先生はじっと黙ったまま壁の一点を見つめていた。作戦でも練っているのだろうか。
玄関のドアは鍵がかかっているけれど、窓を叩き割って入るとか、屋根の煙突から入るとか(煙突なんてものがあったのかは分からないけれど)、あの女ならやりかねないと思った。
妖精がいるかどうかも分かってしまう捕獲ちゃんは、正直なところ勝ち目がない。私には羽がない。飛べもしない。走ったところで人間の子供よりも遅い私が、あの道具を前に逃げることなどできやしない。
「……先、生?」
不安になって尋ねた。
いつまでも先生に庇護されている訳にはいかないことも分かっている。
私がここにいればまた同じように女はやって来るだろう。
だったら投降すれば話は早いはず。
……私は、死ぬのだけれど。
ふと、先生が膨大な医学書やら専門書の本棚から古びたノートを一冊取り出した。先生が時々手にするやつだ。四隅がめくれて相当読み込んでいることが分かるくらいボロボロだ。
先生は昔、落ち着きたい時にこのノートを読むと教えてくれた。内容を聞いてもゆるゆると首を横に振るだけで、教えてもらったことはない。しかも私は字が読めない。絵本なら寝る前にでも読んでもらえるのに。
ノートをパタンと閉じ、先生は言った。
「まずはプリンを食べましょうか」
どうやら落ち着いたらしい。
私は、ひっくり返りそうになった。
(つづく)
第一話はこちらから
数ある記事の中からこちらをお読みいただき感謝いたします。サポートいただきましたら他のクリエイター様を応援するために使わせていただきます。そこからさらに嬉しい気持ちが広がってくれたら幸せだと思っております。

