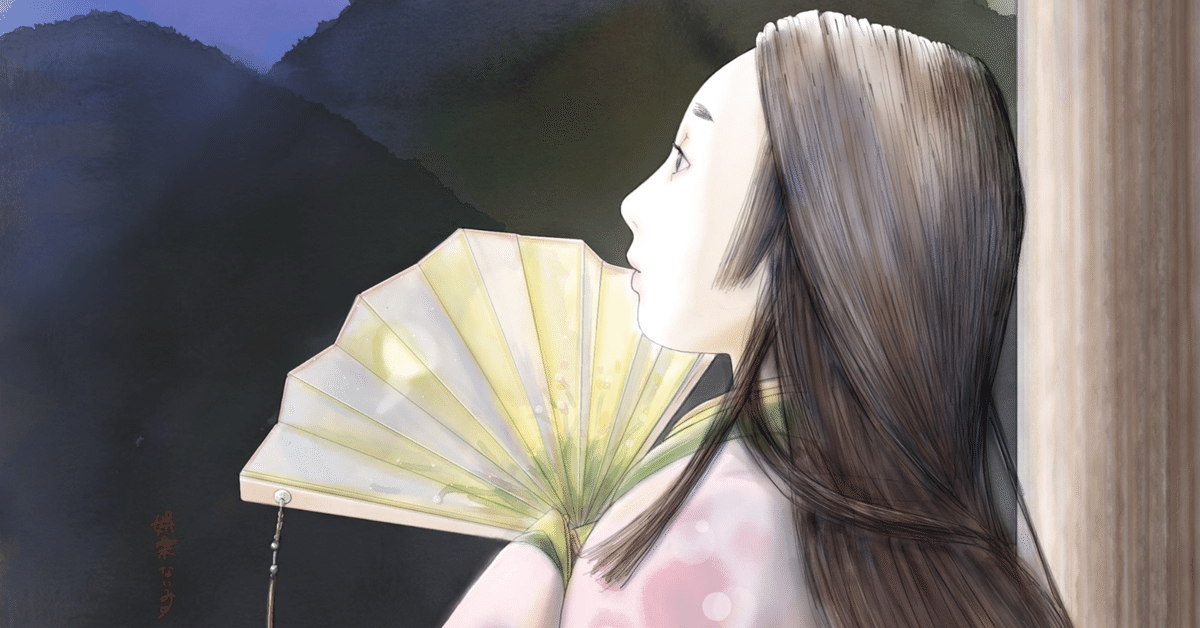
日本の女性名―歴史的展望 (上) (教育社歴史新書―日本史)
日本の女性名―歴史的展望 (上) (教育社歴史新書―日本史)
日本人の女性は、どのような名を持ってきたのかを、解説した本です。たくさんの実例が挙げられています。
本書は、『日本の女性名』の上巻です。大和時代から、鎌倉時代までの女性名が取り上げられています。これ以降の女性名は、中巻と下巻に続きます。
日本史を知りたい方にとっては、本書は、必読書の一つでしょう(^^) 大和時代から鎌倉時代までの、実際の女性名が、どっさり載っているからです。
名前を知ると、古代の人々が、身近に思えてきます。タイムマシンで歴史をさかのぼって、「○○さん」と呼びかけてみたい衝動に駆られます。
女性名ばかりでなく、男性名を知りたい方にとっても、本書は、役に立ちます。
日本の古代においては、男性名と女性名の区別が少なかったからです。つまり、男女に共通する名前が多かったのですね。
例えば、小野妹子【おののいもこ】という名は、現代の感覚では、どう見ても女性名ですね。けれども、これは、男性名です。
和気広虫【わけのひろむし】という名は、男性っぽいですが、女性名です。
「男女の名前に差が少ない」のは、古代日本文化の特徴です。重要な特徴のわりに、あまり知られていません。
本書を読み進めば、目から鱗【うろこ】がぽろぽろ落ちるでしょう。
日本史について、新たな視点が得られること、間違いなしです。歴史小説に、突っ込みを入れたくなります(笑)
以下に、本書の目次を書いておきますね。
はじめに
概説 日本女性の名
人間の名前
中世における女性名の研究
近代における女性名の研究
女性名の特色
女性名の種類
第一部 古代
1 大和時代
遠古の女性名
大和前期の特徴
大和時代後期
2 奈良時代前期
庶民の女性名
貴族の女性名
3 奈良時代中期
庶民女性名の分類
庶民女性名の特色
皇・王族と貴族の女性名
4 奈良時代後期
史料の問題
貴族女性名の推移
宮人・尼僧の名
庶民・奴婢の名
5 平安時代前期
桓武・平城【へいぜい】朝の特色
嵯峨朝以降の特色
貴族女性名の子型化
宮廷女性の呼び名
6 平安時代中期(一)――延喜【えんぎ】・天暦【てんりゃく】の時代
子型名の流行と童名
宮廷・貴族の女性名
庶民の女性名
7 平安時代中期(二)――寛弘・永承の時代
貴族の女性名と命名法
呼び名・綽名【あだな】・童名
内裏女房の地位と候名【さぶらいな】
庶民の女性名
法名と遊女名
8 平安時代後期
宮廷の女性名
貴族女性名の特徴
女房たちの候名
庶民の女性名
遊女・傀儡子【くぐつ】・白拍子【しらびょうし】の名
藝名【げいめい】と法名
第二部 混成古代
1 鎌倉時代
混成古代の意味
宮廷貴族の女性名
女房たちの名
庶民女性の名
庶民の女性名の分類
女性の法名
白拍子・遊女などの名
注
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
