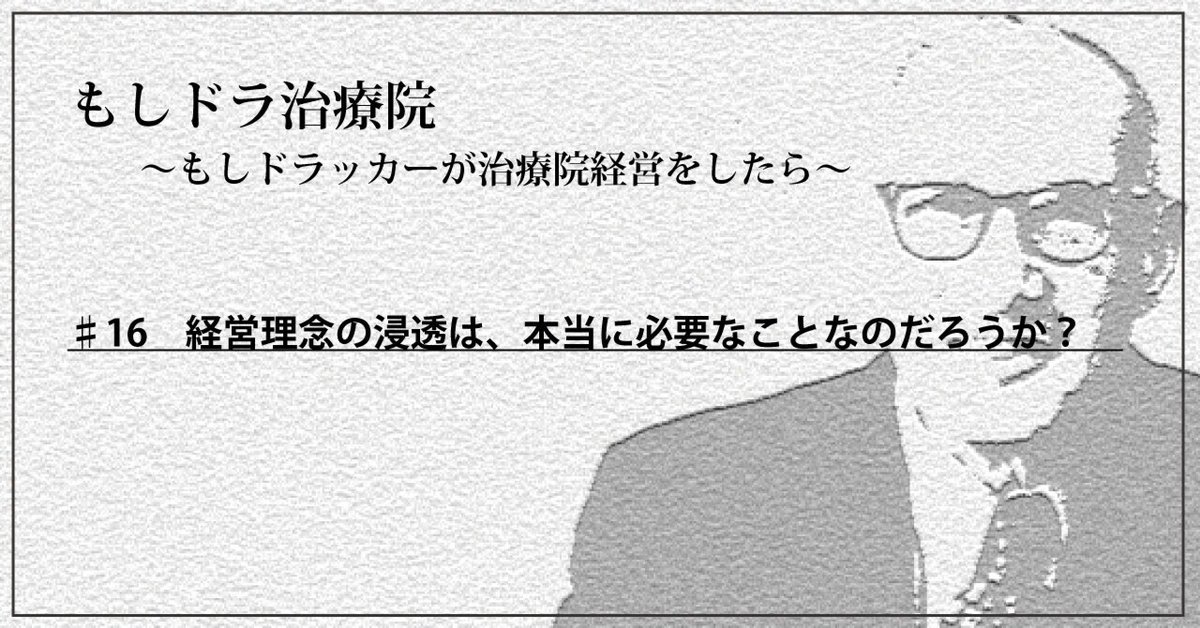
#16 経営理念の浸透は、本当に必要なことなのだろうか?

(この号は、約3分で読めます)
経営者が担う仕事のなかで、最難関のひとつと言えそうなのが「ミッション・ビジョン・バリューの浸透」。
どこの会社にも理念やビジョンはありますが、社員への浸透度はマチマチ...
かく言う当社も経営理念がなかなか浸透せず、苦労しています...
なぜ経営理念の浸透が、これほどまでに難しいのでしょうか?
そもそも、ミッション・ビジョン・バリューを社内に浸透させることが、本当に必要なのでしょうか?
この難しい問いに対し、ドラッカー氏の考え方も参考にしながら、今月と来月の2回に渡り、一緒に考えていきたいと思います。

■ 理念の浸透活動は、往々にして経営者側の一方的な都合によるもの
経営理念の位置付けを中立的な立場から俯瞰して眺めてみると、興味深いことに気付きます。
実は経営理念が組織に浸透することの利害、経営者と社員との間では、短期的には全然一致していないんですよね。
経営者は全体的、長期的視点から、事業を俯瞰する役割を担います。
そして経営理念となる「なんのために会社が存在するのか?」、あるいはビジョンとなる「5年後の在りたい姿はなにか?」という根本的問いは、経営者にとって一丁目一番地。
そこが会社の中心点なので、会社の中心的立ち位置にいる経営者にとっては、理念やビジョンは身近な存在です。
というか、中小零細企業の場合、理念やビジョンは経営者がひねりにひねって絞り出した、経営者自身にとっては思い入れの強い”自分の想い”。
誰かに聞かせたい、社員と共有したい欲求も、自然に働きます。
「経営理念の浸透により、組織が同じ方向に向かって進みやすくなる。
また、個々の社員が自律的に判断し、行動できるようになる。」
そんな目的から、経営理念を組織全体に浸透させたいという強いニーズも、経営者側にはあります。
「組織のベクトルを合わせることは、社員の皆さんも含めた会社全体にとって、とても大切なことなんです」と、私も事あるごとに声高に叫んでいます。
私たち経営者はそれが正しいと信じていますが、社員の視点から見た場合、果たして本当に彼らにとっても正しいことなのでしょうか?

大半の社員には、日々対処すべき目の前の仕事があります。
自ずと意識や関心は、「如何に日々の仕事の質を上げるか?」に向きます。
経営理念の存在は知っていても、内容は極めて抽象的で観念的。
仮にその内容を暗記したとしても、日々の仕事には役立ちません。
たとえば、日本を代表する大企業の経営理念は以下の内容です。
「最高の品質で社会に貢献」 (タイヤメーカー)
「喜びを創り 喜びを提供する」 (食品メーカー)
「確かな安心を、いつまでも」 (生命保険会社)
仮に私がその会社の社員だったと想像した場合、その会社の理念を如何に日々の仕事で活かそうか、正直悩んでしまうと思います...
経営理念は、社員が困難にぶつかったとき、或いは判断に迷ったとき、「羅針盤」として活用できるとよく言います。
一方、社員が実際なにかの困難にぶつかり、その羅針盤を見たとき、その羅針盤には「社会貢献」「人々の笑顔」等、ある意味当たり前、そして観念的なことしか書いていません。
「具体的にどうすればよいのか?」という、すぐに役立つガイダンスとしては活用できません。
それを活用できるようになるには、社員側がその抽象度の高い言葉に近づき、自分なりの解釈を導き出す、修行のような鍛錬を必要とします。
今期の具体的な成果を経営から求められている社員に、そんな時間的、精神的余裕があるのでしょうか?

ちなみに当社の経営理念は、「ずーっと元気な明日(あした)のために」。
経営者である私にとっては、この理念は禅問答のようなもの。
その理念の奥底にある“WHY”を自問自答し、より深淵なる自分への問いが生まれてくることで、私自身を奮い立たせてくれます。
一方、社員視点で考えた場合、その理念の奥底にある“WHY”をどこまで感じてもらえているかは、正直自信がありません...
そもそも、それを社員に期待すること自体、経営者のエゴなのかもしれません...
経営理念は、もしかしたら経営者の自己満足のための道具なのかもと、思い悩んでしまうことが時々あります...
長くなりましたので、今月号はここまで。
次月号では、ドラッカー氏の視点を参考にしながら、「経営理念の浸透は本当に必要だろうか?」という問いについて、引き続き一緒に考えていきたいと思います。

~前号の「リーダーシップとは人の視座を高めることである」を読み返す~
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
