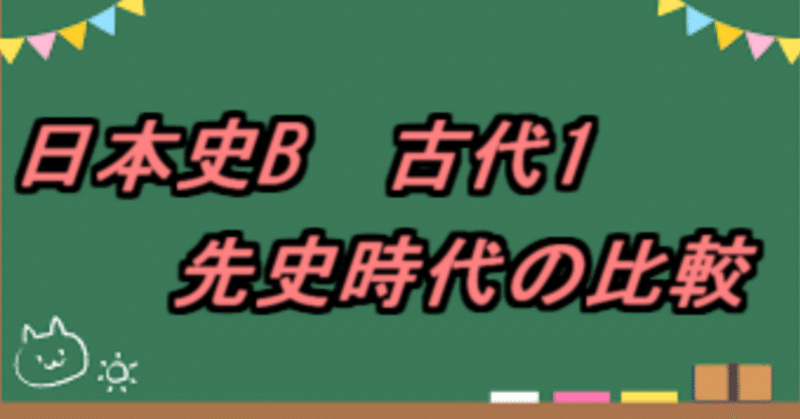
日本史B 古代1 先史時代の比較
Ⅰ旧石器時代
1万年前まで続いた
先土器時代とも呼ばれ土器は使われなかった
狩猟(しゅりょう)・漁労(ぎょろう)・採集(さいしゅう)によって生活
移動生活が中心で、洞窟や岩陰に住んだり簡単な住居を作ることが多かった。
気候は更新世(こうしんせい)
氷期と間氷期を繰り返した
大型動物が生息した
ナウマンゾウやオオツノジカなど
打製(だせい)石器を使用した 画像でチェック!
尖頭器(せんとうき) 細石器(さいせっき)
代表的な遺跡:岩宿(いわしゅく)遺跡
Ⅱ縄文時代
縄文土器を使用した 画像でチェック
狩猟・漁労・採集をによって生活
縄文時代末期には農耕(のうこう)も行った
気候は完新世(かんしんせい)
温暖化:大陸から切り離され日本列島をが形成
中小動物が生息
イノシシやニホンジカなど
中小動物の行動範囲が狭いため、定住生活が可能になった
竪穴式(たてあなしき)住居が誕生する
磨製(ませい)石器を使用した 画像でチェック
弓矢の発明
石鏃を作るために黒曜石(こくようせき)の交易
漁労のための骨角器(こっかくき)
打製石器も並行して使われました
新石器時代(縄文時代以降)が始まっても農耕と牧畜は行われなかった
竪穴式住居に住んでいた
ゴミ捨て場として貝塚(かいづか)があった
縄文時代の信仰
アニミズム…自然物や自然現象に霊意を見出し崇拝すること
土偶(どぐう)を作り、抜歯(ばっし)を行った
埋葬は屈葬(くっそう)によって行われた
代表的な遺跡
大森(おおもり)貝塚
加曾利(かそり)貝塚
三内丸山(さないまるやま)遺跡
Ⅲ弥生時代
弥生(やよい)土器を使用した 画像でチェック
農耕が開始された
米の貯蔵量によって貧富の差が発生
富を巡って争いが発生
気候は完新世
温暖化:から切り離され日本列島をが形成
青銅器や鉄器の伝来
青銅器:祭器としての使用(武器ではない)
銅剣・銅鐸・銅矛など 画像でチェック
鉄器:農具・武器として使用
農業について
前期は湿田・木製農具
後期は乾田・鉄製農具
石包丁(いしぼうちょう)の使用 画像でチェック
高床倉庫(たかゆかそうこ)への貯蔵 画像でチェック
田下駄(たげた)の使用 画像でチェック
敵の侵入を防ぐための集落が作られた
環濠(かんごう)集落…集落の周りに堀を巡らせる集落
高地性集落…高台作られた集落
弥生時代の信仰
墳墓の出現
裕福なものが自らの権力を示すために作った
支石墓(しせきぼ)
甕棺墓(かめかんぼ)
方形周溝墓(ほうけいしゅうこうぼ)
墳丘墓(ふんきゅうぼ)
埋葬は伸展葬(しんてんそう)によって行われた
代表的な遺跡
吉野ヶ里(よしのがり)遺跡
登呂(とろ)遺跡
次に見てほしい記事
いいねやnoteのフォローもお願いします。これから記事を書く時の励みになります。
また、ツイッターもやっているので、こちらもフォローしていただけると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
