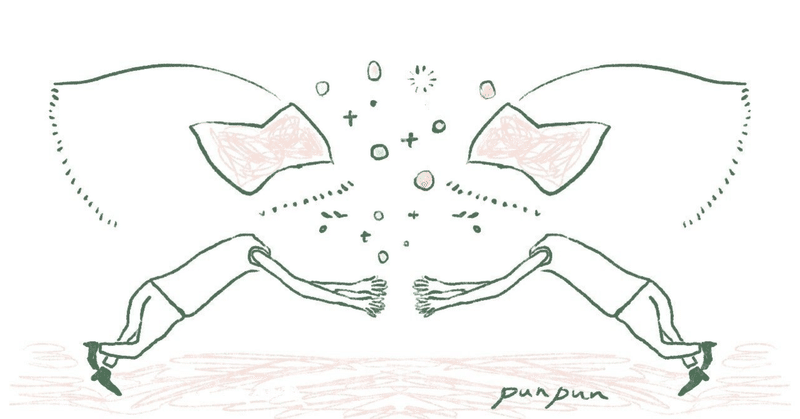
ありたい姿とできる事との、バランスを整える
"絶望"をのりこえる方法は、なんだろう。
"絶望"と言ってしまうと少し大げさだけど、日々の中での"困ったな"を上手にのりこえたい。
たとえば困った事とは別の事を考えて、気を紛らわせる。
気を紛らわせることで気持ちが切り替わり、困った事の捉え方が変わってくる。
人それぞれ困った事の乗り越え方には、経験から生み出されるパターンがある。
人は生きていると、悩みは尽きない。
それは今も昔も変わらない、永遠のテーマであることを哲学者の言葉に見る。
■
「子どもの頃から哲学者」苫野一徳 を読む。
19世紀のデンマークの哲学者キルケゴールは、
「僕たちが絶望しているとき、それは何か特定のことに絶望しているのではなく、実は自分自身に絶望している」という。
18世紀のフランスの哲学者ルソーは、
「わたしたちの欲望と能力のあいだの不均衡のうちにこそ、私たちの不幸がある」という。
そして苫野一徳氏は、不幸から抜け出す三つの道を提示する。
①能力を上げる。
②欲望を下げる。
③欲望を変える。
キルケゴールは"唯一の救いは可能性である"と言った。
その"可能性"を見出すための三つの道。
人が困難を感じるときは、何かうまくいかないと感じるとき。欲望と能力のあいだの不均衡があるとき。
ありたいという姿と現実の姿にギャップがあるとき。
不幸や絶望とまではいかないが、日常的に小さなギャップは沢山ある。
小さなギャップ積み重なると、ストレスに感じたり、それこそ不幸に感じることもあるかもしれない。
子育てをしていても、親が想定した通りに物事は進まない。日常のことだが、困難に感じることもある。
苫野氏が提示するように、ありたい姿を変えてみることで可能性を見出せる。
ありたい姿 A : 本当はまっすぐ家に帰って、夕飯の支度をしたい。
現実の姿 : 子どもが道草していて帰れない。
ありたい姿 B : 夕飯の準備は手軽に済ませられるものに切り替え、子どもとの道草を楽しんでみる。
ありたい姿を変えることで、思っていたように夕飯の支度はできないけれど、準備を簡易的に済ませることで夕飯の時刻には間に合う"可能性"がでてくる。
■
書籍の中では、苫野氏が人生の中で絶望してきたことや哲学を学び、絶望を乗り越えたことについて書かれている。
自分自身と重ねても、人生の中でコレだと思っていた道が塞がっていることに気づいたとき、大きな絶望に襲われる。立ち直れない。
でもそこに、小さくても可能性を感じることができれば、少しずつでも生きる楽しみが湧いてくる。
哲学は難解だと思っていた。しかし苫野氏の本書では、思わず笑ってしまうような人生談と共に、わかりやすく哲学が紹介されていた。
絶望という大きな事でなくとも、日々感じる困難も、苫野氏が提示する三つの道で可能性を見出せる。
困難に感じた事を切り替える術を持っておくと、しなやかさにつながり、二つ三つと道を見つけて進む力が身につくように感じた。
「子どもの頃から哲学者」苫野一徳
— イノウエ ✍🏻💭 (@noz_inoue) November 15, 2021
"絶望において可能性のみが唯一の救い キルケゴール"
"欲望と能力の間の不均衡に不幸がある
ルソー"
"不幸から抜け出す三つの道ー能力を上げる、欲望を下げる、欲望を変える 苫野一徳"#哲学 pic.twitter.com/TJOj0bg8WW
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
