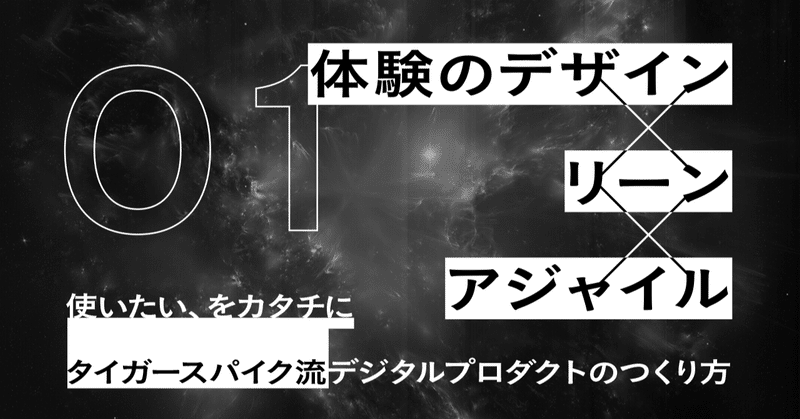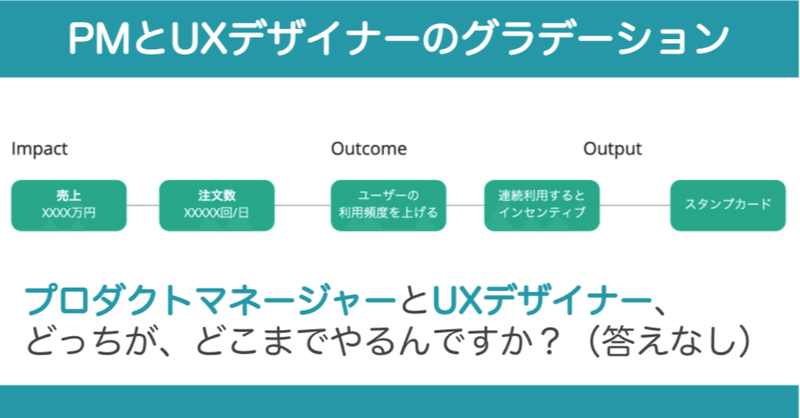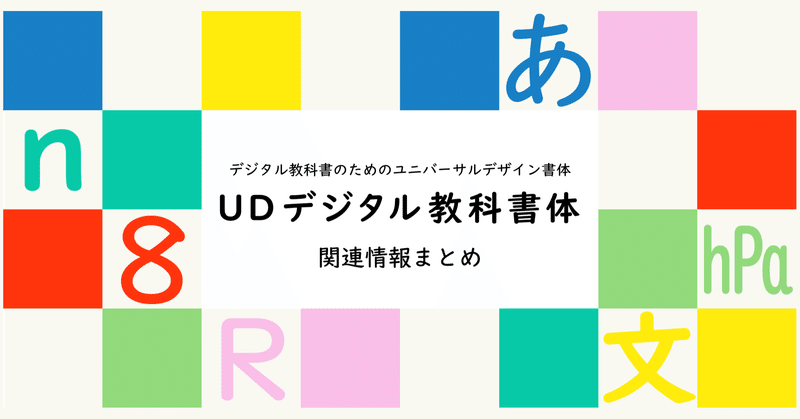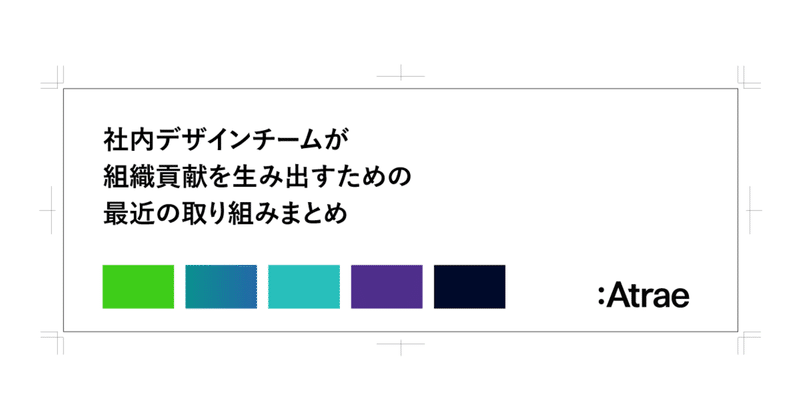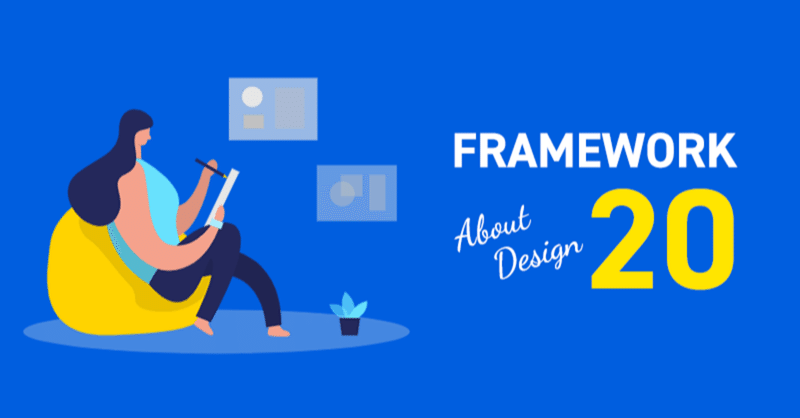デザイン系の記事を収集してまとめるマガジン。ハッシュタグ #デザイン のついた記事などをチェックしています。広告プロモーションがメインのものは、基本的にはNGの方向で運用します。
- 運営しているクリエイター
2021年7月の記事一覧

わたしの、あなたの、関わりをほぐすために、新たな方法を見つけたい。身体と思考と感覚をほぐしていくこと。その可能性や手法とは?企画を立ち上げたナビゲーターへ、8つの質問!【8/2(月)12:00まで締切延長!】
Tokyo Art Research Lab の東京プロジェクトスタディ1「わたしの、あなたの、関わりをほぐす ~共在・共創する新たな思考と身体を拓く~」では、ただいま参加者募集中です!(8/2[月]12:00申込締切) ナビゲーター・和田夏実さん(インタープリター)と岡村成美さん(Designer/Director/Costume Designer/Artist)は、手話を第一言語とするコーダ(ろう者の両親のもとに生まれた聴者の子供[CODA/Children of Dea