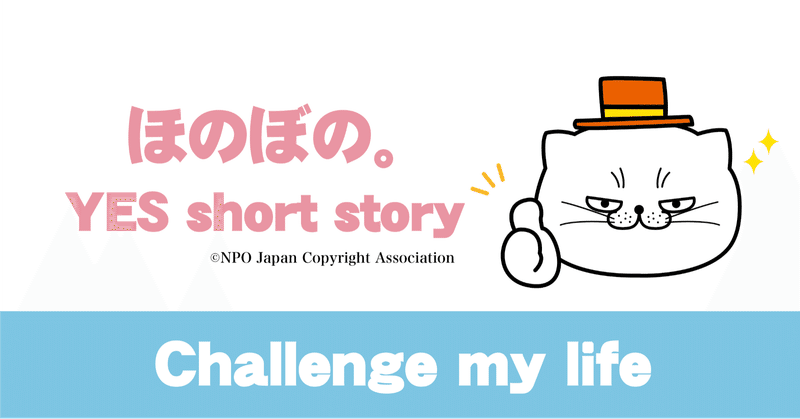
111.どちらが不幸の花で、どちらが幸福の花なのですか?そのうちの一つがお前の子供の花だ。
ある母親の物語
母がこの世を去ってから161日目を迎えた日、私は中学生のときに読んだアンデルセンの童話『ある母親の物語』を思い出した。
あれから50年以上の時が過ぎたのに拘わらず、子どもにとってアンデルセンの童話はとても残酷で、哀しく、胸の痛む作品ばかりであまり興味はなかった。
それぐらい酷い物語ばかりだったからだ。
だが、なぜか心に母の姿が浮かんできた…。
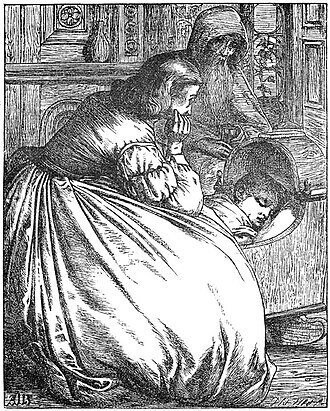
ある母親の物語(Alfred Walter Bayes, Dalziel Brothers)
話は、まだ幼いわが子を案ずる、ある母親の物語だった。
その母親は病弱な我が子が死んでしまうのではないか、といつも心配し続けていた。その子は病気を患い、その顔は青白く、かすかな弱々しい息を繰り返し、その息は今にも止まりそうだったからだ。
ある日、家の扉を叩く老人がいた。扉を開けるとみすぼらしい一人の老人がいた。彼は寒さに震え何かを伝えに来たかのように思えた。
外は凍るような冷たさと、雪が積もり氷の世界と化していた。
母親は、眠る子どもを後にして、老人を温かな暖炉に案内をした。
母親はその薄汚くみすぼらしい老人に温かな飲み物を出して、子どもの話をした。
「この子はまだ、生きることができるでしょうか?私はかみさまを信じていますから決して私から取り上げたりしないと思っています…」
母親にしてみれば子どもと二人きりの生活の中で、この老人がかみさまの使いだと思ったのか、我が子の状況を話し続けました。
しかし、老人は他人事のように、「そうだ」とも「そうではない」とも取れるような頷きを繰り返すだけだった。
母親は我が子の看病で三日三晩、いやもうそれ以上かもしれないがほとんど眠っていなかった。そのため話しながら深い眠りに落ちてしまった。
一瞬、ふっと目を開けたとき、老人はいつのまにか消えてしまったのだ。
後ろを振り返ると、子どもも一緒にいなくなっていた。
すると、突然大きな音がした。
それは、部屋の隅にかけてあった古い時計の振り子が床に落ちた。それと同時にその時計は止まってしまった。
母親は慌てふためいた…。
すぐさま扉をあけて雪の積もった氷の世界に飛び出した。母親は我が子の名前を泣き叫ぶ。まさか、あの老人が子どもを連れ去ったのか、と考えながら、狂ったかのように雪の中を走り続けた。
外の雪は容赦なく母親に降り注いでいた。
すると、真っ白な世界にぽつんと黒い服を着た女の人がいた。
彼女は、哀れなその母親に声をかけた。
「あれは、かみさまなんかじゃあないよ!神は神でも死神だよ!私はあんたの子どもを連れ去るのを見たよ。可哀想だが、死神は一度連れて行ったものは二度と返すことはない。諦めた方が早い…」
なんと恐ろしいことなのでしょう。
「どこに行ったのか教えてください!」
母親は大きな声で話すと、彼女は、
「私は知っているが、その前に、あんたがいつも子どもに歌っている子守唄を聞かせてほしい。私の名は『夜』という。私は子守唄が大好きなんだよね!」
母親は泣きながら歌いました。それで我が子と会えるならば…。『夜』は座ったまま静かに聞き続けた。

©NPО japan copyright association Hiroaki
すると、
「向こうの暗いモミの木の森の中へ行きなさい。そっちへ行くのを見たよ!」
母親はいわれるままに森に入ると、道は十字に分かれ、そこに、葉も花もついていないイバラの藪があった。途方に暮れた母親はその『イバラ』に話しかけた。
「『死神』が、私の坊やを連れて通るのを見かけませんでしたか?」
「見たとも!だが、私をお前さんの胸で温めてくれないと、言わないよ。
私は凍え死にそうなんだから」
母親は、すぐさまいわれた通り胸にイバラを抱いて温めた。そのとげが胸に刺さって、血を流した。その代わり、このイバラは緑の葉を出して、冬なのに花を咲かせた。それほど、母親の胸は温かだったのです。
ここで、約束通り、『イバラ』は道を教えてくれた。
次は、大きな湖の前に来た。
しかしそこには、船もボートもない。我が子を取り戻すためには、この湖を越えるしかない。
母親は、最後の手段として、この湖を飲み干そうとして身を投げた。
しかし、人間が湖を飲み干すことなどできるわけがない。
するとその姿を見ていた『湖』が、
「そんなことしたってだめだよ。
それより相談だが、わしは真珠を集めるのが好きでね。
あんたの目は、今まで見た中で一番澄んだ真珠だ。
もしあんたが、泣いてその目玉を流し出してわしにくれたら、向こう岸の温室まで運んであげよう。死神はそこに住んでいて、その花や木、一つ一つが、人間の命なのだよ。」
すると母親は躊躇なく承知して、泣いて、泣いて、両方の目玉は湖に沈めると、美しい真珠となった。
『湖』は約束通り、母親を向こう岸へ運んでくれた。そこには、何マイルもある不思議な家があったが、母親は目がないので、それを見ることができない。
何やら人の気配を感じた母親は、
「私の坊やを連れ去った死神には会えるでしょうか?」
「まだここには戻ってないよ。けれど、どうしてここが分かったんだい?」
どうやら、この人はこの死神の家の温室の世話係の墓守のばあさんらしい。
「かみさまが助けてくださったのです。あなたもきっと、優しい方でしょう。私の坊やは、見つかりますよね?」
するとばあさんは、
「かみさまだって?そんなものはいないよ!それに、そんなこと、わたしに分かるもんかね。それに、昨夜はたくさん、花や木がしぼんでしまったんだよ。もうじき死神が来て、植え替えられるだろうよ。人間はそれぞれ、命の木か、命の花を持ってるんだ。これには心臓の音が聞こえるんだ、お前の子どもも、音を頼りに探せば分かるかもしれない。けれどもお前さん、このことを教えてあげた代わりに、何をくれるかね?」
「もう何も、あげるものはありません。」
「それじゃ、お前さん、その美しい長い黒髪をくれよ。その代わり、私の白い髪をあげよう。」
母親は、
「その他に、望むものがないなら、喜んで差し上げましょう。」
こうして母親は、美しい黒髪をばあさんにやって、ばあさんの白い髪をもらうことになった。
そして、二人は、死神の家の隣にある大きな温室に入った。
その中には花や木が、いろいろ生えてあり、あるものは元気に、あるものは病気で、どの植物も、それぞれ名前を持っていた。
そして、それぞれが人間の命で、世界中に散らばって生きているのだった。
母親は、一つ一つの植物から心臓の音を聞き、とうとう自分の子どもを見つけました。
「これです!」
母親はそう叫んで、小さな青いサフランに両手を伸ばしました。
しかし、この花は、すっかり衰えてしまっていました。
「こらこら、その花に触っちゃいけないよ!死神が来たら、その花を引き抜かせないようにするんだよ。引き抜こうものなら、お前の方から、他の花も抜いてやるとおどしてごらん。死神は、神様の許しがなければ、どんな草でも引き抜かないと約束してあるから、困るだろうよ。」
ばあさんはそう言いました。

©NPО japan copyright association Hiroaki
ようやく我が子のいる場所にたどり着いた母親は涙を流す目もない、とその時、死神が帰ってきた。死神は驚いた…。
「お前はどうしてここが分かった?どうしてわしよりも早く来れたのだ?」
「私は母親でございますもの。」
死神は、その長い手を、衰えている花へ伸ばしました。
母親はその花を、かばうように自分の手で覆い、触らせないようにした。
すると死神は母親の手に、息を吹きかけると、それは冷たく、母親の手はしびれて、ぐったりなってしまった。
「わしに逆らおうとしてもだめだぞ。」
「子供を返してください!」
母親は涙を流してそう言い、いきなりそばにあった美しい花を二つつかんで、ばあさんのいう通りに、
「あなたの花を抜いてしまいますよ。どうなったって構うもんですか!」
死神は、たじろぐ。
「それはやめろ!やめてくれ!お前は、自分が不幸だというが、他の母親も同じ不幸に陥れようとしているのだぞ!」
「なんですって!」
母親は、すぐ花を手から離した。
死神は、
「このお前の目を受け取りなさい。わしはこれを湖から拾って来たのだ。
それで、そこの深い井戸をのぞいてみなさい。お前が今引き抜こうとした二つの花の人間を見せよう。その花の行く末と、その人間の一生を映してみせよう。そうすればお前がどういうものを引きちぎろうとしたかがわかるはずだ。」
目を戻した母親は、井戸の中をのぞいてみた。
そこには、一つの命が、世の中に多くの幸福を広げていくのが見えた。
今度はもう一つの命が映り、それは悲しみや苦しみ、不幸が満ち溢れていた。
死神は、
「どうだ、両方とも神様の御心だ。」
母親は、
「どちらが不幸の花で、どちらが幸福の花なのですか?」
死神は、
「それは言うまい。だが、そのうちの一つがお前の子供の花だ。お前が見たのは、お前の子供の行く末なのだ。」
これを聞いた母親は、
「どちらが私の子供なのか、言ってください!あんな不幸な目には遭わせないでください!いっそ、神様の国へ連れて行ってください。私の言った事、お願いも、みんな忘れてください。」
死神は、
「お前はよく分からん。お前は子供を返してもらいたいのか、それとも、お前の知らない国へ連れて行って欲しいのか?」
母親は、ひざまづきながら、
「神様!私の願いは聞かないでください。
あなたの御心こそ、この上ないものです。」
こう言って、母親は涙を流して頭をうずめました。
死神は、母親の子どもを連れて、知らない国へ行ってしまいました…。

アンデルセンの肖像(1869年)

coucouです。みなさん、ごきげんよう!
ここまで読んでくれて、ありがとう。
しかし、なんと酷い、哀しい物語なのでしょう?
この童話は、母親の愛情がものすごく伝わってくる話でした。
イバラを抱いて血を流し、目を失い、美しい黒髪まで失っても、決して子供をあきらめませんでした。死に逝く子どもを目の前にした親はそのときにどう考え、どんな思いを馳せるのでしょう?
私はアンデルセンの童話の中で、なぜだかこの物語が、幼い頃からずっと忘れられませんでした。母は子どもの為に命を捨てる事さえ覚悟しています。そのためには何をしてでも、と考えます。これは、まさに母親の執念の物語です。
しかし、死に逝く子どものいのちを長引かせるために苦しみを与えてしまう恐れがあります。
私が子どもの頃、医者から余命を宣告され、治すことのできない病にかかりました。母はそれでも薬を望みます。たとえどんな薬でもいいから飲ませてほしいと医者に縋り、私の身体は注射針の後だらけ、内出血で針の後は紫色に変色し、どこにも張りを刺す場所がなくなりました。
私の身体はさらに酷くなりました。酷くなればなるほどさらに強い薬を飲まされるようになりました。私の母にしてみれば、どんなことをしてでも我が子を活かしたかったに違いありません。
まさに、アンデルセンの『ある母親の物語』に似ていました。
私の母の執念も凄いものでした…。
自分より子どもが先に旅立つことなんて考えられない、許しがたい、あまりにも不憫すぎる、と私たちは考えてしまいます。しかし、その愛情も度が過ぎれば子どもを追い詰め苦しませる場合もある、死神はそう伝えているのかもしれません。
この童話は、こんなにも母親は苦しみ、童話「幸せの王子」のように何もかも失い、最後に王子はつばめとともに天に上ったようなハッピーエンドではなく、我が子が不幸な花なのか、幸せの花なのかもわからないまま、神に子どもを託しました。楽しい幸せな物語ではなくて、悲しいまま終わってしまって釈然としないまま、恐ろしくて救いようのない物語がある事に衝撃を受けたのを覚えています。
誰もは、母親が、父親がこの世からいなくなることに恐れを抱きます。ましてや我が子が病になり、この世を去るなどと考えるだけでも恐ろしく感じます。ましてや、愛する人が目の前から消え去ることも同じ、考えられないくらいの恐ろしさです。
しかし、それは相手を愛するあまりだけでなく、自分がいてもらわないと辛い、寂しいという自己愛もそこには存在していることは事実です。失う寂しさではなく、自らが寂しい、哀しいという一種の我儘に似たものかも知れないからです。
この物語は、ただの童話ではなく、人生の哲学なのかもしれません。
人の運命は私達人間にはどうすることもできないのですから。自分の幸せのために運命に抗って我が子を取り戻しても、それは我が子の幸せではないのかもしれません。
最後に母親は、運命という神にすべてを委ね、あの日から止まったままの時計の針が少しずつ動きだすような気がします。
「神の御心に従って我が子の魂を神の国へ連れて行ってほしい」と。
愛する人がこの世からいなくなっても、どこにいても、どうか幸せでいてほしい。それがこの物語の背後にある意味のように思える、この頃です。

岩波文庫 完訳 アンデルセン童話集
「児童文学のノーベル賞「国際アンデルセン賞」」
アンデルセンの名を冠する「国際アンデルセン賞」のメダルには、
アンデルセンの横顔が刻まれている。アンデルセンの「業績」を示すために最も手っ取り早いのは、やはり「国際アンデルセン賞」の存在でしょう。二年に一度、「児童文学への永続的な寄与」に対する表彰として開催されるこの賞は、「小さなノーベル賞」と評されるほど絶大な影響力を誇っています。
![]()
みなさん、いつも、長いnote記事におつきあいありがとう!
また、あしたね!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
