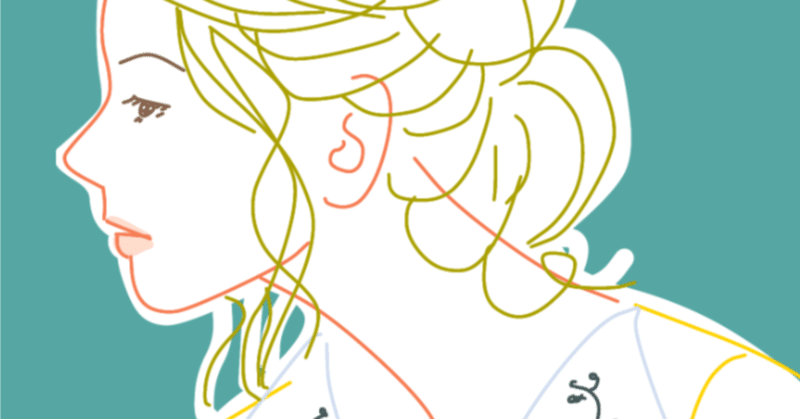
組織を組織たらしめるものとは「学習しない」硬直性であり、そうであるがゆえに巨大化可能で、政治的ステークホルダーになれるのかもしれないね説。
藤原祥太郎. "地域開発をめぐる諸団体の論理とその動態分析-京都市崇仁地区をケーススタディとして." eJournal of Urban Management/Creative Cities 17.1 (2022).を読みました。面白かったです。
京都市の特徴として政治社会学者の筒井清忠は「日常行政については原局主義がとられている。すなわち政策決定にあたっては、各部局の見解に大きく依存し、全体に権限を下に移譲しながら組織運営を行っていくシステムとなっている」(注25)とし企画調整機能が弱いことを指摘している。また京都市元職員である淀野実は「京都市は戦災を免れたことで維持管理がベースとなり、建設局等の事業部局が重視され、事業ごとに対策室を設けるという場当たり的な組織編成で、90年の企画調整局設置まで、経常的な市政全体の計画策定、進行管理の機能が不在であった。また財政基盤は極めて脆弱」(注26)と指摘している(P122)
なるほど、江戸幕府っぽい。各藩の自治が基本で、よそのことには口を出さない。翻って、自治が強く統治機構が弱いということでもあり。
本論を通じて筆者が最も強調したい成果は、「開発構想の策定やそのものの物理的・政策的な範囲の拡大など、地区を取り巻く要因が変化しても、組織の論理・認識そしてまちづくりにおける各アクター相互間の関係には変化が見られない」ということである。言わば「学習しない組織」として相互のアクターが同様の課題を引きずっている、そのことによって新しい外部からの変化に対し、柔軟に対応できていない結果を招いている。(P128)
なるほど、このような地域のステークホルダーを「学習しない組織」の特徴
で説明するのか。
「学習する組織」って本が一時期話題になったけど、話題になる程度には、一般の組織体は「学習しない」のである。
サポートされると小躍りするくらい嬉しいです。

