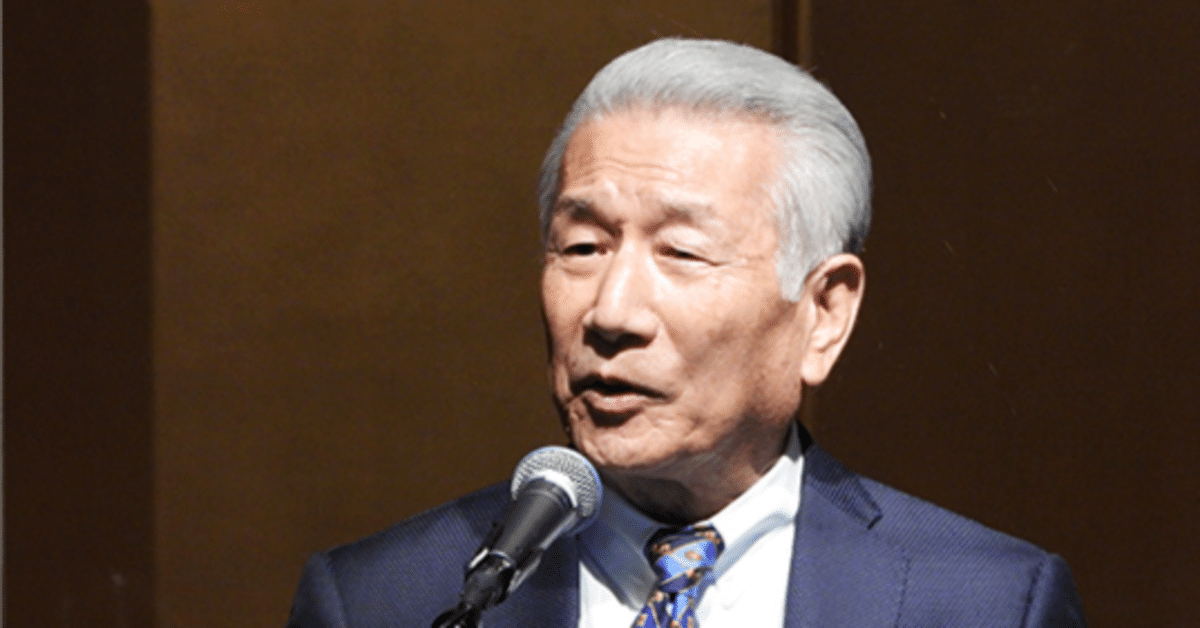
緊急連載・第3回「医療人は、患者の『もっと生きたい』を受け止め、全力を尽くすべき」
*最適な介護を、自分で選ぶための情報紙*
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌日本介護新聞┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
*****令和4年8月2日(火)第149号*****
◆◇◆◆◆─────────────
緊急連載・第3回「医療人は、患者の『もっと生きたい』を受け止め、全力を尽くすべき」
─────────────◆◇◇◆◆
今回の「緊急連載」は、第1回の「はじめに」で書いたように、日本慢性期医療協会が6月30日、第47回通常総会後に開催した「武久洋三先生・会長ご退任記念講演会」=写真・「日慢協BLOG」より=の内容で、日慢協が「BLOG」に掲載した内容を、弊紙向けに抜粋して構成しています。
元々は日慢協の会員向けの講演であるため、医学用語等がたびたび登場します。可能な限り本紙でも注釈を加えましたが、その部分は読み飛ばして頂いても十分、武久前会長の主張はご理解頂けると思います。どうか気軽にお読み頂ければ幸いです。
────────────────◇
【緊急連載・第2回「基準看護だけでなく『基準介護』『基準リハビリ』を新設するべきだ」から続く】
◆───────────────────
「医療区分も看護必要度制度も廃止し、急性期・慢性期で共通する重症度評価が必要」
───────────────────◆
これからの医療・介護をどうすべきか? 病期に関係なく、統一した重症度評価が必要である。すでに医療区分が導入されて10年以上が経過し、療養病床の入院患者の病態は多彩となり、年齢分布も広くなってきている。
医療区分1の中には重度の病態も多く含まれており、医療区分制度は既に使命を終えている。医療区分の問題点はいろいろと言われている。医療区分1には、このような重症者も多く入ってしまう。現場では非常に苦労する。
重症度の問題も、脱水のBUNの値も全く入っていない。療養病棟の「入院料1」は、90%以上が「医療区分2・3」で埋まっている。これ以上、重くはならないだろう。次に、一般病床で用いられている重症度、医療・看護必要度について述べたい。
これらは、今回(の診療報酬改定で)もさまざまな議論が繰り広げられていたが、そもそも重症度、医療・看護必要度は、看護業務の度合いを示すものであって、医療必要度を具体的に示すものではない。繰り返すが、あくまで看護業務の度合いである。
重症度、医療・看護必要度は、死亡するリスクの高い患者はみな該当する項目である。重症患者が死亡するような状況での医療行為には本来、病棟種別による差はない。療養病床であっても、死亡前は全部、この看護必要度が非常に高くなる。
医療区分制度も、重症度、医療・看護必要度制度も廃止して、急性期だけでなく慢性期も共通する重症度評価が必要となってくるだろう。
◆───────────────────
「医療人は、患者の『もっと生きたい』という思いを受け止め、全力を尽くすべきだ」
───────────────────◆
これからの医療・介護をどうすべきか? 終末期を考えてみよう。「もう歳だから、ろくな治療もせずに『終末期』として対応する」のがよいのだろうか? 治る見込みがあれば、全力で治療するべきなのか? いろいろな意見がある。
日本の80歳以上の高齢者に尋ねてみてほしい。「もう十分生きたから、いつ死んでもいいよ」と言うか? 「元気でもっと長生きしたい」と言うのか? 本人に聞けば「元気でもっと長生きしたい」という人が多いだろう。
私たち医療人は、患者の「もっと生きたい」という思いを受け止め、全力を尽くさなければいけない。症状の改善に努めていても、治療法がなかったり、治療が功を奏さない場合に、はじめて「看取り」を考える。
看取ることよりも、むしろ治療して改善させて日常生活に戻すほうが、非常に大変なことである。看取ることは簡単である。
◆───────────────────
「日本の入院医療は、健康に生活している時よりも、悪い環境で病気を治療している」
───────────────────◆
病院・病床数がどんどん減っている。病床利用率も低下している。一般病棟ではもう7割を切っている。入院も外来も患者数がどんどん減っている。65歳以上の高齢患者の入院受療率が、明らかに低下傾向である。
人口減少による影響も大きいが、病院を施設代わりにして入院していた「社会的入院患者」が、4人部屋以上の多床室で狭い・暗い・汚い病院から、個室で療養環境の恵まれた介護施設へとドンドン移ったからだろう。
終戦後は、6畳に4~5人が寝ていて、食卓を出して、寝るときはたたんでしまって、布団を敷いて寝ていた。今も一緒である。4人部屋~6人部屋である。夜中にトイレに何回も行く。認知症の人が叫ぶ。窓際の人が死にかけている。皆さん、そこで寝られるか?
健康に生活している時よりも、悪い環境で病気を治療している。全て個室にするのは、当然である。その方が早く治る。なぜ、こんなことがわからないのだろうか? 日頃、生活しているよりも悪い環境に無理に入れ込んで治療する。これでは良くなるわけがない。
人口減少が加速するから、病院も病床も減る。4人部屋を2人部屋にして、仕切りをすれば、1人部屋が2つになるではないか? 同じ部屋で一緒に寝ていない夫婦も多いが、入院したとたんに、ほかの人と一緒に寝ることになる。
これは、ありえないだろう? これが日本の入院医療の現状である。病院は「患者にとって、どうしたらいいか?」を真剣に考えて動くことが、結局は病院のためになる。死亡退院率の高い病院が、地域で評価されることはないから、自然淘汰されていく。
◆───────────────────
「病院は治療して病状を改善し、病気を治す場所。介護施設とは機能を明確に分けるべき」
───────────────────◆
今後、医療サービスだけに特化していては厳しい時代になる。関連施設として介護保険施設の設置、在宅(訪問・通所)サービス提供は必須である。入院患者へのリハビリテーションを充実させ、入院期間を短縮する。
急性期病院からの紹介入院を増やす。自宅等からの入院患者を増やす。自宅からの入院患者を増やすためには、地域連携部門の拡充が必要である。そして、外来患者数・往診患者数を増やす。さらに、地域の診療所とこまめに連携をとり、紹介入院を増やす。
もちろん、時間外の救急患者にも対応する。このように地域連携を使わなければいけない。そうすれば、地域内での連携がきちんと回る。病院と診療所の役割分担を明確にする。病院は、地域連携部に優秀なスタッフを配置し、自院に有利な運営をしない。
患者の希望を優先し、かつ紹介元の意向を尊重する。地域包括ケア病棟などでリハビリを実施し、短期間で在宅復帰してもらう。往診をされている近隣の診療所とうまく連携する。
緊急入院の受け入れのほか、診療所が行っていないデイケアや訪問看護、訪問リハ、訪問介護などの在宅サービスを担う。病院と介護施設の役割分担も、明確にすることが重要だ。
介護施設の入所者等の症状が急変しても、医療スタッフがほとんどいない介護の現場ではできることは限られるから、治療効果として満足のいく結果は得られない。その場合はキチンと病院へ行く。
一方、介護ケアがほとんどない急性期病棟で治療して病気は治ったとしても、介護の必要な状況に陥ってしまっている。医療と介護をより密接なものとして、それぞれの専門性を評価する必要がある。
病院には介護ケアを取り入れ、介護の場では病状が変化すれば直ちに病院へ搬送して入院管理し、短期間でもとの施設に戻る。病状に応じて、それぞれの機能に応じた場所で細かく行き来してもらうほうが、確実に患者の状態が良くなる。
これで、有意義な余生を送れるのではないか! 病院は治療して病状を改善し、病気を治す場所である。介護施設とは機能を明確に分けて、運用すべきである。
◆───────────────────
「高齢の慢性患者や要介護者の急変も治療できない病院は、地域では必要とされなくなる」
───────────────────◆
結果的に、住民に選ばれる病院しか生き残れない。地域多機能病院として、地域の信頼を得る努力をしなければいけない。地域包括ケア病棟と回復期リハビリテーション病棟を配置して、二次救急を取る。
さらに、自宅・居住系施設等の入所者の急変時対応を行うことが、地域に選ばれる病院になる。日本はほとんど皆保険だから、どこの病院でもあまり変わらない負担金で医療を受けられる。そのため、よりよく治してくれる病院が選ばれる。
患者が来なければ、病院は継続できない。外来も入院も、地域の他病院より少しでも良いサービスを提供すべきである。患者が病院に望むのは「良い結果」である。急性期医療だけでは、日本の医療制度は完遂しない。
そして、全床療養病床だけの病院は、やがて消滅するだろう。地域の高齢の慢性患者や要介護者の急変も治療できないような病院は、地域では必要とされなくなる。私は「良質な慢性期医療がなければ、日本の医療は成り立たない」を訴え続けて、長くやってきた。
だが正直、くたびれたので(日本慢性期医療協会の会長職を)今日で終わる。
◇─[おわりに]───────
これまでの、日慢協の武久前会長の様々な指摘は、介護業界人にとっても極めて参考になる提言だと、弊紙では捉えています。しかし残念だがら、その貴重な提言は「実現」していない事項が多くあります。
例えば「基準介護」。日慢協では、様々な場でこの「実現」を主張していますが、弊紙が取材している限り厚労省の有識者会議等で、これが議題として取り上げられた記憶はありません。
武久前会長は6月30日で、日慢協という医療業界団体のトップを退かれました。弊紙では、武久前会長の提言に感銘を受けた介護人・医療人は、その意志を引き継ぐべきだと考えています。
弊紙は介護業界の専門紙であるため、今回の講演会の内容を記事として取り上げていくことが、それに応えることにつながると考えています。多くの介護人・医療人が今、それぞれの立場で「最適な介護」「最適な医療」を目指していくことが重要だと、改めて痛感しています。
────────────────◇
◆日本介護新聞・本紙(エンドユーザ─版)バックナンバー=http://nippon-kaigo.blog.jp/
◆日本介護新聞「ビジネス版」バックナンバー(2022年4月分まで)=http://nippon-kaigo-b.blog.jp/
◆ホームページ=http://n-kaigo.wixsite.com/kaigo
◆Twitter=https://twitter.com/Nippon_Kaigo
◆Facebook=https://www.facebook.com/nipponkaigo/
(C)2022 日本介護新聞
