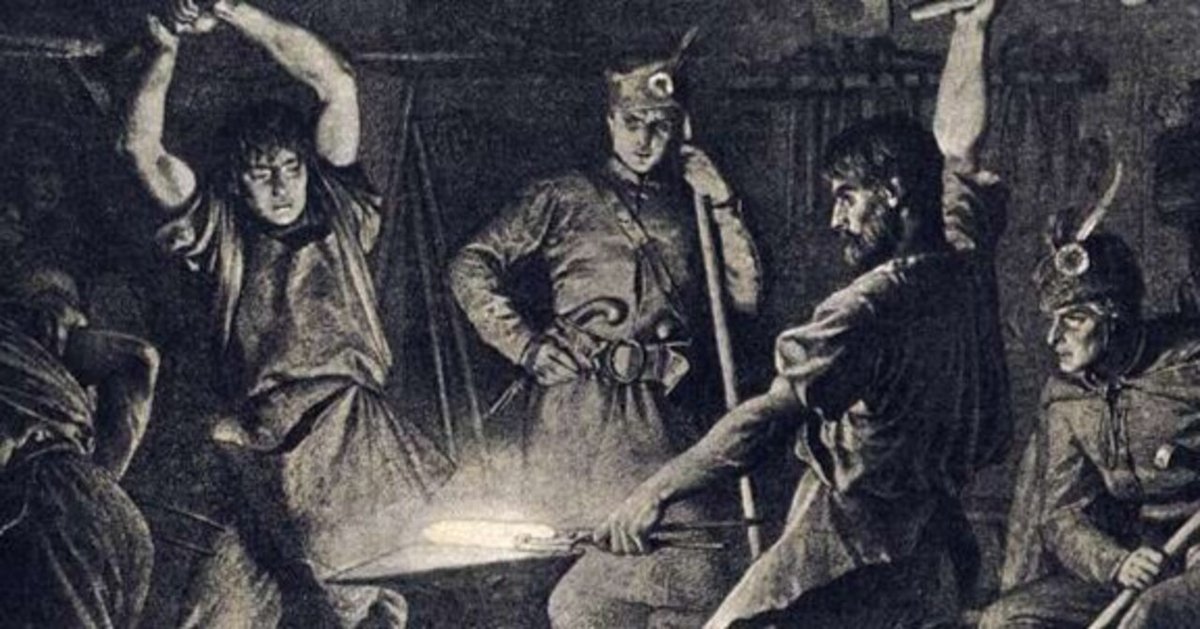
ざっとわかる分割後のポーランドと祖国解放運動
1.はじめに
18世紀後半に行われた、ロシア、オーストリア、プロイセンによる3度にわたる分割によって、ポーランドはヨーロッパの地図から姿を消しました。しかし、19世紀から20世紀にかけて、ポーランド人たちは支配に抵抗し、独立を目指して祖国解放運動を行いました。今回は、列強支配に対するポーランド人たちの抵抗と1918年の独立達成までを見ていきたいと思います。
2.ナポレオンの到来
第二次分割に反対した、タデウシ・コシチューシュコの蜂起に参加したジャコバン派と呼ばれる急進派の多くは、蜂起失敗後にフランスに逃れていました。彼らが期待を寄せたのが、当時北イタリアでオーストリア軍と戦っていたナポレオン・ボナパルトでした。1796年1月、ナポレオン軍が捕虜としていたオーストリア軍のポーランド兵士たちによってポーランド軍団を編成され、以降ナポレオン軍に従い、オーストリア領内へと侵攻しました。

総裁政府によりミラノから派遣され、ナポレオンと協議してポーランド軍団を編成した
1806年、プロイセンがナポレオン軍に敗北し、翌年結ばれたティルジットの和約によって、プロイセンの領土の一部からワルシャワ公国が成立しました。ワルシャワ公国は、ナポレオン法典に倣った憲法を持ち、ポーランド軍団が公国軍となりました。しかし、フランスの行政官が国政を監督し、軍隊もフランス駐留軍の統制下に置かれるなど、実体はフランスの傀儡国家でした。
1812年、モスクワ遠征の際には、公国は遠征軍の兵站基地となり、10万人の部隊を派遣するなど過重負担を強いられました。最後のポーランド国王スタニスワフ・アウグストの甥であるユゼフ・ポニャトフスキがポーランド軍を指揮しましたが、退却するフランス軍の擁護にあたり、そこで落命しました。

ポニャトフスキはワルシャワ公国の軍務大臣に任じられ、フランスの元帥にまで昇進した。
その英雄的最期は、国民詩人ミツキェヴィチの叙事詩『パン・タデウシ』で謳われた
3.ウィーン会議とポーランド王国
ナポレオン失脚後、1814~15年に開かれたウィーン会議の結果、ワルシャワ公国は消滅し、それに代わってポーランド王国が誕生しました。ポーランド王国は、市民的諸権利や言論の自由、法の下の平等などを明記した自由主義的な憲法を持ち、一定の自治権を有していましたが、ロシア皇帝を君主に戴き、外交権をロシアに委ね、軍隊の統帥権をツァーリが握るなど、ロシアの監督下に置かれていました。

By Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk, based on layers of user:Poznaniak - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84316632
1829年にポーランド王として即位した皇帝ニコライ1世は保守的であり、憲法の廃止と王国軍の廃止を断行しようとしました。この動きに対し、フランスの七月革命に影響を受けたユゼフ・ヴィソツキ率いる士官候補生を主力とする愛国派が、1830年11月29日に蜂起を起こしました。地方から愛国派が義勇軍を編成しワルシャワに結集する気配を見せはじまると、議会は満場一致でニコライ1世の退位を宣言し、アダム・チャルトリスキ公を首班とする国民政府が構成されました。

ベルヴェデル宮殿は総督である皇帝の弟コンスタンチン大公の居所であり、愛国派がここを攻撃したことが、十一月蜂起の狼煙となった
しかし、国民政府は左右の対立によって統一した方針を出すことができず、期待された西欧からの軍事支援も受けられませんでした。1831年5月26日のオストロウェンカの戦いで蜂起軍の主力がロシア軍に敗退し、9月7日にはワルシャワがロシア軍に制圧され、この十一月蜂起は終息しました。
4.ロマン主義時代の状況
11月蜂起の敗北後、ニコライ1世は王国憲法の無効を宣言し、王国軍と国会を廃止しました。さらに、合同教会信徒の正教への強制改宗、地方行政の官吏としてのロシア人の登用、公教育でのロシア語の導入など、ロシア化政策が実施されました。他の分割列強におけるポーランド政策も基本的には同じでした。国民政府の首班となったアダム公をはじめ、迫害を恐れた人々は、フランス、イギリス、ベルギー、トルコ、アメリカなど多方面へ亡命しました。その数は1万人を超えたため、「大亡命」と呼ばれています。

パリへ亡命後、「無冠のポーランド国王」として政治外交を指揮した
こうした亡命者たちは、亡命先で組織した「ポーランド民主協会」は、1846年に3つの分割領での一斉蜂起を計画しました。しかし、計画が事前に漏れ、実際に蜂起が起きたのはオーストリア領のクラクフだけでした。そのクラクフ蜂起も、首謀者のエドヴァルト・デンボフスキが射殺されたため、2週間も経たずに終焉しました。
これと同時期に、西ガリツィアでヤクプ・シェーラ率いる農民一揆が起こりました。オーストリア政府は農民と地主との分断を進めていたため、農民たちは200名以上の地主を虐殺しました。これは「ガリツィアの虐殺」と呼ばれ、オーストリアにおける農業改革の実施を急がせる結果となりました。
その2年後、1848年2月には、パリで勃発した二月革命からヨーロッパ各地で革命運動(諸国民の春)が始まり、ポーランド人たちもこれに呼応しました。ポズナンでは「国民委員会」が結成され、ガリツィアではポーランド語の公用語化と賦役廃止を求める請願運動が行われました。しかし、ポズナンはプロイセン政府によって鎮静化させられ、ガリツィアでの運動は、やはり農民とシュラフタの分断によって骨抜きにされました。また、ハンガリーでの蜂起にも多数のポーランド人が参加しましたが、ニコライ1世率いるロシア軍に敗北しました。
5.一月蜂起
クリミア戦争での敗北を機に、ロシアの後進性を痛感した皇帝アレクサンドル2世は、1857年以降、農奴解放や鉄道の敷設、大学や地方自治などの社会的諸改革を目指す「大改革」に乗り出しました。ポーランドでも改革の機運が高まり、検閲の廃止や農民の賦役労働からの解放が議論されました。さらに、繊維、冶金、製糖など工業が発達し、鉄道の敷設も進められました。

ウッチは1820年代末に繊維工業を主体とするマニュファクチュアが勃興し、ポーランドの近代産業の中心地として発展した
一方で、革命的民主主義思想に影響された蜂起の動きも進行していました。1861年2月25日、十一月蜂起を記念する民衆デモが開催され、鎮圧のために警官隊が発砲し、参加者5名が殺害されました。これを機に、ウッチ工業地帯での機械打ち壊しが始まり、農村でも賦役義務に反対する動きが目立ち始めました。ロシア当局は、ポーランド人のアレクサンデル・ヴィエロポルスキを起用し鎮静化を図りましたが、民衆の示威行動はやまず、ついに10月には全土に戒厳令が布告されました。

1863年1月22日、急進的知識人グループである「赤党」の指導部が「臨時国民政府」を称し、蜂起宣言を発表しました。蜂起が各地に拡大したことで、地主やブルジョワジーを主体とする「白党」も合流し、さらにヨーロッパ各地から義勇軍が参加しました。しかし、赤党と白党の主導権争いによって国民政府は混乱し、やがて農民も蜂起から離れていきました。翌年4月、赤党の指導者ロムアルト・トラウグトが逮捕・処刑されると、一月蜂起は急速に衰退し、逮捕されたポーランド人たちは財産を没収のうえ、シベリアに流刑となりました。
6.社会主義と愛国主義
1860年代後半から80年代にかけて、ポーランド王国では工業化が進み、それに伴い労働運動も活発になりました。ロシア領における社会主義運動は、ナロードニキに影響を受けたルドヴィク・ヴァリンスキによって始められ、1883年には初の社会主義政党「プロレタリアート」が結成されました。「プロレタリアート」はワルシャワ郊外の繊維工場で8000人の労働者によるストライキを指導しますが、翌年にはメンバーが大量逮捕され、解体に追い込まれました。

ペテルブルク大学時代に社会主義活動を開始し、ロシアのテロ組織「人民の意志」党をパートナーとしたが、ストライキ失敗後は悪名高いシュリッセリブルク要塞監獄に収容された
1892年のウッチでのゼネラルストライキを機に、翌93年に「プロレタリアート」の流れを汲むポーランド王国社会民主党が結成されました。これを指導したのは、後にドイツで活動することとなるローザ・ルクセンブルクです。同党は、1900年にはポーランド王国・リトアニア社会民主党と改称しますが、ローザの方針により、民族独立は目指さず、労働者の連帯を標榜しました。これに対し、1892年にパリで結成されたポーランド社会党は、民族主義路線堅持し、本国の労働者の間に愛国主義を宣伝しました。

ポーランドに生まれ、後にマルクス主義者としてドイツ社会民主党で活動する。1918年のドイツ帝政崩壊の際に、党首エーベルトが革命否定路線をとったため、脱退して最左翼を指揮し、社会主義革命を目指した。最後は義勇軍部隊により虐殺された
1897年にはポーランド王国で民族主義を基本理念とする国民民主党が誕生しました。同党は反ドイツを掲げ、ロシア政府との妥協も辞さない、排外主義的な民族主義運動を展開し、都市民や富裕な農民の間に支持を広げ、強大な政治勢力へと成長しました。
7.日露戦争と第一次ロシア革命
1904年、日露戦争が勃発すると、2人のポーランド人政治指導者が来日しました。ひとりは、国民民主党の中心人物ロマン・ドモフスキであり、もうひとりは、ポーランド社会党のユゼフ・ピウスツキです。

後にポーランド共和国建国の父となる
ピウスツキは、満州でロシア軍に徴兵されているポーランド兵を投降させ、日本側にポーランド・レジオンを編成する案を示しましたが、ロシアとの融和を重視するドモフスキは、ポーランドで革命が起こるような事態は得るところがないと日本側を説得しました。ドモフスキの説得が影響したのかは不明ですが、結局日本側はピウスツキからの要請を断ったため、彼の対日政策は失敗しました。
満州でのロシアの敗戦はポーランドにも伝わり、厭戦気分の高まりから各地でサボタージュやストライキを誘発しました。さらに、1905年にロシア第一革命が勃発すると、ポーランド社会党、ポーランド王国・リトアニア社会民主党の呼びかけで、ワルシャワ近郊やウッチの工業地帯を中心に約40万人の労働者がストライキに入り、ストライキは農村にも波及しました。

こうした革命運動は1906年半ばから退潮していきますが、ポーランド民衆の政治的、社会的、民族的な意識を深めました。
8.第一次世界大戦と独立の達成
1914年に第一次世界大戦が勃発すると、クラクフで最高国民委員会が設立され、オーストリア領内のあらゆるポーランド諸政党がその傘下に入りました。ガリツィアを活動拠点にしていたピウスツキもその統制下におかれますが、独自のポーランド軍事組織の再編に成功し、ロシア前線での諜報活動や破壊工作に乗り出します。しかし、ドイツ政府はポーランド軍団は同盟組織となりえないと判断し、1917年7月にピウスツキを逮捕します。

1917年2月に帝政ロシアが崩壊し、オーストリア・ハンガリー帝国も解体寸前に追い込まれると、ポーランドはドイツの統制下に置かれ、同年9月には摂政会議が設立されました。しかし、そのドイツも、穀物を目当てにロシアに対して自治を宣言していたウクライナ中央ラーダと個別に条約を結び、ヘウムとポドラシェをウクライナに割譲したため、ポーランドの政治指導部に動揺が走りました。さらに、1918年3月には、ブレスト・リトフスク講和が結ばれたため、ポーランドはドイツともソヴィエト・ロシアとも連帯することができなくなりました。
1918年7月になるとドイツの西部戦線での敗退が決定的となり、ウィルソン米大統領が十四カ条からなる講和計画を宣言しました。この中ではポーランド人の独立国家を創設する案が明記されていましたが、同盟国によって擁立された摂政会議は諸勢力を統率するには力量不足でした。同年11月10日にドイツ帝政が倒壊すると、ピウスツキがワルシャワに帰還してポーランド軍の指揮権を掌握し、臨時国家主席に就任しました。こうして123年ぶりに、ポーランドは独立を回復しました。

ソヴィエト・ロシアからリトアニア、ベラルーシ方面を、ドイツからポズナン、シロンスク、グダンスクからバルト海につながる「ポーランド回廊」を獲得した
By Halibutt - Own work; based on an earlier raster map made in 2005, as well as similar maps made by myself in 2004 (see below).In preparation of this map I used many other maps as sources and backup. Among them were:a German roadmap of Poland printed in 1938 (colours and the shape of East Prussian border)Cznuts2.svgshape of CzechoslovakiaPolish and German riversparts of German shoreline and bordersAustriaSweden and Norway, parts of Denmarkand perhaps a dozen others., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3703674
9.まとめ
19世紀から20世紀初頭にかけてのポーランドは、独立を狙う蜂起の連続でした。それだけ、分割列強による支配は過酷であったと言えます。現在も続くウクライナ侵攻において、ポーランドがロシアに対して強硬な姿勢を示しているのは、こうした歴史的背景があるからだと考えられます。しかし、ポーランドの受難はこれで終わらず、独立から20年ほどで再びロシア(ソ連)の支配下に置かれてしまいます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考
関連記事
分割以前のポーランド・リトアニア共和国については、こちら
分割されたポーランドにおける合同教会については、こちら
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
