
日建グループ オープン社内報|わたしのこだわりの住まい④
白い館の主人が大切にする「縁」
柄澤 薫冬
日建設計 都市・社会基盤部門 都市開発グループ(現在グループ会社である日建設計総合研究所に出向中)
彼は、築40年約120㎡鉄骨造3階建てのビルを所有している。「bunkyo blanc(ブンキョー ブラン)」と名づけられたこの物件は、住居目的だけでなく、1階はバー、2階はゲストハウスを展開しているという。2016年入社、この若さで都内のビルオーナー? 驚きと胸にお話を伺ったところ、縁を大切にして自分の興味ある分野に全力で挑む(それでもどこか自然体な)姿が見えてきました。

地域としっかりとした関係を築くために
――ご自分でビルを所有しようと思ったきっかけは何ですか?
大学院での研究テーマと、そこで得た体験が大きかったと思います。大学院ではプロジェクト型のまちづくりをテーマにしていました。たとえば福井県の三国湊では、北前船の寄港地として栄えた時期に建てられた伝統的な建築物が空き家になっているのですが、それをリノベーションして地域の活性化につなげるという取り組みや、東京神田で生じているコミュニティの分断という課題を解決するプロジェクトなどです。プライベートでも「地域活動に参加する代わりに学生が安く住める」というコンセプトの神田淡路町ワテラスの学生マンションに1期生として入居していまして、その縁もあって町会長や藪そばのご主人等、生粋の神田の人々と仲良くなったり、神田祭に参加してお祭りの面白さを知ったり、地元の居酒屋の人と深夜まで飲んだり、地域の方と結ぶ縁のようなものに魅力を感じていました。私自身は何度も引越しを経験していて、「地元」と思える場所がなかったので、とても新鮮な体験でした。卒業を機にマンションは退去しなければならなかったのですが、社会に出てからも町会のイベントに継続的にかかわっていきたいという思いで、同じ神田地域に引っ越しました。
しかし入社当時は残業も多く業務をこなすことで手いっぱいで、町会行事等に積極的に参加できませんでした。一方で、学生マンションを含め、賃貸に住んでいる人は少なからず「いずれは出て行ってしまう人」と思われてしまうもどかしさもあり、自ら責任を持って地域に関わっていくためにも、路面に面した物件を買い、長い目線で地域と関わっていきたいという想いに至りました。
そこで住んでいた神田から会社のある飯田橋までの間や、大学時代に通いなれた本郷を中心に物件を探しました。しかし神田を筆頭に路面物件は高く、中々購入に至らない中、1年と少し探して、ようやく現在の物件に巡り合いました。場所としては本郷エリアの中で、学生時代からよく通っていた谷根千(谷中、根津、千駄木)のちょうどギリギリ内側にもあたり、 有名な根津神社のお祭りにも参加できるということで、ここに決めました。余談ですが、物件探しをしている時はちょうど妻とつきあい始めた頃で、彼女も早稲田大学で都市計画を学んでいたこともあり、デートにかこつけて様々なエリアの物件探しをしていました。今思えばよく許してくれたな、と(笑)。「きっかけ」というには少し長くなりましたが、以上がここの物件を購入した経緯です。

築40年の中古物件をセルフリノベーション
――購入した物件で、居酒屋、ゲストハウス、シェアハウスを始められたそうですが、用途は初めから決めていたのでしょうか?
妻(当時彼女)とも、どういう形で地域と関わっていこうかとずいぶん語り合い、「一緒に住もうか」というような漠然とした話はしていたのですが、結局購入時には同居しませんでした。
一方で、大学の後輩で、当時(現在も)大学院の博士課程に在籍している三文字(さんもんじ)君という人がちょうど会社を立ち上げたところでタイミングが合い、一緒に活動することになりました。
三文字君は当時、町会・商店会に関わると安く住めるという魚屋さんの木賃長屋に住み、ビールサーバーを置いて自分の家を「居酒屋」と呼んで様々な人が出入りする場所にするなど、人を巻き込み巻き込まれていく力のある大変魅力的な人で、一緒に何かできれば面白いと思っていました。
そこで、彼の会社「流動商店」(https://ryudoshoten.tokyo/)のオフィス兼自宅としつつ、共同代表のもう一人:豊田君が南インドを中心としたスパイス系の料理が得意ということから、じゃあ一緒に居酒屋と宿屋も始めようか、ということになりました。
地名の「白山」、真っ白なところから始めるという意味で、フランス語の「白(blanc)」を使ってこのビルをbunkyo blanc(ブンキョー ブラン)と名づけました。「ブランと泊まれる」というフレーズも気に入っています。
モデルとなったのは、月光荘京都(有名な銭湯の向いにあるゲストハウスで、1階居酒屋になっている)
で、銭湯に訪れた地元の人と宿泊者との交流で新たな文化が生まれることに共感し、そういう地域と新しい文化が交錯するような場所にしたいという思いを基盤に店舗を計画しました。
3階建ての最上階を私と三文字君でルームシェアして、2階の2部屋をゲストハウス(民泊=住宅宿泊事業)として2018年9月にオープン、ついで1階の居酒屋「ことことことぶきkitchen」を2019年1月にスタートさせました。
3階の住居スペースも含め、すべてをセルフリノベーションしたため、2018年6月に購入してから全面オープンまで半年以上かかりました。

――なぜセルフリノベをしようと思ったのでしょうか?
一番の問題はお金がなかったこと(笑)です。工務店にフルリノベーションを頼むと坪単価数十万円しますが、自分たちでやれば坪単価数万円くらいですから。平日は三文字君を中心に、休日は僕も手伝ってという形でコツコツ進めていましたが、いつの間にか参加型のワークショップ形式のようになり、知り合いをはじめ、多くの方に手伝ってもらっていました。わからないことは三文字君の知り合いの大工さんに頼み込んで教えて頂いたり、区役所でのパネル展示で「今度こういうお店をつくろうと思います!」と発表したら、「それじゃあ今度手伝ってやるよ」みたいに地域の方が応援してくれて新しいつながりが生まれたり、色々な縁が重なりました。
建物は鉄骨造なのですが、昭和感あふれるレトロな物件だったので、思い切ってほぼスケルトン状態から自分たちの好きなように改装しました。1階の床を自作するためにトン単位でモルタルをホームセンターで買ったら乗ってきた普通車が重量オーバーで動かなくて急遽2tトラックを借りたり、本当に勢いだけでやっていましたね(笑)。厨房設備や什器などは、商店会長から廃業する居酒屋を紹介してもらい無料で譲ってもらうことができたのも運がよかったです。若さの特権というか、怖いもの知らずだからできたのだと思います。

やってみて初めて気づくことがたくさんありました
――収益性の問題はどう解決しているのでしょうか? 運営方法を教えてください。
私はあくまでも建物大家で、運営は流動商店が行うという形です。自分の住宅も兼ねているので「損してもいいや」という気持ちでいられるのがいいのだと思います。三文字君もまちづくりコンサルや設計業で食べているようなので、お互い収益だけを見込んでいないという気軽さはあります。とは言えきちんと収益もついてきたものの、コロナ禍でゲストハウス、居酒屋とも集客が大きく落ち込んだこともあり、2021年初頭から改装を進めています。
1階の「ことことことぶきkitchen」は開放的な雰囲気のバーに、2階の2部屋あったゲストハウスは1部屋に縮小(改装中)してもう一部屋は三文字君のオフィスに、3階は私と妻の住居としました。
また、1階の空きスペースではギャラリーや無人店舗として、地元の方々が気軽に立ち寄れるような場所を提供しています。
この改装では解体やインフラ関係等ベースとなる部分を工務店さんにお願いしました。セルフリノベーションは愛着も湧きますが、どうしても個人では難しい部分もありますので、壁の塗装や家具などできる範囲はなるべく自分たちでやって、お願いできるところはプロに頼もうと。
――実際に運営を始めて、どんな過程をたどっていますか?楽しかったこと、苦労したこと、勉強になったことを教えてください。
「まちづくりに関わりたい」という気持ちで始めたことですから、会社との両立は苦になることはなく、地域の方たちとの関わりやお祭りなどのイベントに参加できることはとても楽しいです。それでもすべてが順調というわけではなく、リスクも大きいと実感しています。
たとえばゲストハウスを始める際にも「よくわからない人が入って来ることで地域の価値が下がる」というご意見の方もいらっしゃるので、周辺住民に周知して信頼関係を築くのに苦労しました。
また、何かしようとしても人(担い手)がいない、アイデアはあるが実行に移せない、といった問題は、私が本業で取り組んでいる都市開発において「特区などで地域に貢献できるどのような導入機能を入れていくか」という問題とも共通点が多く、これは自ら運営して得られた学びだと思います。
まちの核となり、ためになる新しいイノベーションができたら、という思いは常に持っています。将来的に自らの活動が、特区貢献の具体的な導入機能のメニューの一つとして取り上げられるのが大きな夢ですね。
変化を楽しむ、生まれた縁を大切にする
――家・ライフスタイルのお気に入りのポイントを教えてください。
自分の住まいや地域に深い愛着を持てることです。まだ初めて3年くらいですが、ブンキョーブランはどんどん進化していて、そうしたダイナミズムの中にいられるというのはわくわくします。
「ことことことぶきkitchen」は、もともと私が買う前にこのビルで営業されていた「ことぶき食堂」にあやかり、これからいろいろな「こと」が重なるようにという思いを込めて名づけたのですが、名前どおり、いろいろな縁が重なってきています。
今のキッチンの責任者である来春(こはる)ちゃんは、近くにキャンパスのある大学の元学生です。
これも偶然が重なったのですが、妻の大学時代の恩師が今その大学で教えられていて、近所ということもあり、学生を連れてよく飲みに来てくれています。
来春ちゃんはその中の一人で、実家が古くから続くお肉屋さんをやっていて我々と同じ「商店街を活性化したい」という強い思いから、卒業後に流動商店に就職してくれました。

最後になりますが、このように、大学時代から、仲間や地域の方々から、そしてもちろん日建設計に就職してから係らせて頂いた方たちから、さまざまな「ご縁」を頂いて今があります。これからも出会いを大切にして多くのことに挑戦し、広く社会に還元できるように成長していきたいと思います。
※これは、2021年9月に社内報(日建グループ報)に掲載したインタビュー記事です。
【近況報告】
店内営業だけでなく、料理をレトルトパウチ化して販売もできるようキッチンを追加改修し、2022年7月1日より店名を「流動商店.tokyo」と改め営業を再開します。もともとお店を担当してくれていた来春ちゃんだけでなく、関連メンバーが日替わりでお店に立つスタイルです。より気軽に楽しんで頂けるようになりますので、是非遊びにいらして頂ければ嬉しいです。

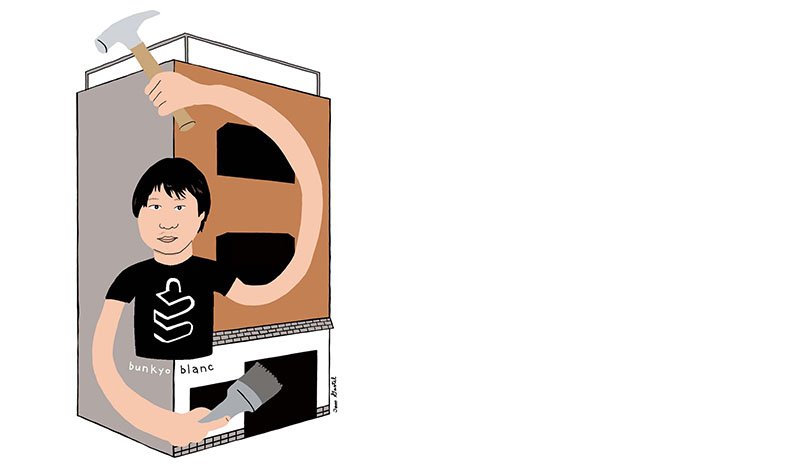
柄澤 薫冬
日建設計 都市・社会基盤部門 都市開発グループ(現在グループ会社である日建設計総合研究所に出向中)
2016年東京大学大学院都市工学専攻修了、日建設計入社。都市開発部、再開発計画部、パブリックアセットラボを経て、2022年より日建設計総合研究所へ出向。都心複合開発(車両基地の跡地活用や駅前再開発)や都市開発制度の設計などの都市計画コンサル業務、P-PFI制度の提案や指定管理業務等に携わっています。プライベートで2018年に本物件を購入。実際に住みつつ、大学時代をきっかけとする仲間とともに「ブランと集まるまちのかど」を営んでいます。
みなさんのお悩みを募集しています
リノベーションについてのお悩みがありましたら、こちらのアドレスwebmaster@nikken.jpまでお寄せください。日建グループのメンバーがそれぞれの専門性を生かして、楽しくまじめにお答えします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
