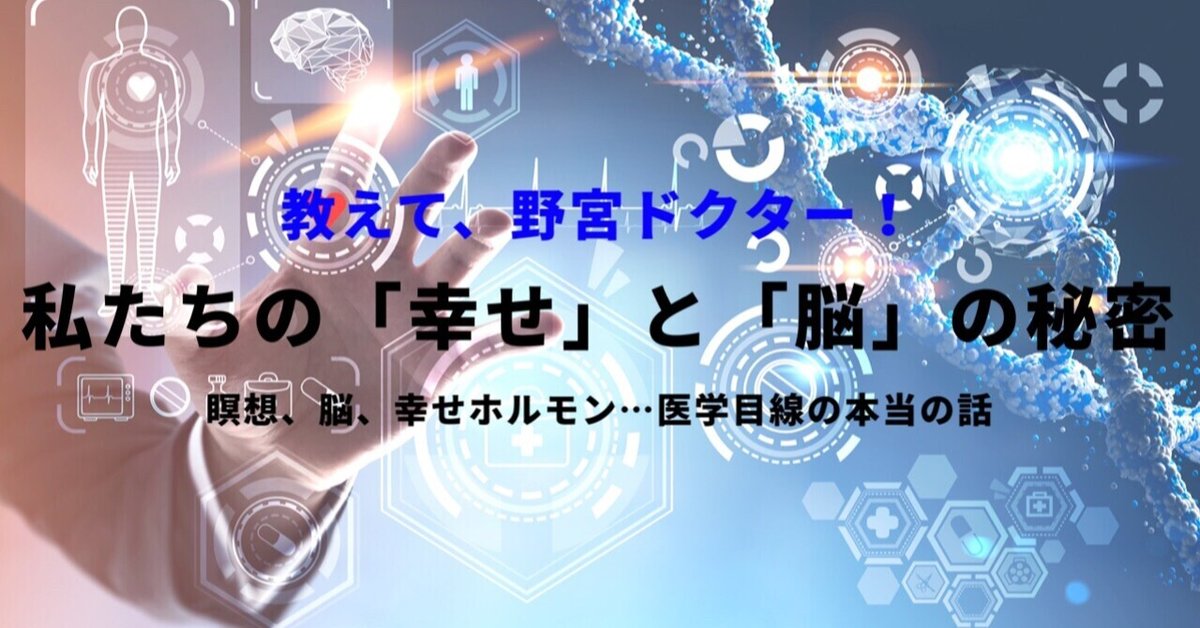
瞑想と睡眠の違い
これまでの記事では「瞑想と脳内物質セロトニンの関係(*1)」や「リラクゼーション瞑想と脳内物質ドーパミン (*2)」について紹介し、瞑想を行うことで“脳内に明らかに物質レベルで変化が起こる”ということが科学的に証明されてきました。そこで疑問に挙がるのが、「何も考えずに無心で瞑想を行う」ことと「何も考えずに普段寝ている」ことはどう違うのだろうか? と考える人もいるのではないかと思います。
私も過去に授業やセミナーで居眠りしていた時に「瞑想していました」と誤魔化したこともあります(怒られましたが、居眠りの口実にしてはいけませんね)。「瞑想していると寝てしまう」「寝てしまうと瞑想の効果はあるの?」という方もいることでしょう。今回は「瞑想状態と睡眠状態の違い」についての研究を紹介します。
論文タイトルは「AN ELECTROENCEPHALOGRAPHIC STUDY ON THE ZEN MEDITATION (ZAZEN):禅瞑想(座禅)における脳波の研究(*3)」で東京大学附属病院の笠松医師らによって報告された研究です。現代では“脳波は勉強中はアルファ波が優位、瞑想中はシータ波優位、云々”ということは基本的なこととして多くの人が知るところですが、この論文は1966年(今から50年以上前)に出版されたもので「瞑想の基本中の基本を解明してきた研究」に焦点を当ててみたいと思います。
この研究実験の協力被験者は禅宗(曹洞宗・臨済宗)の僧侶(高位の僧侶から若い修行僧まで)48名で年齢は24歳〜72歳で満遍なく選ばれました(1〜5年:20人、5〜20年:12人、20年以上:16人)。座禅瞑想に習熟したこれらの被験者の頭部に脳波計の電極を付け、禅瞑想中の脳波が記録されました。脳波計の電極は5点(前頭部、前頭ー頭頂部、頭頂部、後頭ー頭頂部、後頭部)に取り付けられ、瞑想の集中を妨げないような工夫がなされました。禅瞑想の実験は通常通りの禅修行場で行われました(図1)。

座禅瞑想のやり方は禅修行と同様で、足は胡座(あぐら)のように足を組み、開眼して前下方を見つめ、両手を合わせた姿勢(図1)で1回約30分間行います。
比較対照群として、18名の研究員(年齢23〜33歳)と4名の高齢男性(年齢54〜60歳)が選ばれました。これら22名の比較対照者らはいずれも座禅や瞑想の経験はありませんが、被験者の禅僧達と同じ条件で脳波が計測されました。
結果ですが、まず20年以上の熟練した僧侶の瞑想時の脳波を図2に示します。瞑想前は通常の開眼時の意識状態であり、脳波に特徴的な波形は見られません(図2a)。しかし、禅瞑想を開始するとともに1分も経たないうちに脳波に変化が現れました。振幅が40~50μVで周期が11~12/秒のアルファ波が全体に出現しているのが分かります(図2b)。そして8分を経過したところではアルファ波の振幅が60~70μVと大きな波形が出現していることが分かります(図2c)。

続いて、瞑想開始から27分経過した頃に周波数が7~8/秒のリズミカルな波形が1~2秒間程度現れ始めます(図3a)。そのさらに20秒後には周波数6~7/秒、振幅も70~100μVの大きなシータ波が観察されるようになり、瞑想終了までシータ波が出現する状態が持続しました(図3b)。そして瞑想が終了した後も通常時の脳波に戻らずにアルファ波が持続した状態を維持しており、この脳波の持続も禅瞑想による脳への効果と考えられます。

これに対して比較対照となった人達の脳波を図4に示します。これをみると先ほどのベテラン僧侶の脳波と異なるのが一目瞭然です。時折アルファ波が出現していることもありますが、ほとんどの波形が小刻みで振幅も小さく、日常の意識レベルに近いベータ波が支配的であることが脳波からも読み取れます。瞑想経験のほとんど無い被験者はいずれも同じような反応で、瞑想前・中・後を通してほとんど変化が現れなかったようです。そして、20代でも60代でも大きな差は無かったことから加齢による影響ではなく、瞑想の経験に関連していると言えそうです。

研究著者らはこの脳波の変化を以下のように分類しました。
・ステージI: アルファ波が出現するがわずかな変化
・ステージII: 持続的なアルファ波と振幅の増加
・ステージIII: アルファ波の周波数の低下(シータ波へ移行)
・ステージIV: 律動的なシータ波の出現。
そして、48名の被験者のうち修行中の僧侶23名を経験年数別、精神レベル別(上級僧侶による評価)に3グループに分け、脳波のステージとの相関をまとめたのが図5です。図をみて分かる通り、経験年数が多いほど/または修行者の精神レベルが高いほど、脳波のステージが高く、アルファ波からシータ波への移行が進みやすいことが分かります。

続いてクリック刺激に対する反応の実験結果を示します。このための実験では、瞑想中に“「カチッ」というクリック音を聞かせる”という外部刺激を1分間隔で与えます。これによって一瞬瞑想状態が途切れます。このとき脳波ではアルファ波のブロッキングが起こり、集中が途切れますが数秒すると意識が瞑想状態になり、またアルファ波が出現します。
図6は覚醒しながら瞑想している時と傾眠(うたた寝)しているときにクリック刺激を受けたときの比較です。図6aのように上級僧侶が覚醒しつつ瞑想しているときは、クリック音によって一時アルファ波やシータ波が消失しますがまた数秒後にアルファ波/シータ波が出現します。これに対して図6bのように傾眠時は既にアルファ波/シータ波が消失しているのが分かります。そしてクリック音によって意識が戻り、また瞑想時の脳波に復帰しているのが見て取れます。

次に上級僧侶と比較対照者でクリック刺激に対して反応がどう変わるかを示したのが図7です。前述の通り瞑想中に1分間隔でクリック音が聞かされますが、上級僧侶の方は瞑想初期も20分経過した時点でも変わらず、“音に反応して脳波のブロッキングは見られるが数秒でまたアルファ波/シータ波が出現”というパターンを維持します。これに対して比較対照の一般人では“瞑想初期は音に反応して脳波のブロッキングが見られるが、次第に慣れてしまい後半では睡眠状態で反応もしなくなった”という結果となりました。
この辺りは、“禅瞑想で無心の状態を保ちつつも外部刺激に反応する”熟練者と、“意識をコントロールできずに瞑想状態を保てず眠りに落ちてしまった”一般人との明確な違いと考えられます。

これらの実験結果から研究者らは瞑想状態と睡眠状態を図8のように図式化しています。脳波の観点からみると、瞑想前の開眼時(平常時)の脳波状態→瞑想開始とともにアルファ波が出現→アルファ波の振幅の増加→アルファ波の周波数の減少→シータ波の出現→リズミカルなシータ波の反復、というように瞑想が進むにつれて脳波のレベルも前述のステージのようにステップアップしていくようです。
しかし、睡眠になってしまった場合はアルファ波が減衰し、スローウェーブ(徐波)やスピンドル(紡錘波)バーストといった脳波が出現します。これらは熟練者の瞑想中の脳波には出てこないということです。

このほかにも研究者らは“トランス状態”や“催眠術士に催眠術をかけられた状態”の脳波を比較していますが、いずれもシータ波は見られず瞑想中の脳波とは異なる状態だったと報告しています。
この研究をまとめると、
・瞑想時と睡眠時は脳波が異なっている
・熟練した瞑想者はアルファ波の後にシータ波が出現する
・瞑想熟練者は瞑想状態を持続しながらも意識を保っている
・経験や精神レベルに応じて脳波の質も変化していく
・睡眠中は瞑想中には出てこない脳波が出現する
(逆に瞑想中は睡眠時特有の脳波は出現しない)
・瞑想中でも睡眠に移行してしまうと瞑想中の律動的な脳波は消失する
ということが言えるようです。
こうしてみてみると、“瞑想と睡眠の違い”とは“自分の意識を制御しコントロールを保ちつつ内省/内観する”ことが瞑想状態(接心)であり、“自分の意識を保てずに、思考も脳波も自分のコントロールを失った無意識の状態”が睡眠状態(昏沈睡眠)であると言えると思われます。
やはり瞑想時と睡眠時では脳波や脳の状態が全く異なっていることが分かりました。これまでに紹介してきた瞑想による脳内の変化(*4)もやはり意識的に瞑想を行わないと得られない効果だと考えられます。そして熟練度が増すほど、瞑想の質も向上していくことはこの研究でも科学的に立証されています。
この研究は1966年と筆者も生まれる前の研究ですが、瞑想という”目に見えない世界”を科学的に解明しようという発想とそれを実際に論文として公表した実績はとても尊敬に値する研究だと思います。これまでの瞑想に関する研究の草分け的な位置づけの重要な研究だと言えます。今まで瞑想をした経験がない人でも是非瞑想習慣を身につけて脳内革命を起こしていきましょう。
(著者:野宮琢磨)

野宮琢磨 医学博士, 瞑想・形而上学ガイド
Takuma Nomiya, MD, PhD, Meditation/Metaphysics Guide
臨床医として20年以上様々な疾患と患者に接し、身体的問題と同時に精神的問題にも取り組む。基礎研究と臨床研究で数々の英文研究論文を執筆。業績は海外でも評価され、自身が学術論文を執筆するだけではなく、海外の医学学術雑誌から研究論文の査読の依頼も引き受けている。エビデンス偏重主義にならないよう、未開拓の研究分野にも注目。医療の未来を探り続けている。
引用/参考文献:
*1. 脳内物質セロトニンと瞑想の関係
https://note.com/newlifemagazine/n/n0a07608b82cd
*2. リラクゼーション瞑想と脳内物質ドーパミンについて
https://note.com/newlifemagazine/n/n67caa776ea39
*3. Kasamatsu A and Hirai T. AN ELECTROENCEPHALOGRAPHIC STUDY ON THE ZEN MEDITATION (ZAZEN). Folia Psychiatrica et Neurologica Japonica, Vol. 20, No. 4, 1966, 315-336.
*4. 瞑想がもたらす脳の変化
https://note.com/newlifemagazine/m/mb580e4b26aa4
前回までの関連記事はこちらから
※引用文献の内容に関する著作権は該当論文の著者または発行者に帰属します。
※当コンテンツに関する著作権は著者に帰属します。当コンテンツの一部または全部を無断で転載・二次利用することを禁止します。
※著者は執筆内容において利益相反関係にある企業等はありません。
★LINE友達限定!毎週金曜日「星読みまどかのNEW LIFE星占い」配信中!★

モダンミステリースクール 公認マガジン「NEWLIFE」は、
理想の新しい世界”を本気で希求する、
すべての人に向けたオンラインメディアです。
銀河レベルのぶっちぎりに新しい情報で、
誰もが本質を生きる時代を目指します。
更新情報はライン公式でお知らせしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
