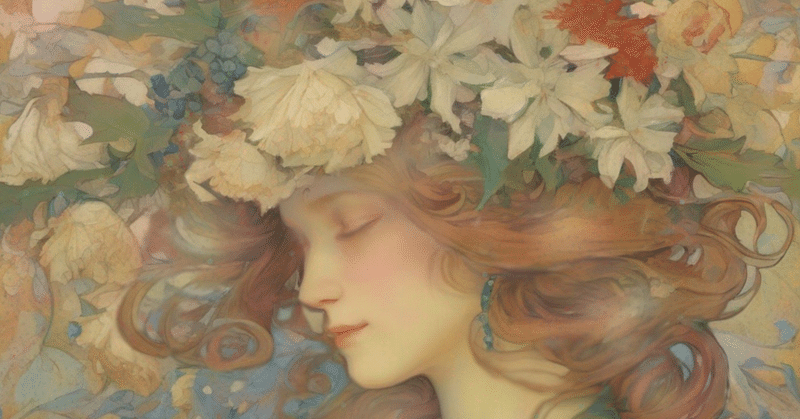
家族の良いも悪いも全部見た(6/6)
前回のお話はこちら。
最初のお話はこちら。
******
あと一晩越えればショートステイだから
少し風のあたたかさがました3月、
夫が出張で10日ほど家をあけることになった。
美紀はこれまでの生活から一人ではとても無理だと決断し、
ショートステイの利用を決めた。
父は腫瘍熱で39℃の熱が出たり、
しびれの出る手足により物を落としたり、
飲食物をこぼしたり、
一般的には介護というほどでもないケアに時間がとられるようになってきていた。
夫が出張に出かけ、
ショートステイも翌日に迫った夕方、
父の部屋からドスンと大きな物音が聞こえた。
ちょうど息子のおむつを替えていた時だった。
息子に謝りながらおむつ替えの手を止め、
父の部屋へ様子をうかがうと、居間に倒れた父が目に飛び込んだ。
座布団に躓いて転んだ父は、
フラフラしながらも自分で立ちあがりそのままトイレへ向かった。
息子のもとに戻りおむつ替えの続きを進める。
またドスンと音がする。
トイレの前で転んでいる父にあれこれするも足に力が入らず立ち上がれない。
息子の泣き声がする。
どうしようもなく訪問看護師へ電話をかけ、助けに来てもらった。
<一晩越えればショートステイに行ってもらえる>
それだけを励みに今晩だけリハビリパンツを使用する。
漏れないように尿取りパッドも差し込んだ。
「もう一人でその夜を過ごすのが怖くてたまりませんでした。
寝る前にリハビリパンツ替えようとしたら、
おかゆ食べたいなんて言い出すんで、
どんどん息子のお世話が後回しになることもすごく苦痛で。
また転ばれてもどうしようもないので、
『トイレには行かないで、ベッドからは降りないで』
と散々伝えていました。」
これまでの言動が証明するように、
そのお願いを父は聞いてくれなかった。
もう間もなく日付が変わろうとする頃、父から電話があった。
同じ家に住んでいるものの、
階が異なるため電話でコミュニケーションをとる。
また転んだか、吐血したか、嘔吐か…
もともと心もとない夜だった。
一気に心拍数があがるのが手に取るようにわかる。
「助けて…」
状況を聞いても、か細い声でそう繰り返すだけだった。
授乳を中断し、父のもとへ急ぐと、
下半身がベッドからずり落ち、
上半身はベッド柵に支えられた状態でいた。
呆れて絶句した。
<何度言ったらわかってくれるんだろう。
どうして私と息子を困らせるんだろう。>
美紀は途方に暮れた。
ベッドに戻そうと手伝うも、
必死にしがみついている父の力は強く自力ではどうにもならない。ベッド柵を引き抜いて畳の上に寝かせることにした。
柵に挟まれていた脇腹に血が滲んでいる。
疲れ果てた状態で朝を迎えた。
ショートステイのお迎えが来て父を預ける。
一晩張り詰め続けた緊張がほどけていった。
施設のスタッフの専門的な目で見れば
父は要介護3か4にまで衰弱していた。
いつの間にか父は瘦せ細って手足は枯れ枝のようだった。
皮膚に刻まれる深いしわが目立つ。
目の前のことに精一杯の毎日でじっくり父を観察していなかったことに気が付き、
ふぅっと息を吐きながら天井のシミを仰ぎ見る。
ただただ疲れていた。
ショートステイに預けた父は少し体調を持ち直したようだった。
スタッフと面談を重ね、そのまま施設へ入居することに決めた。
1カ月が過ぎたころ、施設から連絡が入る。
「昨晩から体調が急変し、そろそろかもしれません。」
一旦は様子見として電話を切った。
死に際のサインとは尿量が極端に減り、
下顎呼吸といって下顎が上下に動く呼吸が始めることが一般的と言われている。
父の場合は尿量が極端に減ったことにより、危篤と判断された。
その後しばらく経って再び携帯が鳴る。
「意識がなくなりました、急いでください。」
大慌てで支度をし、向かう。
<こんなに世話かけたんだから、
最期は一人で行くなんてしないで、ちゃんと待っててよね>
そう祈りながら車を急がせた。
美紀たちが到着すると、
予想に反して父は意識が戻っており、
ほっとするやら拍子抜けするやらであった。
酸素量をあげても酸素マスクをしても父の呼吸は浅く、
高地に行ったような息苦しさがある。
到着した美紀たちが口々に
「桜を見に行こう」
「酸素マスクしてたら少しは楽か?」
など父を元気づけることを言おうと必死になっている。
「もうしゃべらんといて。寝たい。」
普段とはトーンの違う刺すような口調に、みなが押し黙った。
「寝たいってもう帰れってこと?」
と言うとにわずかに頭を上下させた。
「本人に帰れって言われたら仕方ないですよね。
帰り道は『せっかく急いできたのに、あの態度はないだろう!』と愚痴を言い合って帰路につきました。
焦って駆け付けて、帰れだなんて、
その自己中具合はある意味父らしかったですけど。」
それが最後の会話になった。
その夜、介護職員が見回りに行くとすでに呼吸が止まっていた。
満開の桜だけが静かな父の死に際を見守っていた。
少しだけ開いた窓から雨上がりの湿気を含んだ柔らかな風が父の頬を撫でていた。
◇
赤ちゃんと父の怒涛のダブルケアを終えてどんなことを感じているのか、美紀に尋ねてみた。
「とにかく必死な毎日でしたが、
父の病と赤ちゃんの誕生が私たち家族を引き留めてくれたと思っています。
癌になっていなければ同居はなかったし、
父の大好きな家である程度のサポートが出来たことは長い反抗期を持った私にとっても救いでした。
もし妊娠していなければ、夫ともきっと離婚していたし、
もちろん父に顔を見せてやることもなかった。
一つでも欠けていたら家族は家族じゃなくなっていたと思います。」
長いインタビューを終えて、彼女は優しい目で笑った。
ダブルケアによって降りかかった日々は、
美紀にとってかけがえのない日々といつしかなった。
彼女は今ダブルケアを支援する団体を立ち上げている。
あれらの日々が今の彼女を作ったのだった。
*******
おしまい。
special thanks
荒井美紀さま
山吹さま
https://note.com/heart1g
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
