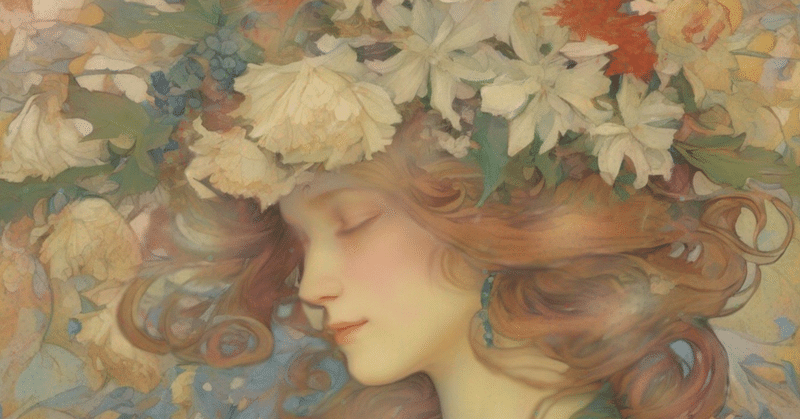
家族の良いも悪いも全部見た(5/6)
前回のお話はこちら。
最初のお話はこちら。
******
ダブルケアの始まり
町中からクリスマスソングが流れ、
人の背丈を優に通り越す高さのもみの木と
色とりどりの電飾が夜を彩る。
人々が大切な人への贈り物を購入し、浮足立つ。
バスケットボールを入れたように膨らむお腹を撫でる美紀も幸福に満ちていた。
12月14日、意識が遠のくほどの痛みを10時間ほど耐えた。
通常ならもう十分生まれることができるほど子宮口が開いているのに赤ちゃんの顎が引っ掛かる。
数回のいきみで人間界の空気に触れるはずの赤ん坊も
狭い産道に居続けるのは危険だった。
人間の最大値の痛みを2時間経験したのち、
ようやく息子がこの世に生を受けた。
美紀自身も交通事故レベルのダメージをくらうと言われた出産を経てボロボロだった。
さらに最高潮に分泌していた女性ホルモンも
産後すぐにほぼ皆無になると言われている。
この急激なホルモンの変化がマタニティーブルーズとも言われ、
気分の落ち込みが激しくなり、
長引けば鬱の経験がない人でも産後うつと呼ばれる状態に陥ることさえある。
産後の女性は踏んだり蹴ったりだ。
それでも最愛の赤ちゃんを迎えて、
父を含む4人の生活に希望を持って退院した。
彼女が出産という大仕事を終えたことを知らないこの町は
妊娠前よりも遠く感じ、
鮮やかなイルミネーションは少しだけ色を失ったように見えた。
赤ちゃんとの毎日は想像を絶した。
お互いに初めてのことばかりだった。
赤ちゃんはこの世界でうまく眠ることもできず、
上手におっぱいを飲むこともできなかった。
美紀自身もちゃんと母乳が出なかった。
昼間は微動だにしない赤ちゃんは夜まったく眠らなかった。
母乳が出ない。
赤ちゃんは泣いている。泣いていて飲めない。
どうくわえさせたらいいのか。
また泣いている。
おむつを替える。
すぐにうんちが出る音がする。替える。
また泣いた。授乳量が少なくてお腹がすいているんだ。
でも出ない。ミルクを作る。
その間もずっと泣いている。
抱っこをしてみる。
体が重たい。
眠い。
眠い。眠い。眠い。眠い。
当時、紙おむつよりも布おむつのほうが
「発達に良い」「肌に優しい」
など、布おむつに軍配があがっていた。
過去には戻れない育児、
選択肢があるならより良い選択をしたかった。
当然ながら紙おむつのほうが吸水力もあり、漏れも少ない。
替える頻度は2倍3倍になり、そのたびに洗濯ものも増えた。
赤ちゃんが夜眠らないということは
美紀も眠らないのとイコールで、
それなのに昼にぐっすり眠ることができる赤ちゃんに対して
昼間は父の食事を用意するなどの家事があった。
出産を終えた女性は“産褥期”という言葉があるように
1か月ほど育児以外は体を休めていなくてはならない。
大きなダメージを負っている体で活発に動こうとすると
体調の戻りが悪くさまざまなトラブルを引き起こす。
父の癌の状態は手の施しようがない、
と言われてから約1年半。
父が体調不良を訴えることも多くなってきたタイミングだった。
「『今日はあかん。ふらつく。』と言いながら、
ペンや紙を散らかした床の上を歩いていたり。
トイレも薄暗い中、立って用を足したり。
ふらついて危ないと思うなら、
まず目の前のほんの少しの行動で環境が改善すればいいのに、
やらないんです。
イラついて強く責め立てれば、
わけのわからない言い訳が返ってきて、それにもまた苛立ちました。
結局は“かまってちゃん”なだけなんじゃないか、
と思わなくもありませんでした。」
赤ちゃんが家に戻った初日は、
父も赤ちゃんを気にかけ、育児を手伝ってくれた。
それも初日だけだった。
寝ていれば顔を見ることもおろか、
いつも通り他人に無関心で自分の欲求にはいたく素直な父に戻っていた。
<孫相手ならば父も変わるのかも>
一瞬でも期待した美紀は、
自分の愚かさにも、変わらない父にも大きく失望した。
その後も父の言動には振り回された。
CT検査を受けに病院に行く予定があった父は、一人で行けるはずもないのに、何も言い出してこない。
<何も言わなくてもやってもらえると思っているその態度が鼻につく>
かと言ってそのまま病院に行かないわけにはいかないので、
夫が車を出す。
自身のボロボロの体に、
父のことも気にかけなくてはいけない美紀のストレスは極限状態だった。
腹立ちまぎれに
<もう帰ってくんな>
と思いながら病院に立つ二人を見つめる。
しばらくすると夫から連絡が入った。
「CTで肺に穴があいていて、気胸が見つかった。
これから診察するけど、多分入院することになる。」
帰ってくるな、と思ったら本当に帰ってこなかった。
息子が生まれて1か月。
初めて育児に専念できた夫婦の肩は一気に軽くなった。
1週間で退院できるはずの入院は、
穴がうまくふさがらず処置や手術をする間に1カ月にもなった。
退院時のカンファレンスでは、
父の退院後の生活について話し合われた。
もう父の面倒はみきれない、
そう思っていた美紀はホスピスへの入所の方向で
病院のソーシャルワーカーとも話し合った。
いざ希望を口にすると、
急にホスピスへの入所が現実味を帯び、
父の最期がそれでいいのか、迷いが生じ始めた。
というのも束の間、入院ですらかなり渋った父は自宅を希望した。
発達障害のためか、
自分の生活を崩すことには人の倍以上のストレスがかかっていた。
「それも『やっぱり自宅に戻りたいですなぁ~』なんて呑気に言うんです。
こっちの苦労なんて、絶対これっぽっちも考えてなかった。
でもこれでいいのか迷いがあった分、
父の希望を退けることはできませんでした。」
自分の決断に自信がなかった彼女は、
父の希望に背中を押されたように自宅で過ごすことを決めた。
病院のスタッフたちは、美紀たちを気遣い、
「いつでも無理って言っていいんだからね」
と今後の生活を想った。
訪問看護や宅配弁当を手配し、父には
「自宅でもこれまで通りはサポートできないから、一人暮らし同然であると思ってほしい」
と改めて伝えた。
生温い返事が返ってきただけだった。
******
次のお話はこちら。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
