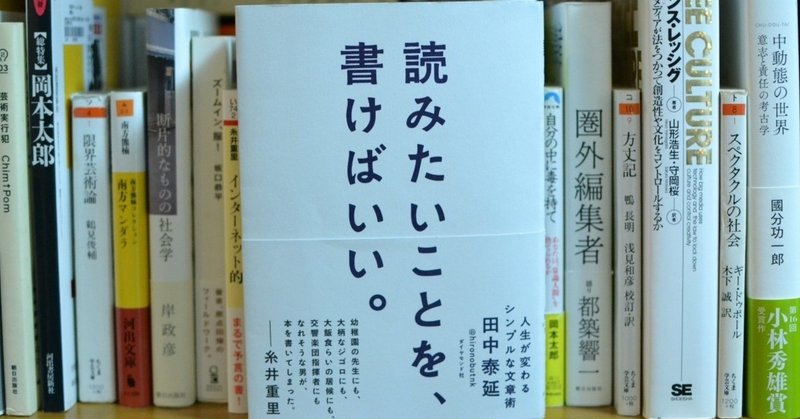
ブラックホールになりたい 『読みたいことを、書けばいい。 人生が変わるシンプルな文章術』
なぜ自分は文章を書いているのか。この本を端緒に、自分なりに改めて考え直してみたい。
『読みたいことを、書けばいい。 人生が変わるシンプルな文章術』
田中泰延、ダイヤモンド社、2019

しかし、怖れることはない。なぜなら、書くのはまず、自分のためだからだ。あなたが触れた事象は、あなただけが知っている。あなたが抱いた心象は、あなただけが覚えている(p224)
ファーストひろのぶ
著者の田中泰延さんとの個々の出会いについて書く「 #ファーストひろのぶ 」というハッシュタグがTwitterにあったので、自分の「 #ファーストひろのぶ 」をまずは少し。
最初は、映画『太陽の塔 TOWER OF THE SUN』(関根光才、パルコ、2018)の感想ツイートから。素晴らしい映画だった。noteやらブログやら書く場所を持っておらず、ひとまずと分割で感想をツイートした。それを、わざわざまとめてくださったのが田中さんだった。
⚡️ "秋吉成紀さんによる関根光才監督・映画『太陽の塔』感想"https://t.co/jieMfptFYf
— 田中泰延 (@hironobutnk) October 25, 2018
正直に最初はどういう方か知らず、「おお、なんか誰かまとめてくれてら」なんて思った。失礼ながらこの時まで存じ上げておりませんでした。
自分は何も語らなくてもいいやつ読んでしまった。ここから考えます。
(秋吉成紀さんによる関根光才監督・映画『太陽の塔』感想)
この言葉は素直にめっちゃうれしかったし、友達に少し自慢した。ここで恐れ多くもフォローしていただき、以後フォローさせていただいている。これが自分のファーストひろのぶ。
この一連の感想ツイートも、どうも自分が気になったところなどについて言及している人がいないな、だとかなんとか思ったのも書くきっかけの1つだった気がする。
助産
自分の中でモヤモヤとしたものをひとまずかたちにしようと、先月から少しづつnoteを更新している。いまのところ約10本。どれも普段から悶々と思いふけるテーマをなにかにつけて書いてみているもので、歯切れよく結論がでるわけでもない。ひとまずのオチを、と心掛けつつも納得しきるわけでもなく…、それでも文章として自分の中の及第点を落とさないようにしている。
インターネット上誰しもが閲覧できるところに置いているくせしてなんだが、このnoteは他所様のことに気がまわるような人間が書いていない。自分のことで精一杯だ。誰かを意識している余裕はない。(もとより生半可に「共感」だとかには興味がない。)保存に都合がいいのだ。嘘。ちょっとどこか期待してしまうダサさは0ではない。
どうしてもこのモヤモヤに対するそのままの答えは、外のどこを探しても見つからない。答えらしき近いことを書いている本はあるにはあるが、全くを納得できる答えという訳ではない。調べ尽くしても、いくら巨人の言葉だろうともそれはない。だからいつも仕方なく、ひとまずの手がかりから書き出してみている。
自分はその本について書くことよりも(そもそもそんなことその本を読めばいいだろと思う。)そこから自分で何を考えたのか、それを改めて言葉にしてまとめておきたいという考えのもとに書いている。雑多に散らばった脳みその中身を自分なりに線にして点にして、自分中心にモノゴトの分別をつけていきたい。その手がかりとして本を使って、といまは考えている。
(限界ルネサンスに限界ファッションの夢を見る 『限界芸術論』)
そうこうしているなか、自分のうちでスッと腑に落ちるような瞬間がときたまある。無意識らへんからポロっと転がり出て来る言葉が、悩み果てている物事を前進させてくれたりする。意識のコントロールの外に飛び出て、自ずとストーリーが進んでしまうかのように、言葉が勝手に当てはまることがある。スッと言い得ているような言葉が。
自分の中でいままでの人生で見て聴いて感じてきたあらゆる諸々が、ずっと奥の方でこんがらがって散らばっている。書くことで自分のそんなところにあるものが、言葉というかたちを持って飛び出してくる。その快便感というか、それが気持ちよくてやめられない。
パッツパツに詰まったポケットから何かを取り出そうとしたとき、一緒に転がり出てしまったような。そんなもの。それと同じ。
(〜)
書いていくなかで、思いがけず一緒くたになって転がり出てきた忘れていたような諸々。ついついそれらを拾い集めているうち、最初に思い描いていたストーリーラインは跡形もなく消え去り、気づけば思いがけない結論に辿り着いていた。妙なトリップ感。
(結果よりも、プロセスにこそ意義がある ゴジラ検定)
見て聴いて感じてきた諸々は、見て聴いて感じたその瞬間、すぐさまに言葉として現れるわけではない。これは単純な語彙力の程度の話でもない。それこそ、他の見て聴いて感じた諸々が自分の内で積み重なったとき、忘れる手前くらいまでずっと奥の方に沈んでいったときこそかえって、現れる。あの時のあれ、あの感覚。それをひとまとまりに呼び起こすことも間違いなく書くことの意義の1つだと思う。その瞬間に現れることのできなかった、生きられなかった心象をもう一度生まれなおさせるための助産。
自分にとって書くということの1つ、大きな1つは、そんなある瞬間に生まれることのできなかった心に、あるいは答えらしきものに、ようやく顔合わせをするようなことなのかもしれない。その生まれたもの、それこそを自分は読みたい。あの瞬間を今この瞬間思い返すために。永遠に思い返すために。それでいて、そのかたちのままで固まってしまわないように。
だからこそ読みたい。だから自分は書く。
これもまた厄介なもので、生み出そう、生み出させようと意識してしまうと出てこなかったりする。ひとまず書き始めてみたなかで、その緊張がほぐれたときにしか出てこない。執念が解けたそのときにだけフッと現れる。ずいぶん難儀な話だと思う。
人がへばりついたものごと
オチがついた気がしたが、読みたいものが出てきた。続ける。
ところで、自分は「人がへばりついたものごと」が好きだ。そもそも自分が何にも増して読みたい、見たい、聴きたい、感じたいと思うものごとには、大抵人がへばりついている。
他の言い方が思いつかないからひとまずの表現だが、それは、人=創造主とその創造物の間に明確な境界がなくなってしまっているようなものごと。「オリジナル」なんて言葉が生半可に思えるほど、その人からでしか生まれえないと強く感じるようなものごと。創造物単体で見ることができないほど、創造主が色濃く出しゃばるような。とにかく色濃い。例えば、竹原ピストルの歌(...ものの例えとしてとりあえずピストルさんを例に挙げたけれどもこれは、THE BLUE HEARTSでもMOROHAでもなんでもよかった)。そんなものごとを見て聴いて感じることが好きだ。
なぜ好きなのか?
例えばピストルさんの歌は、あの人にしか訪れなかった言葉がその歌を織り成している。たぶん、果てしなく内側に向き合ったときに生まれた言葉。その言葉の背景にはあの人だけの孤独がある。
何かを生み出すには、必然的に孤独な作業がついてまわる。己と向き合うひたすらに過酷な孤独。それでなおなぜそこまでして生み出すのか。きっと、自分にまつわる何事かを自分なりにひとまずの決着をつけるためだと思う。
自分自身のためだけの極めて局所的な答えを求めて。同じ人間がこの世に他にいない以上、その人自身からしかその答えを見出すことはできない。だから孤独と向き合うしかない。「人がへばりついたものごと」というのは、自分の人生における何事かに対して、自分でしかつけることのできないその人のためだけの決着のことなのだと思う。
何よりも辛く苦しい孤独を超えてそれに決着をつける。その人自身でしか生み出せない生み出し方で。その人の孤独を、その孤独に打ち勝った強さを、自分の孤独さえも愛でるまでに至ったその気高さを感じられるから、「人がへばりついたものごと」が好きなのだと思う。
みんなブラックホール
極限まで内に突き詰めたものはやがて凄まじい引力を持つようになる。ブラックホールのように。
自分が読みたいから書いたものが、結果的にウケがよかったという話は、まさしくそういうことだと思う。生み出したものがブラックホールになった。自分とはなんぞやの果てに自分を肯定できるまでになった人もブラックホールだ。そんな生み出したものは、人はとにかく魅力的だ。
誰しもの内側がその外側にあるはずがない。まだ世の中にはない。もちろんそうだ。自分の中にあるあれこれは、どこを探そうとも自分の外にはないのだから。ということは、まだ世の中にないものが個々の内に秘められている。誰しもが可能性を秘めている。人間誰しも己を突き詰めればその人にしか生み出せないというものがある。その人にしかなれないその人になる。誰しもがブラックホールを生み出しうるのだ。誰しもがブラックホールになれるのだ。人の限りだけブラックホールは生まれる。末恐ろしくなるようで、満ち足りるような事実。
とはいえこれは、個々が内を突き詰め、世に出したのならばの話。事を起こさない限り、その可能性は外に出ることなく、その内に閉ざされたままでしかない。どうも障壁が多い世の中だし、特殊な才能がないといけないとかの思い込みが敷き詰められている。だから突き詰めようとせずに止めてしまう。
ここまでくると特別な文才だとかなんとかはここにきて必要ではないような気がする。なんでもいい。それを読ませて欲しい。見せて欲しい。聞かせて欲しい。感じさせて欲しい。
どこか悲しくなるのは、俺は俺についてしか書けないということ。(それも拙いということ。)絶望的な気分になる。自分を起点としてしか書くことができない。この主観は消えない。隣の芝生はどこまで行こうとも青い。そういう意味で自分についてしか書くことができない。自分としてしか生きていくことはできない。だからこそ俺の代わりを引き受けてくれるような他者の言葉を求めてしまいたくなる。
そんな言葉も自分は読みたい。いや、言葉でなくともなんでもいい。どんな表現でもいいから。人は生物学上だとかなんとかにおいて、同じもとされているのかもしれないけれども、同じ人、その個その人はどこにもいない。もうそれしかない断片だ。愛おしく思う。だから臆せず、世に出してほしい。
願う未来は総ブラックホール化社会。個性だとか、オリジナリティーとか生ぬるい言葉で言い切れないそんななにか。その状況へと加速させてくれるモノの1つは服だと思う。いや、自己表現だとかのレベルでもなく。着たい服を、つくれればいいのに。
あなたは、まったくだれからも褒められなかったとしても、朝出かけるとき、最低限、自分が気に入るように服を着るだろう(p95)
俺もブラックホールに
自分は自分自身のためにも自分自身を突き詰めていきたい。自分もブラックホールを生み出したい。俺だけのブラックホールを夢見ている。いや引力がほしいという意味ではなく、それほどもまでに突き詰められる人間になりたい。突き詰めた内側を外に出せるようになりたい。自分の問いに、自分自身で答えられる人間になりたい。尊敬している人たちのように。だから、ひとまずにせよなんにせよ書いている。
少なくとも、定期的に文章を書くようになって間もないけれでも、幾分か成長している気がする。だから、恥ずかしながら、最近の自分の文章は好きだ。
『読みたいことを、書けばいい。』を端緒にまた1つ書いてみた。ほとんどこの本自体に触れることがなかったけれども、この本を読んでいたときに思ったことを書いている。トリビュートな感覚で書いたりもしている。言い訳くさいけれども。
「社会人」になることができず、正味人生を攻めあぐねているフリーターのくせして、こうもうじうじ書いている。それでも、これは抱いてる違和感を「常識」や「普通」などで黙殺させないために必要なことなんだと言い聞かせる。いずれや、どこかにたどり着くためにも、今はまず書くしかない。
もし可能でしたら、サポートしていただけると、とても、とても、とにかくありがたいです。よろしくお願いいたします。
