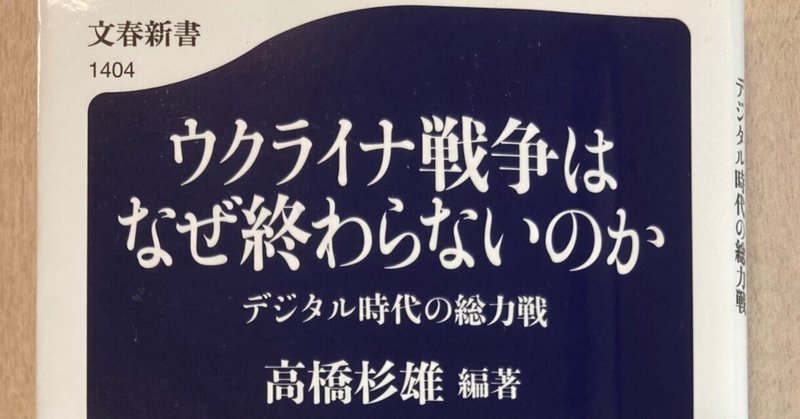
岩手県立大学授業(10月10日哲学の世界・参照論文の解説)―文献紹介:高橋杉雄「ロシア・ウクライナ戦争はなぜ始まったか」(高橋杉雄編著(2023)『ウクライナ戦争はなぜ終わらないのか―デジタル時代の総力戦』文春新書 所収)
防衛省防衛研究所所属の軍事戦略を専門とする研究者で、ロシア・ウクライナ戦争についても発言している高橋杉雄氏が、文藝春秋から新しい編著を刊行した。この本は次のような構成となっている―
まえがき(高橋)
ロシア・ウクライナ戦争はなぜ始まったか(高橋)
ロシア・ウクライナ戦争―その抑止破綻から台湾海峡有事に何を学べるか(福田潤一/笹川平和財団)
宇宙領域からみたロシア・ウクライナ戦争(福島康仁/防衛研究所)
新領域における戦い方の将来像―ロシア・ウクライナ戦争から見るハイブリッド戦争の新局面(大澤淳/中曽根康弘世界平和研究所)
ロシア・ウクライナ戦争の終わらせ方(高橋)
日本人が考えるべきこと(高橋)
あとがき(高橋)
私の関心からは大澤の章も面白かったが、ここでは両国の「アイデンティティ(自己認識)」を巡る戦いという、当初から明らかな筈であったが「NATO東方拡大」などのレトリック(一見「政治的リアリズムに基づく論」という体裁を取った、物語論的レトリック)に惑わされて我々(特に日本人)が明確に認識して来なかった、この戦争の最も重要な根本的原因についての、高橋氏の例の如くクリア(論旨明快)な議論が有益であったので、「ロシア・ウクライナ戦争はなぜ始まったか」の章を紹介することにする。
著者はこの章の冒頭で、今回のロシア・ウクライナ戦争を「古さと新しさとが同居した大国間戦争」であると特徴付ける。ここで古さとは、第一次大戦における塹壕戦や第二次大戦における重火力戦闘が見られる点を言い、新しさとは宇宙戦やサイバー戦を含めた最先端技術が駆使されていることを意味する。
その上で、「なぜ」このロシア・ウクライナ戦争が始まったのか、という問題を考察するための二種類の具体的な問いを掲げる―一つは、「なぜ」ロシアとウクライナ、あるいはウクライナを支えている米欧とロシアとが対立したのかという問いであり、もう一つは、「なぜ」ロシアが開戦の決断をしたのか、しかも「なぜ」2022年に開戦の決断をしたのかという問いである。
まず、最初の問いに答えるために、著者は冷戦後の米欧とロシアの(徐々に変化する)状況と関係を詳しく跡付けて行く。
ソ連と東側世界の敗北によって冷戦が終結すると、ソ連の同盟国であった東欧諸国では相次いで共産主義政権が打倒され、ソ連自体も、ロシア共和国、ベラルーシ共和国、ウクライナ共和国その他に分裂した。この時の米欧における重要課題は、総体としては旧ソ連、旧東欧諸国をどう扱うかであったが、具体的に最も重要なのは旧ソ連の継承国家ロシアとの関係をどのように再構築して行くかということであった。
結論として、その大きな枠組みは、いわば「ロシアへのソフト戦略」であった。すなわち、米欧はロシアを封じ込め完全無力化を図ろうとするのではなく、「新たなパートナー」としてロシアを迎え入れることを選択し、経済支援、市場主義化支援、政治的コミュニティーへの迎え入れなどを試みた。ロシア側も当初は米欧側に対して協力的な態度を取った。このような流れの中で、米国国防省による2006年版QDR(4年ごとの国防戦略見直し)は、「戦略的岐路にある国家」として中国、インド、ロシアを位置付け、今後対立関係に陥る可能性もあるとしながらも協力関係の発展についても含みを持たせ、さらに2014年3月4日公表の2014年度版QDRには、「米国はヨーロッパの平和と繁栄を達成するために努力し続けるし、その目的を支援するためにロシアに建設的に関与し続ける」との記述さえ現れた。第二期オバマ政権期であった。
ところが、ロシアによるクリミア不法占領が行われたのはまさにこの直後の2014年3月18日であった。これに対して、米欧主導でのロシア制裁が行われ、同時に米欧は中国との連携を強化しようとした。この流れの中で、2021年秋からロシアはウクライナ周辺で大規模軍事演習と称する大兵力集中を行い、軍事的圧力を背景とする瀬戸際外交を展開した。著者の言葉を引用すれば、「冷戦が終結し、核戦争による人類絶滅の恐怖が去り、1990年夏のイラクのクウェート侵攻に対しては国際連合を中心とする侵略阻止の枠組が機能してイラクからクウェートを取り戻し、大国間の協調によって世界の問題が管理されることが期待されてから30年あまり経った時期における開戦であった。」(p.26)
これに続く部分で著者は、以上の現実の歴史的経緯の、「選択肢」と「分岐点」という観点からの、いわば解剖作業に取り掛かる。そのような言葉が使用されているわけではないが、一種のシナリオ的分析乃至ストーリー的分析であろう。
冷戦終結後、旧ソ連諸国及び東欧諸国には次の二つの選択肢があった。一つ目の選択肢は、西欧との関係を深め「ヨーロッパの一部」になることであり、もう一つの選択肢は、西欧との距離を維持しながら東欧とロシアとで「旧ソ連的な勢力圏」を形成することである。
ここで、東欧諸国の側は第一の選択肢を選んだ。当時の米国クリントン政権は「関与と拡大」政策を採用し、東欧に民主主義を広げ、ヨーロッパにおける対立を今後恒久的に除去することを目指したが、EUや「NATO拡大」もその政策的一環であった。
米欧は、将来的にロシアを組み込んだ形での「協調的安全保障」の枠組み構築を目指し、NATOと旧東欧諸国や旧ソ連諸国との協議枠組みであるPfP(平和のためのパートナシップ)その他を立ち上げた。しかしながら、結果として、このような「ロシアのヨーロッパへの組み込み戦略」は失敗に終わった。
著者はこの失敗の原因について考察するが、その際幾つかの「あや」を想定する。ここで言うあやに関する明示的な定義はないが、ある結果が実現される際にいわば駆動的に機能した偶然の要因のようなものかと思われる。
最初のあやは、エネルギー資源開発を通じたロシア経済の安定、特に天然ガスをパイプラインで供給することで欧州諸国との関係に深化がもたらされたことである(もう一つのあや、すなわち中国という存在については、後述される)。ロシアはこれによって一種の自信を得た。その結果、米国への反発と組み合わされた政治面での独自性の主張が強化されただけでなく、「多極化世界」における一極すなわち自立した戦略プレイヤーとしてのロシア、という世界観が浮上するに至った。
ここで著者は、ロシア・ウクライナ戦争の原因としてNATO(東方)拡大を強調する国際政治学における「構造的リアリズム」を紹介しつつ(その主張は結果としてなのかは不明であるが、プーチン自身の言明に理論的基盤を付与する効果も持ってしまっている)、その欠点や問題点を明らかにし、構造主義リアリズムでは解き明かすことが出来ない「なぜその意思決定がなされたのか」という問題への著者自身の考察につなげて行く。
国際政治学における構造的リアリズムは、国際政治の基本力学を「アナーキー」と把握し、また国際政治における最高・最大の権力を国家と見做す。国家の上位階層における超国家組織は存在せず、国連は国家間協力のための組織であり、国家の上位階層にある超国家組織ではない。さらに、構造主義リアリズムは、国際政治の安定はパワーによって保持されると考える。1970年代後半から形成されて来た構造的リアリズムの見解では、パワー配分が世界の構造を決め、その構造による規定の中でそれぞれの国家の行動が決まる。「二極世界」とは二つの国が巨大パワーを独占している状況であり、「多極世界」とは多くの国がパワーを分かち合っている状況である。
なお、高橋氏によれば、国際政治学における構造的リアリズムとは、「システム全体の構造が決まれば、システムを構成する個々の主体の行動もその構造に規定されると考える構造主義を、国際政治学に応用したもの」(p.31)とされる。
私(小方)はもともと構造主義に大きく依拠した物語論(ナラトロジー)を人工知能と結合するところから学術的研究を開始したので、構造主義という言葉にはどうしても反応してしまう。1980年前後には大学で政治学も学んだが、アルチュセールのような「現代思想的な政治思想」以外、構造主義と政治学が結び付く動向に関しては知識がなく、その後この分野からは離れてしまった。確かに構造主義は、システム全体としての挙動を究明するには便利な方法であるが、例えばその中の個々の主体の意識や意図を理論の中に組み込もうとすると非常に苦労する。あるいは、そのようなことは無視しているとも考えられる。私も自分の研究では、全体構造は構造主義で行い、部分構造(機構)はその他の方法で行う、というハイブリッド方式を立てた。ここでの著者の高橋氏の議論も、誤解があるかも知れないが、そのようなものとして私は捉えている。
さて著者の議論に戻る。構造的リアリズムには、国家はパワーの最大化を求めて行動すると考える「攻撃的リアリズム」と、国家は安全の最大化を求めて行動すると考える「防御的リアリズム」とがある。
構造的リアリズムの最大の特徴は、世界をパワー配分という形で抽象化することであり、同じ構造に置かれればアメリカでもロシアでも同じ行動をすると考える。しかしながら、現実の政策決定はそう単純ではなく、特定の状況に直面した国家の行動は、実際には国際政治におけるパワー配分だけでなく、国内政治や意思決定者の心理状態等によっても左右される。構造的リアリズムが重視するのは、個々の事象の説明ではなく、あくまで国際政治に共通するパターンの解明であり、従って個別の意思決定が「なぜ」なされたのかの説明は構造的リアリズムでは困難である。
著者によれば、構造的リアリズムが、国際政治上の個々の事象における「なぜ」について答えられないことの典型は、「バランシング」と「バンドワゴン」を巡る議論の中に現れる。それらは、国際政治上のあるパワーが他のパワーに対抗する際の異なる(対立する)オプションである。バランシングとは、他のパワーと均衡させたり、優越したパワーを持つことで、そのパワーからの脅威を軽減しようとする行動を意味し、自国の軍拡や同盟国の獲得などが含まれる。一方バンドワゴンとは、パワーに対抗するのではなく、「勝ち馬に乗る」ような形で協力し、そのパワーが自国に対する脅威にならないようにすることを指す。
国家をパワーの最大化を求める主体と考える攻撃的リアリズムでは、バンドワゴンは安全を保証しないものであり、選択肢に入らないが、しかし国家を安全の最大化を求める主体と考える防御的リアリズムの場合、バンドワゴンを有効な政策選択肢と見做すことは可能である。すなわち、バランシングとバンドワゴンの選択条件はパワー配分だけではない。構造的リアリズムの主眼は国際政治のパターンの解明であり、各国の個性を捨象してパワー配分のみによって構築されているが、それでは、ある特定の状況下で、ある国がどちらの選択を行うかの理由の説明は不可能であると著者は批判する。
実際は、冷戦後の米欧の重要な政策課題は、ロシアを如何にしてヨーロッパの安全保障秩序に組み込むか、ということであり、ロシア側には次の二つの選択肢―
① 米欧にバンドワゴンする=ヨーロッパの一部になること、
② 米欧にバランシングする=西欧と切り離された「旧ソ連的な勢力圏」を形成すること。
があった。結果としてロシアは②を選択したのであるが、著者は、東欧諸国がバンドワゴン、ヨーロッパの一部になることを選んだのに対して、「なぜロシアは米欧へのバランシング(旧ソ連的な勢力圏を構築して米欧にバランシングして行くこと)を選んだのか」という問題をより深く追求する。
NATO東方拡大の問題に関しては、NATOの拡大そのものがロシア・ウクライナ戦争に至る対立悪化の原因となったのではなく、多極化世界における独自の極であることを希求するロシアのアイデンティティによって、NATO拡大が脅威となった、という明瞭な意見を表明する。つまり、米欧への敵対路線という枠組みの中で、NATOは脅威と解釈されるのである。より具体的には、NATO拡大が脅威になるかならないかは、ロシア自身の自己規定(=自分が何者であるかの定義すなわちアイデンティ)によって左右される。そして、ロシアのアイデンティティとは、「多極世界において独自の極を形成する大国」としてのロシア、というものであった。
ここに、本章における最重要タームとしてのアイデンティティが現れる。本章には、プーチンが心酔していたとされる「ユーラシア主義」や「新ユーラシア主義」などの哲学・思想という、いわば内発的動機付けについては言及されていないが、上述の「あや」などの諸要因によって駆動された上記アイデンティティの強化が戦争を現実化した最も重要な因子として位置付けられる。
次に、先に言及したもう一つの「あや」すなわち中国という存在についての論述が続く。1980年代以降、中国は鄧小平が進めた「改革・開放」路線により爆発的な経済成長を遂げた。2000年代には、米国は「責任あるステークホルダー」概念により、中国を責任ある行動を取る大国に誘導する政策を取った。
しかしながら中国は、2010年前後には南シナ海で一方的な埋め立てによる人工島建設を強行し、その後尖閣諸島を巡り日本との間に緊張を高めて行った。2012年年1月、オバマ政権はアジア太平洋へのリバランス戦略に切り替え、米中対立が深まって行った。
一方で、中国の抬頭と米中関係の悪化は、米欧への対抗を図るロシア側にとっては非常に重要な「補助線」となった。すなわちロシアにとっては、冷戦期には対立していた中国との連携を進めることで、冷戦期とは異なる形での「旧ソ連的な勢力圏」構築への見通しが立つようになった。
こうして、ロシアにおける、冷戦から旧ソ連的勢力圏構築へのプロセスにおいて最も重要なのは、自分が何者であるかという自己認識=アイデンティティであり、「ロシア、あるいはプーチン大統領は、「ヨーロッパの一部」ではなく、「旧ソ連的な勢力圏」を持つ「極」としてのアイデンティティを形成し、そのアイデンティティをベースに中国に「バンドワゴン」しつつ米欧に「バランシング」することを選択したと考えられるのである。」
これとは逆に、ウクライナは、旧ソ連諸国の中でベラルーシのルカシェンコ政権が、ロシアの支援を受けながら民主化運動(=ヨーロッパの一部になる運動)を弾圧し、結果としてロシアの一部になることを選択したのとは異なり、2013年12月から2014年2月にかけてのマイダン革命によって親ロシアのヤヌコヴィチ政権を打倒することに成功したウクライナは、2013年3月からのロシアによるクリミアの不法な一方的併合、同じくドンバス攻撃というロシアの「自己失敗的成功」をきっかけに、ロシアと根本的に対立するようになり、決定的にヨーロッパを志向するに至った。ロシアのアイデンティティにとってウクライナは不可欠なピースであったが、ウクライナ自身は、自分は何者なのかというアイデンティティのレベルで、ロシアとの離反・断絶の道を選択した。
ところで著者はアメリカのいわば責任についても触れている。無論、NATO東方拡大原因論に対してと同様、2014年3月の第一次ロシア・ウクライナ戦争勃発時から喧しかった一方的・全面的なアメリカ帰責論の類(不思議なことに、今でも数多くの著名な論者が感情的に主唱している)の議論からは完全に距離を置いた、「ロシアを抑止できなかったアメリカ―二正面のジレンマ」に関する冷静な論理を展開している。
それによれば、この戦争なマクロレベルでの背景は、「米欧とロシアとの戦略的な相互作用の中で、ロシアが「旧ソ連的な勢力圏」の再構築を追求したために対立が発生・悪化していったこと」であるが、アメリカはNATO未加盟のウクライナ防衛の義務を負っていたわけではないにしても、ロシアのウクライナ侵攻を抑止し得た世界唯一の国であった、というのは事実である。ところが、状況悪化の中で米国による「抑止力」が発揮されることはなかった。バイデン政権が2021年1月に発足した当初、対中戦略(アジア戦略)が政権の国際関係を巡る戦略の中心であり、台湾海峡問題も意識化されたが、それとは対照的に、対露戦略は後回しとされ、史上初めて、ロシア戦略が対中戦略の従属変数として扱われるようになった。アメリカにおける対中戦略との関わりにおいて、中露の離間の追求が主たる課題となったのである。
但し、著者はよりマクロな観点から、「米国の大戦略は中国を抑止することである。仮にロシア・ウクライナ戦争の抑止に失敗したとしても、現在行っている大規模な軍事支援によってウクライナ防衛に成功し、さらに台湾海峡での中国の抑止に成功するには、全体としてはむしろバイデン政権のグローバルな戦略は成功したと評価できることになる。その意味で、バイデン政権の戦略と判断が成功したのか、失敗したのかは現時点ではまだ判断できない。」と述べ、含みを持たせている。
このようにして、「冷戦終結後、世界が平和になるという「ユーフォリア」が広がったが、その期待は30年を経て崩れ去った。結局、ロシアを「ヨーロッパの一部」に取り込んで協調的安全保障の枠組みを作っていこうとする試みは、ロシアのエネルギー開発の成功といった「あや」もあって失敗し、中国の台頭というもう一つの「あや」とも相まって、「旧ソ連的な勢力圏」を構築しようとするロシアと米欧の対立がウクライナにおいて深刻化した。この対立を管理できる可能性が最も高かったプレイヤーは米国であろうが、米国も様々な要因ですべてのリソースをウクライナ問題に投じることができなかった。」(p.46)
以上までが、「ロシア・ウクライナ戦争は「なぜ」始まったのか」という問題を構成する第一の問いすなわち、「「なぜ」ロシアとウクライナ、あるいはウクライナを支えている米欧とロシアとが対立したのか」という問いに対する回答内容である。
本章のこれ以降の部分では、第二の問いすなわち、「「なぜ」ロシアが開戦の決断をしたのか、しかも「なぜ」2022年に開戦の決断をしたのか」という問いに対して、ロシア自身の政策決定の観点からの考察(プーチンはなぜ開戦を決断したのかの考察)が行われる。
著者は、2021年秋から冬にかけて、ロシアが大規模地上戦力をウクライナ周辺に配置し、ウクライナ情勢が「危機」として認識された時期からの展開に着目する。そして、この時期、ロシアは寧ろ、以下のような「四つの外交的勝利」を得ていたという、現代ロシア政治の専門家廣瀬陽子の説を紹介する―
① ロシアが世界の中心を成す国家の一つである状況を作り上げたこと、
② ウクライナのNATO加盟問題について米欧がロシアに歩み寄ったこと、
③ 米欧にロシアのレッドラインと影響圏を明確に意識させたこと、
④ ウクライナ政治を混乱させたこと。
しかし、プーチンの真の意図すなわち「願望」は、「旧ソ連的な勢力圏を再構築すること」にあり、ウクライナをロシアの一部とすることであり、上記のような外交的勝利を得ること自体にはなかった。
著者によれば、「戦略」を構成するのは「願望」と「能力」であり、ロシアのアイデンティティに関連する願望と共に、ロシアの能力の問題の考察も必須となる。ここで注目されるのは、直接的な軍事的能力ではなく、その組織の特徴乃至欠陥としての「インテリジェンスの政治化」という概念である。
組織における「インテリジェンス・サイクル」は、
① 政策部門から意思決定に必要な情報が要求される、
② 情報部門は、この要求に基づき必要な情報を収集・分析し、政策部門の助けになるプロダクトを作成・報告する、
③ 政策部門は、このプロダクトに基づき意思決定を行い、必要に応じ関連情報の要求を行う、
という三つのプロセスから成る。
因みに、Information(インフォメーション)とは、生の情報そのものであり、Intelligence(インテリジェンス)とは、政策部門からの情報要求に基づき収集・分析・加工された情報である。
ここでインテリジェンスの政治化とは、政策部門が既に政策の方向性を決めている場合に、情報部門がその方向性に沿う形の情報を選別してプロダクト化してしまうことを意味する。
著者は、プーチン政権において、インテリジェンスの政治化が発生していた可能性があるのではないかと推測している。そうだとすると、ロシア軍の侵攻によってウクライナが早期に自壊し、クリミア不法併合の際と同じように電撃的に勝利できるとプーチンが本気で信じていたということは、組織から歪んだ情報しか付与されていなかったのかも知れないプーチンにとっては、それ程不自然なことではなくなる。開戦後短期間で攻略に成功した南部のメリトポリやヘルソンのようなことが、ウクライナ全土で起こるとプーチンが考えていたとしても、おかしくはない。「インテリジェンスの政治化」によって、ウクライナのロシア化という「願望」を支える「能力」的基盤があるとプーチンが認識していたのだとすれば、プーチンが武力侵攻を実施したことは、寧ろ合理的な行動であったということを高橋は述べている。
さらに、侵攻がなぜ2022年2月に行われたのか、という第二の問いにおける二番目の問題に関しては、大規模兵力の展開を長期間継続することは不可能であり、タイムリミットがあった、という現実的理由を著者は挙げている。
最後の「おわりに」の節で、著者の高橋はここまでの議論を総括・要約している。最終的な結論は、二つの異質なアイデンティティ(自己認識)の戦争として、ロシア・ウクライナ戦争を把握することができる、というものである。ロシア側における「自分は何者なのか」というアイデンティに関わる問いに対するプーチンの答は、「ロシアは旧ソ連的勢力圏を形成するプレイヤーである」というものであり、これに対して、ウクライナ側のアイデンティティは、東欧諸国と同様、「ヨーロッパの一部」となること、であった。
米欧とソ連の対決であった冷戦後米欧の戦略とロシアの戦略が離反して行ったこと、中国の抬頭によりロシアが中国と接近して行くようになったこと、そして、アメリカの主要課題は中国抑止であり対ロシア戦略は対中国戦略に従属していたこと―これらが、上述のようなアイデンティティの戦いの背景乃至基盤であり、あるいはそれを現実化するに至る水路の役割を果たした。
私は、私自身の物語生成研究―人工知能・認知科学や物語論(ナラトロジー)に基礎を置く―の観点からするロシア・ウクライナ戦争論『物語戦としてのロシア・ウクライナ戦争―物語生成のポストナラトロジーの一展開』を執筆し、間もなく新曜社から発刊される予定であるが、私がこの本で唱える物語戦は、高橋杉雄が言うアイデンティティの戦いと部分的に重なる所のある概念である。勿論私は国際関係論の専門家でもロシアやウクライナの専門家でもなく全くの素人であるが、あまり限定されない、つまりもっと「厳密でない」観点から物語戦という概念を捉えているため、無理に関連付けようと思うことはない。しかし、戦争勃発当初から期待していた類の議論が日本でもようやくされるようになったので、僭越ながらここに、新書の一章として書かれた高橋杉雄氏の論文を紹介させていただいた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
