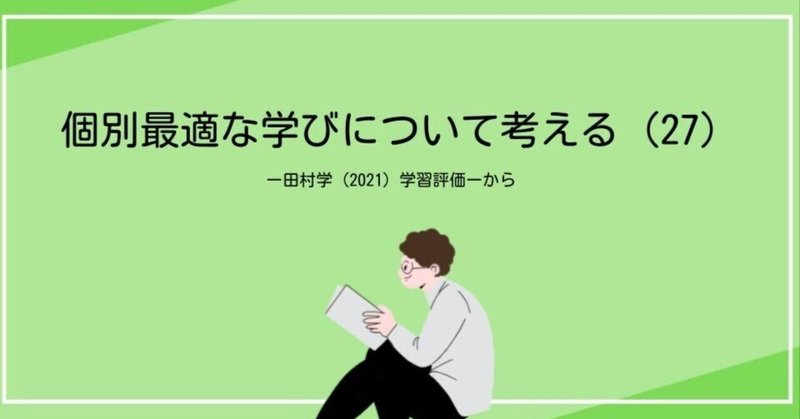
個別最適な学びについて考える(27)ー田村学(2021)学習評価ーから
今回は、田村学氏の2021年の著書『学習評価』をテーマに、学習の評価に焦点を当て、なぜ評価が学びにおいて重要なのか、そして個別最適な学びにどのように結びついているのかについて考えていきたいと思います。
学習において、進捗を測ることは不可欠ですが、それがどのように行われるかが、学習者や教育者にとって大きな影響を与えます。田村氏はその点にフォーカスし、学習評価が単なる評価だけでなく、個々の成長を促進する手段としていかに活かせるかについて議論しています。
さて、一緒に田村氏の洞察を追い、学習評価がもたらす可能性を共に考えてみませんか?学びのプロセスにおける評価の意味を掘り下げ、より良い学びの方向性を模索していく旅に、ぜひご一緒に!
「見取り」とは,子供の学びを捉え,解釈する教師の行為と考えることができる。評価を行う中で,指導の改善に機能させる教師の行為とも言えよう。実際の指導の最中に行うもので,一人一人の子供に対して,評価の観点などから子供の学びを捉え,即座に判断して指導の改善に反映させていく。
一方,「評価」は,確かな見取りを基盤に,評価規準に対する学習状況を見定める教師の行為と考えることができる。とりわけ総括のための評価として評定に反映させる行為とも言える。指導の最中や最後に,全ての子供に対して,同一の評価の観点から評価し,その結果を通信簿や指導要録に記載していくデータとなるものでもある。
「見取り」と「評価」の違いがあります。
自分も考えなければいけない点ですが,混合して使ってしまっているところがありませんか。
通信簿は「評価」なので同一の観点から考えなければいけません。「見取り」も少しはいるのかもしれませんが,ここでは同一を守っていきたいです。
個別最適な学びのためにも,常にしなければいけないことは「見取り」だと私は考えます。今は,子どもたちの思考過程や学習過程がクラウドで見やすくなっています。そうした姿を,教師である人たちが見取らなければいけません。だからこそ,教師はさらに忙しくなるのかもしれないですね。
今まではノートでしか,学習の様子が見取れなかったわけですが,常に見えるということは,教師は常に指導の改善を図り,その児童に合った助言がしやすくなっているということです。
実はこの続きでは,その見取る時の方法が5つの視点から書かれています。この先は,ぜひ書籍を購入して読んでみて下さい!
個別最適な学びのヒントはたくさん転がっています…一緒に勉強を頑張りましょう!
本日はここまで!また次回の記事でお会いしましょう!
よかったらサポートもお願いします!
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
