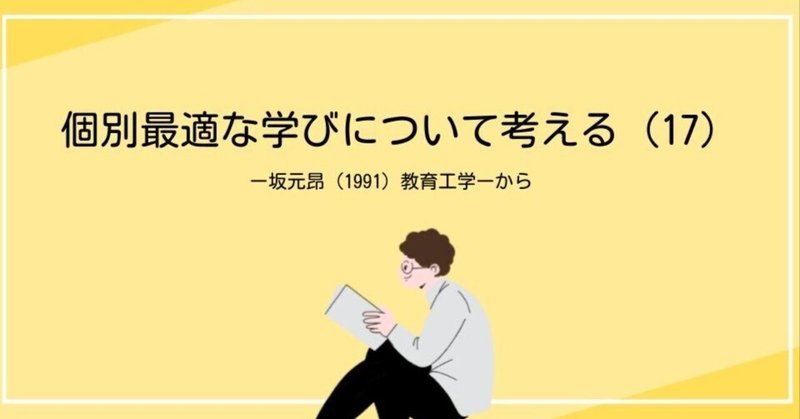
個別最適な学びについて考える(17)ー坂元昂(1991)教育工学ーから
さて,もう少しで11月も終わりですね。
気づけば今年ももう終わりそうです。
寒くなり体調不良になりやすいこの季節ですが,しっかり手洗いうがい,睡眠時間をとって健康に生きたい今日この頃です。
年末まで気合いを入れて学んでいこうと改めて思い連続投稿中です。
もっと頑張ります。
早速本題へ!
本日は,「坂元昂(1991)教育工学.放送大学教育振興会,東京」です。教育工学というタイトルで学術的!?と一歩引いてしまうかもしれませんが,勇気を振り絞って見ていきましょう!
学習者は,学習に際して,さまざまな学習の方略や方策を用いる。ところが,授業の中では,学習内容についての指導は,いろいろな工夫をこらして改善の努力がなされるが,学習者の学習のしかた,たとえば,ノートのとり方,本の読み方,資料のまとめ方などについては,大切であるにもかかわらず,系統的な訓練や指導がなされないことが多い。
方略の方については,問題の発見,解説,資料収集,実験,結果の整理,まとめ,表現などの過程を順を追って進める形で,授業が進められるような場合,自然に学習者に,問題解決や学習のしかたが身についていくことがある。しかし,細かな学習技能については,ふつうは系統的な指導がなされないままになっている。
今だからこそ学習方法を教えることに意味があるのではないでしょうか。子どもたちは学習を調整していかなければなりません。その中でなんとなく指導してしまっているということになってはいないでしょうか。
今まではノートの取り方や,黒板の書き方から勉強法を身につけていたのかもしれません。しかし,現在ではそれぞれの学習の進度も方法も異なってくるわけです。加えて,学習方法をしっかり学ぶことが重要になってくると考えます。
使った時にしっかりその学習方法を身につけることができるように指導することが教師の役目になるのでしょうか。また,この教科,この単元であればこの学習方法がしっくりくるかもしれないと予想立てて,適切に支援することも大事になるはずです。
例えば,インタビュー調査など一度しっかりと身につけてしまえば,その児童にとっての学習方法として武器になりうる可能性もあります。次の時間からは,インタビュー調査もいれば文献から調査もいればといった学習方法の多様化にもつながると思います。
最終的には,児童自身で調整していくことを目指していきたいので,学習方法も選択して調整して学習する経験をたくさん積ませたいと考えました。
本日はここまで!また次回の記事でお会いしましょう!
よかったらサポートもお願いします!
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
