
他人の気持ちはわからぬもの 『行人』
夏目漱石というと、学校で習った『こころ』しか読んだことがなかったのですが、少し前に『草枕』を読んで、そのあまりの美しさに仰天しました。
今まで知っていた日本語表現の概念を根底から覆されるような、日本語ってこんなにも美しくなれるのか、という新しい地平線を見たかのような衝撃です。
見たことない表現や読んだことのない漢字の組み合わせがたくさん出てくるのですが、しかし漢字とは便利はもので、読み方がわからなくとも意味を感じ取ることができます。
漢字の持つ絵としての機能のおかげで色彩を感じ、意味が浮かびあがり、情景が身体に染み入ります。言葉って本当に豊かです。
何かについて説明するとき、私なら形容詞を並び連ねるだけ。薄っぺらく浅いです。
ところが夏目漱石が何かを説明しようとすると、全ての表現が瞬く間に詩へと昇華されてしまいます。形容詞というより形容詩あるいは形容漢詩。言葉と言葉が繋がり輪を広げ、文章に奥行きと四方へ広がる立体感が生まれる様子は魔法のようです。こんな日本語の使い方、今まで知りませんでした。
『草枕』はピアニスト、グレン・グールドの愛読書だったそうです。グレン・グールドにハマった学生時代、一度『草枕』を手に取ったことがあったのですが、その時はさっぱりわからず。面白くなくって、読み終えることなく手放してしまいました。
ところが10年経って同じ本を手にしてみると、日本語観を覆されるほどの衝撃を受けるのです。少しは成長したということでしょうか。
本ってつくづく出会うタイミングが大切だなと思います。きっと本が面白くなかったんじゃなくて、私の方が本に見合うほど面白い人間じゃなかったのでしょう。
日本語表現の美しさはもちろんですが、主人公が結構面白くて笑える一面もあります。堅苦しくありません。そして夏目漱石の芸術論が非常に興味深い一冊です。日本語を理解できることの喜びに痺れる体験でした。
さて、今日の本題は夏目漱石の『行人』です。『草枕』を読み終えて、次に手を出したのがこちら。
何を読もうか選ぶとき、大抵、本の裏に書いてあるあらすじを参考にします。
夏目漱石の小説はあらすじだけを読むと、正直あんまり惹かれません。しかし"妻の心を疑って、自分の弟に一晩妻とどこかに泊まってみてくれないかと頼む兄"という『行人』のあらすじにはちょっと興味をそそられるところがあり、買ってみました。果たして兄嫁は夫の弟に惹かれているのか?一晩泊まって2人はどうなるんだ?という下世話な気持ちから読み始めたのですが、手に取った時の低い期待値に反してもの凄く面白く、人間を深く描いた小説でした。
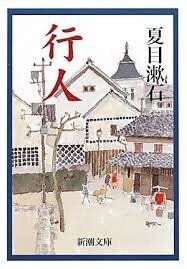
物語の語り手は、弟の二郎です。
兄の一郎や、友人の三沢が主人公でもドラマチックな一冊の小説が出来上がりそうだけど、二郎目線で語られるところにこの小説の妙があるのだと思いました。
というのも二郎はゴタゴタに巻き込まれるのを嫌い、のらりくらりとかわすタイプ。それゆえ、家族と肝心な話をするのを避けるのです。読者としては何度も何度もクライマックスかと期待させられるやスッと落とされて、とにかく焦ったい。
母はあの時何を言いたかったの?兄嫁にもっと核心に迫る質問をしてくれ!お兄ちゃんともっと話し合いなよ!と思うのだけど、しかし肝心なところで二郎はいつもはぐらかし、逃げる。
読者としてはもっと家族とぶつかって話を聞いてほしいと気持ちがはやり、焦らされます。
このジリジリとした気持ち、神の視点で俯瞰して物語を読める読者という立場にありながら、二郎以外の気持ちの奥は覗かれないもどかしさに人間のリアルを感じて癖になる味わいがあります。
この分からなさこそが行人の面白さなのでしょう。他人のことはどうしたって分からないのです。例え話し合ってみたところで、本当のことを語っている保証もないのです。
それだけに、他人の心が分からずもがき苦しむ一郎の姿に共感が生まれます。
他人の言葉や優しさが、誠から出たものかどうかと鋭く感知する一郎。こういう気持ち、思春期に誰もが一度は覚えるものではないでしょうか。少なくとも私には、ありました。テレパシーのように心から心へとダイレクトに通じるのでなければ、どこかに隠す心があるのでは、と人を信用できない気持ちや、嘘偽りのない"本当"を知りたい気持ちの切実さが痛いほどわかります。
しかし常人であれば思春期は過ぎ去り、いつの間にか他人と世界と折り合いをつけて生きて行けるもの。いや、生きてしまうもの、と言えるかもしれません。
一方で、どこまで行ってもひたすらに、頭でっかちに生きることしかできない一郎。一郎は確かに賢い。遠くまで見ているし、時間をかけて考えます。どんなに小さな事象でも気になると立ち止まっていちいちひっくり返して裏表確認します。ちょっとした言葉に敏感です。Hさんとの宗教が絡んだ問答は秀逸です。
誰にでもできる生き方ではないという意味でとても大変そうですが、しかし誠実とも言える生き方をしているのだと思います。にも関わらず、一郎には決定的に何かが欠けているのです。
人間は頭の中だけでは生きられません。一郎自身が述べる、地図を見るだけですべてを知ろうとする人と、実際に出かけてみる実地の人との比喩はストレートに腑に落ちました。
一郎自身が一番、自分に欠けているものをわかっていたのでしょう。しかし理解できるということと、やってみるというのは全く異なることです。その狭間で身動きが取れなくなる一郎の苦しみが、痛みを伴って心に響きました。
物語は唐突に、Hさんからの手紙で終わります。これから一郎はどうなるのでしょう。この家族は一体どこへ向かうのでしょう。何も解決しないまま、ここでもまたクライマックスを迎えずにブツッと途切れるような幕切れです。
しかしあとに引く余韻のせいで、本を閉じた今もまだずっと、この家族と一緒にいるような気持ちに取り残されるのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
