
コンビテンシー面接の活用術Vol.9(4/4)
10.次世代リーダーの発掘と育成
最後にもう一つ、コンピテンシー評価の活用例として、MSCが実施している「次世代リーダーの発掘・育成」プログラムについても記しておきましょう。
これも基本的には前項のアセスメント手法と同じですが、このプログラムでは行動面接ではなく、アセスメントセンター形式――評価対象者の行動そのものを観察し、そのデータを判断材料にする方法――をとっています。また、その目的は文字どおり、次の世代を担うリーダー(社長をはじめとするボードピープルの候補者)たり得るかどうかを診断すること、そして育成の方向性(さらに伸ばすべき能力要件や改善すべき行動特性など)を明らかにすることです。
一方企業サイドの目的は、次世代リーダーを選別し、その方たちに互いに競わせるなど、リーダーとしての育成・能力開発を意識的に行いつつ、常にそういう人たちが社内にプールされている状態にしておくことにほかなりません。
というのも、現在はどの企業においても、グローバル競争という新たなビジネス環境の下で「次世代リーダー」の発掘と確保、そしてグローバルリーダーのリーダーシップ開発が大きな経営課題になっているからです。ことにグローバル展開を推進して戦線が海外にも拡大している企業には、重要な問題といえるでしょう。
もちろん、次世代リーダーに求められる能力要件は、各企業によって異なります。このプログラムを実施するにあたっては、あらかじめクライアント企業とともに「リーダーに求められるコンピテンシー」を検討し、その定義と主要行動(キーアクション)を一つひとつ確認していくことからはじめるのは、コンピテンシー面接の準備と何ら変わるものではありません。
こうした準備を十分に整えたあと、リーダーとしての適正評価にとりかかるわけです。
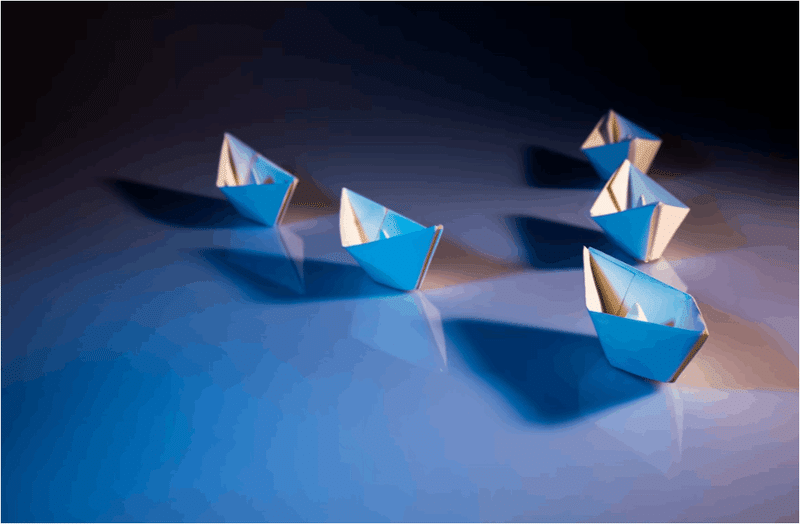
11.行動を観察することによってリーダーとしての能力を診断
私たちMSCでは「次世代リーダーの発掘・育成」プログラムを行うため、会議室や欧米スタイルの執務用個室などで構成される専用フロアを本社に設けています。評価対象者となる方には、通信機器や情報機器などが整ったその個室で実際の仕事と同様にさまざまなマネジメント――主要行動が評価者に判断できるようあらかじめシミュレーションされたいくつものビジネス課題――に取り組んでもらうわけです。
アセスメントを担当する評価者(アセッサー)は、訓練と実績を積んだMSCのプロであることはいうまでもないでしょう。このプログラムを活用されているのは大手の精密機器メーカーや自動車メーカーなど大企業が中心ですが、その中には自社で評価者を養成されているところもあり、その場合は社内アセッサーの方たちとともに私たちは共同で評価にあたります。
また、そこでのマネジメント・シミュレーションは、たとえば部下からの相談事に対して裁定する場面、会議で重要な経営課題について意思決定をくだす場面、部下をコーチングする場面、一人で困難な業務を処理する場面、急を要する重要取引先からの電話に返答する場面、顧客に対して企画を作成し、プレゼンテーションする場面など、じつにさまざまです。
当然ながら、これらの場面における評価対象者(次世代リーダーの候補者)の反応や行動はすべて違います。評価者はそれら行動事実の一つひとつを実際に観察し、あるいはビデオでモニタリングして、そこにあらわれる行動特性がリーダーとしてのそれにふさわしいかどうかを見極めるわけです。
ここで診断される能力要件には、対人スキル、リーダーシップ・スキル、ビジネス・管理スキル、個人的資質(経営幹部としての性向)などがあります。
すべてのシミュレーション・プログラムが終了するまでには、短くてもまる一日、通常は二日間かけて行います。評価対象者の疲労困憊(こんぱい)のほどは推して知るべしでしょう。「もう2度と受けたくない」とおっしゃる方がほとんどです。
そうではあっても、このプログラムの価値は診断・評価の精度がずば抜けて高いというところにこそあります。先に挙げた「評価手法の精度」で「アセスメントセンターの信頼性」が「0.65」の最高値であることを思い起こしてください。ちなみに、これに次ぐ高い信頼性をもつ評価手法が「行動面接」です。ここにコンピテンシー面接をとり入れると、さらにその精度は上がり、DDI社のデータによると、その信頼性は「0.93」という驚くべき数値が報告されています。

12.人材戦略の大きな流れを紹介
さて、ここまで本書では「従来の採用面接のあり方に問題意識を喚起し、人の行動にフォーカスをすること」がいかに重要かを述べながら、「コンピテンシー面接」の全体像を通じて採用面接における人材の正しい見極め方と面接データを生かした個々人の育成、そして組織の活力を高める方策」ということをメインテーマとして述べてきました。
最後に紹介した「次世代リーダーの発掘・育成」プログラムは、「ある人の現在までの行動は、将来の行動を予測する」という基本の考え方を実証しているものといえるでしょう。
アセスメントセンターで観察されたその人の「行動」観察、そして、実際の場では見えない行動を浮き彫りにする「コンピテンシー面接」、そこで収集した行動情報に基づく「コンピテンシー評価」の基本思想――評価だけにとどまらず、その情報を個々の能力開発につなげる――が最も凝縮され、強いリーダーを育成し、付加価値を創造できる人材の確保が、ひいては強い組織をつくっていくという、大きな人材戦略の流れがご理解いただけたのではないでしょうか。
なお、次世代リーダーの選別とその考え方の詳細については、『「AP方式」による 次世代リーダーの発掘と集中的育成』(ウィリアム・C・ゴイアム、オードリー・B・スミス、マシュー・J・ペース著 竹内清之[MSC代表]監訳、MSC訳)を参照願うことを付記して、筆を擱(お)くことにいたします。

【著者プロフィール】 伊東 朋子
株式会社マネジメントサービスセンター執行役員 DDI事業部事業部長。国内企業および国際企業の人材コンサルティングに従事。
お茶の水女子大学理学部卒業後、デュポンジャパン株式会社を経て、1988年より株式会社マネジメントサービスセンター(MSC)。
人材採用のためのシステム設計、コンピテンシーモデルの設計、アセスメントテクノロジーを用いたハイポテンシャル人材の特定およびリーダー人材の能力開発プログラムの設計を行い、リーダーシップパイプラインの強化に取り組む。
(※掲載されていたものは当時の情報です)
🔵おすすめソリューション
🔵会社概要
会社名:株式会社マネジメントサービスセンター
創業:1966(昭和41)年9月
資本金:1億円
事業内容:人材開発コンサルティング・人材アセスメント

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
