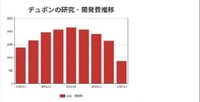記事一覧
読書記:「アメリカ海兵隊--非営利型組織の自己革新」(野中郁次郎著、中公新書) (2011.6.30日経産業新聞寄稿)
「アメリカ海兵隊」は複合的な機能(陸海空)を持ちながら、「分化」と「統合」のダイナミックな関係を確保しつつ、専門軍とは異なる強みを発揮する。様々な成功失敗を経て、現在の「最強組織」を築く方法論が形成された。 著者は現在の海兵隊を、有事即応部隊としての「使命」を有する組織と定義する。時代とともに変化する使命に対応してきたがゆえに、海兵隊は持続発展してきた。それは人間の普遍の価値(正義、自由、勇気、愛など)を堅持し、機能的価値については革新を続けるという目市新組織であり続けたこと