
MOSH CEO籔×キャスター石倉さん対談:リモートワークのプロに聞く体制構築のイロハ
キャスター取締役CROの石倉秀明さんにアドバイスを受けつつリモートワークの体制構築に力を入れているMOSH。これまで多数の企業を見てきた石倉さんがMOSHの社内を見て気づいたことは? 一般的にリモートワーク導入時の企業がやりがちな勘違いあるあるなどを始め、具体的なアドバイス、評価制度についてまで。組織づくりに対峙するCEOの籔が、リモートワーク中心の組織に移行する中で「今」リアルに考えていることを、フルリモート組織運営のプロである石倉さんに詳しくお伺いしました。
*この記事は先日podcastで行われた対談の記事verです。podcastはこちらから聞いていただけます。
フルリモートワーク推進のきっかけ
籔:本日はよろしくお願いします!
石倉:よろしくお願いします!
籔:石倉さん、まずMOSHのフルリモート化を促進するにあたって社内を見ていただいて何か感じたことや、ジェネラルに他の会社さんも含めて(支援に)入っている中ででも良いのですが、気付いたことなどありますか?
石倉:そうですね、何十社とか見てるわけではなくて、ご相談をいただいてSlackとか入らせていただいてみたりとかってことが多いんですけど、リモート化を推し進めていくっていう中で、苦手としているところや、課題のがあるポイントみたいなものが各社ちょっとずつ違っていて、揃っている人の特性なのか、仕事の進め方だとか、社長の性格とか仕事の進め方なのかとか、結構違ってるなっていうのは面白いなと思います。
籔:なるほど。
我々のこれまでの働き方みたいなところの経緯を簡単にお伝えすると、ちょうどコロナのタイミングでフルリモートになりまして、それまでは結構オフィスでガッツリ仕事してたというような形でした。
事業的には20年の3月ぐらいまでは、業務委託の方にちょっと手伝っていただきながらもほぼ創業メンバーだけでやっていたような会社で、20年の10月に調達をして、そこから結構採用を推し進めていったんですけれども、採用も組織作りも含めて、基本的にはフルリモート下で進めていったという経緯がありました。
ちょうど昨年は、それこそ創業メンバー以外の初めてのメンバーにどんどん入ってきていただいて、昨年だけで13,4名ほど増えて、結構大きく組織を作ってきて、その中でコロナ禍の(規制などが)定常化してきて、組織として継続的な対応としてどういうふうにやっていくのかみたいなところを考える中で、我々として新ためてフルリモートと、もしくはオフィス出社を選べるような形のワークスタイルっていうところを明確にスタンスを切った方がいいだろうというようなことを考えていたんです。
でも今までの延長線上で進めていたので、やっぱり働き方の部分を裁量と合わせてメンバーの評価だったりとか制度の部分の整備や、より働きやすい環境、組織全体でのスループットを上げていくためにはどうしたらいいかみたいなところが課題に挙がっていたので、その中で石倉さんに相談させていただいて少しずつ推進されてきたというような、経緯になっております。
石倉:ありがとうございます。
籔:今日はフルリモートで体制整備をしていく上で考えないといけないことなどをディスカッションできるといいなと思ってるんですけれども、その前に、石倉さんはキャスターでずっとやられてきたと思うんですけど、どういう経緯があってフルリモート化を推進されてたんですか?
石倉:僕自身とキャスターとって話だとちょっと別なんですけど、僕はちょうど子供が生まれるタイミングに独立をして起業というか、自分の会社をやることになったんですよ、当時キャスターじゃない会社ですけど。
このタイミングで会社をやろうと思ったのは、自分の働く場所とか時間にあんまり左右されず、働けるようになりたいなっていうのがあったんですよね。なので、当時としては、人数も少なかったからあれなんですけど、もう最初から出社もせずというかオフィスを借りずやるっていうことを、前提でスタートしたってのは僕自身としてはあります。
この個人でやってた会社として、キャスターはお手伝いしてた立場からスタートしてるんです。キャスターは、代表の中川が創業するときに、元々の前職とかでクラウドソーシングとかを使う機会があったらしいんですよ。なんかすごい普通に働ける人たちなのに、オンラインってなると急になんか内職みたいなイメージだったりとか、なんかよくわかんないすごい低い単価で仕事したりみたいな、当時やっぱりそれぐらいしかなかったみたいなことがあって。
よく考えると、例えばですけど籔さんが東京にいて、それがやっぱ高知県に行きましたってなったときに、なぜか仕事も減り、給与も下がるみたいな。よく考えるとあんまり意味わかんないっていうルールが世の中的には普通じゃないですか。
籔:うんうん、そうですね。
石倉:よくわかんないルールなんで、それに苦しんだりとか、それがおかしいと思ってる人は結構世の中にいるだろうということで、それを当たり前にできるような事業体をやろうみたいなことからスタートしてるんですよね。もう創業からずっとリモートなので、1回も集まることも基本的にはなくやってるっていう感じですね。
出社とリモートワークは競技が違う
籔:なるほど。この辺、本当に細かいところとか含めて結構工夫されてきたかなと思うんですけれども、他社のその共通した課題感とかも含めて、この辺がすごい大事なポイントだみたいなところって、石倉さん的に挙げるとすると、どういうところがありそうですか?
石倉:リモートワークをどううまくやるかみたいな議論になるときに、もうみんな前提は、「Webミーティングをどううまくやるか」っていう話がほとんどなんですよ。リモートワーク=ウェブ会議なんですよね。
籔:なるほど、面白いです。
石倉:というのが世間の認識で。だから今まではオフィスにいたら執務スペースというかデスクのとこでも話もするし、ご飯とか食べながら話もするし、会議室で会議をするっていうものが、リモートワークになったことで一日中ずっと全員が会議室にだけいてそこでしか話さない、みたいな人がめっちゃ増えちゃったってのが今なのかなっていう感じがして。いや、そりゃ疲れるよねと。
リモートワークの良さが何かっていうと、場所に関係ないっていうことがあるのもそうなんですけど、結局なんか僕はテキストのコミュニケーションの良さをどこまで活かせるか、なのかなと思ってて、テキストコミュニケーションとか非同期のコミュニケーションをどこまで生かせるかだと思うんですよね。
籔:うんうん。
石倉:例えば会議だと1時間のうちに1個の話題にしか話せないわけですけど、チャットで議論ができるんだったら、1時間のうちに3つぐらいもしかしたら同時に進められる可能性もあって、その3つぐらいに結論を出せる可能性があるじゃないですか。これを1年続けた人とはすごい差になると思うんです。
そういうのをどう使えるかなんじゃないかなっていう気がしています。出社とは競技が違うというか、今までは会議とかで喋って、デスクで仕事をして、その中でちょこちょこっとコミュニケーションとりながら修正していくっていうやり方だったのを、いかにチャットをベースにしたテキストでのコミュニケーションをベースにしながら、必要なときだけ会議をするっていう風に進められるかどうかっていうのはありますね。
コミュニケーションの比率がだいぶテキストに寄るっていう。それはやっぱり大きな違いだと思うんですよね。
籔:うーん。なるほど。

籔:一番最初お話させていただいたときに、石倉さんからSlackは執務エリアでミーティングは会議室だよね、っていう話で、やっぱり執務エリア=Slackでの会話みたいなものがMOSHは結構少ないよねというところがあって、この辺の考え方のインストールって推進していく上で非常に大事だなと思っています。
オンラインでやるから、仕事の仕方というか効率が劣化するよねみたいな形ではなくて、むしろ非同期であることによってさっき言っていただいたような、捌けるissueとか、その人の状況とかに応じてリアルタイムに進めていける、みたいなところが、むしろ良さなはずで。
それを生かしていくような体制というか、制度にしていかないといけないよねと感じたし、個人的にSlackオフィスであるっていうところはとても腑に落ちたというか、個人的にめっちゃアップデートされた感じがありました。

”一回で伝えなければならない”症候群
石倉:そうですね。あとなんか見てて思うのは、テキストになると、1回で伝わらなければならない、みたいな、なんとなく暗黙の了解みたいなのがあるじゃないですか。
籔:確かに確かに。
石倉:1回で伝えるために結構長く書いたりとか、うん、整理して書かなければならないみたいなことってあると思うんですけど、でもSlackのチャットを執務エリアでの会話やコミュニケーションを捉えた場合、うん、対面のコミュニケーションでそんなことしないじゃないですか。結論だけ言って終わり!みたいなコミュニケーション取り方ってあんまりしないわけですよね。
籔:そうですね、確かに。
石倉:普段は人間的にやらないコミュニケーションをなぜかテキストだとやらなければならないっていう風に、なぜか勝手にみんな思ってて、それに苦しんでたりとか、苦労してる会社が結構多いんじゃないかなと思っています。だからキャッチボールすりゃいいじゃんって思うんですけど、なぜかテキストになると1回で終わらせなければならない症候群みたいのがあるんですよね。
籔:確かにそれはありますね。何か抜け漏れがあると論理的に問題があると思われる(のを恐れる)みたいな感覚ですよね。
石倉:そう。でもそれって別に直接話せる場合でも起こるわけじゃないですか。それをどういうこと?とかこういうこと?とかって、聞きながら会話ってお互いによって成立させていくわけです。
これは別にテキストでも多分一緒のはずなんだけど、何かこうメールの名残なのか、テキスト=連絡事項っていう認識だからなのかわかんないですけど、そんなコミュニケーション普段取らないじゃんよく考えたらみたいな。
籔:確かに。いや、それは大事ですね。
石倉:そうそう。普段できないことをやろうとしたらできないよそりゃ、みたいなのが結構多い気がするんですよね。
籔:その辺のアップデートは結構、考え方を変えていかないと、やっぱりSlackが連絡する場所だっていうふうに捉えてるとか、そういう前提になってる可能性はあるなと思うので。
石倉:LINEぐらいの感じが多分本当は正しいんだと思う。
籔:確かに。メールの延長線上とかで捉えちゃうと、結構、ギャップが出ちゃう感じがしますよね。
石倉:それはなんか結構みんな苦労してるかなと。あと、よく何をチャットで話していいかわかんないみたいなことを結構言われるんですけど。いや、思ってることとか考えてること全部言えばいいんだよと思うんですが、割とその過程を出すっていうことに違和感がある人はあるみたいですね。
籔:この辺は非常にありそうですね。
石倉:普段の会社だったらやってたはずの会話ですが、テキストに落とすっていう行為においては、ちょっと抵抗を感じるっていうのは、あるんだろうなと思います。
基本全てオープン?社内での情報公開
籔:このあたり、経営チームとかでClosedで話してるテーマみたいなものって各社あると思うんですけど、うちで言うと例えば採用の細かいところとか、そういうこと決めていくプロセスってどれぐらいそのオープンにしてるとか、この辺意識されてることありますか?
石倉:僕は基本個人情報とか、あとはさすがにみんなが触れるものではない情報ってやっぱあると思うんですね、会社経営していると。それはプライベートにしますけど、それ以外は基本オープンチャンネルかな。
籔:なるほど。
石倉:施策の考え方とかもそうだし、その辺はずっとオープンの中でやってますね。だって執務室で話してたら聞こえるじゃないですか。なぜチャットになると聞こえてはいけないのかって言われると、大体聞こえていいよねみたいな。
籔:それはそうですよね、
石倉:むしろ執務スペースだともうちょっと個人情報も意外と喋ってた気がするんだけど(笑)
籔:確かに(笑)
石倉:だから、僕の中では会社にいて何か喋るときに、「ちょっと一瞬良いですか」って会議室に行って喋らなきゃいけないような内容ってあるじゃないですか。あれはプライベートでやるべきだと思うんですけど、普通スペースで話せることは別にオープンでいいかなと思います。
ドキュメント化だけでは伝えられないこと
籔:なるほど。少し話が戻っちゃうんですけどうちも結構notionとかを使ってドキュメント化はすごいやってたんですけれども、やっぱ量が膨大すぎてそんなにみんな見に行けないよねっていう状態に陥ってて、その中で過程も含めてnotionに結構書いてたんですけど、それだと本質的な思考のプロセス開示にあんまりなってなかったっていうところがあって。
この辺はやっぱりSlackで対話しながらやっていくといいよねっていうのは、個人的に結構すごい新しい発見だったなと思ってますね。
石倉:そうですね。notionでドキュメント化してくのはめちゃくちゃ大事で、やっぱりSlackでいっぱいコミュニケーションを取るのが苦手な会社とnotionとかのドキュメントが苦手な会社と、どっちもできませんみたいな会社があるなと思っていて。そういう意味だと、ドキュメント化はめっちゃしっかりされてるんだけど、基本的にはドキュメントにないことは実はチャット見てみても、あんまり空気感がわかんなくて、最初に入ってくる人からすると、情報はわかるんですけど、なんかよくある「ノリ」みたいのがわかんない、みたいなことがあるのかなと思っていて。この人なんかすげえめっちゃいろんなところで絡んでいくんだみたいな。
籔:うんうん、ありますね。
石倉:僕は「ノリ」を残すの大事だなと思います。社長をいじっていいのかどうかみたいな(笑)

籔:はいはい。なるほど。
石倉:なんかこの「いじられキャラである」みたいなものってなんかこう、チャットに残ってるとなんとなくわかるんですけど、残ってないとオンラインランチとかして初めてわかるみたいな。
籔:確かに確かに!
石倉:でも次に来た人はまたわかんないからまたオンラインランチまではわかんないっす、みたいなのが繰り返されるから。最初に雰囲気がわかるといいなというのは思います。
籔:確かに。雰囲気はやっぱりそこのプロセスでわかるっていうのはありますもんね。
石倉:会話の中の「ノリ」みたいなのと、あとはスタンプがいっぱい作られる作られないとかね。
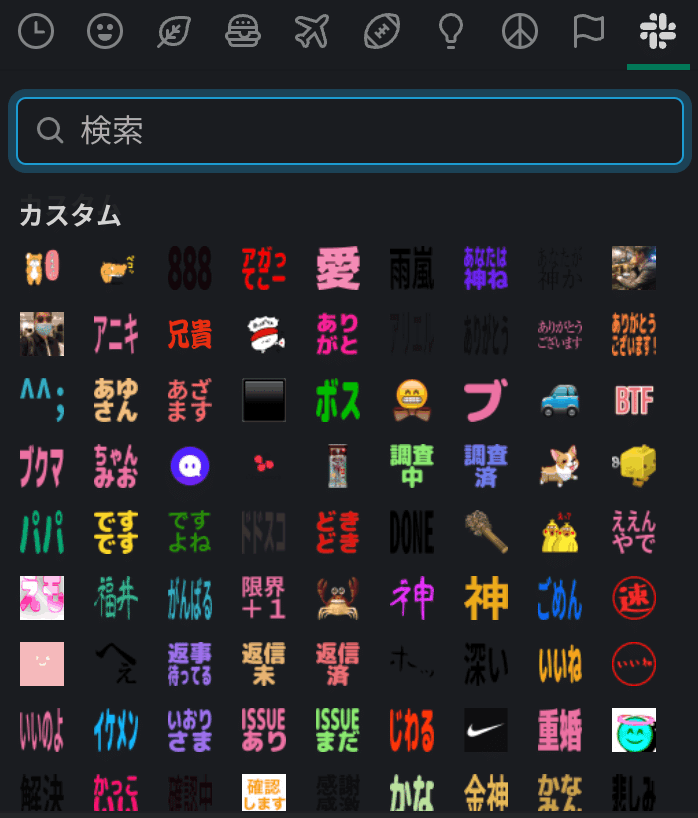
フルリモート下での評価制度ーー成果と評価は分けて考える
籔:僕としてはここら辺がすごいコアかなと思ってるんですけれども、ここと合わせて、当時考えていた課題感として、評価しづらくなってないのかとか、全体の会議とかがもう少し盛り上がるような設計ってないのかなとか、オフラインでやったらいいんじゃないかとかいろいろ試行錯誤してきたんですけど、この辺りの制度とか、評価みたいなところだったりとかって、リモートになるにあたって何か変わる部分ってありますか。
石倉:いやー評価は、別にリモートじゃない頃ももちろんやってたわけですけど、結果むずいっすよね。
籔:結果むずいっすね(笑)
石倉:目標設定をめちゃくちゃちゃんとやらない限りは。目標設定がすごく適切で、かつ測定可能で、数字じゃなくても、例えばこの3ステップがあったら2ステップ目まで終わってるみたいな、しかもそれがチームに影響するものが個人でできるものかみたいなちゃんと設定したりとかして初めて何かできた、できないってジャッジできるじゃないですか。なので評価って、結局目標設定低の正しさがほぼ全てで、目標設定をちゃんとするってすごい難しいんだと思うんですよね。
籔:そうですよね。
石倉:しかも事業と連動的じゃないですか。施策も変わるし下手したらOKRが途中で変わるとかあり得るので、なかなか評価が難しいのは(オンラインでもそうでなくても)一緒だなと思ってて。
どっちかというとちゃんと目標を立てれるようなところに時間を使いましょうっていう話と、その進捗をずっとちゃんとその人の目標とかチームの目標みたいなのが、今どうなってんだっけって追えるように、もう会議のアジェンダをそれにするみたいなぐらいでちゃんと追っていくとかっていう。もうそこかなあっていう気はしますね。
籔:確かに確かに、そうですね。なんか前提としてのその目標設定の難しさありつつ、多分結構「納得感」みたいなものって重要だと思うんですけど、その納得感を醸成するプロセスとして、オフラインってなんとなく「見てる感」みたいなものがあったりとか、場を共有してるコンテキストがある種作られたと思うんですけど、何かその辺がやっぱり機能としてなくなったときにどうお互いちゃんと「見てる感」みたいなものをオンライン上で作っていくかみたいなのは、すごい大事なのかなと思ってますね。
石倉:そう、だから目標設定したものをずっとお互いちゃんと追ってる状態で、見てる、ふり返ってる、みたいなのがやっぱりその期中を行われてるっていうのは大事だと思ってて、やっぱり目標設定の方がすごい大事なんだろうなと思うんです。
籔:そうですね。
石倉:普段の会話で出てこない目標は設定されてもきついんだろうなってのは、多分すごいありますし、なので僕はなるべく目標を測定可能な状態でどう受けるかっていうのはやっぱりすごい考えてて、もうそこが全てですかね。
籔:なるほど。確かにそうするとウィークリーの進捗確認とかマンスリーの進捗確認を結構形骸化せずやりやすくなりますもんね。
石倉:そうですね。僕あの、数字的に活躍している人と、数字的にはそんなに活躍数がまあまあ中程度の人で、でもこの人はすごい上司と仲良くて何かバイブスが合うから評価がほぼ一緒んなっちゃう、みたいのってあり得るじゃないですか。これは避けたいなというのは結構いつも思っていて、そっちの方が成果を出す人から見ると、優しくない会社だなと思うんですよ。
結局自分のミッションを達成したかしないか、じゃないところで何が点数かわからず評価されて決まるっていう変数のブラックボックスがでかい方が嫌じゃないですか。それをどう減らすかとかはすごく考えてます。
籔:うんうん。やっぱりマネージャーとかその管理職側の、意識みたいなものも昔と比べると変えないといけないなと思っていて。それこそ目標設定と、そこの進捗管理と、そこにおける対話みたいなところを密にやっていかないと、後ほど修正が難しかったりするなと思ってて、この辺はマネージャーも結構意識しないといけないなってフルリモートにしてからすごい思いますね。
石倉:そうですよね。難しいところだなあと思うんですよね。だからなんか一番いいのは目標設定がすごくうまくいって、事業で大事な KPIとかOKRで定めているKRってのがあって、これを達成するためにずっとミーティングしてたら、個人の目標もリンクして達成してたっていう状態をうまく作れたら一番いいと思うんですね。
籔:なるほど。ここ一つやっぱりポイントとしてはその測定可能な目標設定みたいなものと、あるアクションした結果めちゃくちゃ遠い指標とかだと、どんだけやっても、その結果で指標は動かないみたいなことも結構あるのでそこら辺はコントローラブルな指標を手前に置いてみたりとか、何かそういう工夫は結構必要そうですよ。
石倉:そうですね。だから測定科目別に数字にならなくても、これができた、できないというのは置けるよなっていうのと、僕は結構「結果」と「成果」っていう言葉を分けて一応僕の中で考えていて、結果は事実なんですよ。成果はその結果をどう評価するかっていうものだなと思ってて、基本は結果で見る。
解釈を入れない。できたか、できないか。3本企画するとしたら、3本企画したかしないか、ぐらいシンプルにしないと、結構マネージャーが評価するのがきついんじゃないかなと思います。
籔:今の結果と成果を分ける考え方、非常にわかりやすいなと思いました。ただ一方で、いろんな外部環境の変化とかいろんな状況を受けて結果が出ないことってあると思っていて、その場合は中間の成果を評価することって割と大事なのかなと思ってるんですけど、成果っていうのはどういうものが該当する感じなんですかね。
石倉:成果って結局はやったことに対して、それがすごいことなのか、そうじゃないのかっていう「解釈が入ったもの」っていう感覚なんです。例えば、ユーザーを3000人取りたいですとなったときに、3000人行ったか行かないかっていう事実じゃないですか、それが良かったか良くないかみたいなのが、解釈が入ったものが成果だと思う、というぐらいの認識で、さっき言ってたような、結果の中にも外部要因に左右されるものと、その手前にある自分のアクションでコントロールできるものがあったとしたときに、僕は二つを両方置いて、あとはもうパーセンテージの比率の問題だと思うんですよ。
例えばジュニアの子だったら、自分ができる方に8置いて、外部要因が関係するところに2を置くけど、マネージャーだったら逆だよねとか。
籔:なるほど、なるほど。わかりやすいですね。
石倉:役職者の上に行けば行くほど、外部環境も含めて何とかせいやがお前の仕事だみたいな感じかなと僕は思ってますけどね。
籔:逆に言うとその成果っていうのは、結果をもとにその結果が、事業に対してどういうインパクトを与えたのかっていうものを考えて次の戦略とかに生かされるものが成果になる感じなんですかね。
石倉:そうですね。僕らの中で成果として良い成果だったな、っていうような判断が入るものっていう感じですかね。
籔:なるほど。成果自体は評価に対してはそんなに何か大きくインパクトを与えるわけじゃないって感じなんですか。
石倉:評価の中にも評価をしてお給料を決めたりとか、等級を決めたりとかっていうのがあると思うんすよ。ここに関してはそれ入れてなくて、ただ、アサインメントしたりとか、ポジションを新しく登用したりとかあったときに、結局人が判断するわけじゃないですか。そういうときにそういうのが入ってくるんだろうなっていう。
籔:わかりやすいですねそれは。
石倉:だからそのポジションが変わるとか、アサインされるとかっていうことと、その人の評価が給与がどうなるかっていうのは分けて考えてます。
籔:なるほどなるほど。
石倉:やっぱり嫌じゃないですか、給与を上げるためにすごい僕が好きそうなことばっかり言われたりとか。面倒くさいじゃないですか。本当に事業に向き合ってくれと思います。
MOSHのフルリモート推進の中でCEO籔が感じた一番の変化
籔:なるほど。すいません、MOSHがなぜオンラインで働ける環境の構築を目指したかっていうところが抜けてたので改めてちょっと補足すると、まず最近プロダクトを中心に成長させている会社でエンジニアとかビジネスも含めて地方に住まれてる方っていうのも結構増えてきていて。
あとは弊社で言うと取締役の村井とかも関西の方で働いているっていうのもあって、個人の状況とか本人のWillみたいなところの中で場所は自由に選択できる方が純粋にいいよねっと思ったことと、僕個人で言うと創業者とかってやっぱりずっと東京にいないといけないよねというのが暗黙の了解としてあると思っていたんですが、そうすると、いろいろインプットとのところでしづらかったりとか、結果的に経営者もメンバーも結構いろいろ働き方の制限ってやっぱり出てくるなと思うんです。
そういうものに対してあまり制約を与えない形での働き方に改めてスタンスを切ることの重要性が増してるなと思ったので、今回こういう決断に至ったっていうのが背景にあります。
石倉:なるほど、創業メンバーというかボードの中で元々だから離れた場所で働く人がいたっていうのもあるのは大きいですよね。慣れてるというか。
籔:そうですね。状況に応じてもちろん東京にどうしても来ないといけない、とかいうケースはなくはないので、そこはそこでちゃんとサポートしていけばできそうだなと思ったのも背景として大きいです。
石倉:今はコロナがあるんで家でみんな働いてますけど、僕はリモートで働くって究極的にはみんながどこにいてもいいって話なので、その働き方が実現できるようになると、オフィスに集まって働くこともできるしみんなが離れててもいいし、っていうのが両方が選べてる状態になってるっていうのは会社としてすごく強いと思うんですよね。
籔:そうですよね。ありがとうございます。そこで今ちょうど「フレキシブルワーク」という制度を作っていて、その取り組みの中で一番やっぱり大きい変化は、さっき言っていただいた価値観などのアップデートがあって、「Slack=執務エリア」というふうに捉えたときに、何がどうあるべきなんだっけとか、本来どうだったんだっけみたいなところで、結構コミュニケーションを変えていったことが一番変化としては僕は大きかったなと思っております。
今後これを強化していったりとか、そこの前段階の、全社的なモメンタムをどう作っていくかみたいなところの解は結構模索してる感じではあるので、そこは引き続き課題として捉えつつ、取り組んでいけるといいなと思ってます。
石倉:はい、ぜひぜひ。あと僕はSlackの1週間の個人あたりのポスト数を、なんかどこまで上げるかみたいな話なのかなと思ったりします。この辺をKPIにしてボードメンバーからやってくとか、そういう形で意識改革できるとよさそうな気がします。
なんかやっぱり仕事の話をすごいしてると結果的に雑談も勝手に増えてるんですよね。なのでそれを(指標に)置いてみると変わるかもしれないと思ったりしますね。
籔:なるほど、石倉さん今日はありがとうございました!
改めてMOSHではフルリモートか、オフィス出社の働き方を選べるフレキシブルワークも含めていろいろと制度を整備している最中です。そういった柔軟な働き方や、MOSHミッションにご興味ある方など、ぜひぜひご連絡いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
