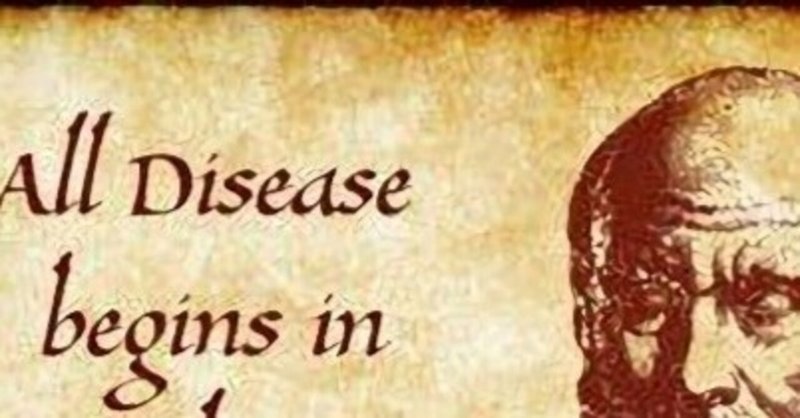
続・アトピー対策備忘録18: 体質改善16 ミトコンドリア・抗酸化物質
最近また新たにサプリメントとしてαリポ酸とグルタチオンを飲み始めたが大変良く効いている。双方共に強力な抗酸化物質であるが、体内のミトコンドリアにとって必要な栄養素である点も共通している。
同物同治という訳でもないが、アトピー性皮膚炎やアレルギー性疾患では体内の酸化ストレスが高まっている状態にあり、ミトコンドリアに必要な栄養素を優先して摂取する事は治療として理に適ったものと思う。
以前も触れたが活性酸素の過剰産生は体内での組織障害性物質や自己分解性酵素の増加を招き、それが末梢循環障害による蓄積と相まって表皮障害を発症させる。そしてその表皮症状の機序は褥瘡とも似通っていた。
今回はαリポ酸とグルタチオンを用いたが、結局の所抗酸化物質や抗炎症物質を充分に摂取・産生出来ればアトピーの表皮症状の治癒は可能であり、昨今偶に耳にする水素水等でも治療は可能との報告もある(ただ信頼性の有る機器は費用が十数万掛かる模様)。
また機序が類似しているため理屈としては納得のいく事だが、これが褥瘡治療としても効果があるらしい。
上部リンクは水素の治療効果に関する研究。因みに腸内にて産生される水素では治癒に充分な量は賄えない模様。
そもそも軽症ならばサウナ等HSP療法でも治療は可能であり、治り難い様でいて、要点さえ押さえれば表皮症状の治療法は多様に有るというのがアトピー性皮膚炎やアレルギー性疾患の実態の様だ。
…勿論根本的な胃腸障害や新型栄養失調・免疫機能の改善も、併せて行う事が最も望ましい治療ではある。
抗酸化物質は多様な疾患と関わりが有り、単純に疲労や寝不足による体調不良、二日酔いや表皮の色素沈着にまでその摂取により改善が見込める。
何より免疫機能向上の効果は直接的にアトピー性皮膚炎患者の症状の改善に繋がり、また不必要な頭痛薬や抗生剤の使用を控え間接的に腸内環境を改善する事にもなる。
αリポ酸やグルタチオン、抗酸化物質の効果については下部リンクも参考のこと。
酸化ストレスがストレス・タンパク質とも呼ばれるHSP産生を促す点は当然でありつつも中々に興味深いが、アレルギー性疾患により高い酸化ストレスが常態化した患者においてはそれも症状の治癒には繋がらないのだろう。
HSP産生と活性酸素の間にもミトコンドリアの活動を介した人体の恒常性維持機能における深い関係があると言える(同時に酸化ストレスよりも直接的に危険な熱ストレスにより警戒している事も理解出来る)。
個人的にも思っていた以上の炎症鎮静効果が得られた事もあり、引き続きサプリの摂取を行っていきたい。
・追記
活性酸素の除去がアトピー性皮膚炎の表皮症状の改善に繋がる事は分かったが、そもそもアトピー性皮膚炎において活性酸素はどういった経緯で血液中に増加するのだろうか。
重症者であれば腸内から腸管組織内に侵襲したカンジダ菌等の真菌による産生と考えられる(これは症状の軽重の違いこそあれ、敗血症にて血液中に活性酸素が増加する理由と同様である)。
また軽症者でも軽度ながら同じ理由で増加し得るだろうし、そもそもアトピー性皮膚炎患者は多量の活性酸素を産生する能力を有する好酸球が増多している状況にあり、その点からも活性酸素の増大は引き起こされる。
では腸管カンジダ菌症を治療すればそれだけで良いかといえばそうでもなく、長く患ったカンジダ菌症により侵襲された腸管内壁の修復や、カンジダ菌の産生する有機酸により低下したミトコンドリア機能を回復させる必要が有る(グルタチオンとαリポ酸の摂取もこの理由から行う)。
そもそも活性酸素を除去するSOD酵素はミトコンドリアにて産生される。アトピー性皮膚炎患者はミトコンドリアの機能低下によるSOD酵素の産生低下と、カンジダ菌による直接的な活性酸素の産生(通性嫌気性菌であるため)、更に体内のカンジダ菌や表皮にて繁殖した常在真菌に対する免疫応答として好酸球の増多、これら三つの理由により体内の活性酸素が通常より増加していたものと思われる。アトピー性皮膚炎の重症化に腸管カンジダ菌症が深く関わる理由もまたこの事によるのだろう。
抗炎症物質と抗酸化物質によりアトピー性皮膚炎の表皮症状は治癒可能である。しかしながら根本的な治療として腸内細菌叢のディスバイオシス改善とミトコンドリアの機能回復を行うべき理由は、将にこの活性酸素を巡るミトコンドリアの機能と腸管カンジダ菌症の関係にあると言える。
上述の理由から腸内細菌叢のディスバイオシスの治療とミトコンドリアの機能回復をせずに表皮症状のみを治療する行為はやはり対症療法に過ぎず、本質的にはステロイド治療と変わらず、ステロイド治療が再発を防ぐ根本的治療たり得ない理由もまた同様であろう。
因みにこういった医療を機能性医学と呼称するそうである。
…ただ一度免疫記憶を形成し真菌アレルギーやその他アレルギーを発症してしまったものを、果たしてどの程度治療可能なのかについてはやや疑問が残る。
腸内環境の改善や免疫機能の向上により真菌増殖を抑え、除去療法とヒスタミン・コントロールや抗酸化物質の摂取・産生、ミトコンドリアの機能回復により皮膚症状の発症は限りなく抑制されるだろう。
しかしながら根本的に一度発症したアレルギーや獲得してしまった免疫記憶、さらに免疫機能の発達不良については起きた後からでは如何ともし難い。
それ故予防医療やそれらを包括する医療政策、そしてその是正が極めて重要となる。事こうした状況の根本的な是正においては最早個々の治療や医学の問題には収まらず、その解決に政策としての見直しを必要とするものだろう(個別に対応を行うと酷く効率を損なう事となり、単純に解決が遠のく)。
少なくとも現状ではこの辺りが「治療」としての限界なのかもしれない。今後の研究の進展に期待する他無い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
