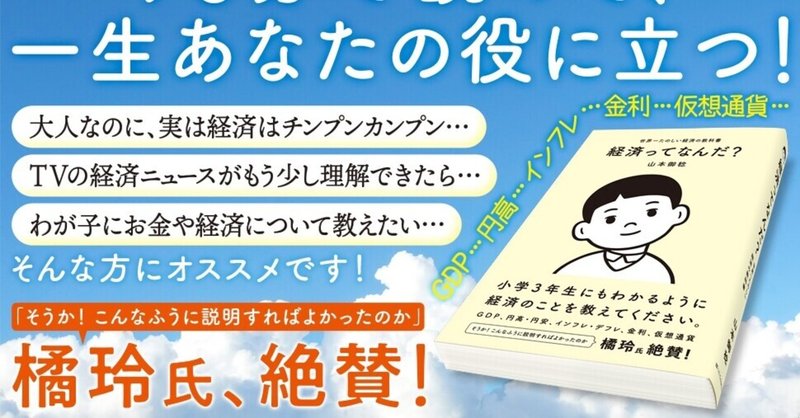
おじいちゃんが教える世界一たのしい経済の教科書7
第5章 日本銀行ってなんだ?
◉日本銀行は銀行の親分
銀行のための銀行とは……。
あ、その前に! 一つ質問してもいい? あのさ、おじいちゃん。そもそもおじいちゃんって大学の先生だったのに、どうしてそんなに銀行に詳しいの?
おじいちゃんがどうして銀行に詳しいかって? 聞いて驚くんじゃないよ。領太、おじいちゃんはその昔……銀行強盗だったんだ。
は?
あれ? 信じてない?
うん、それで?
それで?って……。もっと驚くでしょ、普通。
驚かないよ、だっておじいちゃんは優しいもん。人が困るようなことは絶対しないと思う。
りょ、領太……。泣かせてくれるねぇ……。
それで? 本当の答えは?
実は、大学の先生になる前、うんと若い頃、銀行で働いていたんだよ。
え? マジ?
マジマジ。大マジ。
それで銀行でどんな仕事してたの?
融資とか為替をやっていたんだ。そうだ、一つ面白い話がある。ある時、大きなリュックを重たそうに背負ってきたお客さんがいてね。
もしかして、その中身って……。
そう! リュックの中身は全部お金! 1億円が入っていてびっくりしたよ。
い、1億円? そんなの持って歩いてる人いるの? どれくらい重いんだろう。想像もつかないや。
1万円札が1万枚だよ。重さにすると10キロ。高さが40センチ、幅が30センチで、奥行が10センチほどだよ。とにかく重かったのを覚えているよ。
その1億円は銀行の金庫に入れるんでしょ? そんなお金持ちがたくさん来たら、銀行の金庫はすぐにいっぱいになっちゃうじゃん。
たしかに。昔は、1億円とか10億円とかを金庫に入れておくなんてことがあったんだけど、実際には、現金は今、銀行にはあまり置かないんだよ。
じゃあ、どこに置いとくの?
それも日本銀行さ。
日本銀行って、さっき言ってたお札を作っている銀行?
そうだよ。日本にたくさんの銀行があるけど、その親分みたいな存在が日本銀行なんだ。おじいちゃんも、その1億円を日本銀行に持って行ったんだよ。まぁ、昔の話はさておき、日本銀行には三つの役割があるということを話しておこう。
◉日本銀行の役割その① お札を刷る
お札の正式名称は「日本銀行券」というのだよ。
日本銀行券? なんだかボードゲームのチケットみたいだね。
たしかに、そうとも考えられるが、勝手にコピーしたり似たものを刷ったりしたら逮捕されちゃうんだぞ。
逮捕? お札をコピーするのは犯罪ってこと?
あぁ、そうさ。「通貨偽造罪」という重い罪で、コピー機によっては、コピーした瞬間に警報器が鳴って警察が駆けつけることもあるんだ。
こわっ。でもさ、おばあちゃんが見てる時代劇に出てくるお金は、お札じゃなくて小判とか銀色の小銭みたいなお金だよ。コピーしただけで逮捕されちゃうなら、簡単にコピーできちゃう紙のお金じゃなくて、小判とかにすればいいのに。
なるほど。小判なら簡単にマネすることはできないかもしれないね。でも、実は紙のお金も簡単にマネできない技術によって作られているんだよ。
どういうこと?
手に取って見るだけではわからない「透かし」という技術が使われているんだ。
スカシ?
そう。光に当てることで現れる絵や模様のことだよ。紙の厚さを部分的に薄くしたり厚くしたりして、シャープで立体感のある絵や模様を表現する技術。そして、透かしの部分はどんなに高性能なコピー機でコピーしても写すことはできないんだ。それによって本物かどうかすぐに見分けられるんだよ。海外のお札にも透かしの技術は使われているけど、伝統技術に優れた日本の透かしは、世界でもトップクラスらしい。
そうなんだ。お札ってただの紙でできてるわけじゃないんだね。
うんうん、そうだよ。たくさんの人が知恵を出し合って作ってきたんだ。ちなみに、日本銀行が初めて透かしの入ったお札を刷ったのは、1885年に発行された十円券。
十円券? そんなのあったの?
あぁ、当時は五円券、一円券なんてのもあって、一円より小さい額の十銭券や五銭券なんてものもあったんだ。お札を刷る技術は時代と共に改良され続け、明治時代には紙の強度を増すために「こんにゃく粉」を混ぜてお札を作ったなんてこともあったそうだ。ただ、ネズミがお札を食べてしまう事件があり、こんにゃく粉は使われなくなったけどね。
へぇ~。昔の人はたくさん苦労してお札を作ってきたんだね。
ここで領太に質問。1882年に業務がスタートした日本銀行だが、お金を刷る役割を担うようになったのはなぜでしょう?
え? なぜ日本銀行がお金を刷るようになったかって? そりゃー、銀行のボスみたいな存在だから……じゃなくて?
あながち間違いではないが、お金を刷る役割となったきっかけは……戦争さ。
戦争?
そうなんだ。1877年に西南戦争という戦いが日本で起きたんだよ。西郷隆盛って知ってるかい? 薩摩藩の武士で、薩摩のリーダーともいえる人。今で言う政治家ってところかな。薩摩のリーダーである西郷隆盛と明治政府の間で戦いが起き、政府はその戦争に勝つためにお金を刷りたい放題刷ったんだ。政府ってわかるかい? 国をまとめる権限を持つ人々の集団や場所のことだよ。
え? そんな偉そうな集団が好きなだけお金を刷ったってこと? それって犯罪じゃん!
そう。今なら重い罪になるよね。でも当時はまだそういったルールがなかったんだ。だから、なんとかして戦争に勝つためにお金をたくさん刷ったわけ。でもそのあと、そんなことが起きないよう日本銀行券(すなわちお札)をいつ発行するかは日本銀行が決定し、何枚刷ったかもしっかり管理され、勝手に刷ったり持ち出したりすることができないような仕組みを作ったんだよ。
そっか。そんな昔にきちんとした決めごとができたんだね。じゃあ、日本銀行の二つ目の役割もお札に関わること?
◉日本銀行の役割その② 銀行のための銀行
二つ目の役割は、日本銀行は「銀行のための銀行」であるということだよ。
銀行のための銀行? 銀行が銀行の預金口座を作る……とか?
おっ! 領太はするどいね。さっき、おじいちゃんが話したように、民間の銀行に置ききれなくなったお金を日本銀行に預けるんだ。
ミンカン?……民間の銀行って?
民間とは、モノやサービスなどを提供してお金を得る組織や会社のこと。例えば、お巡りさんに道を聞いてもお金を取られないよね? それは、お巡りさんは民間の仕事ではなく、「国や地方公共団体の職員」として働いている人だからなんだ。そういう人を「公務員」と呼ぶんだけど、聞いたことあるかい?
ある! 学校の先生は公務員だってママが言ってた。
その通り。公立の学校の先生は、塾や習い事の講師と違って、教育サービスを提供してお金を得ている職業ではないからね。ここまでわかったかい?
うん、お金を預かったり貸したりするサービスを提供している民間の銀行の金庫がいっぱいになっちゃったら、日本銀行にお金を預けるってことだよね? そもそも日本銀行は民間の銀行じゃないってこと?
そう。日本銀行は民間の銀行ではないんだ。だから、領太や領太のパパやママのように、一般の人が日本銀行にお金を預けることはできないんだよ。日本銀行の三つ目の役割でも話すけど、日本銀行はあくまでも「銀行のための銀行」であって、日本銀行に民間の銀行のお金を預ける時は、「当座預金」という口座に預けることになってるのさ。
トウザヨキン?
当座預金とは、利子がつかない口座のことだよ。
利子って、お金を預けると追加して多くもらえて、お金を借りると追加して多く返さなきゃいけないお金のことだったよね。
ブラボー! よく覚えてたね領太。民間の銀行が日本銀行に預けたお金は利子がつかないから、民間の銀行が「持って帰ります」と言えば、いつでも元の銀行に戻すことができるんだ。
なるほど。だから、銀行のための銀行なんだね。
◉日本銀行の役割その③ 政府のための銀行
そして最後の三つ目は、「政府のための銀行」という役割だよ。
さっき、おじいちゃんが話していたことだね。日本銀行は民間の銀行じゃないって話。
あぁ、そうだよ。日本銀行はね、銀行のための銀行でもあり、政府が持っているお金を預かる銀行でもあるんだ。
政府が持っているお金って? 例えばどんなお金?
いわゆる一つの「税金」ってやつ。国民の誰もが国とか地方とかに払わなきゃいけないお金。
ゼイキン?
税金とは、国や地方公共団体が、必要な経費をまかなうために国民から集めるお金のことだよ。消費税とか、所得税とか、いろいろな種類の税金があるんだ。
集めて何に使うの?
例えば、道路や橋、港、ダム、河川の整備などの公共事業。あとは、学校の先生やお巡りさんなど公務員の人たちのお給料としても税金を使うわけ。年金や医療費などの社会保障も税金の大きな使い道だね。そんな国民全員で使うお金を、政府が日本銀行に口座を開いて預けるんだよ。
すっごっ! 日本銀行すっごっ! どんだけ大きな金庫があるんだろう。
ほんとだね。ヤバいね。
おじいちゃん、「ヤバい」とか若者言葉使うのやめなってば。ぜんぜん似合わないよ。
そんなこと言うなよぉ、おじいちゃんの見た目はこんなんだけど、心は領太と同じくらい若いんだ。おじいちゃんの魂は、ピッチピチなんだぞ。
わかったわかった。おまけに、日本銀行の三つの役割もよくわかったよ。
それは何よりだ。領太は本当に教え甲斐があるよ。おまけの話だけど、日本銀行は今話した三つの大事な役割を果たしながら、景気についても考えているんだよ。
ケーキ? イチゴケーキ? チーズケーキ? チョコレートケーキ?
残念ながらそのケーキじゃなくて、お金に関わる景気。景気とは、「世の中の活気」みたいなこと。ま、景気についてはまた明日話すとしよう。それより領太、例のあれ、どうだい?
例のあれ? あ! もしかしてお風呂!
ビンゴ! 風呂に入って一杯ひっかけようじゃないか。
いいね! そんでもってお風呂上がりには……?
アイスキャンデー!
おじいちゃん、「キャンデー」じゃなくて「キャンディー」ね。さっきまで若者言葉を使ってたのに、急におじいちゃんに戻っちゃったじゃん。
……。
おじいちゃん? あれ? おじいちゃんどこ? 傷ついたからっていちいち消えないでよ!
次回、第6章 「景気ってなんだ?」へ続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
