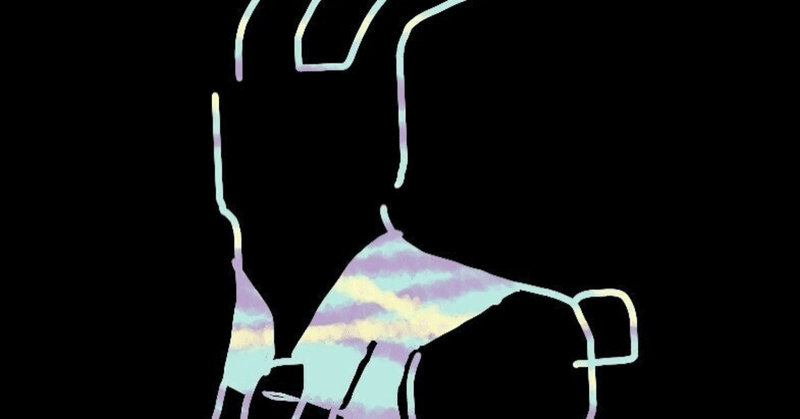
プラスアルファの努力から得られる”何か”
この10月の英語学習には隙がない。
特に最近は文法書を使った英文法の復習、動画教材を使った発音の復習、単語帳2冊を使った語彙学習。
学習時間の間にそれらを何度も何度もローテーションで回している。
それぞれを別々にこなさないのは
それぞれの知識を不自然な形で分けてしまわないようにするためだ。
30分か1時間ごとに自分が行う学習内容を変えていくことによってそれぞれの知識同士の繋がりも見え、応用も効いて来る。
そんな感じで毎日自分のノルマをこなしていくうちにその瞬間瞬間の自分が具体的にどの知識を復習すれば良いのかも分かるようになってきた。
また、最低あと何回その内容に触れれば本当の意味でその知識を自分のものに出来るのかなどといった嗅覚が身についてきたようにも思える。
「今日明日中に最低あと2回復習をすれば
この知識は自分のものに出来る!」
そう思いながら実際にその回数をこなしてみると予想通りの感覚を得られ、どんどん学習自体も進んでいく。
しかし最近はその努力に多少拍車がかかり
予想の回数にプラスして復習の回数をこなすようにもなった。
「あと2回の復習でこの知識が定着するのであれば
3回目、4回目の後にはどうなるのだろう」
「より質の高い土台が出来るのではないか」
日々学習していくうちにいつの間にか
そんな余分な向上心を持つようになった。
いわゆるプラスアルファの努力というやつだ。
この感覚は筋トレでも似たようなものがある。
僕は毎回の筋トレ、
15回を1セットとみなしそれぞれ3セットずつ行っている。
それぞれの間には1分半のインターバルを挟む。
トレーニング後半になるにつれて疲労が溜まり
筋肉も自分の言うことをあまり聞いてくれなくなる。
長い時間休憩していてはトレーニングの効果自体も薄れてしまうのでトレーニング中にはその疲労は拭えない。
僕はダンベルやバーベルなどよくある典型的なトレーニングは行っていない。
現時点ではまだそのレベルに達しておらず
間接的に重りを動かすマシンを使ってトレーニングをずっと行っている。
名前を挙げるとチェストプレスやアブドミナルなどがそれにあたる。
これらは、毎回一度持ち上げた重りを下ろす際
一瞬でも重りが床に着いてしまえば重りの負荷を逃してしまうことになり十分な効果を得ることが出来ない。
なのでもし力加減を間違えて1番下に重りをつけてしまった場合にはその回数は無効にしてカウントしないようにしている。
重りを持ち上げる際の純粋な負担に加えて
1セット最初から最後までその負荷をコントロールしないといけないわけだ。
しかし筋トレを続けていく以上
この不便さからは一生解放されることはないのだろう。
先ほど僕は毎セット15回を目安にトレーニングを行っていると言ったが、今説明したように
マシンでのトレーニング特有のミスをカウントしてはいないのでいつも実質15回以上はしていることになる。
そしてそれに加えて
ミスが起こらなかった場合にもなぜか
プラスアルファの1回2回が毎セット加算されていたりする。
1セットただの15回ではなく自分が満足のいく15回を。
1セットただの15回ではなく余分は1〜2回を加えた17〜8回を。
いつの日かそんな気持ちが芽生えるようになった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
