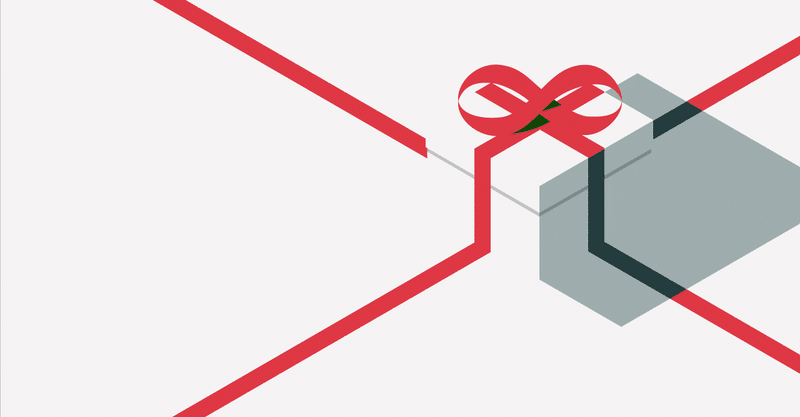
「贈与」としてのマーケティング(part1)
150年ぶりくらいのnoteです。
最近読んだこの本からもやもやしていたことを言葉にしてみたくなったので、したためております。
読んだのは哲学者の近内悠太さんの著書「世界は贈与でできている」です。
まず最初に質問してみます。
「一人の消費者として、あなたには信頼できる会社が何社ありますか?」
「その会社が炎上していたり、経営的に厳しくなっていたとしたら、何とかして助けたいと素直に思える企業はどれだけありますか?」
・・・
たぶんほとんど無いんじゃないでしょうか…?
あったとしても自分が働いている会社くらいですよね。
そんなポイズンな世の中に言いたいことを言ってみたいと思います。
ではまいります。
1.「贈与」とは何か
フランスの社会学・文化人類学者のマルセル・モースが唱えた「贈与論」というものがあります。
儀式や婚姻といった古代の社会活動にみられる「贈る」「受け取る」「返す」ことが、現代においても社会活動をなすための日々の営みに埋め込まれた無視できないメカニズムだという主張です。
僕らは何かを受け取ると、そのままではどこか落ち着かない気になります。その気持ちを「お礼に…」と様々なカタチでお返ししようとする。差出人に対して何らかの理由でお返しができないときは「自分はこんなにも与えられてしまった」。そんな気持ちが、別の誰かに対して贈ることを駆り立てる。
そして、受け取ってもらった差出人は、相手が受け取ってくれたことを、こちらと何らかの関係性・つながりを持つことを受け入れてくれたと感じ、うれしく感じる。
こうして人から人へと贈与がぐるぐると繰り返される。
それが、利得や効率性、合理性を重視しがちな現代の資本主義経済において居場所がない「お金では買えないもの」を生みだしていく。
「贈る」というものをそういう角度から捉えたものです。
「贈与」をかんたんに言ってしまえば
『「贈与」とは、「贈与」を生み出すもの』
とも言えます。
年賀状、バレンタインといったものもそういう意味では、「贈る」「受け取る」「返す」という贈与的な慣習と言えますし、こうしたやり取りは毎年続いてますよね。
贈与という活動は、
僕たちの生活に深く根付いているわけですね。
2.「贈与」の不合理性
ですが、こうした年賀状やバレンタイン、結婚式のご祝儀といった「贈与的な慣習」に、私たちは一種のわずらわしさを感じる時があります。
そのわずらわしさを不便なものとみなし、
排除したりテクノロジーで置き換えたりしようとしすることもあります。
哲学者の近内悠太さんは著書「世界は贈与でできている」(この本)の中で、こう述べています。
贈与にはある種の「過剰さ」「冗長さ」が含まれています。なぜかというと、ある行為から合理性を差し引いたときそこに残るものに対して、僕らは「これはわたし宛の贈与なのではないか」と感じるからです。
たとえば、他者からの「敬意」や「礼節」も、そのようにして僕らに伝わります。帽子をかぶっている男性は、誰かと会ったときには脱帽するのが「マナー」です。それが何ら合理性を持たないからこそ、こちらへ向けた敬意の表れだと気づくのです。
その行為にみられるわずらわしいともいえる不合理な部分にこそ「自分に向けた贈り物」として認知される。
つまり
「贈与とは不合理から生まれるもの」
であり、そういうものなんだということですね。
もし、会社の人からのバレンタインの義理チョコがECショップからそのまま自分の自宅に送られてきたらどうでしょうか。チョコがその人から「バレンタインの日に届いた」だけで、「贈られた」気分はしないと思います。
「丁寧に包装して、手渡しする」。
そういった一見無駄でわずらわしいと思えるこの不合理な行為に「意味」が生まれ、その行為自体が「贈り物」であるとも解釈できるわけです。
贈られたモノそのものが特別なわけではなく、「贈る」ことでモノに特別な意味が付与される。だからこそ、その人にとって特別で価値のある贈り物になるわけです。
仕事でもそうですよね。
100点ではなくて120点の仕事をしようとする。
その20点という頼まれてもいなかった+αは、ある意味不合理ともとれる。
でも、その20点にこそ意味が生まれ、それを依頼者は特別な仕事をしてもらえたと認識できる。
じゃあ次は、自分が130点、140点にして仕事をして返そう。
そう思えるわけです。
3.「薦める」という贈与
僕は普段は企業のマーケティング活動の支援を行っていますが、
こうした贈与論の考え方の有効性を実務を通して実感することがあります。
昨今、「NPS経営」を行う企業が徐々に増えてきています。
<NPS(Net Promoter Score)とは>
顧客ロイヤルティ(企業やブランドに対する愛着・信頼の度合い)を数値化する一つの指標。「当社(の製品、サービス)を親しいご友人、ご家族におすすめする可能性はどのくらいありますか?」というアンケートの質問に11段階で回答してもらい、それをスコア化したものです。
これを「(他者)推奨意向」と呼ぶこともあります。
なぜNPSの話をしたのかというと、
ここからは僕の主張ですが、こういったNPSに代表される
「他の人に薦める」という行為も、一種の「贈与」ではないか。
と考えています。
他の人に薦めるという行為は、相手からの見返りを求めているわけではないし、多少なりとも自分の時間を削ってでも(無駄をつくってでも)そうしようとしている。そういう意味ではこれも「贈与」ですよね。
「NPSが高い」とは、こういう状況のことを指し「贈与性の高い行為」なのです。
「顧客満足度」や「継続購入意向」といったこれまでよく測定されてきた指標とはそういう意味で大きく異なる性質をもつと言えます。
4. 顧客への贈与
『「贈与」は「贈与」を生み出す』と前述しました。
もしそうであれば、「他の人に薦める」という贈与性の高い行動に駆り出された顧客もまた、企業からモノやサービスと通して贈与を受け取っていたはずです。
「自分だけがひとり占めしていていいのか?誰かに教えてあげなければ」。
どこか無意識的な健全な負債感を感じ、思わず「語ってしまう」ようなそんな贈与をです。
昨今のマーケティングにおいて重視されている、
良いブランドや顧客ロイヤリティが高い状態を成立させるためには、
ある種の不合理が伴った「贈与性のある価値提供」が不可欠である。
僕はそんな風に考えています。
5. 「贈与」と「交換」
インフルエンサーを起用したマーケティングは「贈与」と言えるでしょうか?
インフルエンサーが企業から見返りや報酬をもらい、企業はインフルエンサーを介してものを買ってもらおうとすることが動機になっている時点で、それは「贈与」ではなく、対をなす意味の「交換」にあたります。
互いの経済的な利益を最大化することを目的においたビジネスです。
僕らが注意しなければならないのは「打算的な贈与」であってはならないという点です。「いくら儲かるのか?」と打算的に考えていることが、受け手に見え隠れしている時点で、それは「贈与」ではなくなってしまいます。
自社の製品やサービスを売りつけるために、自社の都合の良い様に顧客をコントロールしようとすることもそうですね。(かんぽ生命の不正販売問題なんかはその最たる例だと思います)
そういった打算的な売り方は、顧客からは「自分は利用されようとしている・手段としてしか見られていない」と見透かされてしまいます。
今や顧客は、企業のそうした態度に「そういうものだ」と半ばあきらめすら感じ、企業と顧客の信頼関係はじわじわと崩れていっています。
信頼のある関係性とは「自分に何かあった時は、相手は犠牲を払ってでも助けてくれるし、逆の立場の時は自分もそうするつもりだ」と互いにそう思える相互扶助の状態のことを言うのだと思います。
近内悠太さんは、同著書でこう述べています。
問題は、僕らは、自分のことを手段として扱おうとして近づいてくる人を信頼することができないことです。親切にされればされるほど、何か裏がある、打算があるはずだと感じてしまう。
そして、彼らの言動や行為には「お前の代わりは他にいくらでもいる」というメッセージが透けて見えます。
なぜなら、この〈私〉はあくまでも利益という目的に対する手段でしかないからです。だから信頼できないのです。つまり、贈与が無くなった世界(交換が支配的な社会)には、信頼関係が存在しない。
裏を返せば、信頼は贈与の中からしか生じないということです。
6.「贈与する」ことの難しさ
今の資本主義経済では、この「交換の論理」は強く根付いています。
でも、それが良しとされシステムとして埋め込まれているからこそ経済が回り、今の便利な世の中があります。
我々が取り組んでいる「マーケティング」というものは、そこに立脚しているのですから、「交換の論理」がはたらくのは当たり前なわけです。
一方で、昨今のマーケティングトレンドでは「SDGs」「ウェルビーイング」「ブランドパーパス」「カスタマーサクセス」「顧客ロイヤリティ」といった、合理性・コスパといった「交換の論理」による価値基準だけでは判断できない概念の存在が大きくなってきています。
僕らは今、「交換の論理」と「贈与の論理」という大きなパラダイムのあいだで揺れ動いているわけですね。だからこそ企業の意思決定はより複雑で一筋縄ではいかない状態なんです。
大きな企業であるほど、関わる人が多いほど、何かをやろうにも集団の意志を統一するために説明責任が伴います。一人なら一人で好きなように決めればいいのだが集団ではそうはいかない。
集団で意思決定をするということは、これまで皆の共通の価値基準であった「交換の論理(これは割に合うのか?)」が重視されやすいわけです。
そして長い意思決定プロセスの間で、不合理な「贈与性」はそぎ落とされ、合理性だけが残ってしまう。
これが、今の資本主義社会の中で、(僕らが取り組もうとしている)贈与としてのマーケティングを行う上での、根本的な経済システムがもたらした難しさなんだと思います。
ここまでいろんな話をしてきました。
企業として贈与性の高い「売らない」マーケティングを行うことの難しさに触れてきたわけですが、
実際に贈与性を取り入れ、合理性と不合理性を共存させた事業のケースもあります。
僕らはそこからヒントを得ることができるはずです。
ですが、長くなってきたので続きはまたpart2にでも書きたいと思います。
もし続きが気になるという方は、この本を読むことをおすすめします。
マッキンゼー/VC出身の影山知明さんという方が書いた本です。
マーケティングに携わる人間として必ず為になる一冊だと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
