
BUMP OF CHICKENが歌う「強さ」と「強がり」の境界線
人の強さってなんだろう?
頭の隅にずっとありながら答えが出なかった問いだ。誰かの言葉で簡単に傷ついたり、誰かをむやみに傷つけたりしない強さを持った人間になりたかった。
なのに、そうあろうとすればするほど本当の自分を置き去りにしているように思えた。強さの意味を履き違えていた。
BUMP OF CHICKENの音楽と出会ったのは、そんな自分を持て余していた10代と20代の狭間だった。
うだる暑さの2001年夏。地元の小さなライブハウス。
ステージの中央に立つ青年は、ひょろっこい体と腕を携え、見た目そのままの繊細さを覆い隠すかのように声を張り上げて歌っていた。あれほどの熱狂の中でも哀愁の色を纏うボーカリストの姿が忘れられない。
彼らが歌うのはどこか既視感がある人間の憂いや孤独だった。
救われた気がした。でも心配にもなった。あの歌っているひと、いつか壊れてしまうんじゃないかと思った。
強がりの音楽と変化
あのライブハウスの光景をよく思い出すようになったのは、2018年にリリースされた楽曲「話がしたいよ」を聴いたのがきっかけだった。
バス停で佇みながら、今は会うことのない大切な人とその記憶に思いを馳せるバラード。
この楽曲を初めて聴いたとき、得体の知れない感情が押し寄せてきた。何かが引っかかる。それはネガティブな意味ではなく、喜びや驚きの中に少しの寂しさが入り混じる感覚だった。
この瞬間に
どんな顔をしていただろう
一体どんな言葉を
いくつ見つけただろう
ああ 君がここにいたら
君がここにいたら
話がしたいよ
(話がしたいよ)
私の記憶にあるBUMPの中でとびきり声色が優しかった。
大人になった。成熟した。簡潔にそう言い表すこともできる。年月が経つにつれて、BUMPは初期の怒りや嘆きなど複雑な心情が絡んだ荒削りとも言える音楽からどんどん進化していた。
歌にのせる魂やメッセージそのものは変わらないのに、それを形作る要素がきれいになった。言葉は優しくなり、声質は柔らかくなり、サウンドは重厚で美しくなった。
でも、この曲を聴いて感じたのはそれだけじゃない。
「話がしたいよ」を聴くと、必ずある楽曲がセットで思い起こされる。2002年に発売されたサードアルバム『jupiter』収録曲「ベル」だ。
耳障りな電話のベル
「元気?」って たずねる君の声
僕の事なんか
ひとつも知らないくせに
僕の事なんか
明日は忘れるくせに
そのひとことが温かかった
僕の事なんか知らないくせに
(ベル)
くたびれた日常の中にかかってくる一本の電話。それを受け取る男の葛藤を切り取った楽曲。
かつて私にも経験があった。自分の「わかって欲しい」ばかりが先立ち周囲に苛立っていた。手を差し述べてくれた人がいたのに「あんたにわかってたまるか」と反発心を隠せず相手を困らせた。本当は救われていたのにちゃんと伝えられなかった。それは弱い人間ゆえの愚行だった。
このパートに込められた「優しくされるのが嬉しいと同時に怖い」という矛盾。差し出された手を握ったとして、その手を払われたり失ったりするのが怖い。だから心の奥の奥までは見せられない。
そうして他人には見せない一部を残しておく行為が自分の心を守る最後の砦となる。
<僕の事なんか知らないくせに>と強がる姿に私自身を重ねながら、独りよがりで勝手だよなぁと思った。
ここから16年経ってリリースされた楽曲のタイトルが「話がしたいよ」なのだ。
どうやったって
戻れないのは一緒だよ
じゃあこういう事を
思っているのも一緒がいい
肌を撫でた今の風が
底の抜けた空が
あの日と似ているのに
(話がしたいよ)
「ベル」では<僕のことなんか知らないくせに>と突っぱねていた青年が、自ら<話がしたいよ>と言う。
心を通わせられなかった過去があった。もし<君がここにいたら>話したいことがたくさんあるのに、それはどうにも叶わない。だったらせめて君も同じ気持ちでいて欲しいと、ささやかな願いだけを抱えて生きていく。
ひとりで大切な人との思い出に浸るのは孤独だ。けれど、それに上塗りされた大きな愛としなやかな強さが透けて見えた。だから声色がこんなに優しいのだと腑に落ちた。<一緒がいい>のフレーズが甘く素直に響く。
小さなライブハウスで歌っていた孤高なボーカリストの姿が脳裏に蘇る。
あのとき、どこにもぶつけようがない苛立ちや戸惑いは誰しもが持っているものなのだと、私だけじゃなかったと思えた。それでも自分なりに折り合いをつけて生きていくのだと。
BUMPが奏でるのは、そうした「強がり」な音楽のはずだった。
「話がしたいよ」を初めて聴いたときに胸がざわついたのは真の強さが垣間見えたからだ。君や僕と美しい思い出の断片だけでなく、未熟さや後悔もすべて受け止めて、包み込む強さ。
それは私がずっと欲しかったものだった。
強さとは積み重ねること
強がりから真の強さへ変化した軌跡を知りたくなった私は、改めてBUMPの楽曲を隅々まで聴き始めた。
ファーストアルバムやセカンドアルバムの収録曲には、実際に「強がり」を自認する歌詞が登場している。どちらもBUMPらしさを象徴する一節だ。
ただの強がりもウソさえも
願いを込めれば誇れるだろう
望めば勇気にもなるだろう
(バトルクライ)
ポケット一杯の弱音を
集めて君に放った
強がりの裏のウソを
放った ぶちまけた
(リリイ )
強がりの裏側には、理想とのギャップを隠そうとする虚栄心や周囲の優秀さと比較した劣等感がチラリと顔を覗かせている。しかし、BUMPは本当の強さを手に入れるのに必要なピースに気が付いていた。
それは前述した「バトルクライ」にも登場する<勇気>という概念。ファーストアルバムを聴いていると、この言葉を頻繁に耳にする。実際に全8曲中4曲で使われており、以後コンスタントに出てくる。
そのポケットのスミを探すのさ
きっと勇気のカケラが出てくるだろう
自信を持っていいハズさ
僕ら時には勇者にでもなれるんだ
(リトルブレイバー)
胸をはって旅に出るよ
朝の匂いの夢を見るよ
「勇気の出る唄」を思い出すタメに
(ナイフ)
タメ息に勇気かき消されても
「まかせろ」なんていう
(ノーヒットノーラン)
BUMPは自分たちを弱者のように位置付けているが、それに甘んじたり開き直ったりしていたわけではなかった。つねに自身を奮い立たせて臆病者の皮を剥ごうともがいてきた。
それはデビューから24年経った今でも変わらない。最新アルバム『aurora arc』でも3曲の中に<勇気>が登場している。
考え過ぎじゃないよ
そういう闇の中にいて
勇気の眼差しで
次の足場を探しているだけ
(Aurora)
ポケットに勇気が
ガラス玉ひとつ分
それぞれ持っている
(リボン)
絶望の最果て 希望の底
勇気をあげる 鏡の前 盾と剣
(シリウス)
どの時代の楽曲にも一貫して出てきた<勇気>は、自尊心の低さや自信のなさで挫けそうになる心を支えてきた下地。
彼らの楽曲に投影されているのは理想論や綺麗事じゃない。必ずこの暗闇を抜けて光の当たる場所に辿り着くんだという泥くさいほどの反骨精神と「踏み出す一歩」だ。
それを自ら証明してみせるかのように、作詞作曲を担当するボーカルの藤原基央は疲労困憊やスランプなど精神的にも肉体的も極限まで追い詰められた状態のとき、「ロストマン」や「真っ赤な空を見ただろうか」といった後々まで語り継がれる名曲を生み出してきた。
前述の「ベル」もしかり。「天体観測」の大ヒットにより環境が激変して混乱下にあった毎日の中、ふとかかってきた何気ない一本の電話に癒された実話が元になったという。
「話がしたいよ」も怒涛のタイアップ楽曲を完成させたあと、ひどく疲れていた状態で生み出したとインタビューで語っていた。
「“シリウス” “Spica” 書いて、 “Spica” 完成させて、『疲れたなあ……』っていうのがそのまんま曲になった(笑)」
(ROCKIN'ON JAPAN 2019年8月号から引用)
闇が深ければ深いほど見つけ出された光は眩しく、それは美しい音楽へと形を変え、私たちのもとに届く。BUMPの言葉や旋律が時に苦しいほど胸に迫るのは、何より本人たちがもがき悩みながら歩みを前に進めているから。
こうした積み重ねが「強がり」から「強さ」へ変化する土台になったのは間違いない。
強くありたい揺らぎの中で
もう一点、楽曲を振り返って印象に残ったのが、まるで定点観測のごとく存在する「ポケット」という言葉だった。
ときには大切な何かを仕舞う場所として、ときには見せられない何かを隠す場所として。自分と密着した狭く小さなスペースに入れるものによって、その時々のBUMPの精神性が深く表現されている。
前述した「リトルブレイバー」「リリイ」「リボン」の歌詞中にもポケットが出てきている。その中身は<勇気>や<弱音>だった。「スノースマイル」では<思い出>を、「記念撮影」では<鍵と丸めたレシートと面倒な本音>を入れていた。
そして「話がしたいよ」の冒頭にもポケットが登場している。
持て余した手を
自分ごとポケットに隠した
バスが来るまでの間の
おまけみたいな時間
彼らがこの曲でポケットに入れたもの。それは<持て余した手>と<自分>である。
かつては君と繋いでいたかもしれない手。ともすれば君への想いが溢れそうになる自分。歌い出しでそれらをグッと見えないように仕舞い込むところからこの楽曲はスタートする。
きっと自覚があるのだと思う。あえてポケットに隠さないと、その手にいつまでも君の温もりを探して、独りよがりな気持ちが大きく膨らんでいってしまうと。僕はそういう自分の弱さを知っている人だ。
本当の強さとは、弱さと向き合うことから始まる。
無論、この曲でもBUMPは自分たちを強いと評価しているわけではない。これは歌詞の続きにも表れている。
体と心のどっちに
ここまで連れて来られたんだろう
どっちもくたびれているけど
平気さ お薬貰ったし
何のための<お薬>なのかは書かれていないが、こんなに直接的な形で弱さを吐露した歌詞がかつてあっただろうか。ドキッとさせられた後、サビに向かってこう続く。
飲まないし
手元に置きながらも口にはしない、意地。ここでようやく「あぁ、BUMPだなぁ」と安心する。
それと同時に、私がどうしてこんなにこの楽曲に惹かれたのか分かった気がした。
揺らぎだ。歌の中にある、感情の揺らぎ。
強さと弱さのあいだで、矛盾や葛藤を抱えて。
抗いようもなく
忘れながら生きているよ
ねぇ一体どんな言葉に
僕ら出会っていたんだろう
鼻で愛想笑い 綺麗事
夏の終わる匂い
まだ覚えているよ
話がしたいよ
<抗いようもなく忘れながら生きているよ>
うんと昔、何度も聴いた曲にこれと似ているフレーズがあった。ミスチルだ。1994年、奇しくもBUMPがバンドを結成した年にリリースされた「Tomorrow never knows」で、彼らは<人は悲しいくらい忘れてゆく生き物>と歌った。そこに映し出されていたのは「人の気持ちの儚さ」だった。
しかし、この楽曲では忘れゆく様を歌いながらも<まだ覚えているよ>と真逆に着地する。君とその思い出を忘れてもおかしくないぐらいには長い時間が経過した。それでも想いは変わらない。ここに映し出されているのは「人の気持ちの強さ」だ。
忘れながら生きているのに、覚えている。相反する気持ちがどちらも本音だなんて。
きっと人間ってそんなものだろう。「ベル」で僕が君の優しさに躊躇いながらも癒されたように、外側をどんなに取り繕っていても内側では混沌とした感情がぶつかり合いながら存在する。
だから<愛想笑い><綺麗事>とふてくされたように言い放った直後に<夏の終わる匂い>と感傷的になるのも不思議じゃない。むしろ本当の人間に限りなく近い心の揺れ動きで、だからこそこの楽曲は切なくも温かみがある。
誰だって突然強くなるわけじゃないし、仮に強くなった気でいても、一瞬で打ち砕かれるようなこともある。諦めや妥協を強さと呼ばなければならない時もある。
そう考えると、強さなんて推し量りようのない幻想なのかもしれない。
今までのなんだかんだとか
これからがどうとか
心からどうでもいいんだ そんな事は
いや どうでもって そりゃ言い過ぎかも
いや 言い過ぎだけど
そう言ってやりたいんだ
大丈夫 分かっている
けれど、そんな矛盾も葛藤もそれに伴う痛みも一切合切すべて、最後に僕は<大丈夫 分かっている>と受け止めてみせる。
<大丈夫>は君に向かって言っているのか、僕に向かって言っているのか、とらえ方で色が変わる。前者であれば人を想う強さを宿した言葉に聴こえるし、後者であれば自分に言い聞かせる強がりの言葉として映る。
強さと強がりのあいだはひどく曖昧だ。BUMPは自らの生き様と共にその境界線を歌い続ける。おそらく僕はお薬を飲まないのだろう。もしそれが一瞬で心の痛みを取り去ってくれるものだとしても。
おわりに
ステージ上の青年を見上げたあの日。私は救われて、心配して、憧れたのだった。自らの弱さに剣を突き立てる彼らを、射るような目で切り開かれていく未来を、眩しいと思った。
彼らが歌っていたのは人間の憂いや孤独だけじゃなかった。いつだって希望を含んでいた。その音楽で、その姿で、多くの人に勇気を与え続けてきた月日を想う。
臆病者たちはやがて日本を代表するロックバンドとなった。しかしやっぱり今でも歌にのせる魂やメッセージは変わらない。
その一途さこそが、強さの輪郭を作るのだと思う。
*
(こちらの企画に応募させていただきました)
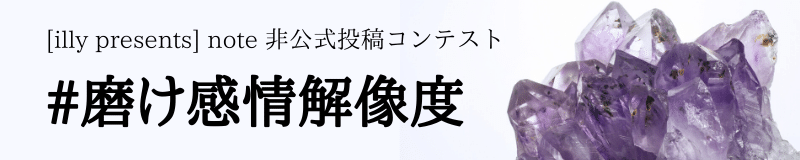
最後まで読んでいただいてありがとうございます。これからも仲良くしてもらえると嬉しいです。
