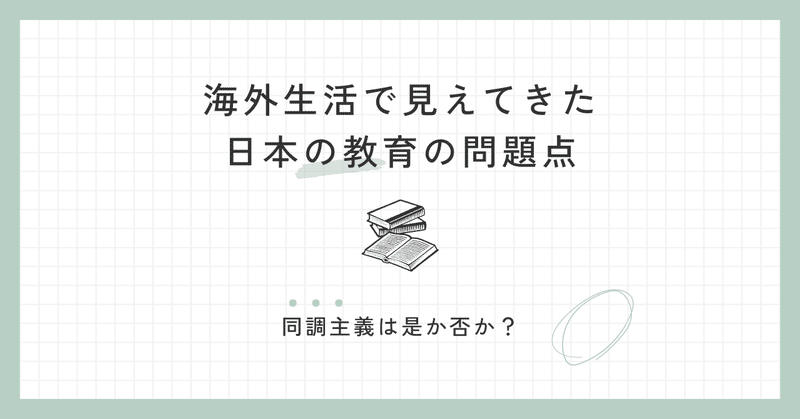
海外生活で見えてきた日本の教育の問題点
私たち家族は、4年前まで10年間ベトナムに住んでいた。
現在10歳の息子は、6歳までベトナムで育った。
ベトナムでは、3歳からインターナショナルスクールで英語教育を受けていた。突然、家庭の事情で6歳から普通の田舎の公立小学校で日本語教育を始めた。
親の都合で申し訳ないと思いつつ、両方の言語が話せた方が良いと勝手に思っていた。
4年生の3学期から、急に学校へ行きたくないと言い、登校できていない。
先日英検準2級に合格したが、ほとんど母国語であるため本人は英語力が十分ではないと思っている。夜になると泣き出して、英語も日本語も中途半端だと自己否定したり、生きていたくない、人生ごみのようだとネガティブなことを言うばかり。
あぁ、こんなに辛い思いをさせてきたんだなと、その時初めて気がついた。発達段階でも、周りを意識し始める時期。周りとは違う自分。友達と話していても心から楽しめないと、ずっと孤独を感じていたようだ。
家庭でももっともっと褒めたり寄り添ってあげるべきだったな、と今は思っても、過ぎ去った時間は戻らない。これから何ができるか、一生懸命ともに考えていくしかない。
家庭での安心も大きいと思うが、学校ではどうだったんだろう?
先生はもちろん、発達障害に詳しいわけではなく、特に問題もなかったように見えたため、通常通り他の子どもと同じように授業をしていただけ。年度初の家庭調書には、毎年発達障害のことと言語的遅れについてはっきり書いていた。
知能的には問題がないので、先生からみたら通常学級で何も問題ない、という判断だった。
ただ本人は、とっても我慢していた。
苦しくても言えず、他の子にできることができない自分がダメなんだと思い込んでしまった。
その結果、うつ病になった。
私は、学校にすべて責任をなすりつけるつもりはない。
本人もできないことを必死に隠していたので、気付きにくかったと思う。
でも、「普通」にできることがよっぽど我慢しないとできない発達障害の子どもにとって、特に息子のように海外で育った子にとっては、地獄のような日々だったに違いない。
私自身も、日本の企業で働いていてうつ病になりかけたことがあった。日本にいたらメンタルが持たないと考えて、海外に移り住んだ。
エネルギッシュで細かいことを気にせず、おおらかな人たちに囲まれたベトナムでの10年は私のメンタルを不動のものにした。それなのに、過去の自分のことを忘れて、息子に同じ思いをさせてしまっていた。
全体主義と同調圧力
帰国後の4年間、日本の社会や小学校を見てきて、まだまだ本当に息苦しいと感じる。ましてやコロナ禍でさらに(心理的な安心のためのもので、感染予防にはそれほど意味のない)規制が増えた。その結果、10代〜20代の死因=自殺が先進7カ国でトップになってしまった。人を自殺にまで追い込んでしまうこの同調社会は異常だと思った。
日本の学校や社会の「ルール」には、もちろん合理的なものもあるが、「心理的安心」のためのものが多い気がしている。つまり、他人に迷惑をかける者が非難されるため、「他人を安心させるためのルール」である。
例えば、「授業中は静かにする」というルール。
公共の場で静かにするのは、もはや日本では暗黙の了解のようになっている。これは、「うるさい人は迷惑」という固定観念があるからだ。
この「うるさい人」は、何かを訴えたい、授業に関係することで話したくてしょうがないことがある、という例外的な発想は全く受け入れられないのだろうか?また、そのルールがなければ、先生が名指しして発表するのではなく、生徒から自発的に意見がどんどん出てくることもあるのでは?
息子がまだ歩けないとき、電車の中でぎゃん泣きする息子を抱きかかえていると、周りから睨まれた記憶はよく覚えている。恐ろしいまでの「沈黙」と「嫌悪感」がただよっていた。
海外ではこのようなことはあまりない。ベトナムでは、泣いている赤ちゃんを見ると周りの人が笑顔であやしてくれた。
ヨーロッパでは、みんなそれぞれの楽しい会話に夢中で、他人の子どもが泣いていても気にならない。
車内の視線からは、「迷惑だろう、泣き止ませろよ」と言う声が聞こえてきそうだった。どうして、「お腹がすいているのかな?」「狭いところでかわいそうだね」というような、温かい気持ちになれないのだろう?
日本で働く人がいかに余裕がないのか、余裕がないから人に迷惑をかけないことを強要したり、嫌悪感をもったりするようになるのではないか、と疑問に思っていた。
そして日本で昔から行われてきた「同調」を重んじる教育。
これには賛否両論あると思う。同調の考え方があるから、自分の意見を押し通さずに周りの人と助けあったり協力したりすることができる。
ところがこれが変に認識されると、逆に「出る杭は打たれる」。
みんなと同じことができない人は、異質、異常であり、いじめの対象となる。
私が小学校に通っていた時代は、それでも地域に優しい人がたくさんいて、自然の中で思い切り遊べる場所があって、心が病んでしまう人は少なかったように思う。
現代の日本は、規制とルールで表向きは人を「安心」させても、安心できないことが起こった時の他人への責任転嫁が多すぎる。
私個人的には、これは「生きる力」に関係していると思っている。大人が不安材料に反応しすぎて柔軟性がないと、他人を攻撃してしまう。
「危ないからやめさせてください」という保護者がいるから、学校はどんどん子どもの自由を奪っていく。
1つの方法がだめなら、違う方法がある。危ないなら見守ってあげればよい。正しい使い方や遊び方を教えてやればよい。大人が責任から逃れるために、子どもに「生きていく力」を育む機会がどんどん減っている。
社会全体で、もっともっと柔軟に考えていかなければ、自分で自分を苦しめることになる。
ベトナムでは、毎年洪水が発生して家が浸水していた。
3日間、電気も水もなかったこともある。
災害だ!とパニックになるのではなく、淡々と荷物を運び、協力して食糧をボートで運び、水が引いたら掃除をして次の日には笑顔で日常生活が戻っていた。
これこそが「生きる力」なのだと思う。
防災グッズを揃えて安心するのもいいが、いざという時に火を熾したり、魚を釣ったり、雨水を飲料水にする知恵が生きてくる。
個人がそれぞれ得意なことを生かして助け合う世の中は、平和だろう。多様性を受け入れてそれぞれの力を伸ばすことで、人とは違う考え方、感じ方をする者を受け入れる「インクルーシブ」。発達障害、身体・知的障害の有無、人種や性別に関係なく、「良いところ」を見つけられる集団にいたら、誰もが居心地が良いに決まっている。
まだ幼い子どもたちは、単純に物事を考えて心ないことを言ってしまうこともある。困難に立ち向かえる心を育て、思いやれる心を育てる。
小学校の教育では、特にこの生きる力を育んでほしいと強く思う。
そんなことはいいから勉強を教えてほしいと思われる保護者もいると思うが、この基礎、土台〜自信〜が、大人になってから責任を他人に押し付けない、将来の人間力をつくっていくような気がしてならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
