
今日も、読書。 |期待や幻想を支えにして、人は生きている
2022.5.29-6.4
ブッツァーティ|タタール人の砂漠
人生という名の砂漠を歩む私たちは、いつか必ずオアシスが現れてくれると信じている。
イタリア文学を読みたい、という思いだけがずっとあって、そのくせ実際に行動には移せていなかった。
そんな時、高校時代の友人と読書会をすることになった。そのテーマ本として、友人が選んでくれたのが、ブッツァーティの『タタール人の砂漠』だった。タイムリーにイタリア文学。運命めいたものを感じて、小さな感動を覚えつつ、ブッツァーティを読み始めた。
『タタール人の砂漠』は、幻想小説の大家として知られる、二十世紀イタリア文学の鬼才・ブッツァーティの長編小説だ。訳者解説によれば、1940年、イタリアが第二次世界大戦に参戦する前日に出版されたという、数奇な運命を辿った作品。国民の士気を高める内容ではなかったためか、当時はそれほど評価されなかったそうだ。
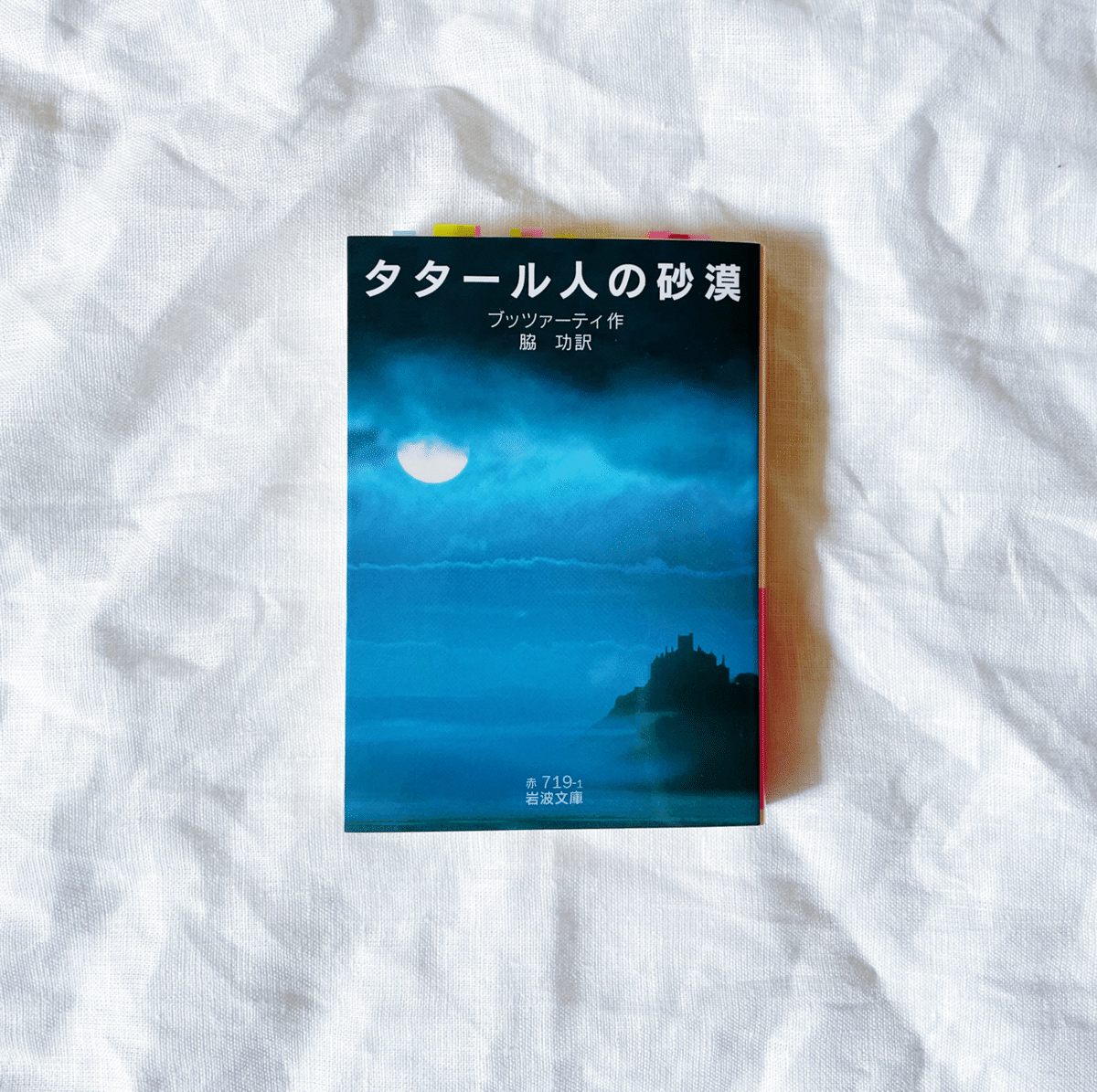
本作は、ジョヴァンニ・ドローゴという、ひとりの将校の一生を描いた小説だ。
辺境の砦に配属されたドローゴは、平和だが単調な日々の繰り返しに、青春を浪費しているという不安を覚え、早々に砦を脱することを決意する。しかし、砦の生活に慣れ親しむうちに、異動の機会を逸し、やがて他の将校と同じように、いつ来襲するとも分からない敵との劇的な戦いを期待しつつ、無為な毎日を過ごしていく。
途中、同僚に射殺されるラッザーリの話や、アングスティーナが悲痛な死を遂げる国境画定部隊の話など、印象的なエピソードが差し込まれる。しかし基本的に、淡々と物語は進んでいく。
そして終盤、ドローゴは肝臓障害を患い衰弱していく。そんな状況下で、彼が一生を通じて待ち望んでいた北国の部隊が、ついに砦に攻め込んでくるのだ。ドローゴは重い身体を引きずって戦に参加しようとするが、現役の兵たちからお払い箱にされ、最後は、ひとり寂しく病室で死んでいく。
ドローゴの人生は、まさに私たちの人生そのものだ。
何か特別なことが起こるという、期待や幻想を支えにして、人は生きている。そんな期待に反して、現実は何も起こらず、虚しく時は流れていくことがほとんどだ。誰の人生にも通じる、こうした普遍的なテーマが描かれている点が、本作が世界中で多くの読者を獲得している一因だろう。
本作を読んでいると、時の流れの残酷さに、胸が苦しくなる。私たちの事情などお構いなしに、一方向に流れゆく時間の中で、ひとたび機会を逃してしまうと、もう後戻りすることはできない。
ドローゴの人生には、あの時こうしていれば……というターニングポイントがいくつもあった。それだけに、最後まで思うような展開が起こらず、寂しく亡くなってしまうドローゴに、どうしようもなくやりきれなさを感じる。
印象に残っている場面がある。終盤、ドローゴが砦に帰還する道中で、新たに配属されたモーロ中尉という将校に、道を挟んで挨拶をされる場面だ。
実は序盤で、ドローゴ自身が新人将校の頃に、全く同じようにオルティス大尉という先輩に挨拶をする場面があった。細かな受け答えの仕方まで、全く同じように反復されていて、明らかに意図的に対比がなされている。序盤では、人生への期待を胸に意気揚々と挨拶をしていたドローゴが、いつの間にかその熱意を忘れ、挨拶をされる立場になっていることに心が揺さぶられた。
本作は、自分自身の人生と照らし合わせながら読むことで、生きることの意義について、深く考えさせられる小説だ。恐らく、読んだときの年齢や立場が変われば、本作から得られる感想も、全く異なってくるだろう。改めて、本作を勧めてくれた友人には、感謝しかない。
高校時代の友人と、読書会を開催するなどした
高校時代の友人2人と、初めて読書会をするなどした。
まず、一緒に読書会をしてくれる本好きの友人に恵まれた、己の幸運を噛み締める。しかも、テーマ本がブッツァーティの『タタール人の砂漠』で、一緒にテンションが上がってくれるような友人だ。本を好きでいてくれてありがとう、と謎の立場で感謝する。
読書会を開いてみて、人によって本の感想や印象に残るポイントが異なるのだということを、改めて実感した。
各々の感想を共有することで、ひとりで本を読むだけでは得ることのない、新しい発見がもたらされる。普段、他の人と本の話をする機会がほとんどない私は、終始嬉しくて、気持ちの悪いテンションだったと思う。
先に述べたとおり、私が『タタール人の砂漠』を読んで最も印象的だったのは、終盤でドローゴが、若い将校に挨拶をされる場面だった。
一方で、友人に話を聞いてみると、全く違う場面を選んでいた。たとえば、ドローゴが砦に配属されて長い年月が経ち、久しぶりに故郷の街に帰る場面だ。
ドローゴは、母が昔のように自分の足音に気づいてくれなくなったことや、恋仲のマリアと思うように心を通わせることができなくなったことなど、故郷での暮らしが、いつの間にか自分と相容れないものになっていることに気づく。砦で過ごすうちに流れ去った時間が、過去の生活を遠いどこかに置き去りにしてしまったかのように。
そう言われてみると、この物語の大きなターニングポイントが、実はこの帰郷の場面だったのではないかと思えてくる。この時、マリアとうまく通じ合って、故郷に戻る選択をすることができていたら、彼の寂しい晩年は大きく変わっていたのかもしれない。彼女の手を取れなかったあの瞬間、あの何気ないワンシーンが、実は人生の大きな分かれ道だったのではないか。
なんて面白いのだろう、読書会は!
次回は、吉田修一さんの『横道世之介』をテーマ本として選出し、1ヶ月後にまた集結する。読書会のために本を読むと、普段よりも深く深く、深淵まで潜っていくような豊かな読書ができる。最近あまり本が読めていない……という方は、誰かと読書会の約束をしてみるのはどうだろう。
↓「今日も、読書。」のイチオシ記事はこちら!
↓「今日も、読書。」の他の記事はこちらから!
↓本に関するおすすめ記事をまとめています。
↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。
↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
