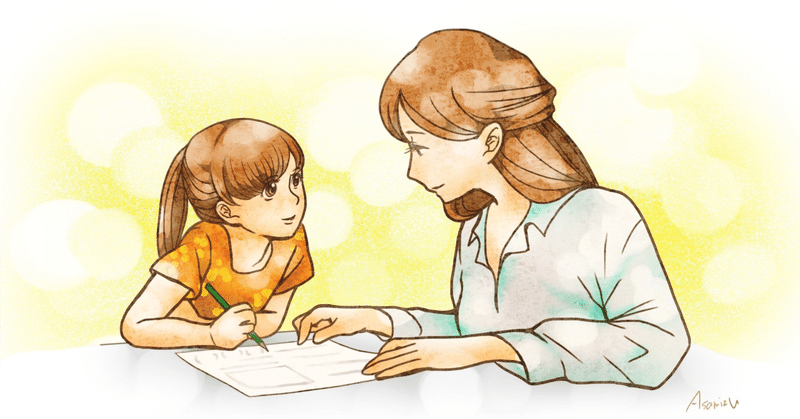
教師は「子ども」を見ているか
「主体性が奪われた先生が主体的な子ども育てることは可能であろうか」
こんな命題が脳内に流れてきた。
もちろん「否!」と言いたいところであるが、文科省の教育政策を現場から眺めていると「それは可能であるし、できないのならば現場の能力が低いからだ(だから、より主体性を奪ってコントロールするしかない)」と考えているのでは無いかと疑いたくなってしまう。
学習指導要領というのがある。
教科書はこれを元にして作られており、授業時間数の規定や、学年ごとに指導するべき漢字なども載っている、いわば公教育の正当性を担保する法的な指針である。現場にいるとこれを読む機会はほとんどないが、なかなか味わ深いことが書かれているので、たまには目を通しておきたい一冊である(なお、学習指導要領には各教科ごとに「解説」という冊子もあるが、こちらには法的根拠がないという見解である)。
実は、戦後すぐはこの学習指導要領に(試案)という文言が付されていたことはあまり知られていない。この(試案)というのは、戦後すぐの当時の指導要領はまだ未完成であったからという解釈が一般的である。後の改訂で試案から告示に代わり、法的拘束力が生まれたとされているが、それまでの学校現場では教育実践における現場の主体性が尊重されていた。
当時は戦後の「民主主義ブーム」も相まって「児童中心主義」という考え方が広く受け入れられていた。これは現在の科学的な「系統主義」と対立する概念であり、子どもたちの「経験」に重きを置く教育的立場である。
現在の系統主義における「教えるべきことを順序立てて、段階的に教えていく」ことに慣れ親しんでいる私たちからするとこれは想像が難しい。児童中心主義の開祖であるジョン・デューイの教育実践を少し紹介すると、たとえば、いきなり「羊毛」を実際に刈り取るということが良いとされる(『学校と社会』岩波文庫 p31)。そこから、羊毛産業と木綿産業との発展の違いを考えたり、と学習が発展していくことになる。これは予め「教える内容を決めておいて、それを教える」というのとはわけが違う。学びが疑問を生み、次なる学びへと連なっていくイメージであろうか。繰り出した羊毛で服を作ることもあるだろうし、工業の歴史を考察することにもなるだろうし、羊毛を顕微鏡で見てその繊維を描いてみるなどの理科的な観察もあり得る。このように書いてみると、私はワクワクするのだが、これは小学校教員では少数派なのであろう。
実際、デューイの実践から着想を得た「総合的な学習の時間」は、創設以来、現場では評判が悪いとされている。それは「何をしたらいいかを指示する教科書がない」ということに起因しており、結果的に、どの学校の「総合的な学習の時間」の実践も似たり寄ったりになる。現在だと「SDGs」が流行しているようだ。現場では「何を教えたらいいかを教えてくれ」という認識の教員が多いみたいである。
この「主体的に教育活動を選択できない」という認識は学校現場では散見される。
例えば、私は給食時間中に「NHK for school」の番組を大型テレビで映している。これは、コロナ禍があけたにも関わらず、「感染対策のため、給食は前を向いて静かに食べる」という学校のルールが残っているため、給食時間中が静かで寂しいと感じるからしているわけであるが、今年度も管理職から「どうしてテレビをつけているのですか?」という質問を受けた。
管理職の言い分は「そのような実践を見たことも聞いたこともない(だからやめてほしい)」というものであった。もちろん、この要求は受けられない。「もしダメな理由があれば教えてください」と突っぱねるとそれ以上は言い返せないみたいである。
この手のやり取りは本当に多い。私自身が主体的に教育実践を選択すればするほど、周りからの声に「不自由さ」を感じてしまう。
先日も「どうして授業中にノートを書かせないのですか」という問いを向けられた。私の考え方としては以下の通りである。
現在の学校における「ノート指導」というのは「黒板を正確に写す」ということに力点が置かれ過ぎている気がする。
確かに、授業後に学習内容が綺麗に整理された黒板が残れば「授業をやった感じ」はするし、それを子どもたちにノートへ写させて持ち帰らせて、それを保護者が見れば子どもたちが学校で「授業を受けてる感じ」はするだろう。
私もそう思っていた。
しかし、ある年「ノートはとても綺麗に作れるのに、テストを見る限り学習内容を理解できているとは思えない児童」に気づいた。
そこで私は考える。確かに、研修を受けているときに必死にメモを取ると「勉強した感じ」にはなるけども、メモを取ることに集中している間は、話を聞くことができないし、話を文脈して把握することも難しい。内容を断片的には覚えているけど、どうにも「聞いている感じ」はしなくなってしまう。もちろん、そうではない人がいることもわかっている。私はそれが難しいという「特性」の話である。
だから、そう考えてから、私は研修などの場では極力メモを取ることを辞めて、代わりに講師先生の目を見て「話を集中して聴く」ということをしている。実際、このような研修では親切にも研修内容をまとめたレジュメやスライド資料が用意されているので、それを見ればメモがわりにもなる。
話を聞きながら、「自分ならこの先生にどんな質問を投げかけようか」とすることで、「聴く行為」の質も上がったと、私自身は感じている。
つまり、前段の私の授業への問いは間違っている。
正確には、「授業中にノートを写さない児童がいるのは何故ですか?」となる。
私の授業を受ける児童には「ノートを写さない自由」がある。だから、もちろん「ノートを写す自由」もある。実際、写したい子は写している。そういうことをした方が理解しやすい子もいるのだろう。
聞いているだけでは頭に残りにくいのではないかと感じる人は、まあ、そうなのだろう。その人の特性を否定することはしないが、一方で、その人と異なる特性を持つ「他者」への理解は足りないのではないだろうか。
学校はどこまで行っても「平等主義」が蔓延っている。良い面もたくさんあるが、こういう場面では「悪平等」と感じてしまう。「全員が黒板を正確に写し取らなくてはならない」という言説に違和感を感じない教員は非常に多い。学習活動における児童の主体性を認めることは、学校の先生にとっては困難なのである。
それもそのはずで、「学校の先生」という人たちは、私も含めて「かなり偏った人たち」なのである。それは少なくとも学校の先生のほぼ全てが「大卒」であるという時点で、国民の半数以上である「非大卒」とは異なっている。さらに「学校文化に適応できた元子ども」という属性もあるだろう。学校に不適応を起こしながら学校の先生になったという人を探してくればいるだろうが、ここでは「傾向」の話をしているので、「特殊な事情」による反例を持ち出されても困る。
つまり、学校の先生という人たちの多くは、「先生の言うことは聞くものであり」、「学校の勉強は努力をしてしなければならず」、「大学くらいは卒業しておくことが「常識」に登録されている人たちの集団」と言うことである。この価値観を共有している集団は、「黒板に書いてあることを写す」と言う学校文化に違和感を持ちにくいであろうことも想像に難くないし、そうではない子どもを「怠惰である」と見下しても不思議ではない。
これを「同質性の高い集団」と呼んでもいい。職員室には男性も女性も若手もベテランも様々な先生がいるように見えて、実は根本のところでは割と大差ないと言うことに気づいていない先生が多い。
それがすべて悪いという話ではない。
学校と社会との垣根をなくしていこうとする現在、多くの人に受け入れられている価値観には反対したいし、学問を学ぶということはそもそも俗世間とは異なる世界へ旅立つということも意味するのであれば、学校という場所の特殊性はそんなに悪いものではない。社会の価値観にそのまま迎合してしまえば、現在の主流の考え方である「経済を回し、税金をしっかり納める人材育成」という単一のものさしでしか教育の効果を測れなくなってしまい、そんな学校教育はディストピアに感じてしまう。
そもそもここまでの議論のように、学校現場で「不自由さ」を感じている教員も少ないのではないだろうか。同質性の高い集団で設定された歪なルールを守っていれば、それはそれで居心地がいい。自己責任論が蔓延している中で、組織の権威も借りられず個人として思った通りの教育ができるほど、学校の権威性も信頼性も高くない。教育実践の成果は測れず(主体性なんて測れない)、失敗の要因は個人の責任にされるくらいならば、公僕として割り切って周りと同じ教育を粛々とやっていくという教育実践は、この時代の教師の生存戦略としてはむしろ賢いとさえ感じる。
では、そうなると「教育における主体性」はどうなるのだろうか。
そんなものは必要ない、というのが、多くの教師の本音ではないだろうか。学校はいまだに「秩序」を重んじる。学級崩壊という予見不可能な災害が恐ろしく、どうしても「自由」に舵を切ることにためらいが生じる。子どもたちに自由を与えたら、管理できなくなるのではないかという不安は本当によくわかる。
しかし「自由なき主体性」というのが空語であることもまた自明である。現在の学校教育における主体性は「教師への忖度である」という私のテーゼも現場を少しでも知っていたら違和感はないであろう。
この論の最後に、少し主体性について考えてみよう(これが主題だったのに)。
哲学的な考察だと、主体は「立ち上がる」ものである。では、どうやって個人の主体は立ち上がるのだろうか。それは「私に見られる」ことである。
ことの順逆が狂っていることにお気づきだろうか。つまり、まず個人という主体があって、それが見られて主体になる、ということではない。
まず、「他者」がいる。そして、その「他者に見られる」ことを通じて、「私という主体」が立ち上がる、のである。
例えば、生まれたての赤ちゃんを思い浮かべてもらおう。
この赤ちゃんはまだ主体として立ち上がっていない。「自分」という概念もない。そういう意味では、生物学的には生まれていても、哲学的にはまだ生まれていないとも言える。では、いつ生まれるのか。それは、周りの養育者に語りかけられて、養育してもらう中で「立ち上がっていく」のである。そういう意味では、少しずつ「生まれていく」とも言える。
我が師である内田樹先生は「死というのはデジタルなものではない。アナログのように少しずつ死んでいくのだ」とおっしゃっていた。「死んでいく」という表現が妙にこびりつく。確かに「老い」を考えるとわかりやすい。あれは「少しずつ死んでいく」感じがする。
では、事故死などはどうか、と言われそうである。その場合は、死後に思いを馳せてみよう。周りの人の記憶から生きていた記憶が少しずつなくなっていく。そうして「少しずつ死んでいく」とも考えられる。亡くなってすぐだと「まだ生きている感じがする」という証言は探せばいくらでも見つかるだろう。
では、学校教育における「子どもたちの主体の立ち上げ」が成功するにはどうすればいいのか。それはもう自明のことであり、先生が「あなたを見ていますよ」と言い続けることである。これを対話と呼んでもいいし、尊重すると呼んでもいい。
教師が同質性とか指導要領とか管理職とかの監視の目から逃れて、目の前の子ども達と自分が選んだ教育実践を真剣に取り組んでいけば、自然と子どもたちの主体は立ち上がるのである。古来よりは人類はそうして未成熟な子どもたちを成熟へと導いていったのである。
それが現代の学校教育で失われてしまっているのであれば、それは由々しき事態なのである。
