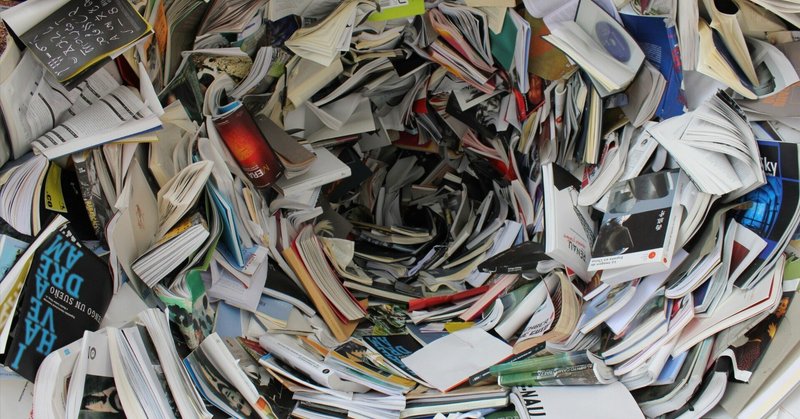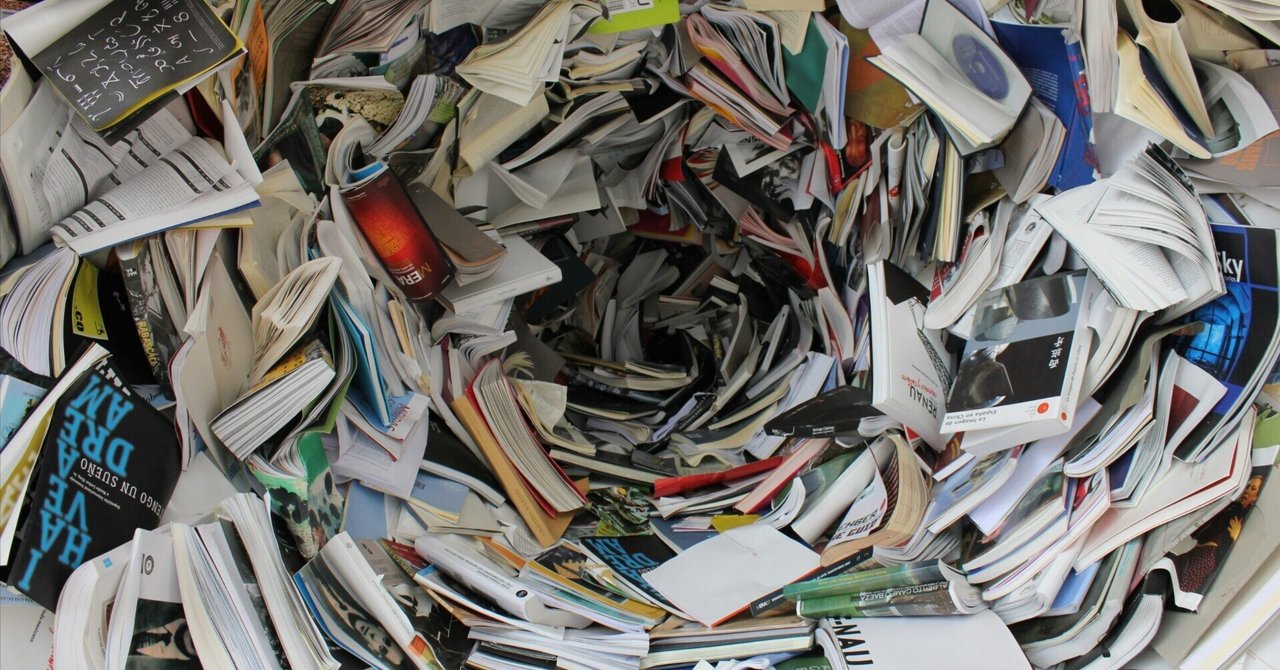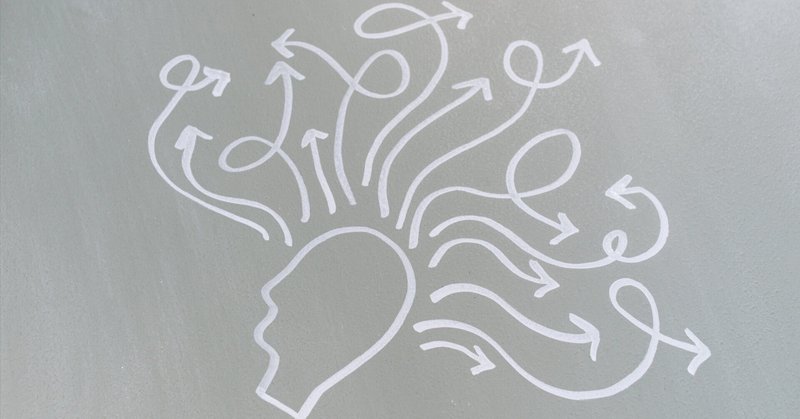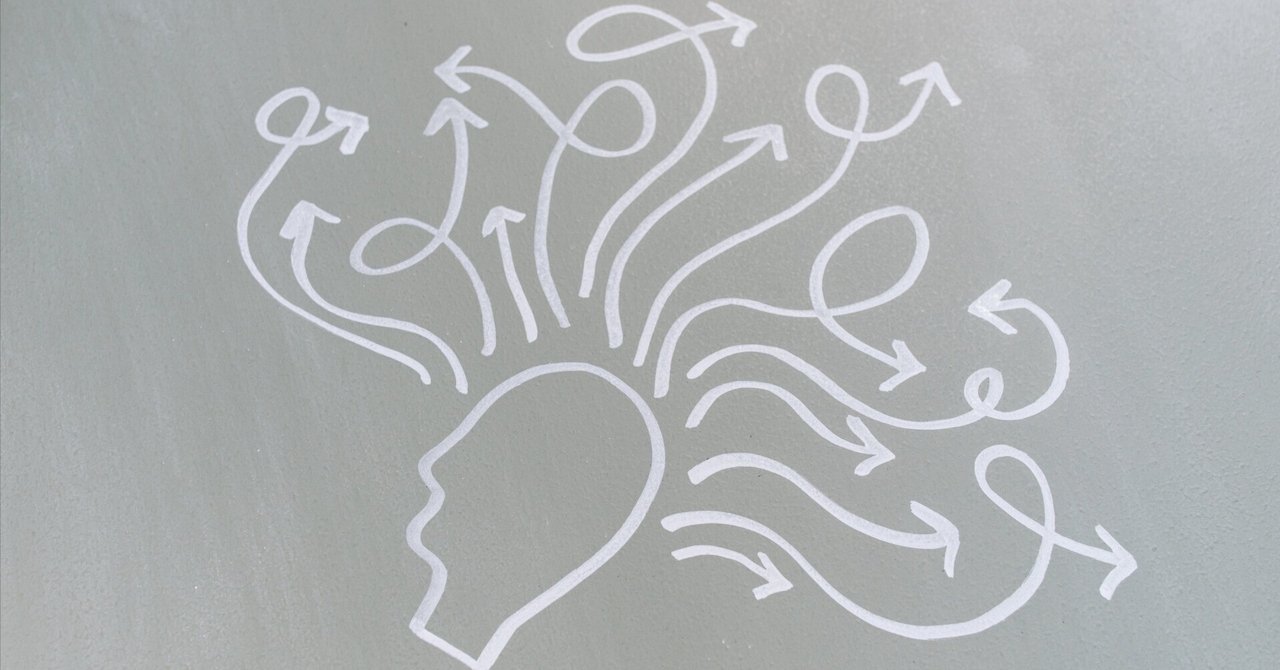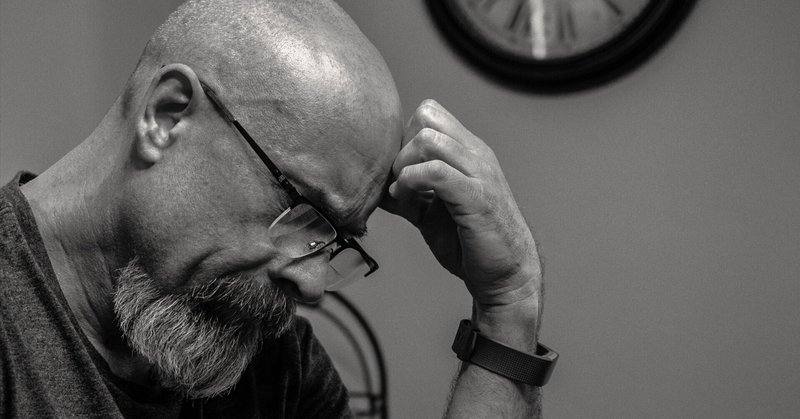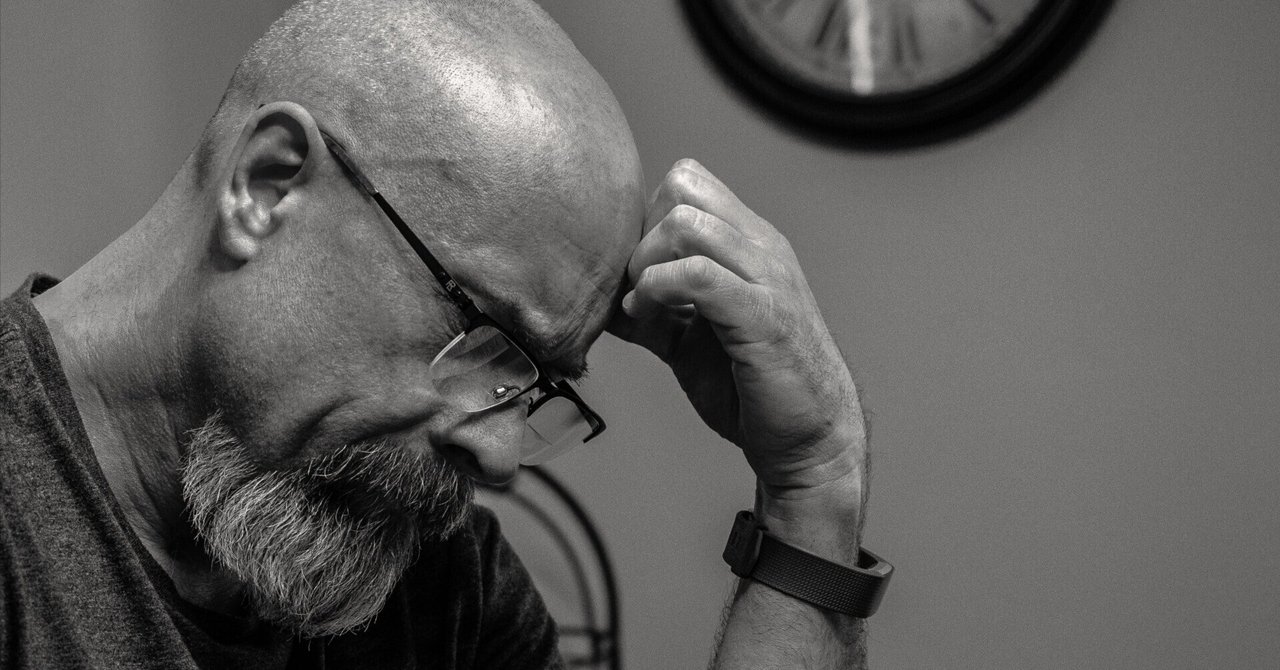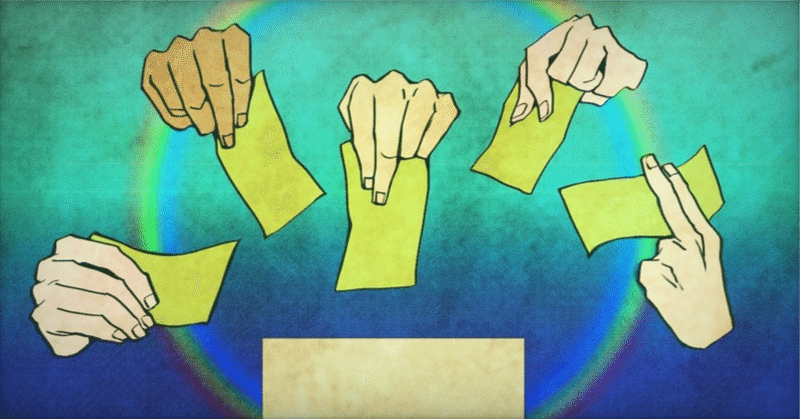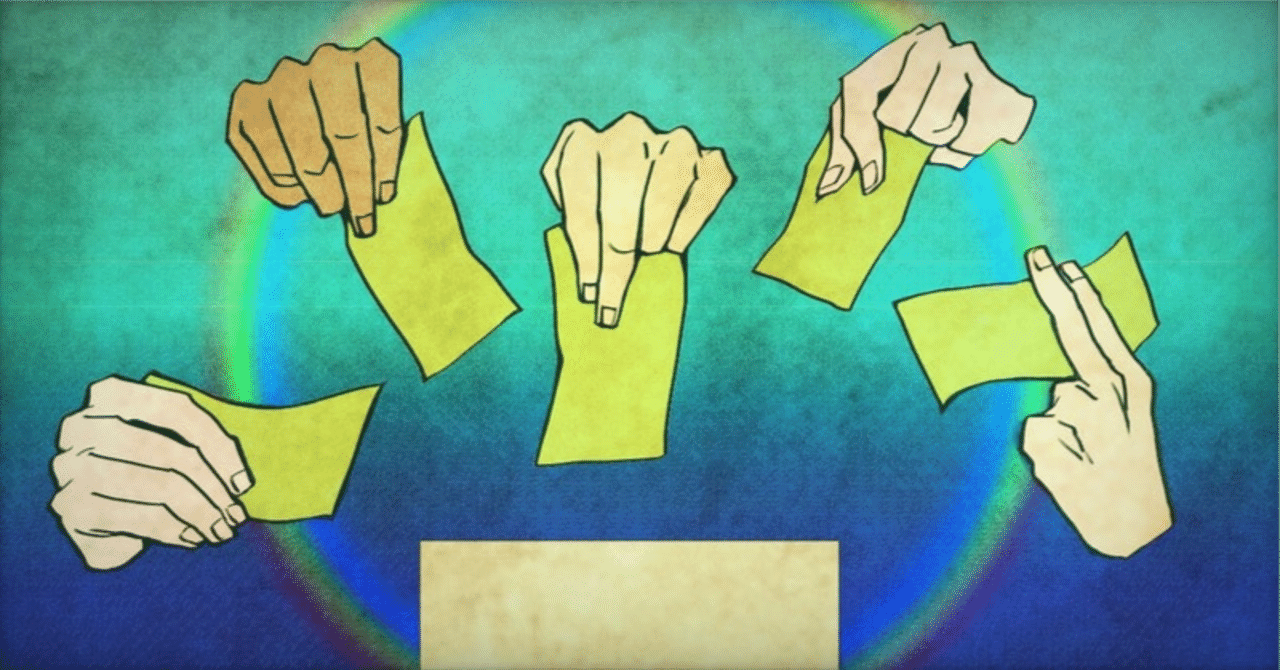高広伯彦(Ph.D. of Management Science)
マーケティング&事業開発アドバイザー。実務家教員。社会構想大学院大学特任教授。…
最近の記事
マガジン
記事

日本の「営業」と欧米の「Sales」はイコールではない、という“前提”の理解なしに、B2Bマーケティングや営業支援はできない。
日本の「営業」と欧米の「Sales」はイコールではない。 外資経験のある人なら構造的に理解をされてるかもしれないが、欧米ではそれぞれの role (職種)がはっきりと別れていて、分業化されている。 最も大きな違いは、例えば日本における「営業」は、客を獲得すると、その客を長きに渡って担当として対応する。一方で欧米における「Sales」は、新規の客を獲得するとそこまでで、customer 化したあとは別の role が顧客対応する。 このあたりは日本企業が外資との取引を考慮
-

生活者はマーケティングにおいてAIをどのくらい受け入れるか?についての米国でのレポートより〜シミュラークル化する社会における広告とマーケティングの話ってこと?
先日、東京ビックサイトで開催されたマーケティングWeek及び併催イベントにおいても、生成AI流行りだった。 SEOやコンテンツマーケティング向けのテキストコンテンツを生成AIで作成する、広告コピーを生成AIで多数生み出す、動画を生成AIで作成する、ヴァーチャルタレントを生成AIで生み出すなどなど、主にクリエイティブの領域での生成AI活用が目立つが、営業系、マーケティングオートメーション系、人材系においても ChatGPT を中心とした生成AIを利用しているものが多く見られた