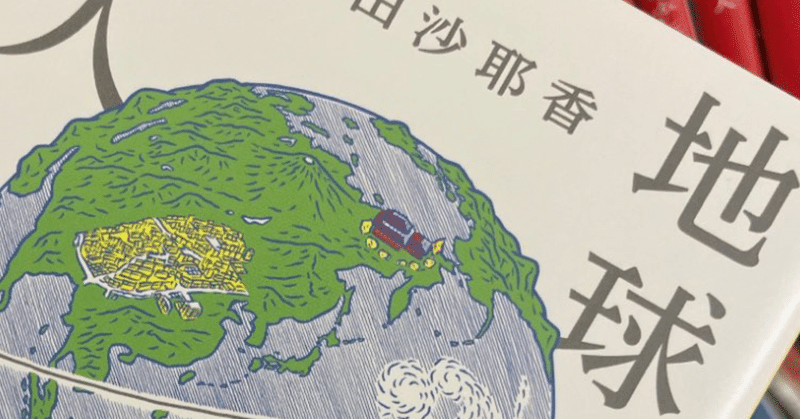
こうして女になっていく。
辟易する、という言葉を覚えたのはいつだったろうか。思い返せば、私は昔から漠然とこの世の何かに辟易としていたような気がする。あるいは、その言葉を知ったときになんとなくしっくりきたから当時の感情をそこに当てはめてみただけで、もっと別の適切な言葉があるのかもしれない。
その言葉を覚えた中学生か高校生の頃、私は事あるごとに「辟易する」と心の中で唱え続けていた。いわば心の口癖のようなものだ。口にしたことは一度もない、しかし心の中では何度も繰り返される言葉というものが私にはいくつかある。
幼い頃、私はとびきりマイペースで手のかかる、ちょっと変な子供だったらしい。その反動か、物心ついてからはなんとか“普通”になろうと、周りに染まりきろうと生きるようになった。この世に辟易としないために、必死こいていた。
恋人が欲しいと思うこと。性行為がしたいと思うこと。結婚したいと思うこと。子供が欲しいと思うこと。それらはかつて私自身の願望というよりも、周囲に染まるために自分に課したおまじないみたいなものだったような気がする。普通の人間に、普通の女になるには必要な願いだと信じていたのだ。
正直、おまじないにはぴんと来ていなかった。
好きな人は絶え間なくいたけれど、そこからどうこうなりたいというよりは相手を落とすのがただ楽しかっただけだし、結婚は漠然といつかするのかな程度の意識だったし、子供はあまりにも痛くて苦しそうだからちょっと嫌だな、ぐらいに考えていた。初めての彼氏ができてからも、彼との結婚から子育てのビジョンは一向に見えてこなかった。
それなのに今、私はあの頃とほとんど正反対の心境にある。出会う相手によってこんなにも人の心は変わるのかと、自分で自分に驚いている。
絶対に子供が欲しいとまでは思わないけれど、「自分の子供がいる生活」「子供がいなくても楽しい二人の生活」をありありと想像できるようになっただけで、私にとってはとてつもなく大きな変化なのだ。
村田沙耶香著『地球星人』は、かつてこの世の“普通”に染まりきれなかった私のような人物たちの物語だ。
私たち地球星人たちは人間どうしの男女でつがいを作り、子孫を残すための「工場」で暮らしている。自称宇宙人(ポハピピンポボピア星人)である主人公たちは、地球星人たちのそのような暮らしに適合するか、あるいは「工場」から逃げて息を潜めて生きていくかの狭間で葛藤する。彼らにとって大事なのは、とにかく置かれた異星でいきのびることだった。
普通になりきれない気持ち。普通になりたい気持ち。普通になりたくない気持ち。どれもが記憶のどこかで味わったことのある感情で、それらが全て生々しくて、痛々しい。そう、だって、私はもうポハピピンポボピア星人ではなく、れっきとした地球星人として洗脳された身なのだから。
ああ、こうして女になっていくのだろうなと思う。男と女になり、子孫を残す「道具」になってしまえた方が、この世界ではよっぽど生きやすいのだ。
恋を知って、つがいを見つけて、ひとつ屋根の下という名の「工場」で暮らす。私はきちんと洗脳が完了した、地球星人の子孫を残すための「道具」になれるのだろう。それは決して悲しくて辛くて、情けないことなんかじゃないのが不思議だ。これは主人公が切望した、地球星人に染まった暁に味わえる感情なのかもしれない。
結婚して、子供を産むという“普通”の人生。それは私のように、洗脳された人間がやるしかないことだ。やりたくないという意見も尊重されつつある今の世の中、できるならやりたい、という意思が少なからずある人間こそが果たすべき使命だと思う。
もし、ここに地球星人になりきれなかったポハピピンポボピア星人がいたとしたら。あなたは染まらなくてもいいんだよ、と言いたい。けれどそれと同時に、染まることで楽になる選択肢を取るのならそれでもいいとも思う。私はただ、“普通”の人間としてこの世に置いてもらいたかった、だから喜んで洗脳されただけなのだ。
辟易する、と唱えるたび、私はため息ひとつぶん世界の住人に近づくか、遠ざかっていた。そうしていつしか、周囲に辟易することすらなくなっていった。結局、辟易としないようにするためには世界に迎合するしかなかったのだ。それが私にとっての、いきのびるための術だった。
ご自身のためにお金を使っていただきたいところですが、私なんかにコーヒー1杯分の心をいただけるのなら。あ、クリームソーダも可です。
