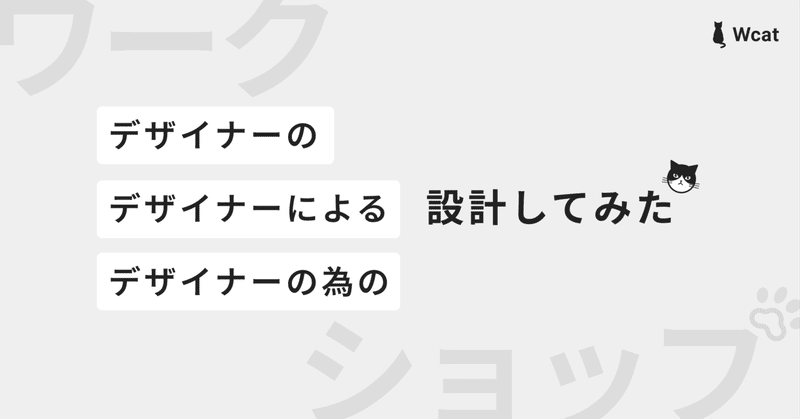
ワークショップを設計して思うこと
ごあいさつ
こんにちは!ますぐです。
事業会社でプロダクトデザイナーとしてUI/UX領域で日々奮闘しています。
今回は私がワークショップを設計し開催しました。
想定とは違うことが大小様々起きてしまい、次に繋がる学びを得られたのでシェアしたいと思います。
ワークショップの記事↓
ワークショップでの目的と課題
10月末メンターの田村さんが居なくなり、私がチームのリーダー的な動きをすることになりました。
『チームをどう成長させていくか』とマネージャーと議論しながら考えていましたがどうも自分が出す答えにピンとこない。
そもそもデザイナーチームとしての経験はほとんどないのでチームの醸成をする事は解像度が低く、なにから手をつけてよいか分かりませんでした。
そのため記事や文献をあさったりして一つのワークショップをベンチマークにしました。
ワークショップとしては『チームメンバーがみずからチームで学びたいスキルを考える』というもので、完全に同じものをしても意味がないと思い、
Wcat仕様にネクストアクションプランまで落とし込む設計にして開催しました。
参加するWcatのメンバーは学習欲がかなり高く、特に心配はなかったのですが、懸念点としては『自分が設計したワークショップがスムーズに行くかどうか。』というところが一つでした。
懸念がズバリ当たる。しかも予想以上に…
もともとは2週間で1時間づつで終了する予定でしたが、結局年内ギリギリまで時間がかかってしまいました。
タイムスケジュールも設定していたんですが予想以上に時間がかかり『ワークショップの設計むずっ』となっていました。
特に時間が掛かってしまったのが
3:アウトプットごとに必要なスキルを展開する

『アウトプットごとに必要なスキル』
言葉にしてみるとシンプルですが、これがなかなか難しい…
どこまでの粒度で言語化・抽象化するのか
このスキルは自分の領域のスキルの言葉として正しいのか。
ただ、逆に言うとここをクリアにすることで自分のアウトプットに対してのスキルが明確に意識することができるので掘り下げていくのは結果的に良いことでした。
チームで学ぶことだけではなく、プロとして自分のスキルを上げていく際にどのスキルを上げていきたいのかを選択もしやすくなると思います。
上位のレイヤーの方も入れるのも大事です。適切なFBや進む方向を間違えたりした時に適切に手助けもいただけます。
本来楽しむことが大事だよね
私自身、デザイナーのイベントやワークショップに参加することがありますがそれに比べてWcatで開催したワークショップはかなり楽しかったです。
大前提として、『信頼関係がある』というのは非常に大事だなということです。
イベントやワークショップではその日会った人と話したり議論したりするという事がありますが、普通にハードルが高い。笑
その点、今回のワークショップでは『Wcat』として活動してきて、社内ブランディング、チームブランディングなど一緒に仕事をしてきて、様々な事で一緒に手を動かしてきました。
ある程度お互いの能力や性格もわかっている状態でするワークショップはやりやすい事この上ないと感じました。笑
最近読んだこの本でもチームとしてアイデアをブレストしていく前にアクティビティをしていくみたいな箇所がありましたが、これは多分めちゃくちゃ大事。
(アクティビティをするのがハードル高いだろ!というツッコミもしたい笑)
終わりに
一応年内までには終了することができ、アクションプラン→アクションまで落としこむことができましたが、やはりワークショップを設計するのは難しいなと感じました。
次回ワークショップを設計する際は、しっかりテストをして、ある程度懸念点が解消できた形で、メンバーが楽しめる設計にすることが出来れば、さらに良い体験になるかなと思います。
チームビルディングにもなりますし、チームとしての方向性だったり相互理解を含める意味では非常に有意義なワークショップになりました。
チームリーダーの方やチームビルディングをご検討の方にご参考になれば幸いです。
最後まで見ていただきありがとうございます!
ぜひ、♡とシェアよろしくお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
