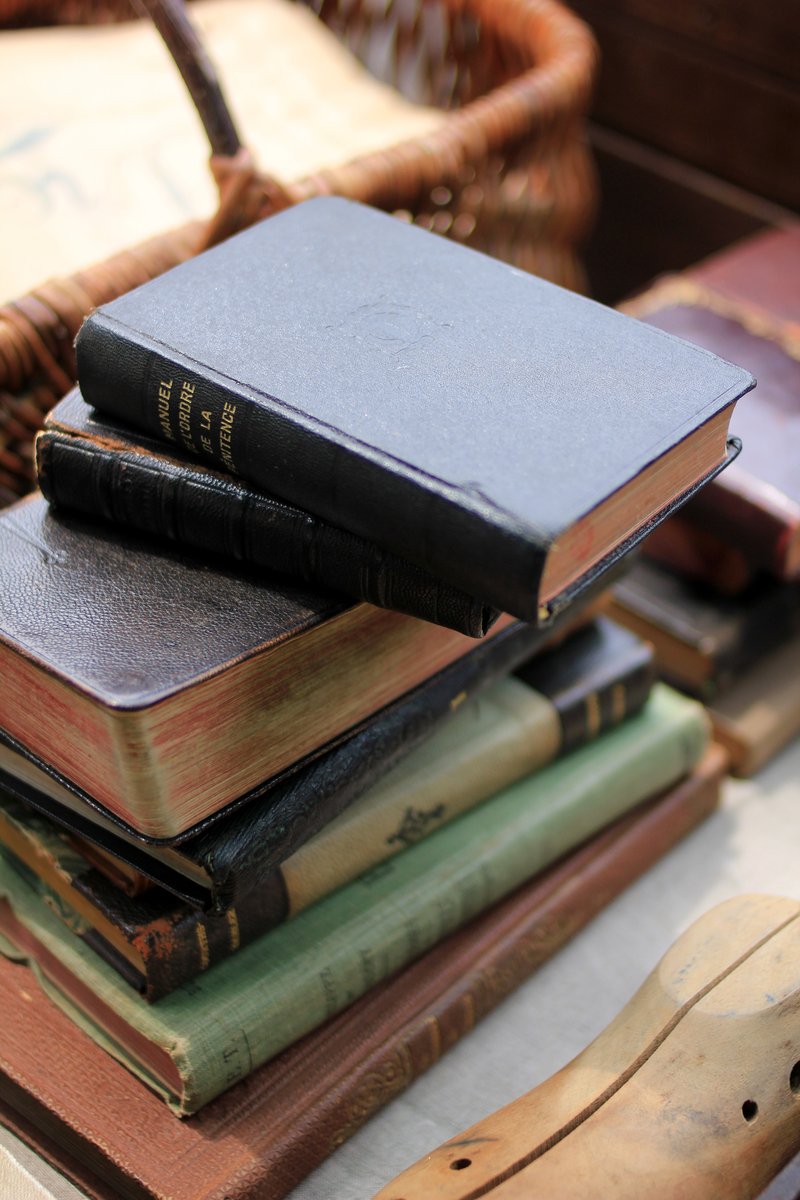#俳句
【俳句鑑賞】夏嵐机上の白紙飛びつくす 子規
季語は「夏嵐」。青嵐とも、風青しとも表現される。青葉の頃に吹き渡るやや強い南風で、繁茂した草木を揺り動かす風。(角川書店「俳句歳時記 夏」より)
躍動感を感じる、青春の句のようにイメージ「青」は若々しさを連想させる。弱弱しい感性の中にも、力強い躍動感がうずまいているような。とてもアンバランスな世界なのかもしれない。かんがえてみれば人生は矛盾にできているかもしれない。体力があり元気な時期はお金
【俳句鑑賞】嫁ケ島見えて昼寝の枕あり 蕪城
夏は昼寝の季節です季語は昼寝。午睡とも。酷暑の折は疲労も激しく、昼寝が推奨されたそうです。職人たちの仕事場での昼寝を「三尺寝」と言うそうですが、これは大工など足場や材木の上の三尺に満たない狭い場所で寝るから、または日陰が三尺動く間だけ昼寝が許されたから、とも言われているそうです。
嫁ケ島が見えるところで昼寝という贅沢嫁ヶ島(よめがしま)は、島根県松江市嫁島町の西約200mに位置する宍道湖唯一
【俳句鑑賞】炎帝につかへてメロン作りかな 鳳作
夏の俳句紹介に入りました。夏の季語はウキウキするものがたくさんあります。ドンドンと紹介していって、みなさんがお気に入りのお酒のように、「いつもの一句」が増えていくお手伝いができればなぁ、と思っているmasajyoです。
「夏」の呼び方いろいろ夏という一字だけで俳句ではもちろん季語になりますが、夏の別名といいますか、いろんな呼び方がありますからご紹介しましょう。
三夏…初夏、仲夏、晩夏の総称。
【俳句鑑賞】停年の後のことなどふらここに 義明
ふらここ。これ、実は「ぶらんこ」のこと。春の季語なんです。ぶらんこはふらここ以外にも、鞦韆(しゅうせん)、秋干、ふらんと、半仙戯(はんせんぎ)とも言われます。俳句をしていると言葉を覚えますね(笑)。
なお、なぜ半仙戯という漢字が当てられているかというと、
〔唐の玄宗が寒食(かんしよく)の日に,宮女に半仙戯(鞦韆(しゆうせ))の遊戯をさせたことから。「半仙戯」は半ば仙人になったような気分にさ
【俳句鑑賞】春深し女は小箱こまごまと 青邨
山口青邨(1892-1988)俳人。岩手県出身で高浜虚子に師事。工学博士として東大に勤めながら作句に励んだ。科学者としての目も生かした写生・観察に加え、省略や象徴、季語の活用によって複雑なものを単純化することを目指した。(以上Wikipediaより)
ところで、揚句の季語は「春深し」。2月4日から5月5日までが俳句でいう「春」となるので、春が深い季節は桜が散った後のちょうど今頃というところか。4
【句作】打つ田より風が生まれし山の間 masajyo
一歩ずつ前に進み耕していく。時間はかかる、でも前に進んでいる実感は感じる。この上ない達成感を感じる。人生と同じだ。今できることを少しずつ行い前に進んでいく。耕す間に見上げる空が広い。春の柔らかな風が、頬を撫でた。
【句作】言い訳はせぬ 紅梅を胸に抱き masajyo
輝くような梅の花の「紅」。ただ、まっすぐに潔く目に映る。梅の花は、きっと言い訳はしない。自分が決めた道にただ、小さな花をたくさん咲かす努力をし生きていく。
【句作】なすがまま 子を見送りて 氷消ゆ masajyo
久しぶりに句作もしたいと思います。これまで、鑑賞文末に作っていたものを一部添削してこちらに掲載させていただきます。どうぞ、十七音の世界を味わいくださいませ。
今回から、よりイメージが湧き立てばいいな、と一句ずつアップさせていただきました!
【俳句鑑賞】しののめの薄氷は踏み砕くもの 雅人
しののめ=東雲。夜明け、明け方のこと。薄氷は俳句の季語では「うすらい」と呼ぶ。これをスムーズに読める人は俳人の疑い大いにあり。言葉の通り、早春の季語である。
夜明けの光を受け、自分の歩く道の先に小さな水たまりが。見れば、その一部は凍っている。暦の上では春だが、ここそこにまだ冬の名残が感じられる。ことに早朝はまだ「冬」と言ってもいいほどだ。そんな中、行き先にある水たまりの氷を踏んで砕いた。
踏む