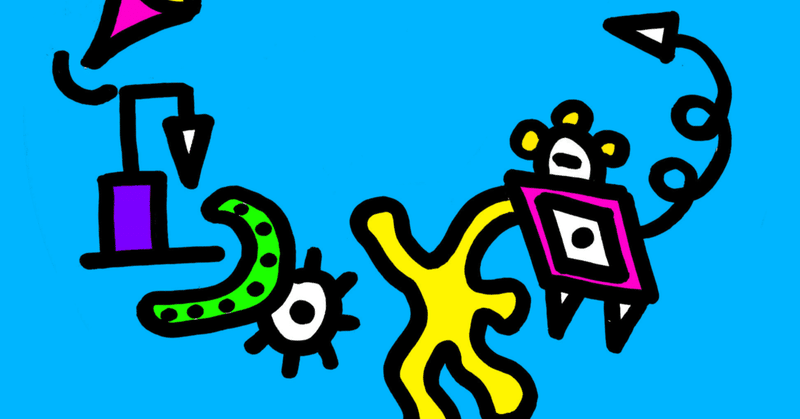
不注意(ADHD)ってなんだろう〜「発達障害」と診断された人のための「発達障害」の説明書10〜
一緒につくるマガジン
【「発達障害」と診断された人のための「発達障害」の説明書】と題して、マガジンの連載をしている。
このマガジンは、『一緒に作るマガジン』という設定。
「受け身ではない、主体的な学びの機会を作りたい」
という思いからの『一緒に作るマガジン』。
マガジンの作成に読者が参加してもらうことで、きっと、受け身ではない、主体的な学びの機会が作れる。
もし何か質問が出たら、次回はその質問について取りあげた記事を書きたいし、もし自分の記事を取り上げても良いという方がいれば、次回はそれについて一緒に考えたい。
そんな風に、発達障害のことについて読者と一緒に考え、理解を深めていきたい。
ここでの皆さんとのやりとりこそ、リアルな「発達障害」の説明書になり得ると考えている。
「発達障害」の説明書、よかったら、一緒に作りましょう。
不注意ってなんだろう?
今日は、ADHDの「不注意」という特性について考えてみたい。
『不注意』と言われてどんなことが思い浮かぶだろう。
忘れ物やなくしもの、ケアレスミス、集中の難しさ…
様々なことがイメージされるかもしれない。
改めて、不注意ってなんだろう。
ADHDの診断基準(DSM -5)で示される不注意としては以下のようになっている。
(1)不注意:以下の症状のうち 6 つ(またはそれ以上)が少なくとも 6 カ月持続したことがあり,その程度は発達の水準に不相応で,社会的および学業的/職業的活動に直接,悪影響を及ぼすほどである.
(a)学業,仕事,または他の活動中に,しばしば綿密に注意することができない,または不注意な間違いをする.
(b)課題または遊びの活動中に,しばしば注意を持続することが困難である.
(c)直接話しかけられたときに,しばしば聞いていないように見える.
(d)しばしば指示に従えず,学業,用事,職場での義務をやり遂げることができない.
(e)課題や活動を順序立てることがしばしば困難である.
(f)精神的努力の持続を要する課題に従事することをしばしば避ける,嫌う,またはいやいや行う.
(g)課題や活動に必要なものをしばしばなくしてしまう.
(h)しばしば外的な刺激によってすぐ気が散ってしまう.
( i )しばしば日々の活動で忘れっぽい.
日常場面で見られる不注意の例としては、具体的に以下のようなものが挙げられている。
・細部を見過ごしたり,見逃してしまう
・作業が不正確である
・講義,会話,または長時間の読書に集中し続けることが難しい
・明らかな注意を逸らすものがない状況でさえ,心がどこか他所にあるように見える
・課題を始めるがすぐに集中できなくなる,また容易に脱線する
・一連の課題を遂行することが難しい
・資料や持ち物を整理しておくことが難しい
・作業が乱雑でまとまりがない
・時間の管理が苦手
・締め切りを守れない
・学業や宿題,青年期後期および成人では報告書の作成,書類に漏れなく記入すること,長い文書を見直すことが難しい
・学校教材,鉛筆,本,道具,財布,鍵,書類,眼鏡,携帯電話をしばしばなくしてしまう
・気が散りやすい
・用事を済ませること,お使いをすること,電話を折り返しかけること,お金の支払い,会合の約束を守ることで忘れっぽい.
これら不注意の具体的な例を見ていただくと、誰にでもあることだろうと思われる人もいるかもしれない。
たしかにこれらのことは誰にでもあるようなことだが、診断がつくかどうかはその程度と、それが生活に支障をきたしているかというところがポイントとなる。
つまり、これらの特徴があればADHDというわけではなく、同年代の人と比べて明らかに頻度が多かったり、程度が相当だったりして、さらにそのことで生活に支障をきたしている場合には、ADHDの診断が検討されるということである。
(ADHDという診断がつくためには、他にもそれらの特徴が12歳になる前から存在していたということや、それらの特徴がその他の障害では説明できないという条件もある)
不注意がもたらす自信の低下
では、不注意の特性があると、心理的にはどんなことが起こり得るのだろうか。
私は不注意の子どもと接することが多いけれど、「自信を無くしやすい」というのが多くの子に共通する点のように思える。
自分では意識しようがないのが不注意である。
たとえば忘れ物。
「気をつけろ」と言われても、忘れてしまうものは忘れてしまうのだから、どうしようもない。
「気をつけよう」ということすら、その時には忘れてしまうのだから。
「常に意識しておけ」なんて言う人もいるが、そんなことは現実的ではない。
人間の中のメモリーというのは有限であり、どんな人も、何かに集中する時には何かを忘れてしまっている。
常に意識しておくというのは、常にメモリーの一部をそれに割いておくということであり、全体のパフォーマンスも落ちることになる。
忘れ物をしない人は、常に意識しているから忘れ物をしないのではなく、意識せずとも忘れ物をしていないのである。
私も、生活の余裕がなくなってきたときに不注意の傾向が出てくることがある。
普段は意識せずとも忘れ物なんてしないのに、生活の余裕がなくなると忘れ物を頻発するようになる。
自分でもわからないうちに忘れているのだから、意識するとかしないとか、気をつけるとか、そういう問題ではないような気がしている。
なのに、学校でも、社会でも、忘れ物をすると叱られたり、ペナルティが課せられたりする。
確かに自分の過失ではあるのだけれど、自分でもどうしようもないことで、自分でも落ち込んでいるところに、さらに罰が与えられるのは苦しいことである。
そのようなことが繰り返されると当然、自信は無くなっていく。
そしてもうひとつ、自信の低下につながるもの、それがケアレスミスである。
不注意はケアレスミスを引き起こす。
たとえば、テストなんかだと、わかっているのにケアレスミスで減点されたり、仕事上では、ケアレスミスで重大な失敗をしたり。
このように不注意は失敗体験を引き起こしやすく、また能力的には高いものを持っていたとしても、不注意により外的な評価が低下することは多い。
失敗体験が繰り返されたり、外的な評価が低くなると当然、自信は無くなっていく。
不注意の人の人生とともに
私は不注意の人と、どのように向き合うことができるだろう。
不注意が生活に支障をきたさないようにするための解決策を一緒に考えるとか、
不注意の症状を抑える薬を出してくれる医者を紹介するとか、
自分の不注意を受け入れられるような自己理解のお手伝いをするとか、
必要があればそんなことをするかもしれない。
でも、私としてはやっぱりその人の人生に寄り添いたいというか、
その人のことを理解したいというか、
なんだかうまく言えないけれど、カウンセリングは、不注意の解決策を提供することではないという思いがある。
前回、発達特性にフォーカスしないようなカウンセリングをしたいと書いたけれど、あえて発達特性にフォーカスしないというのも、それもやっぱり発達特性に自分が囚われているような気がする。
ただ、そこにいる人間に、その人の人生に寄り添う。
そして、そこにいる人間とともに、その人間のことを深く理解し合う。
そんなカウンセリングが、できればいいと思う。
次回予告
次回は、多動・衝動性について書いてみたいと思う。
結論はきっと、今日書いたようなことと同じになるのかもしれない。
いや、もしかすると、まったく別のことを思うかもしれない。
このマガジンを書く過程でも、自分の態度や目指す方向性が次々と変化しているように感じる。
新しいことに気付くということは変化をしていくということ。
自分が変化していくということを厭わないようにしたい。
次回も、よろしくお願いします。
▼【「発達障害」と診断された人のための発達障害の説明書】
▼その他のマガジンは以下よりご覧いただけます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
