【第1回】スキーマ療法とまりんの出会い〜スキーマ療法ってなに?
(2020.6.12冒頭追記)
最近知ったのですが、私のnoteにはブラウザ「スキーマ療法」と検索してくる人が多いみたいですね。
先日、スキーマ療法について勉強しようと思ってブラウザ検索で「スキーマ療法」と入力したところ、私のnoteのこの記事がWikipediaの下に出てきてびっくりしました。
だからこんなに昔の記事に今も一定のアクセスがあるのだなぁと納得したと同時に、せっかくスキーマ療法について知りたいと思ってきてくれた方にあまり情報を提供できていないなぁという申し訳なさも出てきました。
そこで、より実践的に日常でも活用できるスキーマ療法をみなさんに提供したい!と思って、「青空文庫」に収録されている有名な物語を使ってスキーマ療法をトレーニングする練習問題を作ってみました。
スキーマ療法との出会い
筆者のようにメンタルヘルスに問題を抱えている人や病院に行くまででもないけど生きづらさを抱えている人は多いと思います。病院やカウンセリングに通ってもイマイチ症状がよくならなくて、いつまでも通院すればいいの?みたいなことを考えたことはないでしょうか?
私は2015年5月から精神科通院と学生相談室を3年間利用しました。どちらもあまり効果がなく、大学院を休学してストレスと縁を絶つなどをしても、同じようなパニックやメンタル不安を繰り返し、いつまでも治る未来の見えない生活に絶望していました。
そんな時、医師の紹介で出会ったのが「スキーマ療法(schema therapy)」です。
スキーマ療法は、アメリカの心理学者ジェフリー・ヤングが1990年代に構築した認知行動療法を中心とした統合的心理療法です。
ヤングの著書を多く訳している伊藤絵美はスキーマ療法のことを「ニキビを治すのではなく、ニキビのできる体質を改善する療法」と称しています。
私はこのフレーズにとても惹かれて、衝動性と過集中の特性に応援され、スキーマ療法の本を片っ端から読むようになりました。
スキーマ療法入門 理論と事例で学ぶスキーマ療法の基礎と応用 https://www.amazon.co.jp/dp/479110854X/ref=cm_sw_r_cp_api_i_jwkLCbKMMVGDE

ケアする人も楽になる マインドフルネス&スキーマ療法 BOOK1 https://www.amazon.co.jp/dp/4260028405/ref=cm_sw_r_cp_api_i_HAkLCbX4A1TM
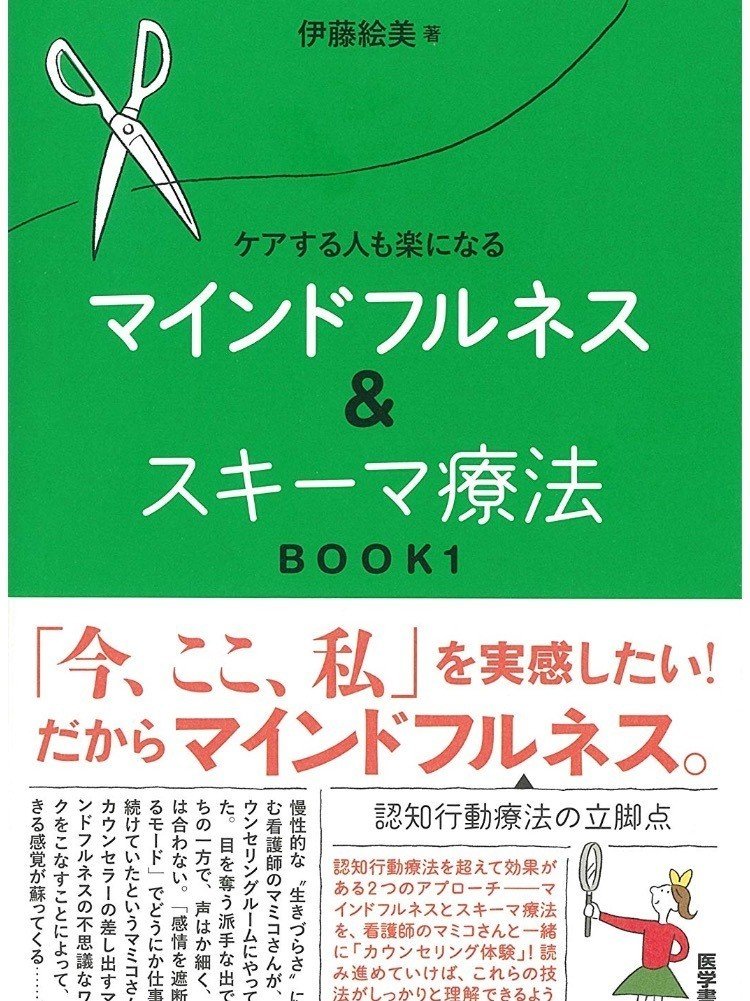
ケアする人も楽になる マインドフルネス&スキーマ療法 BOOK2 https://www.amazon.co.jp/dp/4260028413/ref=cm_sw_r_cp_api_i_1AkLCb3T28WPH
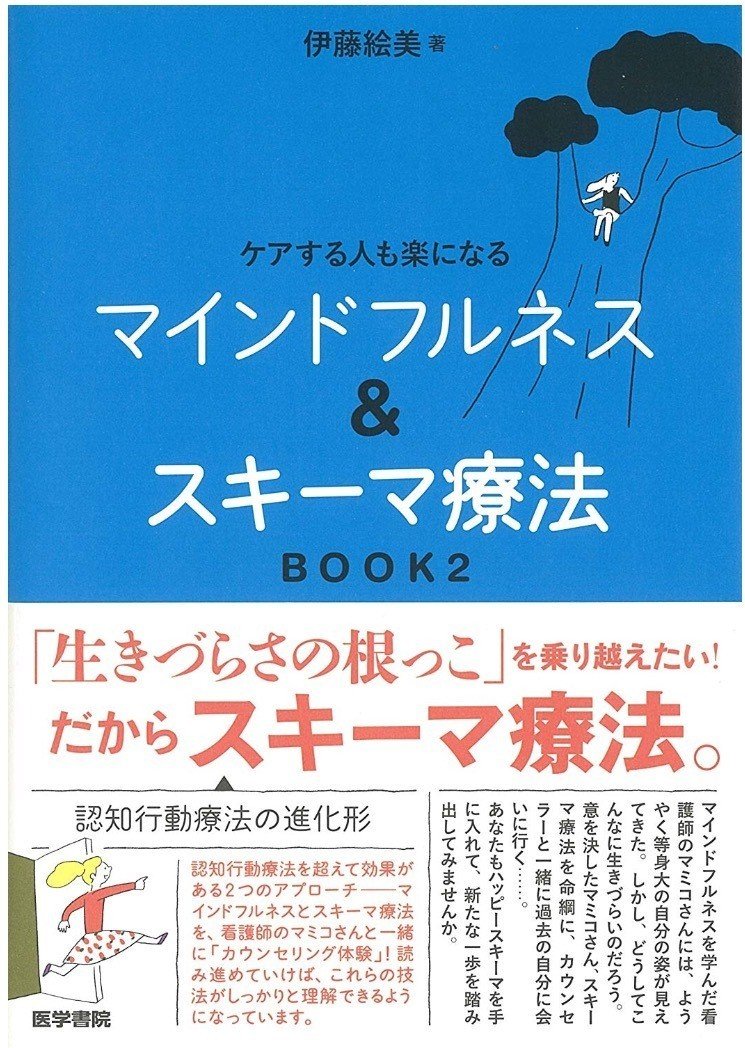
スキーマ療法―パーソナリティの問題に対する統合的認知行動療法アプローチ https://www.amazon.co.jp/dp/4772410465/ref=cm_sw_r_cp_api_i_hBkLCbY0S66RF

自傷行為とつらい感情に悩む人のために―ボーダーラインパーソナリティ障害(BPD)のためのセルフヘルプ・マニュアル https://www.amazon.co.jp/dp/4414414172/ref=cm_sw_r_cp_api_i_IBkLCbH19CEN1

スキーマモード・セラピー-チェ・ヨンフィ(崔永熙)の統合心理療法から https://www.amazon.co.jp/dp/4772412905/ref=cm_sw_r_cp_api_i_kDkLCbE3QWZMD
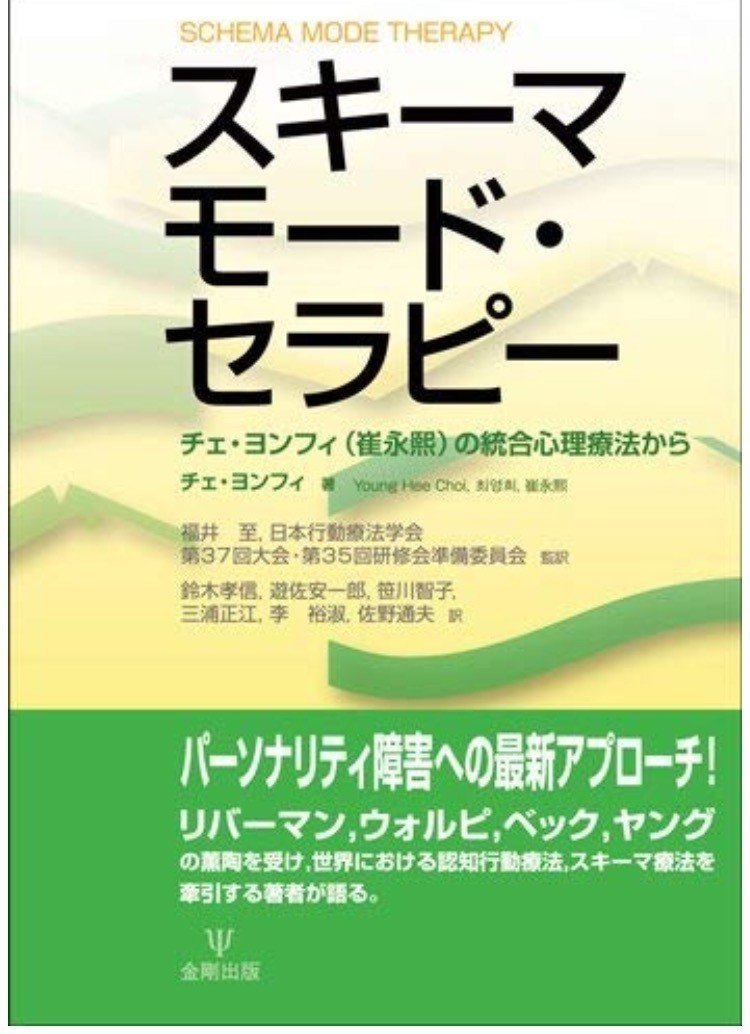
パーソナリティ障害の認知療法―スキーマ・フォーカスト・アプローチ https://www.amazon.co.jp/dp/4772410864/ref=cm_sw_r_cp_api_i_FDkLCbE46V2A6

認知行動療法とは、さまざな派閥や手法があるものの、簡単に言えば、現在主流のカウンセリング手法です。認知行動療法はキッチリやればかなりの困りが改善すると思いますが、それは目の前の困りごとへの対処でしかなく、繰り返してしまう困りごとを起こらないようにすることや生きづらさそのものを解決した人生のQOLの向上は難しいとヤングは考えました。学生相談室などで行われているカウンセリングは認知行動療法までいかず、認知行動療法のエッセンスだけを抜き取ったものも多い印象があります。クライアントである学生の困りごとを傾聴して共感するという傾聴重視のカウンセリングです。
しかし、私はこのタイプのカウンセリングでは何にも人生がよくならないと、この先に生きていくすべを身につけられないと思っていました。もちろん、その時すごく困ってる時に、とりあえず話を聞いてもらうのはいいのですが、それだけです。元気で問題のない期間に、これから起こる問題の対策としての、どうしてもトラブルを起こしてしまう自分の特性の改善としてのワークをすることはありませんでした。
スキーマ療法はこの、未来に起こりうる困難を回避することのできる心理療法として、私はとても魅力的に感じました。
そもそもスキーマってなに?
さっきからなんの説明もせず、スキーマスキーマと言っていますが、スキーマとは、何も新しいものではありません。古くから発達心理学などの心理学領域で「認知構造」という訳語が当てられて使われてきた概念です。
しかし、スキーマ療法のスキーマは認知構造という意味ではなく、わかりやすくいうと「信念」や「思い込み」と訳されることが多いです。
このスキーマというものは、すべての人間に多種多様に備わっています。
「赤信号だ!止まらなきゃ」と思う人の中には、「ルールは守らなきゃいけない」というスキーマがあるかもしれません。
「赤信号だけど、車もいないし渡っちゃえ」と思う人の中には、「ルールは時と場合によって守らなくてもいい」というスキーマがあるかもしれません。
このように、スキーマとは私たちの日常生活のいたるところに影響しています。
スキーマの中には、日常生活に対して悪影響を与えるような「不適応スキーマ」や良い影響を与えるような「適応スキーマ/ハッピースキーマ」があります。もしかしたら、ネガテイブにもポジティヴにも関係のないスキーマもあるかもしれません。
ヤングがスキーマ療法の中で注目したのは、ネガテイブなスキーマである「不適応スキーマ」です。中でも、幼少期の環境になどで人生の早期に形成される不適応スキーマを「早期不適応スキーマ」と名付けました。
早期不適応スキーマは、厳しい生育環境の中で子どもが生き抜いていくために得たスキーマで、その当時は適応的だったスキーマです。しかし、スキーマは一度形成されるとなかなか修正できません。当時は適応的だったスキーマを持ったまま、当時とは違った環境であるはずの大人になった今でも、当時のスキーマを手放せなくなると「早期不適応スキーマ」となります。
ヤングは早期不適応スキーマを5つにカテゴライズし、その中に18個のスキーマをあてはめました。
1.見捨てられ/不安定スキーマ
2.不信/虐待スキーマ
3.情緒的剥奪スキーマ
4.欠陥/恥スキーマ
5.社会的孤立/阻害スキーマ
6.依存/無能スキーマ
7.損害や疾病にたいする脆弱性スキーマ
8.巻き込まれ/未発達の自己スキーマ
9.失敗スキーマ
10.服従スキーマ
11.自己犠牲スキーマ
12.評価と承認の希求スキーマ
13.否定/悲観スキーマ
14.感情抑制スキーマ
15.厳密な基準/過度の批判スキーマ
16.罰スキーマ
17.権利要求/尊大スキーマ
18.自制と自律の欠如スキーマ
これらはあくまで、代表的なものです。早期不適応スキーマには実際にはもっと様々なものがあると思います。実際、スキーマカウンセリングのセッションでは、18個の早期不適応スキーマにとらわれずに、様々なスキーマを見つけて、カウンセリングの中に取り入れています。
早期不適応スキーマの一覧を見ただけで、「ああ、これ自分だ」と思う人もいれば、説明がないとピンとこない人もいると思います。早期不適応スキーマの解説を始めるとそれだけで1つの記事になってしまうので、今回は一覧の紹介だけで、早期不適応スキーマの細かい説明は次回に回しますね。
スキーマ療法の目標
スキーマ療法では、以上のような早期不適応スキーマを手放し、新たな適応スキーマやハッピースキーマを身につけることを目指します。この目標を達成するために、スキーマ療法では、「中核的感情欲求」と「スキーマモード」という概念に注目します。
中核的感情欲求とは、本来子どもが持っている自然な欲求のことです。安心することや、守られること、自分のことを尊重される、など様々なものがあります。
早期不適応スキーマはこの中核的感情欲求が満たされなかったことで形成されるとされています。そこで、スキーマ療法では、セラピストとクライアントの二人三脚で、本来満たされるべきだった中核的感情欲求を満たしていくことで早期不適応スキーマを手放すことを目指します。
しかし、早期不適応スキーマを手放のはとても難しく、頭で理解して、はいそうですか、と修正できるようなものではありません。そのため、クライアントのなかに、ヘルシーモードというモードを育てて、クライアント自身が常に中核的感情欲求を満たしてあげられる存在として機能できるようになることを目指します。
ここででてきた、「モード」という言葉は、あるスキーマが刺激されて活性化されている状態のことをさします。不適応的なモードもあれば適応的なモードもあります。適応的なモードをヘルシーモードと呼びます。
生きづらさを抱えている人の多くは不適応スキーマが活性化されると不適応なモード(状態)になります。例えば、私は上記の不適応スキーマの一覧のうち、「見捨てられ不安スキーマ」をとても強く持っています。あるきっかけでこのスキーマが刺激されると、私は「見捨てられるんじゃないか」と不安になり、見捨てられないように必死に相手の顔色を伺ったり、機嫌を取ろうとしたり、逆に不安のあまり泣いてしまったりします。このようなモードを「見捨てられたくないモード」と私は呼んでいます。
このモードは同時に様々なものが活性化されて、複雑に絡み合っていることもあります。スキーマ療法では、自分の中のヘルシーモードな自分が、自分の不適応なモードのうち、どれがでてきているのかを分析し、そのモードの下ではどんなスキーマが活性化されているのかを観察します。そして、そのスキーマを形成する満たされなかった中核的感情欲求を探し当て、そこに癒しを与えるようなワークを行います。
スキーマ療法では、セラピストが居なくても、自分1人で、中核的感情欲求を癒してあげられる存在になることを目指します。そうすることで、生きづらさを抱えた人たちは、自分の不適応スキーマを自分で手放し、適応的なスキーマを手に入れ、適応的なモードで現実世界を生きていけるようになります。
このマガジンを始めた理由
スキーマ療法は非常に魅力的な療法である一方、新しい療法であること、かなり継続的なワークが必要である点で、受けられる人が限られています。実際、スキーマ療法を行えるカウンセラーは日本で首都圏のごく一部にしかいません。1回8000円以上するセッションを毎週、少なくとも半年以上、長ければ5年以上受け続けることになります。地理的にも経済的にもとても現実にスキーマ療法を受けられる環境はいま整ってません。
そのため、スキーマ療法を日本に導入した伊藤絵美は多くのセルフスキーマ療法の本を出版し、自分たちでスキーマ療法に取り組めるように工夫しています。しかし、私が見る限り、1冊で完璧にセルフスキーマ療法に取り組めるような本は今のところありません。難しすぎたり、簡単にしすぎていたり、一長一短のものが多いです。数冊のセルフスキーマ療法の本と専門書を組み合わせればできなくもないと思いますが、生きづらさを抱えている人が1人で取り組むにはかなりつらい作業になり、続けられなくなると思いました。
自分でできるスキーマ療法ワークブック Book 1 生きづらさを理解し、こころの回復力を取り戻そう https://www.amazon.co.jp/dp/4791109031/ref=cm_sw_r_cp_api_i_2FkLCb1QGPBGZ

自分でできるスキーマ療法ワークブック Book 2 生きづらさを理解し、こころの回復力を取り戻そう https://www.amazon.co.jp/dp/479110904X/ref=cm_sw_r_cp_api_i_jGkLCbZSV9MCP
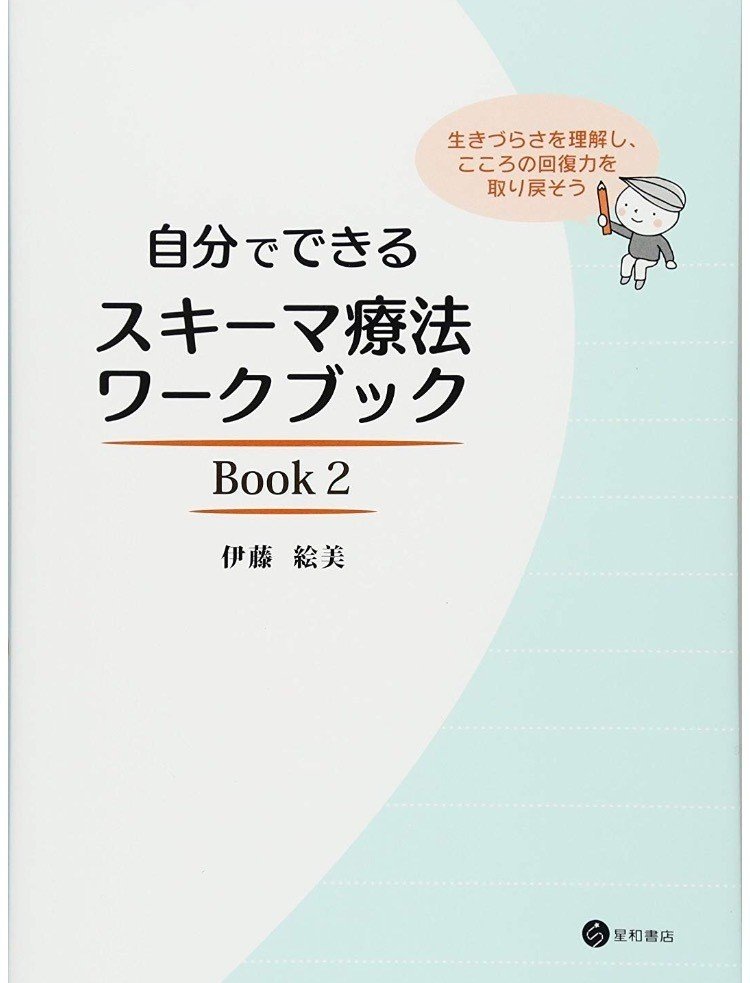
ケアする人も楽になる マインドフルネス&スキーマ療法 BOOK1 https://www.amazon.co.jp/dp/4260028405/ref=cm_sw_r_cp_api_i_zGkLCbNXWWTAX

ケアする人も楽になる マインドフルネス&スキーマ療法 BOOK2 https://www.amazon.co.jp/dp/4260028413/ref=cm_sw_r_cp_api_i_OGkLCbD5J1N06

自傷行為とつらい感情に悩む人のために―ボーダーラインパーソナリティ障害(BPD)のためのセルフヘルプ・マニュアル https://www.amazon.co.jp/dp/4414414172/ref=cm_sw_r_cp_api_i_7GkLCbQNQG1YT

そこで、実際にスキーマ療法をカウンセラーから受けている私が、スキーマ療法の進め方を退園に基づいて発信することで、すこしでもセルフスキーマ療法を試みる人たちの手助けになればいいと思いました。このマガジンはそのような経緯でできています。
スキーマ療法は「早期不適応スキーマ」「モード」「中核的感情欲求」などさまざまなことについて理解していなければ取り組めません。そこで、このマガジンでは、各回に関係するスキーマ療法の用語を解説しつつ、それに関わる私のカウンセリング体験を語っていこうと思います。
次回は、スキーマ療法を始める決意をしたきっかけの事件について、早期不適応スキーマとモードと中核的感情欲求の関係(サイクル)について書きたいと思います。
※スキーマ療法関連書籍の書評は別のマガジンに一冊ずつ丁寧にしようとおもいます。
参考記事
サポートありがとうございます。みなさんのサポートは、スキーマ療法や発達障害、当事者研究に関する書籍の購入やスキーマ療法の地方勉強会、ワークショップ開催などの費用に充てたいと思います。
